みんなのアンケート
言いたい!聞きたい!
【発達・知能検査、受けたけど…】お子さんの発達・知能検査の結果、どのように利用したか教えてください
新版K式発達検査、WISC、田中ビネー知能検査など、お子さんの発達状況を調べるための発達検査・知能検査を受けたことのあるご家庭も多くあると思います。
しかし、検査を受けたあと「これって結局どのように利用したらいいの?」「結果の詳しい見方が分からない」「学校にこのまま連携すれば大丈夫?」など悩んでしまうこともありますよね。
今回はそんな「お子さんの発達・知能検査の結果の利用方法」についてのアンケートとなります。
例えば:
・発達検査の結果ワーキングメモリの低さが分かり、小学校に連携したら宿題を減らしてもらえた
・発達検査の結果と医師の診察でASDと診断。薬を処方してもらい、癇癪などを抑えることができた。
・就学前に知能検査を受け、結果を学校に提出したら一緒に合理的配慮を考えてくれた
・発達検査で微細運動の発達の遅れが指摘され、療育でその部分を集中的に訓練できるようになった
・発達検査を受けたけれど結果の見方が分からなくてイマイチ支援に活かせていない気がする
・発達・知能検査についてこんなことが聞きたい
など
皆さんの経験は、同じ悩みを持つ保護者の方々の大きな助けになります!ぜひ率直な体験談をお聞かせください。
【アンケートへの答え方】
1、本画面下にある「選択肢」から1つを選択してください。
2、よろしければ続けて「このテーマに投稿する」欄に、具体的な体験談をお寄せください。
お寄せいただいたエピソードについては
・発達ナビ編集部が作成する記事にて読者の方からの声として紹介
・発達ナビの連載ライター陣がイラストを描きおろし、体験談をコミックエッセイ化(https://h-navi.jp/user/368843)して、発達ナビで公開などで活用させて頂きます。
【アンケート期間】
2025年7月14日(月)から7月24日(木)まで
▼発達ナビ編集部が作成する記事内にて読者の方からの声としての紹介について
採用、不採用にかかわらずご連絡は致しません。ご了承くださいませ。
▼コミックエッセイ化について
・コミックエッセイとしてエピソードが採用された方には編集部より随時(投稿より最大1か月程)ご連絡致します。ご連絡の際、追加で質問をさせていただくこともあります。
・コミックエッセイ公開の際はお名前公開・非公開を選ぶことができます。
・コミックエッセイとしてエピソードが採用された場合、Amazonギフト券500円分を謝礼として差し上げます。
・採用とならない場合にはご連絡は致しません。ご了承くださいませ。
しかし、検査を受けたあと「これって結局どのように利用したらいいの?」「結果の詳しい見方が分からない」「学校にこのまま連携すれば大丈夫?」など悩んでしまうこともありますよね。
今回はそんな「お子さんの発達・知能検査の結果の利用方法」についてのアンケートとなります。
例えば:
・発達検査の結果ワーキングメモリの低さが分かり、小学校に連携したら宿題を減らしてもらえた
・発達検査の結果と医師の診察でASDと診断。薬を処方してもらい、癇癪などを抑えることができた。
・就学前に知能検査を受け、結果を学校に提出したら一緒に合理的配慮を考えてくれた
・発達検査で微細運動の発達の遅れが指摘され、療育でその部分を集中的に訓練できるようになった
・発達検査を受けたけれど結果の見方が分からなくてイマイチ支援に活かせていない気がする
・発達・知能検査についてこんなことが聞きたい
など
皆さんの経験は、同じ悩みを持つ保護者の方々の大きな助けになります!ぜひ率直な体験談をお聞かせください。
【アンケートへの答え方】
1、本画面下にある「選択肢」から1つを選択してください。
2、よろしければ続けて「このテーマに投稿する」欄に、具体的な体験談をお寄せください。
お寄せいただいたエピソードについては
・発達ナビ編集部が作成する記事にて読者の方からの声として紹介
・発達ナビの連載ライター陣がイラストを描きおろし、体験談をコミックエッセイ化(https://h-navi.jp/user/368843)して、発達ナビで公開などで活用させて頂きます。
【アンケート期間】
2025年7月14日(月)から7月24日(木)まで
▼発達ナビ編集部が作成する記事内にて読者の方からの声としての紹介について
採用、不採用にかかわらずご連絡は致しません。ご了承くださいませ。
▼コミックエッセイ化について
・コミックエッセイとしてエピソードが採用された方には編集部より随時(投稿より最大1か月程)ご連絡致します。ご連絡の際、追加で質問をさせていただくこともあります。
・コミックエッセイ公開の際はお名前公開・非公開を選ぶことができます。
・コミックエッセイとしてエピソードが採用された場合、Amazonギフト券500円分を謝礼として差し上げます。
・採用とならない場合にはご連絡は致しません。ご了承くださいませ。
選択肢をクリックすると120人の回答が見られるよ!
(回答してもタイムラインには流れません)
・アンケートに関する投稿及びアンケート結果を発達ナビのコラム等で紹介する場合があります。
・アンケート結果は、今後のサービス改善・向上の参考とさせていただきます。
・アンケート結果は、今後のサービス改善・向上の参考とさせていただきます。
 特に共感が集まった投稿
特に共感が集まった投稿
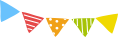
7ヶ月前
違反報告
🔶未入園時
2歳で再検査を受けた時と、親子教室で「遠城寺式乳幼児発達検査」を受けました。この時は検査用紙をサラっと見せてもらって、○○が苦手みたいですねーと言われた程度。親子教室ではどちらかというと私が相談に乗ってもらうことが中心でした。
🔶幼稚園年少~年中
年少の終わり頃、園の巡回相談で受けた遠城寺式の結果(DQ73)から療育の利用を開始。療育でも半年ごとに「遠城寺式」「S-M社会生活能力検査」「絵画語彙検査」の三つの検査を受けました。
年少~年中の間は検査結果だけでなく、日常生活や療育活動の中での具体的な困り事から、こども個人に合った支援方法を一緒に考えてもらった感じでした。
息子は入園当初は言葉での指示がほとんど通らず、また興奮しやすく衝動の強い性格で、私はイライラしていつか虐待してしまうかも知れないと悩んでいました。あの頃は「困ったら何でも療育に相談」を合言葉に、なんとか日々を乗り切っていました。
また、息子が通っていた療育ではペアレントトレーニングにも力を入れていて、私も受講をしました。
ペアトレで最初に教わったのは、子どもの「できないこと」に着目しがちな親側の思考の癖を直すことでした。
それから、ペアトレで指導された子どもに指示が通りやすくなる声掛けの仕方を家で実践してみたら、拍子抜けするくらい息子に指示が伝わりやすくなりました。
毎日寝る前に絵本の読み聞かせをして語彙をふやし、放課後の園庭や公園などで積極的によそのお子さんも一緒に遊んであげることで、お友達と遊ぶ経験値が上がるように働きかけました。
また、自転車遊びやアウトドアや鉄道旅行など、こどもの世界を広げるお出かけにも積極的に連れて行きました。
すると年中の後半には発語がほかのお子さんたちと遜色ないレベルになりました。また、サイクリングにハマったおかげでグネグネだった体幹が褒められるくらい丈夫になり、息子の癇癪も年中が終わる頃にはほぼ解消されました。
🔶年長の検査(新版K式)
年長の秋(5歳8ヶ月)に療育で受けた新版K式の結果は、DQ82でちょうど1年遅れでした。
この時に心理士さんに、小学校に通常級でいくか支援級でいくか迷ってることを相談したところ、「息子くんは通常級でもやっていける子だとは思いますが、お勉強は苦労する子です」と率直に指摘されました。
その上で、小学校に入学したら小2の終わりまでに学習面で取り組むべきこととその後の見通しについて、具体的にアドバイスしていただけました。
このアドバイスのお陰で入学後も焦ることなく、長期的な見通しをもって息子の支援に取り組むことができて、本当にありがたかったです。
また、入学前には療育と幼稚園が連携して支援ノートを作成して下さったので、小学校への配慮事項の引継ぎがスムーズにいき、入学した時点でクラスに支援員が配置されていたのもすごく助かりました。
🔶小2の秋の検査(WISC4)
小学校は通常級に入学し、放課後デイを週1で利用してました。
学校では主に生活面の合理的配慮をお願いし、学習支援やSSTは放デイでフォローしてもらってました。
ですが、小2になって集中力のなさが看過できない状態になり、また学習面でも理解不能な苦手部分が出てきたことから、服薬を検討するために初めて専門医を受診しました。
WISC4の検査結果はIQ91ですが凸凹の差が大きく、ADHDとSLD(書字と計算)の診断がつきました。ADHDは予想してましたが、SLDは想定外でした。
医師からは、言語理解が凸の子なので「これくらい言わなくても分かるだろう」と思わずに何でも言葉で説明してあげると、理解が進みやすい子だと説明されました。また時間感覚が弱いので、早寝早起きで毎日のスケジュールを極力一定になるようにして、体内時計を整えてあげるようにとも。
まもなくアトモキセチンの服薬がはじまると、それまで集中力がもたないせいで何時間もかかっていた宿題が、1~2時間で終われるようになりました。
また、担任に検査結果を伝えたうえで学習面での合理的配慮を追加でお願いしました。板書が間に合わない時は学校のタブレットで撮影してもいいことや、宿題(特に漢字練習)の減量などの配慮を受けられるようになったことで、息子が明らかにホッとした顔になり、安心して学校に通えるようになりました。
🔶現在(小6)
苦手な科目はあるものの、宿題も含め学校での合理的配慮はほとんど必要なくなってます(必要に応じて個別の声掛けをお願いしてる程度)。友達関係は良好でトラブルもありません。
家庭ではまだ親の補助が必要な場面は多少あり、朝の起床、デバイスの音声リマインダーを利用しての時間とタスクの管理、持ち物チェックなど物の管理の手伝い、自主学習用の問題作成や振り返り学習などの手伝いをしてあげてます。
今は放デイも月1の利用に減っており、小学校卒業後は学習支援に絞っていく方向で考えています。
2歳で再検査を受けた時と、親子教室で「遠城寺式乳幼児発達検査」を受けました。この時は検査用紙をサラっと見せてもらって、○○が苦手みたいですねーと言われた程度。親子教室ではどちらかというと私が相談に乗ってもらうことが中心でした。
🔶幼稚園年少~年中
年少の終わり頃、園の巡回相談で受けた遠城寺式の結果(DQ73)から療育の利用を開始。療育でも半年ごとに「遠城寺式」「S-M社会生活能力検査」「絵画語彙検査」の三つの検査を受けました。
年少~年中の間は検査結果だけでなく、日常生活や療育活動の中での具体的な困り事から、こども個人に合った支援方法を一緒に考えてもらった感じでした。
息子は入園当初は言葉での指示がほとんど通らず、また興奮しやすく衝動の強い性格で、私はイライラしていつか虐待してしまうかも知れないと悩んでいました。あの頃は「困ったら何でも療育に相談」を合言葉に、なんとか日々を乗り切っていました。
また、息子が通っていた療育ではペアレントトレーニングにも力を入れていて、私も受講をしました。
ペアトレで最初に教わったのは、子どもの「できないこと」に着目しがちな親側の思考の癖を直すことでした。
それから、ペアトレで指導された子どもに指示が通りやすくなる声掛けの仕方を家で実践してみたら、拍子抜けするくらい息子に指示が伝わりやすくなりました。
毎日寝る前に絵本の読み聞かせをして語彙をふやし、放課後の園庭や公園などで積極的によそのお子さんも一緒に遊んであげることで、お友達と遊ぶ経験値が上がるように働きかけました。
また、自転車遊びやアウトドアや鉄道旅行など、こどもの世界を広げるお出かけにも積極的に連れて行きました。
すると年中の後半には発語がほかのお子さんたちと遜色ないレベルになりました。また、サイクリングにハマったおかげでグネグネだった体幹が褒められるくらい丈夫になり、息子の癇癪も年中が終わる頃にはほぼ解消されました。
🔶年長の検査(新版K式)
年長の秋(5歳8ヶ月)に療育で受けた新版K式の結果は、DQ82でちょうど1年遅れでした。
この時に心理士さんに、小学校に通常級でいくか支援級でいくか迷ってることを相談したところ、「息子くんは通常級でもやっていける子だとは思いますが、お勉強は苦労する子です」と率直に指摘されました。
その上で、小学校に入学したら小2の終わりまでに学習面で取り組むべきこととその後の見通しについて、具体的にアドバイスしていただけました。
このアドバイスのお陰で入学後も焦ることなく、長期的な見通しをもって息子の支援に取り組むことができて、本当にありがたかったです。
また、入学前には療育と幼稚園が連携して支援ノートを作成して下さったので、小学校への配慮事項の引継ぎがスムーズにいき、入学した時点でクラスに支援員が配置されていたのもすごく助かりました。
🔶小2の秋の検査(WISC4)
小学校は通常級に入学し、放課後デイを週1で利用してました。
学校では主に生活面の合理的配慮をお願いし、学習支援やSSTは放デイでフォローしてもらってました。
ですが、小2になって集中力のなさが看過できない状態になり、また学習面でも理解不能な苦手部分が出てきたことから、服薬を検討するために初めて専門医を受診しました。
WISC4の検査結果はIQ91ですが凸凹の差が大きく、ADHDとSLD(書字と計算)の診断がつきました。ADHDは予想してましたが、SLDは想定外でした。
医師からは、言語理解が凸の子なので「これくらい言わなくても分かるだろう」と思わずに何でも言葉で説明してあげると、理解が進みやすい子だと説明されました。また時間感覚が弱いので、早寝早起きで毎日のスケジュールを極力一定になるようにして、体内時計を整えてあげるようにとも。
まもなくアトモキセチンの服薬がはじまると、それまで集中力がもたないせいで何時間もかかっていた宿題が、1~2時間で終われるようになりました。
また、担任に検査結果を伝えたうえで学習面での合理的配慮を追加でお願いしました。板書が間に合わない時は学校のタブレットで撮影してもいいことや、宿題(特に漢字練習)の減量などの配慮を受けられるようになったことで、息子が明らかにホッとした顔になり、安心して学校に通えるようになりました。
🔶現在(小6)
苦手な科目はあるものの、宿題も含め学校での合理的配慮はほとんど必要なくなってます(必要に応じて個別の声掛けをお願いしてる程度)。友達関係は良好でトラブルもありません。
家庭ではまだ親の補助が必要な場面は多少あり、朝の起床、デバイスの音声リマインダーを利用しての時間とタスクの管理、持ち物チェックなど物の管理の手伝い、自主学習用の問題作成や振り返り学習などの手伝いをしてあげてます。
今は放デイも月1の利用に減っており、小学校卒業後は学習支援に絞っていく方向で考えています。
7ヶ月前
違反報告
新しい医師、新しい支援に繋がる際に、検査結果は勿論それ以外にも必要だとこちらが感じた書類は、必ずコピー(もしくはコピーのコピー)を渡しています
限られた時間の中で、私のことを簡単に把握していただくには、ここ数年では有効に活用してこれている方だと思います
(病院都合での、急な転院もあったので。。。)
限られた時間の中で、私のことを簡単に把握していただくには、ここ数年では有効に活用してこれている方だと思います
(病院都合での、急な転院もあったので。。。)










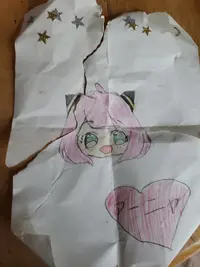



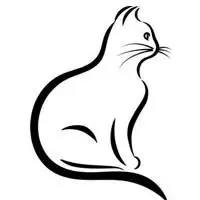
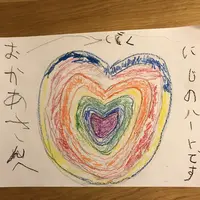



 ...
...








