【専門家監修】児童養護施設とは?受けられる支援、入所条件や手続き、子どもたちの生活と現状
ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
児童養護施設とは、生まれた家庭で生活することが困難だと判断された児童が入所する施設のことです。子どもたちに、できるだけ一般的な家庭生活を提供し、施設を離れた後は、自立して社会生活を営めるよう支援することを目標としています。
この記事では、児童養護施設の現状や支援内容についてまとめています。
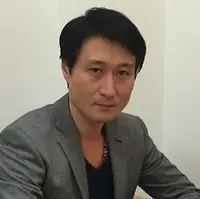
監修: 早川悟司
児童養護施設 子供の家(東京都清瀬市)施設長
社会福祉士
日本福祉大学大学院卒。社会福祉士。
児童養護施設 子供の家(東京都清瀬市)施設長。
都内2か所の児童養護施設勤務を経て、2013年4月より子供の家副施設長・自立支援コーディネーター、2014年4月より現職。
社会福祉士
児童養護施設とは?
このコラムで分かること
- 児童養護施設は、様々な事情で家庭での生活が難しい子どもが暮らし、自立を目指すための「家庭に代わる家」です
- 原則18歳までの子どもが対象で、児童相談所などを通じて入所が決まり、専門職員(保育士・児童指導員など)が生活をサポートします
- 施設での生活は小規模化・家庭的養護が進んでおり、学校へ通いながら社会生活に必要なスキルを身につけていきます
- 退所後も自立援助ホームや身元保証人確保対策などの支援制度があり、就職や進学に向けたアフターケアも充実しつつあります
児童養護施設とは、経済的な理由や虐待など、さまざまな理由で保護者と生活することが難しい、そして社会のサポートが必要と判断された児童が入所する施設です。入所した子どもたちを保護し、生活習慣を身につけたり社会生活に必要なスキルを得られるよう、支援を行います。そして、自立に向けた支援、退所した者に対してもアフターケア支援を行います。
児童福祉法では、どの児童も適切に養育され、生活を保障され、愛され、保護されることで心身の健やかな成長を保障される権利を有すると定められています。そして、児童が適切に養育され、生活を保障されるための一つの手段として、児童養護施設があります。
児童福祉法では、どの児童も適切に養育され、生活を保障され、愛され、保護されることで心身の健やかな成長を保障される権利を有すると定められています。そして、児童が適切に養育され、生活を保障されるための一つの手段として、児童養護施設があります。

子どものための法律、児童福祉法って?目的や支援、法改正についてをわかりやすくご紹介します。
児童養護施設はなんのための施設か
児童養護施設に求められている役割は、入所している児童が健やかに発達できるよう、できる限り家庭的で落ち着いた環境で生活を送れるようにすることです。つまり家庭に代わる家として、子どもが暮らす場所となり、この生活を通して、家庭に戻ることや児童の自立を支えます。
児童養護施設への入所の対象者とは?
どのような子どもが対象なのか
乳児を除く原則18歳まで(必要に応じて20歳まで)の、保護者による養育が困難な児童、また何らかの理由で児童養護施設によるサポートを必要とする児童が対象です。
特に必要があると判断された場合は乳児も対象となりますが、基本的に2歳未満の乳幼児は、乳児院を利用することになっています。
特に必要があると判断された場合は乳児も対象となりますが、基本的に2歳未満の乳幼児は、乳児院を利用することになっています。
どのような理由で入所するの?
児童養護施設に入所する理由は、多岐にわたります。父母の傷病、家庭の経済的な理由や虐待などで、保護者による養育が困難な場合です。相談相手が少ない、離婚率が高まりシングルマザーが増えているなど、現代の子育て環境が保護者の孤立や困難を生みやすいことも、その背景にあると言えるでしょう。
















