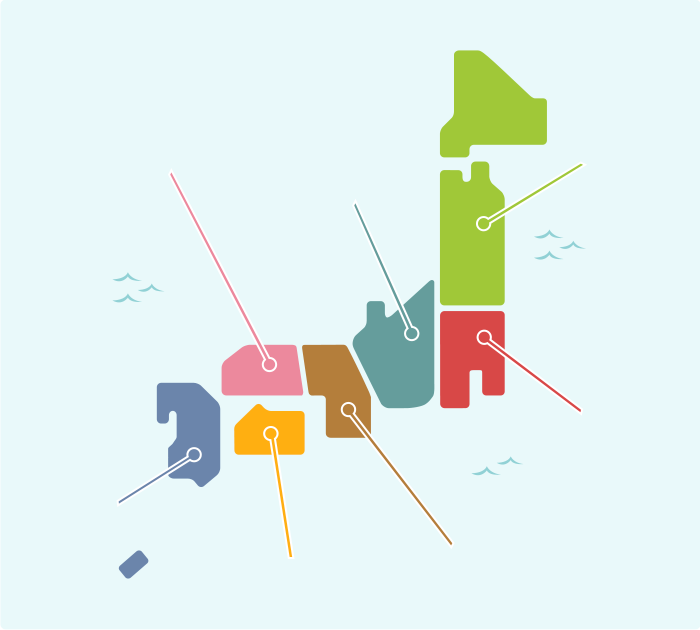22歳ではっきりと「人と違う」ことを自覚する
――沖田さんは、漫画家になる前に性風俗で働いた経験についても、コミックエッセイで描かれています。
沖田:看護師として働いている途中から、昼は病院、夜はおっぱいパブという働き方をしていました。看護師時代はワーカホリックで、「働いていないと生きている意味がない」と感じることもあったんです。当時はお金を貯めることが唯一の生きがいになっていましたし、肉体労働としての共通点も感じていたので、あまり抵抗もなくおっぱいパブで働き始めました。それまではあまりにも人のことに興味がなかったので、わたしなりに「人間を知りたい」とも思っていたんです。
お客さんには「明日結婚するから最後に遊びに来た」「嫁さんがもうすぐ出産で、しばらく性的なことはできないから来た」などと話す人がいたり、社会的地位は高いけれどマナーの悪いお客さんもいたりして、「人って、普段外から見える部分だけではないんだ、いろんな要素が固まって人格になっているんだな」ということを知りました。これは、後々漫画をつくるにあたって非常に役立つ考察になりましたね。
沖田:看護師として働いている途中から、昼は病院、夜はおっぱいパブという働き方をしていました。看護師時代はワーカホリックで、「働いていないと生きている意味がない」と感じることもあったんです。当時はお金を貯めることが唯一の生きがいになっていましたし、肉体労働としての共通点も感じていたので、あまり抵抗もなくおっぱいパブで働き始めました。それまではあまりにも人のことに興味がなかったので、わたしなりに「人間を知りたい」とも思っていたんです。
お客さんには「明日結婚するから最後に遊びに来た」「嫁さんがもうすぐ出産で、しばらく性的なことはできないから来た」などと話す人がいたり、社会的地位は高いけれどマナーの悪いお客さんもいたりして、「人って、普段外から見える部分だけではないんだ、いろんな要素が固まって人格になっているんだな」ということを知りました。これは、後々漫画をつくるにあたって非常に役立つ考察になりましたね。
沖田:風俗の仕事は、中身のある会話をしなくていいところも息抜きになりました。60分チヤホヤしたら対価がもらえるというのが、シンプルですごく性に合っていたんです。同僚の女の子たちとの希薄な関係も好きでしたね。仮の名前や性格でも通用する世界は、とても気が楽でした。
それでも、当時は看護師をメインの仕事に据えていました。本当は看護師の仕事に一生を捧げたかったんですが、正看護師として美容整形科で仕事を初めて3日目ぐらいで、初めて「人と違う」という自覚が出てきたんです。22歳のときでした。
――「人と違う」というのは、どういう感覚ですか? 小学生での、周りがロボットに思えるという感覚とは違うものでしょうか。
沖田:日本語はわかるのに、相手が何を言っているかわからないことが多々あったんです。みんなが何か一言言われるだけで動けているときに、自分だけわからないという問題が、すごくはっきり出てきました。学生時代は「わたしはいいかげんな性格だから」とすませていましたが、国家試験にも受かって准看護師から正看護師になっている今回は、「あれ?」と思いました。
そのとき、自分の頭にはごそっと何かが足りなくて、それが補えずに苦しんでいるんだなとぼんやりわかったんです。それでも、具体的にどんな風に困っているのかはどうしても説明できませんでした。
――すでに診断されていた発達障害とは、沖田さんの中で結びついていなかったのですね。
沖田:今になってみれば、それが発達障害を自覚したときだったと思うのですが、当時は自分に発達障害があるということも全部頭から抜けてしまっていましたね。わたしには、自分と特性の似た、不登校経験のある弟がいて。彼みたいな状態こそが「発達障害」なのだと思っていたんです。弟とは似ているところも多い分、昔はすごく嫌っていたので、かえって発達障害フォビア(憎悪)のようになっていた面もあると思います。
そうやって、原因はわからないながらも自分は人と違うんだと思っていたころ、同い年の看護師の先輩に「本当に役に立たないね」と言われたんです。同い年だから余計につらくて。その人に「死ね! ハゲ!」などと言われたときに、「もう死んじゃおう」と、一度自殺未遂をしてしまいました。
ロープが切れて自殺には失敗し、「ああ、今日死ぬ予定だったのに死ねなかった」とがっくりしました。でも「とりあえずルーティーンをしよう」と、いつも通り病院に行ったんです。上司に怒られながら仕事をして、家に帰ってからはめちゃくちゃになった部屋を片付けていたら、なんか、やっと…「わたし、病院以外のところでも生きていけるかもしれない」と思い始めました。その日からが、おまけの人生みたいな感じになったのかな。
それでも、当時は看護師をメインの仕事に据えていました。本当は看護師の仕事に一生を捧げたかったんですが、正看護師として美容整形科で仕事を初めて3日目ぐらいで、初めて「人と違う」という自覚が出てきたんです。22歳のときでした。
――「人と違う」というのは、どういう感覚ですか? 小学生での、周りがロボットに思えるという感覚とは違うものでしょうか。
沖田:日本語はわかるのに、相手が何を言っているかわからないことが多々あったんです。みんなが何か一言言われるだけで動けているときに、自分だけわからないという問題が、すごくはっきり出てきました。学生時代は「わたしはいいかげんな性格だから」とすませていましたが、国家試験にも受かって准看護師から正看護師になっている今回は、「あれ?」と思いました。
そのとき、自分の頭にはごそっと何かが足りなくて、それが補えずに苦しんでいるんだなとぼんやりわかったんです。それでも、具体的にどんな風に困っているのかはどうしても説明できませんでした。
――すでに診断されていた発達障害とは、沖田さんの中で結びついていなかったのですね。
沖田:今になってみれば、それが発達障害を自覚したときだったと思うのですが、当時は自分に発達障害があるということも全部頭から抜けてしまっていましたね。わたしには、自分と特性の似た、不登校経験のある弟がいて。彼みたいな状態こそが「発達障害」なのだと思っていたんです。弟とは似ているところも多い分、昔はすごく嫌っていたので、かえって発達障害フォビア(憎悪)のようになっていた面もあると思います。
そうやって、原因はわからないながらも自分は人と違うんだと思っていたころ、同い年の看護師の先輩に「本当に役に立たないね」と言われたんです。同い年だから余計につらくて。その人に「死ね! ハゲ!」などと言われたときに、「もう死んじゃおう」と、一度自殺未遂をしてしまいました。
ロープが切れて自殺には失敗し、「ああ、今日死ぬ予定だったのに死ねなかった」とがっくりしました。でも「とりあえずルーティーンをしよう」と、いつも通り病院に行ったんです。上司に怒られながら仕事をして、家に帰ってからはめちゃくちゃになった部屋を片付けていたら、なんか、やっと…「わたし、病院以外のところでも生きていけるかもしれない」と思い始めました。その日からが、おまけの人生みたいな感じになったのかな。
トーン貼りにハマり、4コマを描いたのがきっかけで漫画家に
――その後はどうされたのですか?
沖田:これをきっかけに本格的にリセットし、親の手の届かない、知らない土地でイチからやり直そうと、看護師を辞めて名古屋へ向かいました。23歳のときです。しばらくはまた性風俗業で働いていたのですが、当時の彼氏が漫画が好きで。彼の持ってきたルポ漫画がものすごく面白くて、ファンレターを送ったのが、現在の夫との出会いでした。
電話をしたり、会って話したりする中で、夫がわたしを面白いと気に入ってくれたようで。東京に来ないかと誘われたときは一瞬考えましたが、そのほうが面白そうだと思って行くことを決めました。
そのときはまだ、漫画は何もやっていません。夫と一緒に暮らすようになったときに、初めて漫画のトーン貼りを手伝って、「もっとない?」「わたし一生これで生きていく!」と言うぐらいハマってしまいました(笑)。
沖田:これをきっかけに本格的にリセットし、親の手の届かない、知らない土地でイチからやり直そうと、看護師を辞めて名古屋へ向かいました。23歳のときです。しばらくはまた性風俗業で働いていたのですが、当時の彼氏が漫画が好きで。彼の持ってきたルポ漫画がものすごく面白くて、ファンレターを送ったのが、現在の夫との出会いでした。
電話をしたり、会って話したりする中で、夫がわたしを面白いと気に入ってくれたようで。東京に来ないかと誘われたときは一瞬考えましたが、そのほうが面白そうだと思って行くことを決めました。
そのときはまだ、漫画は何もやっていません。夫と一緒に暮らすようになったときに、初めて漫画のトーン貼りを手伝って、「もっとない?」「わたし一生これで生きていく!」と言うぐらいハマってしまいました(笑)。
――トーン貼りを手伝っていたところから、どのようにしてご自身も漫画家になろうと思ったのでしょうか。
沖田:ある日、わたしがあまりにも「暇だ」と言うので、彼が4コマの枠だけを出して「これで何か描いてみてよ」って言ったんです。そうしたら、わたしは5分で書き上げたらしくて。それを見た彼が「お前、漫画家になれ」って。そのたった一言で漫画家になりました。わたしはコマが4つしかないからラッキーと思ったのですが、4コマ漫画って描くのが難しいらしいんですね。その時点で、漫画の基礎ができていたみたいです。
ただ、絵は全然ダメで。4コママンガの中でキャラクターがどんどん痩せていって、4コマ目には別人になっているんです。左右の区別がつかないので、指の位置を逆に描いてしまうこともありますし。書けない文字がたくさんあることにも、漫画を描き始めてから気づきました。自分で漫画にセリフを書き込んだら、4コマ漫画なのに30個も赤字で修正が入っていたんです(笑)。とくに横の線は苦手で、ペンネームである沖田×華の「華」の字も3年ぐらい間違っていました。
同じ字を何度も修正しているうちに、「見え方が他の人と違っているようだ」ということにもやっと気づきました。横線が動いたり、滲んだり、広がったりして見えるんですよ。どうも明朝体はダメらしくて。学習障害の一種であるディスレクシアも、そこで初めて自覚することになりました。ゴシック体だと理解できることは、最近わかりましたね。
沖田:ある日、わたしがあまりにも「暇だ」と言うので、彼が4コマの枠だけを出して「これで何か描いてみてよ」って言ったんです。そうしたら、わたしは5分で書き上げたらしくて。それを見た彼が「お前、漫画家になれ」って。そのたった一言で漫画家になりました。わたしはコマが4つしかないからラッキーと思ったのですが、4コマ漫画って描くのが難しいらしいんですね。その時点で、漫画の基礎ができていたみたいです。
ただ、絵は全然ダメで。4コママンガの中でキャラクターがどんどん痩せていって、4コマ目には別人になっているんです。左右の区別がつかないので、指の位置を逆に描いてしまうこともありますし。書けない文字がたくさんあることにも、漫画を描き始めてから気づきました。自分で漫画にセリフを書き込んだら、4コマ漫画なのに30個も赤字で修正が入っていたんです(笑)。とくに横の線は苦手で、ペンネームである沖田×華の「華」の字も3年ぐらい間違っていました。
同じ字を何度も修正しているうちに、「見え方が他の人と違っているようだ」ということにもやっと気づきました。横線が動いたり、滲んだり、広がったりして見えるんですよ。どうも明朝体はダメらしくて。学習障害の一種であるディスレクシアも、そこで初めて自覚することになりました。ゴシック体だと理解できることは、最近わかりましたね。
漫画家になったのは、「異世界転生」レベルの変化。湧いてくるアイデアをすくい、編集者と仕分けして漫画をつくる
――他のお仕事も経験した上で漫画家になった沖田さんですが、漫画家という働き方はいかがでしたか?
沖田:まったく怒られなくなったのには驚きましたね。締め切りを守るのは大前提ですが、わたしが出したものに対して、基本的に誰も文句を言わないんですよ。本当は不満もあるのかもしれませんが(笑)、言ってはこない。それがすごく新鮮で、別の世界に転生してきたようなレベルでしたね。
どの仕事も、つまずくときは仕事内容そのものというより人間関係ですよ。漫画家のすごくいいところは、上司も部下もいないところですが、代わりにアシスタントや編集者との関わりがあります。わたしの場合、デビュー時に、同業者である夫が、アシスタントや編集者とのコミュニケーションの仕方を教えてくれました。
わたし、アシスタントのことを友達みたいに思っちゃうんですよね。「疲れました」と言われたら「あ、いいよ、それやっておくよ」と言うような、なあなあの関係になってしまう。仕事をしてくれるのが嬉しくて、アシスタントの言うことをどんどん聞いてしまうんですが、本当はそういうのはよくないんですよね。仕事上の立ち位置を理解するのは、少し難しいです。
漫画をよいものにしていく中で、修正を編集者から頼まれることもあります。「ここはこういう風に直してほしい」と言われた際、最初に思ってしまうのは、「この人はわたしのことが嫌いだからこんなことを言うんだ」ということなんです。そういう考え方のクセがあるんですね。でも、そうやって友達みたいな関係として捉えていると、「じゃあわたしも嫌いになってやる!」となってしまうので、作品をつくる上でよろしくない。
そういうときは、夫が「編集者は友達じゃありませんよ」「仕事だから仕方なく!」って教えてくれるんです。そう言われると、編集さんが調子の良くない日もニコニコしたり、ご飯を一緒に食べたりするのも理解できて、関係性をとらえ直せます。そして、「そっか、これは仕事なんだ」「漫画をよくするための直しの要求なんだ」と納得して、うまく仕事のやり取りができるようになるんです。夫はいつも、自身の昔のしくじりを元に、怒鳴らずいろんな方向から説明してくれますね。
沖田:まったく怒られなくなったのには驚きましたね。締め切りを守るのは大前提ですが、わたしが出したものに対して、基本的に誰も文句を言わないんですよ。本当は不満もあるのかもしれませんが(笑)、言ってはこない。それがすごく新鮮で、別の世界に転生してきたようなレベルでしたね。
どの仕事も、つまずくときは仕事内容そのものというより人間関係ですよ。漫画家のすごくいいところは、上司も部下もいないところですが、代わりにアシスタントや編集者との関わりがあります。わたしの場合、デビュー時に、同業者である夫が、アシスタントや編集者とのコミュニケーションの仕方を教えてくれました。
わたし、アシスタントのことを友達みたいに思っちゃうんですよね。「疲れました」と言われたら「あ、いいよ、それやっておくよ」と言うような、なあなあの関係になってしまう。仕事をしてくれるのが嬉しくて、アシスタントの言うことをどんどん聞いてしまうんですが、本当はそういうのはよくないんですよね。仕事上の立ち位置を理解するのは、少し難しいです。
漫画をよいものにしていく中で、修正を編集者から頼まれることもあります。「ここはこういう風に直してほしい」と言われた際、最初に思ってしまうのは、「この人はわたしのことが嫌いだからこんなことを言うんだ」ということなんです。そういう考え方のクセがあるんですね。でも、そうやって友達みたいな関係として捉えていると、「じゃあわたしも嫌いになってやる!」となってしまうので、作品をつくる上でよろしくない。
そういうときは、夫が「編集者は友達じゃありませんよ」「仕事だから仕方なく!」って教えてくれるんです。そう言われると、編集さんが調子の良くない日もニコニコしたり、ご飯を一緒に食べたりするのも理解できて、関係性をとらえ直せます。そして、「そっか、これは仕事なんだ」「漫画をよくするための直しの要求なんだ」と納得して、うまく仕事のやり取りができるようになるんです。夫はいつも、自身の昔のしくじりを元に、怒鳴らずいろんな方向から説明してくれますね。
――漫画を描くときに、どんなことを考えているのかもぜひお聞きしたいです。最近では、4コマやコミックエッセイだけでなく、ストーリーものの漫画も描かれていますよね。
沖田:ストーリー漫画を描くことになったときは、どうやって描けばいいんだろうと途方に暮れましたね。編集担当さんが、ものすごく根気よく教えてくれました。
先日、最終回を迎えた『透明なゆりかご』は、ネームにすごく時間がかかっていました。わたしは、そのコマ1つに一点集中型。今どんな話が広がっているのか、描いている最中はまったくわからないんです。それを見て、編集さんが「あ、見えてきました」とか言うので、わたしは「何も見えないじゃない」と思うんですが(笑)。これで話が繋がっているのかなと半信半疑で描いて、いざ掲載されたものを見ると、ちゃんと漫画になっているんですよ。そういうズレみたいなものがあります。
だから、わたしは編集さんに「直して」と言われたら、「はい」と直すんです。多くの漫画家さんは、自分の作品への愛ゆえにこだわりがあって、編集者と衝突することも多いと聞きますが、わたしはまったくそういうことはなく。その道のプロである編集さんのほうが正しいだろうと思うんですよね。
――そこを割り切っているのはすごいですね。
沖田:ADHDの特性なのか、自分が描いたキャラクターや、その名前も忘れちゃうんですよ。キャラクターが5人程度でも、過去の単行本を引っ張り出してキャラを確認しています。
『透明なゆりかご』については、読者さんから「泣いた」という感想をよくいただきますが、自分は泣いたことがなくて。他人のことが描かれているのに、なぜ泣くのかは不思議なのですが…きっと何か、思うことがあるんですよね。わたしはそういった共感がなく、看護師としての経験があるとはいえ、妊娠・中絶は経験していませんが、「それでも描けるんだ!」と今回わかりました。
だからといって、適当に描いているわけではないんです。ADHDの脳みその特徴のようなものだと思うのですが、常にアイデアがポコポコとあぶくみたいに出ている状態で。それをすくってポイッと出し、編集さんと一緒に仕分けするのが、わたしの漫画の描き方です。今は、20ページぐらいの漫画であれば半日ほどでストーリーの構成ができるようになりました。
沖田:ストーリー漫画を描くことになったときは、どうやって描けばいいんだろうと途方に暮れましたね。編集担当さんが、ものすごく根気よく教えてくれました。
先日、最終回を迎えた『透明なゆりかご』は、ネームにすごく時間がかかっていました。わたしは、そのコマ1つに一点集中型。今どんな話が広がっているのか、描いている最中はまったくわからないんです。それを見て、編集さんが「あ、見えてきました」とか言うので、わたしは「何も見えないじゃない」と思うんですが(笑)。これで話が繋がっているのかなと半信半疑で描いて、いざ掲載されたものを見ると、ちゃんと漫画になっているんですよ。そういうズレみたいなものがあります。
だから、わたしは編集さんに「直して」と言われたら、「はい」と直すんです。多くの漫画家さんは、自分の作品への愛ゆえにこだわりがあって、編集者と衝突することも多いと聞きますが、わたしはまったくそういうことはなく。その道のプロである編集さんのほうが正しいだろうと思うんですよね。
――そこを割り切っているのはすごいですね。
沖田:ADHDの特性なのか、自分が描いたキャラクターや、その名前も忘れちゃうんですよ。キャラクターが5人程度でも、過去の単行本を引っ張り出してキャラを確認しています。
『透明なゆりかご』については、読者さんから「泣いた」という感想をよくいただきますが、自分は泣いたことがなくて。他人のことが描かれているのに、なぜ泣くのかは不思議なのですが…きっと何か、思うことがあるんですよね。わたしはそういった共感がなく、看護師としての経験があるとはいえ、妊娠・中絶は経験していませんが、「それでも描けるんだ!」と今回わかりました。
だからといって、適当に描いているわけではないんです。ADHDの脳みその特徴のようなものだと思うのですが、常にアイデアがポコポコとあぶくみたいに出ている状態で。それをすくってポイッと出し、編集さんと一緒に仕分けするのが、わたしの漫画の描き方です。今は、20ページぐらいの漫画であれば半日ほどでストーリーの構成ができるようになりました。