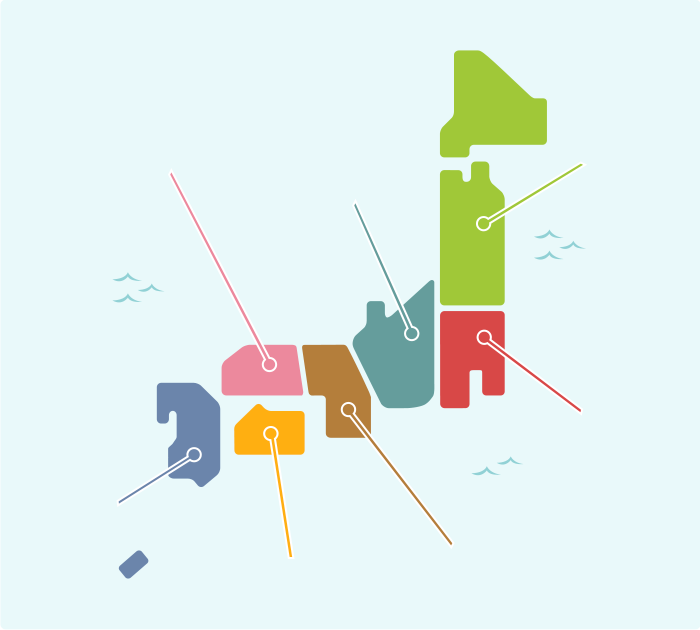小島慶子さん取材。「助けて」が言えなかった子ども時代。天職との出合いや、41歳で発達障害と分かるまでの苦悩も
ライター:発達ナビ編集部

Upload By 発達ナビ編集部
ADHDの診断のある、エッセイストの小島慶子さん。困っていた子ども時代を経て大人になり、アナウンサーという仕事に就いたのち、独立してエッセイストとしても活躍する一方で、生きづらさと向き合ってきました。子どものころの自分に、かけてあげたい言葉とは? 「LITALICO発達ナビ」牟田暁子編集長がお話を伺いました。
情報が頭の中で書き変わる、集中している対象以外の情報が脳に届かない
牟田暁子LITALICO発達ナビ編集長(以下――)小島さんはご自身にADHDの特性があると公にされていますが、ご自身の特性を感じるエピソードについて教えていただけますか。
小島慶子さん(以下、小島): 今日も、リアルの取材だってわかっていたのに、家で原稿を書いているうちに、オンライン取材だと頭の中で予定が書き変わっていたんです。昼過ぎにマネージャーから「15時から中目黒での取材、頑張ってくださいね」と連絡が入って、「あ!リアル取材だった!」と思い出してあわてて支度するという。スケジュール管理が難しくて、何重にもリマインダーを用意しておかないと、こんな風に情報が書き変わったり、抜け落ちたりするんです。
――それは子どものころからですか。
小島:そうです。なんで間に合わないんだろう、どうして勘違いしたんだろう、これは魔法?と思うくらい。情報がすぐ書き変わってしまうのはもしかしたら、ワーキングメモリーが弱いからかもしれません。そして、過集中になっているときには、集中している対象以外のことについて横から何か言われても、脳に届かない状態なんです。
ただ、過集中のときも、私はどうやらリアクションは普通らしくて、何か言われると「わかりましたー!」と返事をしている。それで相手はこれで伝わったと思っているけれど、私の頭には入っていないという具合です。見たもの聞いたものが目と耳で止まっていて、脳まで届いていない感覚です。
――今はスマホなどでさまざまなリマインダーがありますが、子ども時代や学生時代はどうされていましたか。
小島:大事なことは紙に書いて壁に貼ったり手に書いたりしていましたけど、それでもうまくいかないこともありました。私が子どもだった1970年代から80年代当時、まだ発達障害はほとんど知られていなかったので、とにかく困った子どもだと思われていました。
面白そうなことを見つけると、後先考えずにそっちに行ってしまったり、不用意な発言で友達を傷つけたり、場がシーンとなっちゃったり。いわゆる空気が読めない子どもだったから、いじめのターゲットになったこともありました。もちろん、いじめは発達障害の特性があったからというだけでなく、転校生だったことや背が高いことなど、複合的な要因によるものだと思いますが。
そうした経験があって、「どうやら、思いついたことをそのまま言ってはいけないらしい」などと、うまくやっていくための工夫を、傷だらけになりながら学習してきました。
小島慶子さん(以下、小島): 今日も、リアルの取材だってわかっていたのに、家で原稿を書いているうちに、オンライン取材だと頭の中で予定が書き変わっていたんです。昼過ぎにマネージャーから「15時から中目黒での取材、頑張ってくださいね」と連絡が入って、「あ!リアル取材だった!」と思い出してあわてて支度するという。スケジュール管理が難しくて、何重にもリマインダーを用意しておかないと、こんな風に情報が書き変わったり、抜け落ちたりするんです。
――それは子どものころからですか。
小島:そうです。なんで間に合わないんだろう、どうして勘違いしたんだろう、これは魔法?と思うくらい。情報がすぐ書き変わってしまうのはもしかしたら、ワーキングメモリーが弱いからかもしれません。そして、過集中になっているときには、集中している対象以外のことについて横から何か言われても、脳に届かない状態なんです。
ただ、過集中のときも、私はどうやらリアクションは普通らしくて、何か言われると「わかりましたー!」と返事をしている。それで相手はこれで伝わったと思っているけれど、私の頭には入っていないという具合です。見たもの聞いたものが目と耳で止まっていて、脳まで届いていない感覚です。
――今はスマホなどでさまざまなリマインダーがありますが、子ども時代や学生時代はどうされていましたか。
小島:大事なことは紙に書いて壁に貼ったり手に書いたりしていましたけど、それでもうまくいかないこともありました。私が子どもだった1970年代から80年代当時、まだ発達障害はほとんど知られていなかったので、とにかく困った子どもだと思われていました。
面白そうなことを見つけると、後先考えずにそっちに行ってしまったり、不用意な発言で友達を傷つけたり、場がシーンとなっちゃったり。いわゆる空気が読めない子どもだったから、いじめのターゲットになったこともありました。もちろん、いじめは発達障害の特性があったからというだけでなく、転校生だったことや背が高いことなど、複合的な要因によるものだと思いますが。
そうした経験があって、「どうやら、思いついたことをそのまま言ってはいけないらしい」などと、うまくやっていくための工夫を、傷だらけになりながら学習してきました。
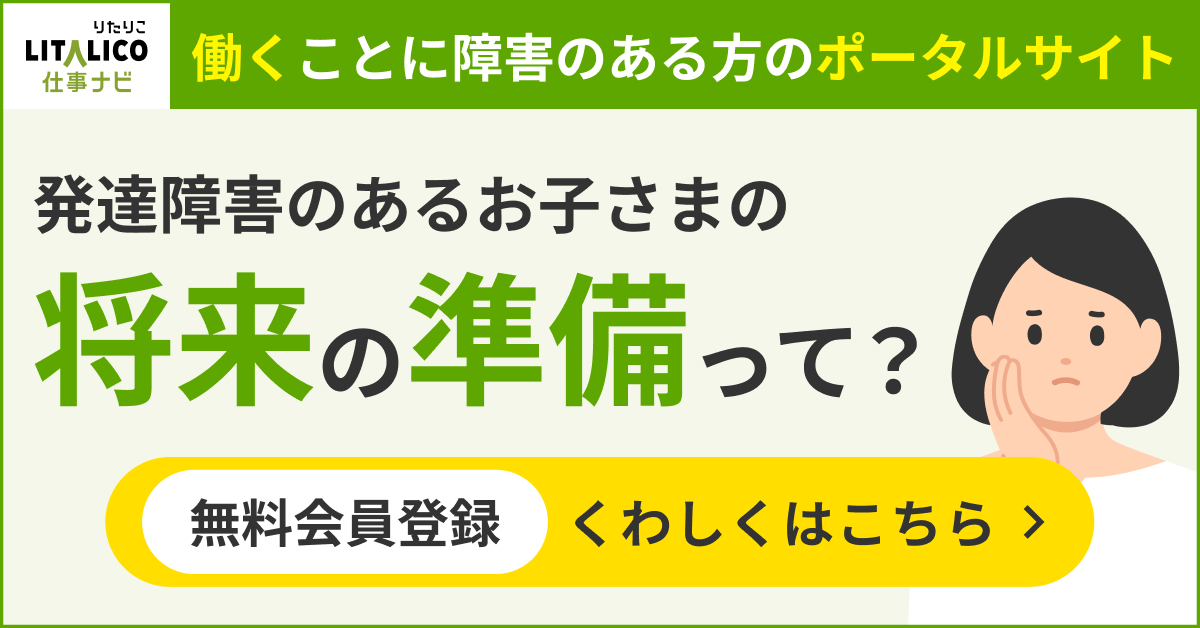
「助けて」と言えない環境だった子ども時代
――そんな小島さんは、家庭の中でどんなふうに育てられたのでしょうか。
小島:私の親は1930年代生まれで、子育てしていたのは1960~90年代。発達障害のことなんて知られていないし、私みたいな子どもを育てるのはほんとに大変だったろうと思います。だけど、あとから思うと、子どもが発達障害であろうとなかろうと、「なんで普通にできないの?」と聞かれるのはかなり重たいことでした。
私は、“わがままでひねくれていて、すぐご機嫌ななめになってしまう子ども”。母は、「どうして慶子はこんなに育てにくいのかしら」と悩んだのでしょう。よく「なんで普通にできないの」と言っていました。母も苦しかったでしょうし、両親を責めることはできませんが、適切な言葉がけではなかったと思います。
子どもの私にしてみたら話を聞いてほしいのに、「ひねくれている」といわれて話を聞いてすらもらえなくて、ますます機嫌が悪くなるという悪循環でした。
――「普通」って重い言葉ですよね。
小島:今考えると、両親が「普通」と呼んだものは青い鳥みたいなものでした。多分、みんながニコニコ笑っていつも仲良く、何のトラブルもない家庭を「普通」とイメージしていたんだと思います。
両親は東京の貧しい家庭に育ち、家族との関係でも苦労していました。戦争で空襲や疎開を経験し、戦後は日本の経済成長とともに、一歩一歩豊かになってきた人たちです。あんなに貧しかった自分たちが、マイカーやマイホームを手に入れることができたという喜びがあったのだと思います。だからこそ、ホームドラマに出てくるような絵になる素敵な家庭への憧れが強くあって、あの時代の集団幻想みたいなものを「普通」と呼んだのかもしれません。
小島:私の親は1930年代生まれで、子育てしていたのは1960~90年代。発達障害のことなんて知られていないし、私みたいな子どもを育てるのはほんとに大変だったろうと思います。だけど、あとから思うと、子どもが発達障害であろうとなかろうと、「なんで普通にできないの?」と聞かれるのはかなり重たいことでした。
私は、“わがままでひねくれていて、すぐご機嫌ななめになってしまう子ども”。母は、「どうして慶子はこんなに育てにくいのかしら」と悩んだのでしょう。よく「なんで普通にできないの」と言っていました。母も苦しかったでしょうし、両親を責めることはできませんが、適切な言葉がけではなかったと思います。
子どもの私にしてみたら話を聞いてほしいのに、「ひねくれている」といわれて話を聞いてすらもらえなくて、ますます機嫌が悪くなるという悪循環でした。
――「普通」って重い言葉ですよね。
小島:今考えると、両親が「普通」と呼んだものは青い鳥みたいなものでした。多分、みんながニコニコ笑っていつも仲良く、何のトラブルもない家庭を「普通」とイメージしていたんだと思います。
両親は東京の貧しい家庭に育ち、家族との関係でも苦労していました。戦争で空襲や疎開を経験し、戦後は日本の経済成長とともに、一歩一歩豊かになってきた人たちです。あんなに貧しかった自分たちが、マイカーやマイホームを手に入れることができたという喜びがあったのだと思います。だからこそ、ホームドラマに出てくるような絵になる素敵な家庭への憧れが強くあって、あの時代の集団幻想みたいなものを「普通」と呼んだのかもしれません。
暗黒の中学時代、生まれ変わろうとした高校時代
――中学校、高校時代は、どのように過ごしてこられましたか。
小島:人間関係がうまくいかなかった中学3年間は、暗黒時代でした。自分も世界も全部消えればいいのにと思っていました。
私が通っていたのは私立の中高一貫校で、当時はいわゆるバブル全盛期。とにかく周りのみんなが眩しく見えたんです。お金持ちのうえに、可愛くておしゃれで成績もよくて、あげくに性格もいい、そんな子たちが羨ましくて。授業中に前に座る友人のセーラー服の四角い襟をジーっと見つめて、じっとり鬱々としていました。「妬ましい…」って。
でも、中学3年生になるころには妬むのに疲れちゃって。一貫校だったんですが、高校になったら校舎も移るし、「よし、生まれ変わろう」と決意しました。で、人に好かれる友人の会話をじっくり観察したんです。ほほう、このタイミングで笑うんだ、ここでそういうリアクションするんだ…と学習しました。
高等科になって、学習したことを実践。まずは挑戦しやすそうな、“無口な人”になる。生来のおしゃべりである私にとっては新鮮な体験でした。とにかく黙る。誰かに話を振られるまでは口を開かない、ニコニコしてただ「おもしろーい」と言うだけ。たった1ヶ月、無口チャレンジをやったところで、「慶子ちゃん、おとなしいよね」なんて言われるようになったんです。中等科3年間の私のトンガリぶりを見ていたはずの同級生たちが、たった1ヶ月で私を「おとなしい子」だと信じてしまう。人はこんなに簡単に、評価を変えるものなのかと思いました。
そこで次に、笑い方や発声、リアクションも変えてみました。古典芸能と同じ。「型」から入って、次第に自分のものになっていくのですね。あとから思うと、これは衝動性をコントロールするためのひとつの効果的な方法だったんじゃないかと思います。無口な人とかふわふわした人とか、どの型もうまくいくようになって、そうか、相手や状況によって使い分ければいいんだ!と学びました。
1年が終わるころには、いちいち考えずに今と同じように普段の自分を出しても、トラブルが起きなくなって、友人たちに受け入れてもらえるようになりました。自分の特性をコントロールするコツをつかんだということかもしれません。
小島:人間関係がうまくいかなかった中学3年間は、暗黒時代でした。自分も世界も全部消えればいいのにと思っていました。
私が通っていたのは私立の中高一貫校で、当時はいわゆるバブル全盛期。とにかく周りのみんなが眩しく見えたんです。お金持ちのうえに、可愛くておしゃれで成績もよくて、あげくに性格もいい、そんな子たちが羨ましくて。授業中に前に座る友人のセーラー服の四角い襟をジーっと見つめて、じっとり鬱々としていました。「妬ましい…」って。
でも、中学3年生になるころには妬むのに疲れちゃって。一貫校だったんですが、高校になったら校舎も移るし、「よし、生まれ変わろう」と決意しました。で、人に好かれる友人の会話をじっくり観察したんです。ほほう、このタイミングで笑うんだ、ここでそういうリアクションするんだ…と学習しました。
高等科になって、学習したことを実践。まずは挑戦しやすそうな、“無口な人”になる。生来のおしゃべりである私にとっては新鮮な体験でした。とにかく黙る。誰かに話を振られるまでは口を開かない、ニコニコしてただ「おもしろーい」と言うだけ。たった1ヶ月、無口チャレンジをやったところで、「慶子ちゃん、おとなしいよね」なんて言われるようになったんです。中等科3年間の私のトンガリぶりを見ていたはずの同級生たちが、たった1ヶ月で私を「おとなしい子」だと信じてしまう。人はこんなに簡単に、評価を変えるものなのかと思いました。
そこで次に、笑い方や発声、リアクションも変えてみました。古典芸能と同じ。「型」から入って、次第に自分のものになっていくのですね。あとから思うと、これは衝動性をコントロールするためのひとつの効果的な方法だったんじゃないかと思います。無口な人とかふわふわした人とか、どの型もうまくいくようになって、そうか、相手や状況によって使い分ければいいんだ!と学びました。
1年が終わるころには、いちいち考えずに今と同じように普段の自分を出しても、トラブルが起きなくなって、友人たちに受け入れてもらえるようになりました。自分の特性をコントロールするコツをつかんだということかもしれません。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています