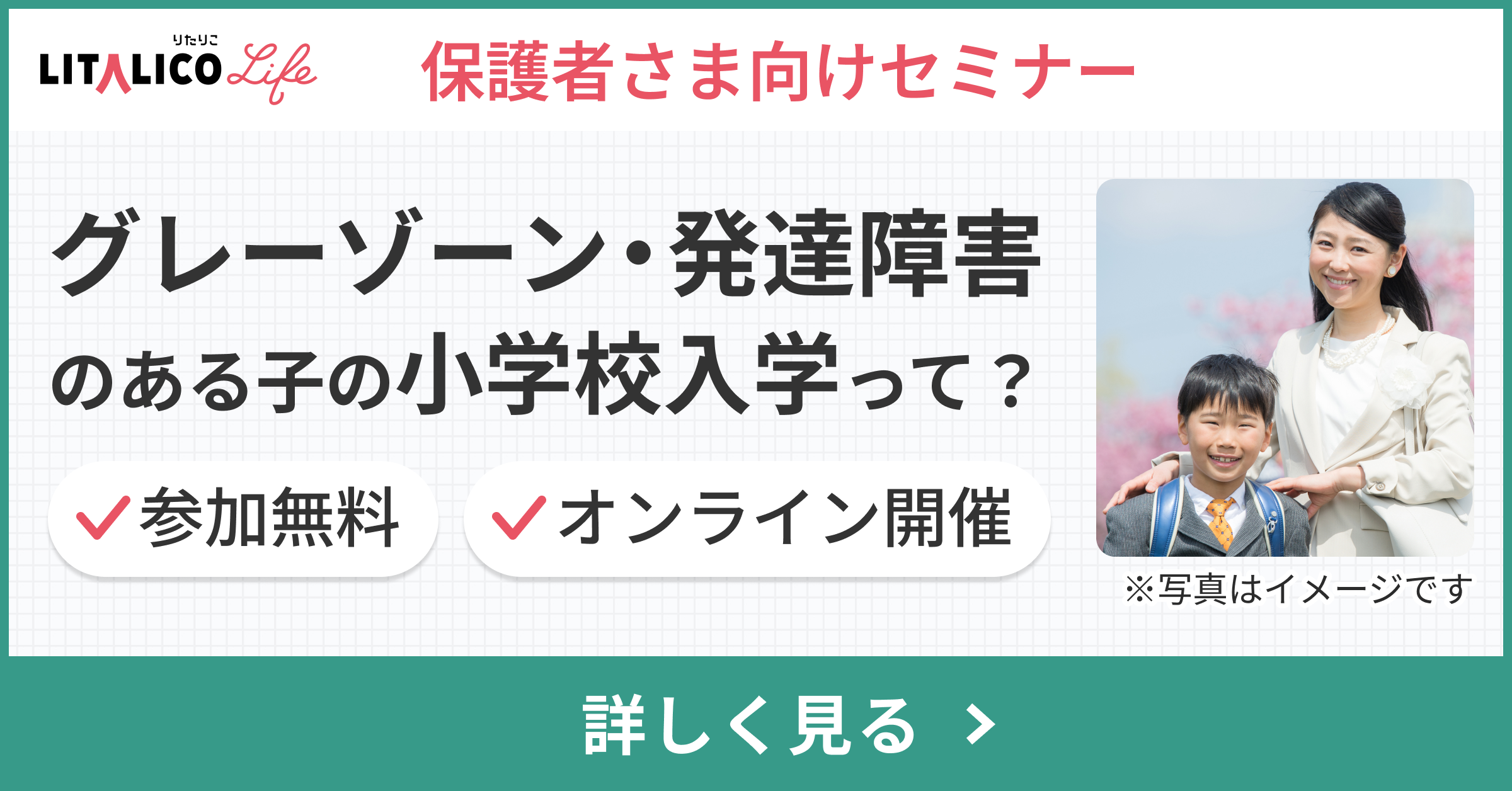小学校では宿題を「ほぼ放置」!?ASD兄妹、高校・大学ではどうなった?
ライター:寺島ヒロ

Upload By 寺島ヒロ
お子さん、宿題やりますか?わが家はほぼほぼやりません。特に小学生低学年の頃は全然やりませんでした。発達障害のある子どもたちの場合、宿題が思うように進まないことは日常茶飯事です。親としては「宿題をちゃんとやらせなきゃ」とつい力んでしまうところですが……。今回はわが家のASD(自閉スペクトラム症)の子どもたちが「なぜ」宿題をやらなかったのか、その後どうなったのかという話です。

監修: 初川久美子
臨床心理士・公認心理師
東京都公立学校スクールカウンセラー/発達研修ユニットみつばち
臨床心理士・公認心理師。早稲田大学大学院人間科学研究科修了。在学中よりスクールカウンセリングを学び、臨床心理士資格取得後よりスクールカウンセラーとして勤務。児童精神科医の三木崇弘とともに「発達研修ユニットみつばち」を結成し、教員向け・保護者向け・専門家向け研修・講演講師も行っている。都内公立教育相談室にて教育相談員兼務。
東京都公立学校スクールカウンセラー/発達研修ユニットみつばち
宿題なんかやってる暇がないータケルの場合
わが家の長男タケル(ASD/自閉スペクトラム症・現在25歳)には、幼稚園生の頃から毎日のルーティンを決めるという癖がありました。
「何時にこれをやる」と決めているのではなく「これの次にこれをやる」という形式なので、学校から帰ってくる時間が遅くなったり予定外の用事で出かけたりと、どこかで「作業」が長引くと宿題までたどり着けないということがよくありました。宿題の方を先にやればと言っても、それはダメなのです。タケルにはこの順番でなければという確固たる理由があるのです。
そこまで厳しくやることを決めているのに、タスクをやり残したまま寝かせてしまうのは比較的容認できるようです。「やろうと思ってたのにもう眠い……」とブツブツ言っていることもありますが、だからといって眠いのを我慢してやるということもありません。そもそも宿題の優先順位がタケルの中で高くなかったのでしょう。
体調や気持ちの不安定さもある
子どもの発達障害あるあるかもしれませんが、体調を崩しやすかったり情緒が不安定になったりすることも多いです。
本人にまあまあやる気があって、自分から宿題の前に座っても、数分で体をグニャグニャーンと揺らしながら床に倒れ込んでしまうこともありました。「何をしているの?」と言いたくなりますが、本人も「ボク、今どうなってるの?」という顔をしながら床でタコ踊りをしていました。
体を倒して背中や手足が伸びると「ちょっと気持ちいい」と感じ、動かすことに集中してしまって、そのうち宿題のことを忘れてしまうみたいです。放っておくとそのまま寝てしまうことも。多分疲れているのに自分で気がついていなかったんだなと思うので、そういう時は大抵そのまま寝かせていました。
夏休みの宿題は8割マッハで片づけて2割残す
妹のいっちゃんの場合は、毎日のプリントなどはしぶしぶやっていました。しかし、休んだ時の物は貯めがちで、提出期限ギリギリになってから、お兄ちゃん(この頃は成長し中学生になっていたので)に見てもらいながらやるというのが定番でした。
この「ちょっと面倒になると途端に手が出なくなる」傾向は、夏休みの宿題により顕著に現れます。いっちゃんは、最初に簡単にできそうな8割を一気にやってしまい、あとは完全に宿題の存在を忘れて過ごす。そして残った苦手な2割を最後の1日(と、次の週末)で「ヒイヒイ」言いながら取り組む──そんな感じでした(これを読んで「うちもそう!」と思う方も多いのではないでしょうか!)。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています