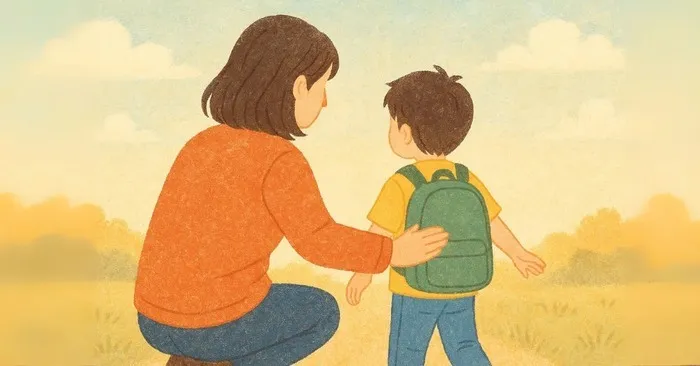
こんにちは(^^♪『かみか企画』です☆
発達障害のあるお子さんを育てていると、
「どうしてうまくいかないんだろう」「こんなに頑張っているのに…」
と感じることは少なくありません。
お子さんの特性を理解しようと努力しても、
思いがけず“すれ違い”が起きることがあります。
今回は、私たち支援の現場で感じる
「発達障害の子を育てる親の課題」を6つの視点から整理し、
少しでも心が軽くなるヒントをお伝えします。
⸻
🧩1.「自分の育てられ方」にとらわれてしまう
「自分の親は厳しかったから」「私は我慢してきたから」と、
自分が育てられた方法を基準に考えてしまうことがあります。
しかし、発達特性のある子どもは「感じ方」「理解の仕方」が違うため、
昔ながらのやり方ではうまくいかないことも。
それは親のせいではなく、育て方の“方向転換”が必要なだけです。
新しい関わり方を学ぶことは、愛情を形にする一歩です。
⸻
💞2.寄り添いすぎて共倒れしてしまう
子どもの気持ちに寄り添うことはとても大切。
でも、子どもの辛さに巻き込まれてしまうと、
親も疲れきってしまいます。
「一緒に苦しむ」のではなく、
「安心できる距離で見守る」ことが大事です。
親が心身ともに元気でいることが、
子どもにとって最大の支援になります。
🧠3.「よかれと思って」が裏目に出ることも
「失敗させたくない」「困らせたくない」という優しさから、
つい先回りしたり、手を出しすぎたりしてしまうことがあります。
でも、発達の土台は“経験”の積み重ねです。
小さな失敗も、子どもが自分で考える力や自信を育てます。
「見守る勇気」も、支援のひとつです。
🌧4.周囲に理解されず、孤立してしまう
「しつけが甘い」「親の責任」など、
周囲の理解不足に傷つく親御さんも多くいらっしゃいます。
同じ経験をしている仲間や、信頼できる支援者とつながることで、
「自分だけじゃない」と感じられる瞬間があります。
孤立しないこと、つながりを持つことが、親の心を守る大きな支えになります。
🌱5.親自身の特性に気づいていないことも
最近では、親自身にも発達特性があるケースも増えています。
感覚の敏感さ、完璧主義、急な変化が苦手など、
親子で似た傾向があると関わり方が難しくなることもあります。
「どうしてうまくいかないの?」と責めるのではなく、
自分の特性を理解し、得意・不得意を知ることが、
よりよい親子関係への第一歩になります。
🌼6.「普通にできるように」が目的になってしまう
「みんなと同じようにできるように」と焦るあまり、
本来の目的――子どもが安心して自分らしく生きること――を
見失ってしまうことがあります。そもそも普通てなんなんと思います💡
大切なのは、「できることを増やす」よりも「安心を増やす」こと。
焦らず、その子のペースを大切にしていきましょう。
💡💡安心をふやす💡💡これ本当一番大事かも
☘️まとめ
発達障害のあるお子さんを育てる親の課題は、
実は「頑張りすぎるほどに生まれる」ものが多いのです。
だからこそ、
「もう少し力を抜いても大丈夫」
「うまくできなくても、愛情はちゃんと届いている」
と、自分に優しく声をかけてあげてください。
私たち支援者は、子どもだけでなく、
お母さん・お父さんが安心できる場所をつくることを大切にしています。
一人で抱えず、いつでもご相談くださいね。
発達障害のあるお子さんを育てていると、
「どうしてうまくいかないんだろう」「こんなに頑張っているのに…」
と感じることは少なくありません。
お子さんの特性を理解しようと努力しても、
思いがけず“すれ違い”が起きることがあります。
今回は、私たち支援の現場で感じる
「発達障害の子を育てる親の課題」を6つの視点から整理し、
少しでも心が軽くなるヒントをお伝えします。
⸻
🧩1.「自分の育てられ方」にとらわれてしまう
「自分の親は厳しかったから」「私は我慢してきたから」と、
自分が育てられた方法を基準に考えてしまうことがあります。
しかし、発達特性のある子どもは「感じ方」「理解の仕方」が違うため、
昔ながらのやり方ではうまくいかないことも。
それは親のせいではなく、育て方の“方向転換”が必要なだけです。
新しい関わり方を学ぶことは、愛情を形にする一歩です。
⸻
💞2.寄り添いすぎて共倒れしてしまう
子どもの気持ちに寄り添うことはとても大切。
でも、子どもの辛さに巻き込まれてしまうと、
親も疲れきってしまいます。
「一緒に苦しむ」のではなく、
「安心できる距離で見守る」ことが大事です。
親が心身ともに元気でいることが、
子どもにとって最大の支援になります。
🧠3.「よかれと思って」が裏目に出ることも
「失敗させたくない」「困らせたくない」という優しさから、
つい先回りしたり、手を出しすぎたりしてしまうことがあります。
でも、発達の土台は“経験”の積み重ねです。
小さな失敗も、子どもが自分で考える力や自信を育てます。
「見守る勇気」も、支援のひとつです。
🌧4.周囲に理解されず、孤立してしまう
「しつけが甘い」「親の責任」など、
周囲の理解不足に傷つく親御さんも多くいらっしゃいます。
同じ経験をしている仲間や、信頼できる支援者とつながることで、
「自分だけじゃない」と感じられる瞬間があります。
孤立しないこと、つながりを持つことが、親の心を守る大きな支えになります。
🌱5.親自身の特性に気づいていないことも
最近では、親自身にも発達特性があるケースも増えています。
感覚の敏感さ、完璧主義、急な変化が苦手など、
親子で似た傾向があると関わり方が難しくなることもあります。
「どうしてうまくいかないの?」と責めるのではなく、
自分の特性を理解し、得意・不得意を知ることが、
よりよい親子関係への第一歩になります。
🌼6.「普通にできるように」が目的になってしまう
「みんなと同じようにできるように」と焦るあまり、
本来の目的――子どもが安心して自分らしく生きること――を
見失ってしまうことがあります。そもそも普通てなんなんと思います💡
大切なのは、「できることを増やす」よりも「安心を増やす」こと。
焦らず、その子のペースを大切にしていきましょう。
💡💡安心をふやす💡💡これ本当一番大事かも
☘️まとめ
発達障害のあるお子さんを育てる親の課題は、
実は「頑張りすぎるほどに生まれる」ものが多いのです。
だからこそ、
「もう少し力を抜いても大丈夫」
「うまくできなくても、愛情はちゃんと届いている」
と、自分に優しく声をかけてあげてください。
私たち支援者は、子どもだけでなく、
お母さん・お父さんが安心できる場所をつくることを大切にしています。
一人で抱えず、いつでもご相談くださいね。

