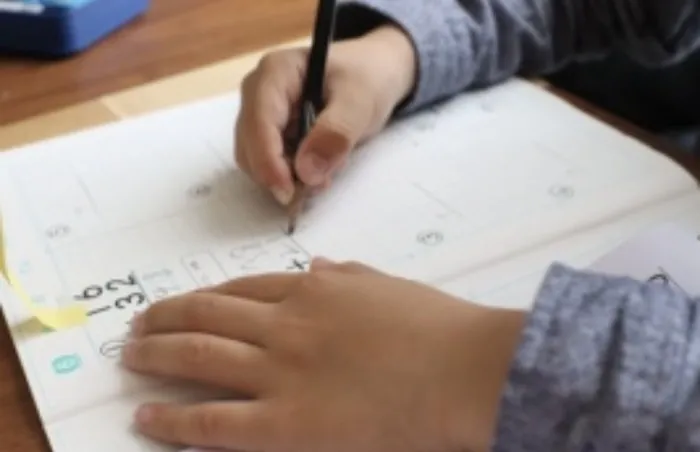
先日、感染症に関する研修に参加しました!
この冬の時期にはインフルエンザが流行しますが、それ以外にも気をつけておかないといけない感染症をご紹介したいと思います!
☆感染症の特徴
〇インフルエンザ
今最も代表的な感染症で、主な症状は突然の発熱(38℃以上)、頭痛、関節痛、倦怠感などの全身症状、咳、鼻汁などの上気道炎症状が出る病気です。
感染ルートは飛沫感染・接触感染で、潜伏期間は、1〜4日です。
〇新型コロナウイルス感染症
2020年の大流行も記憶に新しいですが、未だ感染者のいる感染症となります。主な症状は、発熱、咳、頭痛、嗅覚・味覚障害、咽頭痛、鼻汁などの上気道炎症状、下痢、倦怠感等が出る病気です。
感染ルートは、飛沫感染、エアロゾル感染(明確な定義はないが、飛沫感染と違い、つばの大きさが5μm以下でかつ飛沫より長く空気中にとどまる性質により感染すること)、接触感染で、潜伏期間は2〜3日です。
〇RSウイルス感染症
RSウイルスに感染することで発症する感染症です。主な症状は、発熱、鼻汁、咳、喘息、呼吸困難が出る病気です。
感染ルートは、飛沫感染、接触感染で、潜伏期間は4〜6日です。
〇溶連菌感染症
溶血性連鎖球菌がのどに感染して起こる病気で、主な症状は突然の発熱、咽頭痛、頭痛、胃腸症状(嘔吐、腹痛、下痢)、咳、鼻水、倦怠感、筋肉痛、関節痛です。下が白いコケで覆われたようになり、2〜5日後に赤くブツブツした「イチゴ舌」と呼ばれる状態になり、かゆみを伴う発疹が出てきます。1週間ほどで治まるが指先の皮膚がむけてきます。
感染ルートは、飛沫感染、接触感染で、潜伏期間は2〜5日です。
〇マイコプラズマ肺炎
肺炎マイコプラズマに感染することで発症する病気で、主な症状は、咳、発熱、頭痛の風邪症状がゆっくり進行し、徐々に咳が激しくなる。解熱後も咳が続き、肺炎が重症化する場合があります。
感染ルートは、飛沫感染、接触感染で、潜伏期間は2〜3週間です。
☆感染症の予防法
それぞれ感染の特徴について書きましたが、予防法について書きたいと思います!
1番効果的なのは手洗い、うがい(難しければ緑茶等を飲む)です。また、アルコール消毒や次亜塩素酸ナトリウムでの消毒も有効です。これらを行うことで、ある程度の感染は予防できると考えられます!
感染が疑われた場合には、マスクを着用し、感染を広げるのを防いだり(2歳未満は非推奨)、家庭内でタオルの併用を避けたりすることも家族内での感染を予防し、拡大を防ぐことができます!
にじいろぱれっとでも、感染の予防を徹底しつつ、かつ感染した場合拡大をしないよう、学んだことを実践し、支援に組み込んでいきます!
この冬の時期にはインフルエンザが流行しますが、それ以外にも気をつけておかないといけない感染症をご紹介したいと思います!
☆感染症の特徴
〇インフルエンザ
今最も代表的な感染症で、主な症状は突然の発熱(38℃以上)、頭痛、関節痛、倦怠感などの全身症状、咳、鼻汁などの上気道炎症状が出る病気です。
感染ルートは飛沫感染・接触感染で、潜伏期間は、1〜4日です。
〇新型コロナウイルス感染症
2020年の大流行も記憶に新しいですが、未だ感染者のいる感染症となります。主な症状は、発熱、咳、頭痛、嗅覚・味覚障害、咽頭痛、鼻汁などの上気道炎症状、下痢、倦怠感等が出る病気です。
感染ルートは、飛沫感染、エアロゾル感染(明確な定義はないが、飛沫感染と違い、つばの大きさが5μm以下でかつ飛沫より長く空気中にとどまる性質により感染すること)、接触感染で、潜伏期間は2〜3日です。
〇RSウイルス感染症
RSウイルスに感染することで発症する感染症です。主な症状は、発熱、鼻汁、咳、喘息、呼吸困難が出る病気です。
感染ルートは、飛沫感染、接触感染で、潜伏期間は4〜6日です。
〇溶連菌感染症
溶血性連鎖球菌がのどに感染して起こる病気で、主な症状は突然の発熱、咽頭痛、頭痛、胃腸症状(嘔吐、腹痛、下痢)、咳、鼻水、倦怠感、筋肉痛、関節痛です。下が白いコケで覆われたようになり、2〜5日後に赤くブツブツした「イチゴ舌」と呼ばれる状態になり、かゆみを伴う発疹が出てきます。1週間ほどで治まるが指先の皮膚がむけてきます。
感染ルートは、飛沫感染、接触感染で、潜伏期間は2〜5日です。
〇マイコプラズマ肺炎
肺炎マイコプラズマに感染することで発症する病気で、主な症状は、咳、発熱、頭痛の風邪症状がゆっくり進行し、徐々に咳が激しくなる。解熱後も咳が続き、肺炎が重症化する場合があります。
感染ルートは、飛沫感染、接触感染で、潜伏期間は2〜3週間です。
☆感染症の予防法
それぞれ感染の特徴について書きましたが、予防法について書きたいと思います!
1番効果的なのは手洗い、うがい(難しければ緑茶等を飲む)です。また、アルコール消毒や次亜塩素酸ナトリウムでの消毒も有効です。これらを行うことで、ある程度の感染は予防できると考えられます!
感染が疑われた場合には、マスクを着用し、感染を広げるのを防いだり(2歳未満は非推奨)、家庭内でタオルの併用を避けたりすることも家族内での感染を予防し、拡大を防ぐことができます!
にじいろぱれっとでも、感染の予防を徹底しつつ、かつ感染した場合拡大をしないよう、学んだことを実践し、支援に組み込んでいきます!

