自然な会話が生まれる!質問力が身につくカードゲームのすすめ
ライター:松本太一

Upload By 松本太一
アナログゲーム療育アドバイザーの松本太一です。今回は「質問するスキル」を身につけられるゲームをご紹介します。
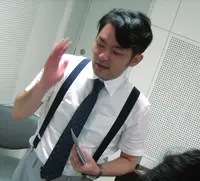
執筆: 松本太一
アナログゲーム療育アドバイザー
放課後等デイサービスコンサルタント
NPO法人グッド・トイ委員会認定おもちゃインストラクター
東京学芸大学大学院障害児教育専攻卒業(教育学修士)
フリーランスの療育アドバイザー。カードゲームやボードゲームを用いて、発達障害のある子のコミュニケーション力を伸ばす「アナログゲーム療育」を開発。各地の療育機関や支援団体で、実践・研修を行っている。
放課後等デイサービスコンサルタント
NPO法人グッド・トイ委員会認定おもちゃインストラクター
東京学芸大学大学院障害児教育専攻卒業(教育学修士)
子どもは6歳ごろから「工夫する力」が伸びてくる
お子さんは6歳を超えたあたりから、どうやったらゲームに勝てるのか、自分の頭で考え、工夫できるようになっていきます。
この時期に、「お互いに会話する」「物のやりとりをする」といったコミュニケーション要素を含むゲームで遊ぶことで、お子さんはゲームを楽しみながら、自然と上手なコミュニケーションを工夫する練習ができます。
この時期に、「お互いに会話する」「物のやりとりをする」といったコミュニケーション要素を含むゲームで遊ぶことで、お子さんはゲームを楽しみながら、自然と上手なコミュニケーションを工夫する練習ができます。
今回のゲームは「わたしはだあれ?」
今回ご紹介する「わたしはだあれ?」は、お子さんが楽しみながら「質問する力」を身につけられるゲームです。
様々な動物と、動物のきぐるみを着た子どものカードが16枚ずつ入っています。
ルールは複数あるのですが、私はこうやって療育に使うことが多いです。
①あるプレイヤーが、他のプレイヤーに見えないように、動物のカードを1枚ひきます。
②他のプレイヤーは、動物を当てるために質問をします。ただし質問内容は「はい・いいえ」で答えられるもの。
③わかったプレイヤーは、同じ動物のきぐるみを着た子どものカードを取ります。
➃正解ならば、そのカードを獲得できます。最後に一番多くカードを集めた人が勝ちです。
様々な動物と、動物のきぐるみを着た子どものカードが16枚ずつ入っています。
ルールは複数あるのですが、私はこうやって療育に使うことが多いです。
①あるプレイヤーが、他のプレイヤーに見えないように、動物のカードを1枚ひきます。
②他のプレイヤーは、動物を当てるために質問をします。ただし質問内容は「はい・いいえ」で答えられるもの。
③わかったプレイヤーは、同じ動物のきぐるみを着た子どものカードを取ります。
➃正解ならば、そのカードを獲得できます。最後に一番多くカードを集めた人が勝ちです。
年齢の違う5人で遊んでみた
このゲームを使った、コミュニケーション療育の様子をご紹介します。6歳の男の子が3人と、8歳の女の子2人の計5人で遊びました。
可愛らしい動物カードを見た6歳の子どもたちは興味津々。
しかし実際にゲームが始まり、質問を促されるとみんな黙ってしまいました。
実は、「質問する」というのは6歳のお子さんからすると中々難しい課題なのです。
可愛らしい動物カードを見た6歳の子どもたちは興味津々。
しかし実際にゲームが始まり、質問を促されるとみんな黙ってしまいました。
実は、「質問する」というのは6歳のお子さんからすると中々難しい課題なのです。
ここで活躍したのが小学生のお姉さんたち。
「くちばしはありますか」「人間が食べられますか」など、的確な質問を出し、正解をあてていきます。
それをみた6歳の男の子たちは、積極的に手をあげるようになりました。一人の子が、「くちばしはありますか」とお姉さんの質問を真似て繰り返しました。
「はい」と聞くと、「これだっ!」と自分の近くにあったカラスのカードを取りにいきます。
しかし残念、不正解。
くちばしがある動物はカラスの他にツルやニワトリがいるからです。ちなみにこのときの正解はツルでした。
そこで、私が「くちばしのある動物は他にもいるね。今回はツルが正解だったけど、どんな質問だったらそのことがわかったかな」と全体に向けて質問すると、お姉さんが「ツルはくちばしが一番長いから『くちばしは長いですか』と質問したら、わかると思う」と答えました。
6歳の子たちは次回から早速、お姉さんの意見に従って「くちばしは長いですか」という質問を繰り返し、彼らの中の一人が見事正解をあてることができました。
「くちばしはありますか」「人間が食べられますか」など、的確な質問を出し、正解をあてていきます。
それをみた6歳の男の子たちは、積極的に手をあげるようになりました。一人の子が、「くちばしはありますか」とお姉さんの質問を真似て繰り返しました。
「はい」と聞くと、「これだっ!」と自分の近くにあったカラスのカードを取りにいきます。
しかし残念、不正解。
くちばしがある動物はカラスの他にツルやニワトリがいるからです。ちなみにこのときの正解はツルでした。
そこで、私が「くちばしのある動物は他にもいるね。今回はツルが正解だったけど、どんな質問だったらそのことがわかったかな」と全体に向けて質問すると、お姉さんが「ツルはくちばしが一番長いから『くちばしは長いですか』と質問したら、わかると思う」と答えました。
6歳の子たちは次回から早速、お姉さんの意見に従って「くちばしは長いですか」という質問を繰り返し、彼らの中の一人が見事正解をあてることができました。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています




















