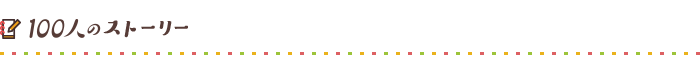今回は、ソニーコンピュータサイエンス研究所の研究員として、そして株式会社Xiborg(サイボーグ)の代表として、義足の研究開発をされている遠藤謙さんにお話をお伺いします。
ご自身が立ち上げたXiborg社の公式サイトには「すべての人に動く喜びを」と掲げ、「才能がない、障害を抱えている、高齢だからといって、この喜びが奪われる事はあってはならないと考えています。」とあります。
ご自身が立ち上げたXiborg社の公式サイトには「すべての人に動く喜びを」と掲げ、「才能がない、障害を抱えている、高齢だからといって、この喜びが奪われる事はあってはならないと考えています。」とあります。

出典:https://www.sonycsl.co.jp/member/tokyo/199/「人間の身体にはまだまだ隠された機能があります。それを引き出すことによって人間の生活スタイルは激変する可能性を秘めています。
例えば、損なわれた機能を補うだけでなく拡張することができれば、障がい者、健常者、高齢者の身体機能の境界線がなくなり、身体能力の欠如に対するネガティブな考え方も変えることができるのです。
私のゴールは、世の中から身体の障がいをなくすことです。」
そう語る遠藤さん。
一体どのような幼少期・学齢期を過ごしてきたのでしょうか。そのライフストーリーをお伺いしたいと思います。
一体どのような幼少期・学齢期を過ごしてきたのでしょうか。そのライフストーリーをお伺いしたいと思います。
なぜ「義足」の道を進んだのか?

編集部:遠藤さんがおっしゃる「世の中から身体の障がいをなくす」という言葉、とても共感しているんです。そのお話からまずは。
遠藤:ありがとうございます。僕は人の身体にまだまだ可能性があると思っているんですよ。目の前の目標としては、義足の開発を通して障害を無くしたいと考えてます。
2020年のとオリンピック・パラリンピックでは、障害の定義が「脚があるかないか」と関係なくなってくる。じゃあ、一体何が「障害」なんだろうとか、そういう議論が起こるだろうと。
編集部:義足の開発は、その議論を起こすきっかけになりそうですか?
遠藤:なると思います。具体的にいうと、今僕たちは陸上競技用の義足を作っているのですが、それはこれまでの義足のように「無い脚を埋める」だけの義足ではありません。
脚のない人が、義足によって「より自分の能力を引き出せる」ことを目指して作っている。陸上選手で言えば、「義足の方がより早く走れるようになる可能性を秘めている」ということです。
すると健常者のほうが障害者よりいいタイムが出るという、これまでの概念が崩れていくのではと考えています。
遠藤:ありがとうございます。僕は人の身体にまだまだ可能性があると思っているんですよ。目の前の目標としては、義足の開発を通して障害を無くしたいと考えてます。
2020年のとオリンピック・パラリンピックでは、障害の定義が「脚があるかないか」と関係なくなってくる。じゃあ、一体何が「障害」なんだろうとか、そういう議論が起こるだろうと。
編集部:義足の開発は、その議論を起こすきっかけになりそうですか?
遠藤:なると思います。具体的にいうと、今僕たちは陸上競技用の義足を作っているのですが、それはこれまでの義足のように「無い脚を埋める」だけの義足ではありません。
脚のない人が、義足によって「より自分の能力を引き出せる」ことを目指して作っている。陸上選手で言えば、「義足の方がより早く走れるようになる可能性を秘めている」ということです。
すると健常者のほうが障害者よりいいタイムが出るという、これまでの概念が崩れていくのではと考えています。

編集部:すごい。遠藤さんは初めからそういう考え方で研究をされていたのでしょうか?それとも徐々にそういう志が生まれてきたのか。
遠藤:もともとはロボットの研究をしていました。
ASIMOが2000年に発表されて注目されて、これは面白いと思った。それまでロボットというといかにも機械っぽくてメカメカしかったのに対して、可愛らしい要素が取り入れられたところに興味があって。
編集部:ご自身でも開発をされていたのでしょうか。
遠藤:はい、最初に開発に関わったのがPINOというロボットでした。松井龍哉さんというデザイナーがデザインしたロボットで、宇多田ヒカルさんの「Can you keep a secret」のPVに出たので見たことがある方も多いかもしれません。
編集部:みんなびっくりしましたよね。友達のような、ロボットとの距離感が新鮮だったのを覚えています。でも、そこから義足の研究に切り替えたのは何かきっかけがあったのでしょうか。
遠藤:友達がガンになり、お見舞いにいったんです。その時僕の研究の話をしたら「ロボットで歩くんじゃなくて、自分で歩きたい 」と言われて、ハッとしたんですね。
編集部:なるほど。
遠藤:誰かの役に立つ技術開発をしたい、そう思いました。
そこから色々なことがあって、マサチューセッツ工科大学(以後MITと表記)のヒューハー教授のことを知りました。
遠藤:もともとはロボットの研究をしていました。
ASIMOが2000年に発表されて注目されて、これは面白いと思った。それまでロボットというといかにも機械っぽくてメカメカしかったのに対して、可愛らしい要素が取り入れられたところに興味があって。
編集部:ご自身でも開発をされていたのでしょうか。
遠藤:はい、最初に開発に関わったのがPINOというロボットでした。松井龍哉さんというデザイナーがデザインしたロボットで、宇多田ヒカルさんの「Can you keep a secret」のPVに出たので見たことがある方も多いかもしれません。
編集部:みんなびっくりしましたよね。友達のような、ロボットとの距離感が新鮮だったのを覚えています。でも、そこから義足の研究に切り替えたのは何かきっかけがあったのでしょうか。
遠藤:友達がガンになり、お見舞いにいったんです。その時僕の研究の話をしたら「ロボットで歩くんじゃなくて、自分で歩きたい 」と言われて、ハッとしたんですね。
編集部:なるほど。
遠藤:誰かの役に立つ技術開発をしたい、そう思いました。
そこから色々なことがあって、マサチューセッツ工科大学(以後MITと表記)のヒューハー教授のことを知りました。
遠藤: 彼はもともとはロッククライマーなのですが、事故に遭い両足を失くしたんです。そのとき彼はロッククライミングを諦めるのではなく、自分で義足の設計をしようと勉強し始め、研究の後に教授になった人物です。
編集部:またすごい人物ですね。
遠藤: 彼に会いに行った時、「MITに来たらいい、受かったら教えて」と言われて、それで受験したら幸運にも合格したんです。
ただ、入学後はこれまでの専門とは違う学問を学ぶので、それはもう猛勉強の日々でしたね(笑)。
編集部:またすごい人物ですね。
遠藤: 彼に会いに行った時、「MITに来たらいい、受かったら教えて」と言われて、それで受験したら幸運にも合格したんです。
ただ、入学後はこれまでの専門とは違う学問を学ぶので、それはもう猛勉強の日々でしたね(笑)。
「できなかったらどうしよう」は考えない
編集部:語学の壁、学問分野の壁、と困難続きだったと思いますが、辞めたいと思ったことは?
遠藤:何回もありますよ。最初のうちは授業に全然ついていけなかったです。解決策は、「寝ないで頑張る」。2〜3年はそんな感じでした。
遠藤:何回もありますよ。最初のうちは授業に全然ついていけなかったです。解決策は、「寝ないで頑張る」。2〜3年はそんな感じでした。

遠藤:でも、1年中力を入れっぱなしというわけではなく、アメリカの場合、授業があるのは8ヵ月だけなので、その8ヶ月はとことん勉強して、残りの4ヵ月、夏休みなどはゆっくり過ごす。そして学期が始まったら、また集中して…、という過ごし方でした。
期間を決めて、その間だけは先の事とか考えずに没頭するんです。
編集部:でも先の事を考えずに没頭するって、意外と難しいことではありませんか。
遠藤:うーん、僕の中に「できなかったらどうしよう」というのがあまり無いのかもしれません。
編集部:あーーー、なるほど。だから今に集中できる。
遠藤:一番になりたいけど、一番にならないと悔しくて死んでしまうってほど執着したことも、あまり無いんですよ。結果的に二番になってもいいと思っているのかも。
期間を決めて、その間だけは先の事とか考えずに没頭するんです。
編集部:でも先の事を考えずに没頭するって、意外と難しいことではありませんか。
遠藤:うーん、僕の中に「できなかったらどうしよう」というのがあまり無いのかもしれません。
編集部:あーーー、なるほど。だから今に集中できる。
遠藤:一番になりたいけど、一番にならないと悔しくて死んでしまうってほど執着したことも、あまり無いんですよ。結果的に二番になってもいいと思っているのかも。
知的好奇心が原動力。支えてくれた親の存在は…
編集部:ただ、没頭したことを、さらに続けていくのって大変なことだと思うんです。遠藤さんを支えたものは何だったのでしょう。
遠藤:知的好奇心。勉強しているのが単純に楽しかったんです。知的興奮を覚える、といいますか、勉強はもちろん大変だけど面白い。もっと知りたい、だから頑張っていられたんだと思います。
編集部:とってもシンプルですね。知的好奇心。ちなみに、高校時代にも一度留学をしたいと、ご両親に相談したことがあると伺いましたが…。
遠藤:あ、そうなんですよ。高校の同級生に帰国子女がいたことで英語に興味が湧いて。それでアメリカの大学に行きたいと両親に伝えたら、もう大反対でした。
遠藤:知的好奇心。勉強しているのが単純に楽しかったんです。知的興奮を覚える、といいますか、勉強はもちろん大変だけど面白い。もっと知りたい、だから頑張っていられたんだと思います。
編集部:とってもシンプルですね。知的好奇心。ちなみに、高校時代にも一度留学をしたいと、ご両親に相談したことがあると伺いましたが…。
遠藤:あ、そうなんですよ。高校の同級生に帰国子女がいたことで英語に興味が湧いて。それでアメリカの大学に行きたいと両親に伝えたら、もう大反対でした。

編集部:なぜでしょう。
遠藤:留学したい理由を聞かれて「英語を身に着けたい、若いほうがいいと思うから」って答えたんです。そしたら「その語学を身につけて、何を勉強したいんだ」と聞き返されて、僕は何も答えられなかった。
反対された時に、押し通すほどの理由や熱量が無かったんです。そんな状態で行っても意味がないなと自分でも思い、その時は行きませんでした。
でも、大学を卒業してMITに行こうと思った時には明確な目的があった。だから受験をしたし、両親も応援してくれましたね。その時に「学費をどうまかなうか」という話をしたのがとても印象的で、今でもよく覚えています。
編集部:そのお話、ぜひ伺いたいです。
遠藤:留学したい理由を聞かれて「英語を身に着けたい、若いほうがいいと思うから」って答えたんです。そしたら「その語学を身につけて、何を勉強したいんだ」と聞き返されて、僕は何も答えられなかった。
反対された時に、押し通すほどの理由や熱量が無かったんです。そんな状態で行っても意味がないなと自分でも思い、その時は行きませんでした。
でも、大学を卒業してMITに行こうと思った時には明確な目的があった。だから受験をしたし、両親も応援してくれましたね。その時に「学費をどうまかなうか」という話をしたのがとても印象的で、今でもよく覚えています。
編集部:そのお話、ぜひ伺いたいです。
次回は
次回は、遠藤さんのご両親とのかかわりや幼少期の過ごし方についてお伺いします。