聴覚障害とは?等級や種類、コミュニケーション方法、進学先も解説【医師監修】
ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
聴覚障害とは、音の情報を脳に送るための部位のいずれかに障害があるために、音が全く聞こえない、あるいは聞こえにくい状態のことです。聴覚障害には、後天性のものと先天性のものがあります。
聴覚障害の原因や種類、障害の等級、コミュニケーション方法や周りに人ができる工夫などをご紹介します。

監修: 守本倫子
国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科診療部長
小児気道疾患センター長
新潟大学医学部卒。慶応義塾大学耳鼻咽喉科入局し、1999年から国立小児病院に赴任、小児の耳鼻咽喉科を学び始める。その後小児高度専門医療施設の中で小児難聴と小児気道疾患に特に熱心に取り組んでいる。
小児気道疾患センター長
聴覚障害とは?
聴覚障害とは、音の情報を脳に送るための部位のいずれかに障害があるために、音が全く聞こえない、あるいは聞こえにくい状態のことです。聴覚障害には、後天性のものと先天性のものがあります。
聴覚障害は、先天的な障害の中で、もっともよく見られるもののひとつといわれています。
聴覚障害のある子どもは、コミュニケーションや言語発達の面に遅れが生じる傾向があるといわれており、できるだけ早く介入(対応)することで障害によって生じるさまざまな問題を小さくする必要があります。そのために新生児の段階で聴覚に問題がないかどうか調べるためのスクリーニング検査を受けることがすすめられています。
子どもに聴覚障害が見つかった際は、音を聞くための訓練や治療、視覚的な手段を使ったコミュニケーションの方法を取り入れることにより言葉の獲得を目指します。
聴覚障害は、先天的な障害の中で、もっともよく見られるもののひとつといわれています。
聴覚障害のある子どもは、コミュニケーションや言語発達の面に遅れが生じる傾向があるといわれており、できるだけ早く介入(対応)することで障害によって生じるさまざまな問題を小さくする必要があります。そのために新生児の段階で聴覚に問題がないかどうか調べるためのスクリーニング検査を受けることがすすめられています。
子どもに聴覚障害が見つかった際は、音を聞くための訓練や治療、視覚的な手段を使ったコミュニケーションの方法を取り入れることにより言葉の獲得を目指します。
聴覚障害の種類
聴覚障害は、音を伝達する経路のどこに障害があるかによって種類が分かれており、それぞれ伝音難聴、感音難聴、混合難聴と呼ばれています。種類ごとに治りやすさや治療、改善の方法も変わってきます。
◆伝音(でんおん)難聴
外耳から中耳の間のなんらかの障害が音の通り道をさえぎることで起こるのが伝音難聴です。
具体的には中耳炎により水や膿が溜まることや、耳小骨の形態不全などが原因となって引き起こされます。
中耳炎が原因の難聴は一時的なものが多く、薬を飲んだり、溜まった水や膿(うみ)を抜いたりする治療を行うことで改善することがあります。治療が困難な場合でも、補聴器の活用が効果的であるといわれています。耳小骨の形態不全の場合は、成長してから手術を行うこともあります、
◆感音(かんおん)難聴
感音難聴は内耳や内耳から脳に音の信号を伝える神経の障害によって生じる難聴の種類です。遺伝などにより先天的に生じるほかに、騒音や加齢によって生じることもあります。
感音難聴の聞こえ方は人により異なり、音が小さく聞こえるだけではなくひずみを伴って聞こえる場合などがあります。急性の場合は薬物治療などで改善する場合もありますが、重度の場合は薬物治療の効果がないこともあります。先天性または加齢による感音難聴の場合は補聴器を使うことによって聞こえの改善を図っていきますが、重度の難聴で補聴器の効果がない場合は人工内耳植え込み術を行うことがあります。
◆混合難聴
上記のふたつの難聴が同時に引き起こされる場合が混合難聴です。症状には個人差があるため、症状に合わせて治療していきます。
外耳から中耳の間のなんらかの障害が音の通り道をさえぎることで起こるのが伝音難聴です。
具体的には中耳炎により水や膿が溜まることや、耳小骨の形態不全などが原因となって引き起こされます。
中耳炎が原因の難聴は一時的なものが多く、薬を飲んだり、溜まった水や膿(うみ)を抜いたりする治療を行うことで改善することがあります。治療が困難な場合でも、補聴器の活用が効果的であるといわれています。耳小骨の形態不全の場合は、成長してから手術を行うこともあります、
◆感音(かんおん)難聴
感音難聴は内耳や内耳から脳に音の信号を伝える神経の障害によって生じる難聴の種類です。遺伝などにより先天的に生じるほかに、騒音や加齢によって生じることもあります。
感音難聴の聞こえ方は人により異なり、音が小さく聞こえるだけではなくひずみを伴って聞こえる場合などがあります。急性の場合は薬物治療などで改善する場合もありますが、重度の場合は薬物治療の効果がないこともあります。先天性または加齢による感音難聴の場合は補聴器を使うことによって聞こえの改善を図っていきますが、重度の難聴で補聴器の効果がない場合は人工内耳植え込み術を行うことがあります。
◆混合難聴
上記のふたつの難聴が同時に引き起こされる場合が混合難聴です。症状には個人差があるため、症状に合わせて治療していきます。
聴覚障害の等級
聴覚障害は身体障害に分類されます。身体障害には症状の程度によって等級が分かれており、聴覚障害の場合は聴力のレベルと、言葉がどれくらいはっきりと聞こえるかを示す語音明瞭度により決まります。
聴力のレベルは音の大きさを示すデシベル(db)という単位により表されます。聴力の場合は、デシベルの値が大きくなればなるほど、耳が聞こえにくいということを意味します。
デシベルの目安は以下の図をご覧ください。正常な聴力は0デシベル付近で、値が大きくなるにつれて聴覚障害の程度が強くなっていきます。
聴力のレベルは音の大きさを示すデシベル(db)という単位により表されます。聴力の場合は、デシベルの値が大きくなればなるほど、耳が聞こえにくいということを意味します。
デシベルの目安は以下の図をご覧ください。正常な聴力は0デシベル付近で、値が大きくなるにつれて聴覚障害の程度が強くなっていきます。
また、厚生労働省により定められている聴覚障害の等級の基準は以下の通りです。
◇2級:両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上、全聾(ぜんろう)の場合
◇3級:両耳の聴力レベルが90デシベル以上の場合
◇4級:両耳の聴力レベルが80デシベル以上の場合、または両耳による通常の話し声の語音明瞭度が50パーセント以下の場合
◇6級:両耳の聴力レベルが70デシベル以上の場合、または片方の聴力レベルが90デシベル以上、もう片方の聴力レベルが50デシベル以上の場合
上記のいずれかに該当する場合には、身体障害者手帳の交付を受けることができます。
◇2級:両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上、全聾(ぜんろう)の場合
◇3級:両耳の聴力レベルが90デシベル以上の場合
◇4級:両耳の聴力レベルが80デシベル以上の場合、または両耳による通常の話し声の語音明瞭度が50パーセント以下の場合
◇6級:両耳の聴力レベルが70デシベル以上の場合、または片方の聴力レベルが90デシベル以上、もう片方の聴力レベルが50デシベル以上の場合
上記のいずれかに該当する場合には、身体障害者手帳の交付を受けることができます。
身体障害者手帳の交付を受けるには
身体障害者手帳とは、難聴を含め、障害のある人が取得することができる手帳です。平成28年の時点で聴覚障害があり、身体障害者手帳を所持している人数は約34万人です(言語障害も含む)。この数値は身体障害者手帳を所持している人の約8%にあたります。
障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスを受けることができます。
身体障害者手帳交付を受けるためには申請が必要で、医師の診断書(または意見書)や申込書、マイナンバーなどを揃えて自治体の障害福祉窓口などで行います。申請後は審査に通れば約2ヶ月程度で発行されます。
手帳の申請については、以下のページに詳しく手順が載っているので参考にしてください。
障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスを受けることができます。
身体障害者手帳交付を受けるためには申請が必要で、医師の診断書(または意見書)や申込書、マイナンバーなどを揃えて自治体の障害福祉窓口などで行います。申請後は審査に通れば約2ヶ月程度で発行されます。
手帳の申請については、以下のページに詳しく手順が載っているので参考にしてください。
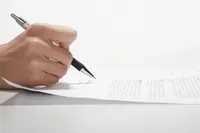
障害者手帳とは?種類ごとの申請方法と受けられるサービスを一挙にご紹介
聞こえない、聞こえにくい子どもとのコミュニケーション方法
聴覚障害がある人は、聞こえを補うためにさまざまなコミュニケーション方法を用いています。それと共に、周りの方ができることもありますので、合わせて紹介します。
聞こえない、聞こえにくい子どもとのコミュニケーション方法の例
聴覚障害がある場合、手話、口話(こうわ)、筆談など、状況によって使い分けや併用しながらコミュニケーションを取っていきます。
◆手話
手や指の形、動きによって、お互いの意思を伝え合う方法です。手話は、話し言葉とは異なる文法や語彙をもつ、ひとつの言語として捉えられています。手話にもさまざまなバリエーションがあり、障害の生じた時期や手話を覚えた時期によって、使用される手話も異なります。まだ言葉を覚えていない時期でも、ジェスチャーやサインなどで意思を伝えることができ、コミュニケーション能力を高めていきます。
◆口話(こうわ)
口話とは、話し手の口の動きや表情などを見て相手が発する言葉を読み取り、聴覚障害の人も言葉を用いて意思を伝える方法のことです。
口話は手話や筆談に比べて意思の伝達が早いという特徴がありますが、状況によっては伝わりにくい場合もあります。例えば、「たばこ」「たまご」など口の動きが似ている言葉などは正確に意味をつかむことが難しくなります。
また、暗い場所や、相手との距離が離れている場合には、相手の口の動きが分かりにくいために、手話や筆談などと併用されて使われることもあります。
◆アプリ
近年ではスマートフォンのアプリを使って聞こえを補う方法もあります。
「こえとら」という無料アプリでは、聴覚障害の人が入力した文字を合成音声として出力することで意思を伝えることができます。「UDトーク」という無料アプリでは、音声認識と自動翻訳が可能です。音声認識で話していることを文字化することができるので、聴覚障害の人が文字を相手の話している内容を理解することができます。
また、よく使う定型文を登録しておくことやイラストを表示するなど、電子ツールならではの機能もついていることも特徴です。このような聞こえを補うアプリはほかにも多数存在しています。
さらに、筆談などが簡単に行えるアプリも配信されているため、聴覚障害の人が身近にいる人も活用できるアプリを探してみるといいでしょう。
◆手話
手や指の形、動きによって、お互いの意思を伝え合う方法です。手話は、話し言葉とは異なる文法や語彙をもつ、ひとつの言語として捉えられています。手話にもさまざまなバリエーションがあり、障害の生じた時期や手話を覚えた時期によって、使用される手話も異なります。まだ言葉を覚えていない時期でも、ジェスチャーやサインなどで意思を伝えることができ、コミュニケーション能力を高めていきます。
◆口話(こうわ)
口話とは、話し手の口の動きや表情などを見て相手が発する言葉を読み取り、聴覚障害の人も言葉を用いて意思を伝える方法のことです。
口話は手話や筆談に比べて意思の伝達が早いという特徴がありますが、状況によっては伝わりにくい場合もあります。例えば、「たばこ」「たまご」など口の動きが似ている言葉などは正確に意味をつかむことが難しくなります。
また、暗い場所や、相手との距離が離れている場合には、相手の口の動きが分かりにくいために、手話や筆談などと併用されて使われることもあります。
◆アプリ
近年ではスマートフォンのアプリを使って聞こえを補う方法もあります。
「こえとら」という無料アプリでは、聴覚障害の人が入力した文字を合成音声として出力することで意思を伝えることができます。「UDトーク」という無料アプリでは、音声認識と自動翻訳が可能です。音声認識で話していることを文字化することができるので、聴覚障害の人が文字を相手の話している内容を理解することができます。
また、よく使う定型文を登録しておくことやイラストを表示するなど、電子ツールならではの機能もついていることも特徴です。このような聞こえを補うアプリはほかにも多数存在しています。
さらに、筆談などが簡単に行えるアプリも配信されているため、聴覚障害の人が身近にいる人も活用できるアプリを探してみるといいでしょう。
◆筆談
紙やボードへの読み書きによって、意思を伝え合う方法です。双方に特別な知識が必要ないため、手話よりも多くの場面で使えるといえるでしょう。
ただ、文字による情報だけでは細かいニュアンスや感情が伝わらない場合があります。
◆耳が不自由なことを周りに伝えるための「耳マーク」
聴覚障害は見た目で分からないことも多いため、聴覚障害のあることを伝えるマークが存在
しています。
紙やボードへの読み書きによって、意思を伝え合う方法です。双方に特別な知識が必要ないため、手話よりも多くの場面で使えるといえるでしょう。
ただ、文字による情報だけでは細かいニュアンスや感情が伝わらない場合があります。
◆耳が不自由なことを周りに伝えるための「耳マーク」
聴覚障害は見た目で分からないことも多いため、聴覚障害のあることを伝えるマークが存在
しています。
「耳マーク」と呼ばれるこちらのマークは、聴覚障害の人が身につけるほかに、銀行の窓口などで聴覚障害の人へ配慮ができることを伝えるためにも使われます。
耳マークをつけている方がいた場合は、文字を用いてやりとりをすることや、口を大きく開けてゆっくり話すなどその方が受け取りやすいコミュニケーション方法を心がけるようにしましょう。
窓口で耳マークが出ている場合のバリアフリー例としては、筆談用の機器やアプリなどを用意しておく、手話ができる職員を配置する、よく使う案内内容の表やイラストを用意しておくなどがあります。
耳マークをつけている方がいた場合は、文字を用いてやりとりをすることや、口を大きく開けてゆっくり話すなどその方が受け取りやすいコミュニケーション方法を心がけるようにしましょう。
窓口で耳マークが出ている場合のバリアフリー例としては、筆談用の機器やアプリなどを用意しておく、手話ができる職員を配置する、よく使う案内内容の表やイラストを用意しておくなどがあります。
聞こえない、聞こえにくい子どもへ周りができること
◆音声での会話に加えて、視覚的な情報を示す
補聴器などで聞こえを補っている子どもは、静かな部屋では言葉のやりとりができるのに、にぎやかな場所など状況によって相手の声が聞き取れなくなるということもあります。
そのため、補聴器などをつけていても視覚的な情報を示すことが大事です。具体的には以下のような工夫があります。
・向かい合った状態でアイコンタクトをとり、相手が自分の顔を見ているか確認してから話し始める
・文節で区切りながら、1つひとつの単語をはっきりと話す
・複数の人数で話すときには、手をあげるなどして話し手が誰か分かりやすくする
・明るい場所で話す
◆その子どもにあったコミュニケーションの方法を確認する
聴覚障害のある子どものコミュニケーションの方法は1つではありません。聞こえの程度などによってさまざまな手段を用いています。
そのため、どの手段が確実にコミュニケーションできるのか把握しておくことが重要です。
子ども本人がどの方法がいいか答えられる場合は、先に確認しておきましょう。年齢などによって答えられない場合は、保護者など周りの方に確認しておく方法があります。
◆状況を伝える
聴覚に障害があると、音の情報がはっきりと聞こえないために、周りの状況がつかめず、場にそぐわないことをしたりすることがあります。周りが騒がしかったり、話し手の声が小さい場合には、その場の状況をもう一度伝えてあげるなどして、大人が援助してあげるとよいでしょう。
そのほかには、クラクションや、近づいてくる車の音が聞こえないことがあります。一緒に外出する際には、あらかじめ危険な場所などを伝えておくと共に、大人が道路側を歩くなどの工夫をするようにしましょう。
補聴器などで聞こえを補っている子どもは、静かな部屋では言葉のやりとりができるのに、にぎやかな場所など状況によって相手の声が聞き取れなくなるということもあります。
そのため、補聴器などをつけていても視覚的な情報を示すことが大事です。具体的には以下のような工夫があります。
・向かい合った状態でアイコンタクトをとり、相手が自分の顔を見ているか確認してから話し始める
・文節で区切りながら、1つひとつの単語をはっきりと話す
・複数の人数で話すときには、手をあげるなどして話し手が誰か分かりやすくする
・明るい場所で話す
◆その子どもにあったコミュニケーションの方法を確認する
聴覚障害のある子どものコミュニケーションの方法は1つではありません。聞こえの程度などによってさまざまな手段を用いています。
そのため、どの手段が確実にコミュニケーションできるのか把握しておくことが重要です。
子ども本人がどの方法がいいか答えられる場合は、先に確認しておきましょう。年齢などによって答えられない場合は、保護者など周りの方に確認しておく方法があります。
◆状況を伝える
聴覚に障害があると、音の情報がはっきりと聞こえないために、周りの状況がつかめず、場にそぐわないことをしたりすることがあります。周りが騒がしかったり、話し手の声が小さい場合には、その場の状況をもう一度伝えてあげるなどして、大人が援助してあげるとよいでしょう。
そのほかには、クラクションや、近づいてくる車の音が聞こえないことがあります。一緒に外出する際には、あらかじめ危険な場所などを伝えておくと共に、大人が道路側を歩くなどの工夫をするようにしましょう。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています


















