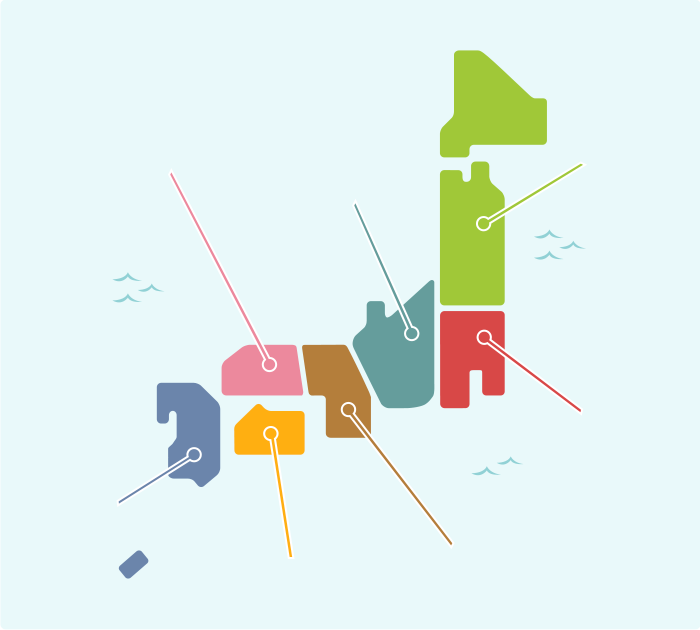俳優・東ちづるさん取材--芸能界で感じる後ろめたさとは。障害がないからチャンスがあった?「自閉症啓発デー」やまぜこぜの社会を目指す「Get ㏌ touch」10年の活動の思い
ライター:発達ナビ編集部

Upload By 発達ナビ編集部
4月2日は国連が定めた「世界自閉症啓発デー」。自閉スペクトラム症のカラーであるブルー、青で、この日をアピールします。LITALICO発達ナビ編集部でも、この日に向けてさまざまな企画を盛り上げていきます! 自閉症啓発イベント、ウォームブルー・デー(Warm Blue Day)を日本で初めて企画した一般社団法人「Get ㏌ touch」、理事長の東ちづるさんに、10周年を迎えた団体の想いを伺いました。
Get in touchの最初の活動が、「ウォームブルー・デー」、世界自閉症啓発デーのイベントだった
発達ナビ牟田暁子編集長(以下――):発達ナビの読者には、東ちづるさんが理事長を務める一般社団法人Get ㏌ touch(ゲットインタッチ)の活動について、あらためてGet ㏌ touchはどういう団体なのかお話しいただいてもいいでしょうか。
東ちづるさん(以下、東):Get ㏌ touchは、「誰も排除しないまぜこぜの社会」を目指すプロボノ団体です。主にアート、音楽、映像、舞台などのエンターテイメントを通じて活動しています。私たちは、まぜこぜ・多様な社会で暮らしているということを見える化・体験化していきます。メンバーはそれぞれ本業があり、さまざまな職種においてプロフェッショナルで、それぞれが培ってきたスキルやアイディア、人脈などを提供しています。特徴的なのはクリエイターやエンタメ業界に関わる人たちが多い、という点です。
私個人は、30年前から社会的な活動をしていますが、ずっと何かモヤモヤしていたんですよね。それは、講演やシンポジウムに参加すると、同じような顔ぶれになりがちということ。社会課題への意識が高い人たちは集まっているけれど、本当は、こうした課題について無関心な人たちをどう巻き込むかを考えなくちゃいけないんじゃないの?と。
――どんな活動がスタートだったんですか?
東:最初は自閉スペクトラム症を啓発する活動からでした。4月2日の世界自閉症啓発デーのイベント「ウォームブルー・デー(Warm Blue Day)」の企画ですね。この4月2日には、先進国ではさまざまな形で「青くなっている」と知ったとき、「私は20年以上活動しているのに知らなかった」ということがショックだったんですよね。それが10年前です。
「青くなる」というのは、街のライトアップをはじめ、新聞の文字をブルーにしたり、アーティストや芸能人、ニュースキャスターが、その日はこぞってブルーの服を着たり、ブルーのものを身につけたりしてメディアに登場するということなんです。そして、ブルーにするのは自閉スペクトラム症の啓発であることをみんな分かってやっている。これって、日本でもできるんじゃない!?と思ったんです。それも楽しみながら。
東ちづるさん(以下、東):Get ㏌ touchは、「誰も排除しないまぜこぜの社会」を目指すプロボノ団体です。主にアート、音楽、映像、舞台などのエンターテイメントを通じて活動しています。私たちは、まぜこぜ・多様な社会で暮らしているということを見える化・体験化していきます。メンバーはそれぞれ本業があり、さまざまな職種においてプロフェッショナルで、それぞれが培ってきたスキルやアイディア、人脈などを提供しています。特徴的なのはクリエイターやエンタメ業界に関わる人たちが多い、という点です。
私個人は、30年前から社会的な活動をしていますが、ずっと何かモヤモヤしていたんですよね。それは、講演やシンポジウムに参加すると、同じような顔ぶれになりがちということ。社会課題への意識が高い人たちは集まっているけれど、本当は、こうした課題について無関心な人たちをどう巻き込むかを考えなくちゃいけないんじゃないの?と。
――どんな活動がスタートだったんですか?
東:最初は自閉スペクトラム症を啓発する活動からでした。4月2日の世界自閉症啓発デーのイベント「ウォームブルー・デー(Warm Blue Day)」の企画ですね。この4月2日には、先進国ではさまざまな形で「青くなっている」と知ったとき、「私は20年以上活動しているのに知らなかった」ということがショックだったんですよね。それが10年前です。
「青くなる」というのは、街のライトアップをはじめ、新聞の文字をブルーにしたり、アーティストや芸能人、ニュースキャスターが、その日はこぞってブルーの服を着たり、ブルーのものを身につけたりしてメディアに登場するということなんです。そして、ブルーにするのは自閉スペクトラム症の啓発であることをみんな分かってやっている。これって、日本でもできるんじゃない!?と思ったんです。それも楽しみながら。
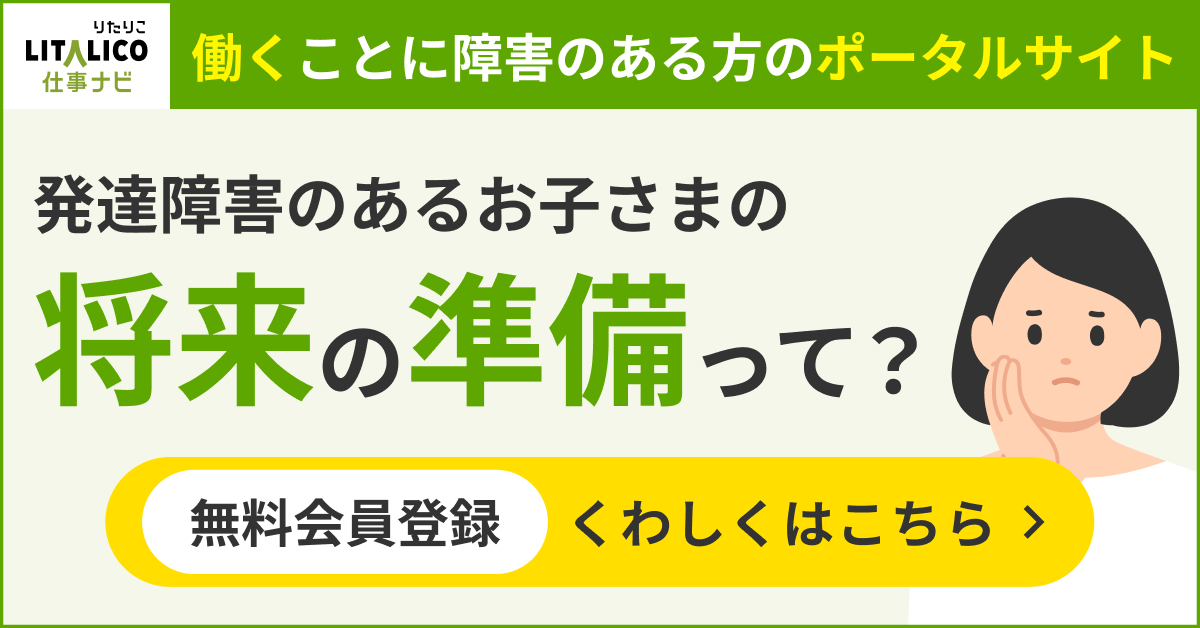
はじめてのウォームブルー・デーのプロジェクトは批判が殺到!?
――それが10年前なんですね。
東:それまでも、自閉症協会さんや厚生労働省の働き掛けで、全国各地で青くライトアップされたり、青を使ってアピールしたりといった動きはあったけれど、「世界自閉症啓発デー」だからということは、一般の人にはほぼ知られていないという状況でした。なぜならメディアになかなか取り上げられないから。メディアに取り上げられるにはどうすればいいの?と考えて、エンタメでやっていこう!となったわけです。
第1回は、東京タワーでウォームブルー・デー(Warm Blue Day)と名づけて、全国各地の自閉スペクトラム症があるお子さんのご家族や当事者、そうではない人たちが「まぜこぜ」に集まるというイベントを開催しました。ショップのウィンドウをブルーにデコレイトしてもらったり、ブルーにペイントされたスーパーカーのパレードがあったり、コスプレイヤーがブルーの服を着て歩いたり。にぎやかな祭典となりましたが、その裏では、警察や厚生労働省、自閉症協会をはじめ、さまざまなところに、私たちは一から企画の説明をして、文字通り泥臭い地道な調整をして実現したイベントでもありました。
…でもね、この初回は、叩かれたりもしたんです。
――そうだったんですか?それは、なぜでしょうか。
東:エンターテインメントでしたから。こうした啓発活動をするときには、真面目にやらなくてはならない、というムードが日本にはありますよね。楽しいことは後ろめたい、というような。だから、「お祭り騒ぎをして何が啓発だ!」というお叱りをたくさん受けました。当事者ご家族、支援団体さん、厚生労働省からも、それはもうかなり賛同を得られませんでした。
ところが、です。実際に蓋を開けてみたら、ものすごくたくさんの人が集まりました。そして、自閉症協会さんはじめ、自閉スペクトラム症や発達障害に関するサイトが問い合わせでパンクしたのです。そこでようやく、「ああ、これも啓発なんだ」と理解していただけました。今振り返ると、本当によく闘ったなと思います。
――そうだったんですね。今やGet ㏌ touchは、自閉スペクトラム症や発達障害の啓発活動ではすっかり頼りにされている存在ですよね。
東:ウォームブルー・デー(Warm Blue Day)に関しては、現在は東京都自閉症協会さんが都内の関連団体に呼びかけて集まった「東京タワー実行委員会(TT実行委員会)」に引き継いでいます。もはや私たちが始めたということも忘れられているくらいの盛り上がりになりました。これはGet ㏌ touchの成果の一つだと思っています。社会的に知ってもらうということが最初の目標でしたから。でも、4月2日には日本全国でさまざまな人たちが自発的に青い服を着たり、SNSで発信するのがあたりまえのように日常に溶け込んだ社会になったらいいなと思っています。たとえば、ハロウィンのようにね。
東:それまでも、自閉症協会さんや厚生労働省の働き掛けで、全国各地で青くライトアップされたり、青を使ってアピールしたりといった動きはあったけれど、「世界自閉症啓発デー」だからということは、一般の人にはほぼ知られていないという状況でした。なぜならメディアになかなか取り上げられないから。メディアに取り上げられるにはどうすればいいの?と考えて、エンタメでやっていこう!となったわけです。
第1回は、東京タワーでウォームブルー・デー(Warm Blue Day)と名づけて、全国各地の自閉スペクトラム症があるお子さんのご家族や当事者、そうではない人たちが「まぜこぜ」に集まるというイベントを開催しました。ショップのウィンドウをブルーにデコレイトしてもらったり、ブルーにペイントされたスーパーカーのパレードがあったり、コスプレイヤーがブルーの服を着て歩いたり。にぎやかな祭典となりましたが、その裏では、警察や厚生労働省、自閉症協会をはじめ、さまざまなところに、私たちは一から企画の説明をして、文字通り泥臭い地道な調整をして実現したイベントでもありました。
…でもね、この初回は、叩かれたりもしたんです。
――そうだったんですか?それは、なぜでしょうか。
東:エンターテインメントでしたから。こうした啓発活動をするときには、真面目にやらなくてはならない、というムードが日本にはありますよね。楽しいことは後ろめたい、というような。だから、「お祭り騒ぎをして何が啓発だ!」というお叱りをたくさん受けました。当事者ご家族、支援団体さん、厚生労働省からも、それはもうかなり賛同を得られませんでした。
ところが、です。実際に蓋を開けてみたら、ものすごくたくさんの人が集まりました。そして、自閉症協会さんはじめ、自閉スペクトラム症や発達障害に関するサイトが問い合わせでパンクしたのです。そこでようやく、「ああ、これも啓発なんだ」と理解していただけました。今振り返ると、本当によく闘ったなと思います。
――そうだったんですね。今やGet ㏌ touchは、自閉スペクトラム症や発達障害の啓発活動ではすっかり頼りにされている存在ですよね。
東:ウォームブルー・デー(Warm Blue Day)に関しては、現在は東京都自閉症協会さんが都内の関連団体に呼びかけて集まった「東京タワー実行委員会(TT実行委員会)」に引き継いでいます。もはや私たちが始めたということも忘れられているくらいの盛り上がりになりました。これはGet ㏌ touchの成果の一つだと思っています。社会的に知ってもらうということが最初の目標でしたから。でも、4月2日には日本全国でさまざまな人たちが自発的に青い服を着たり、SNSで発信するのがあたりまえのように日常に溶け込んだ社会になったらいいなと思っています。たとえば、ハロウィンのようにね。
障害がない人だけにマーケットが用意されているということへのモヤモヤ
――まぜこぜの社会を顕在化することを達成して、10年で解散することが目標ということでしたが、解散していないのはまだまだ課題があるということですね?
東:新たなことがどんどん出てきますからね。でも、確実に社会はアップデートされています。その半面、分断はまた広がっているというか、生きづらさを抱える人が増えているのが現実です。
私は、芸能界がグレードアップするといいなと思っています。「まぜこぜ一座」を立ち上げたときに、マイノリティの表現者たちのすごいスキルを目の当たりにしました。彼らの才能と努力は素晴らしい、けれども発揮する場が限られている。その才能を広く披露するチャンスがあらかじめ絶たれているという現実があります。
最近気づいたことなんですが、私には、マイノリティの表現者たちに対する「後ろめたさ」もあるのだと思います。私は劇団出身でもないし、偉大な師匠について修行したわけでもない。そういうベースがなくても、芸能界で仕事をさせてもらってきたんですよね。もちろん、努力はしてきましたけどね。
一方でマイノリティの表現者には、プロダクションもなく、活躍できるチャンスがまずない。私にはそれがあったんです、障害がないから。フラットにみんなにチャンスがある方が、私自身も気持ちよく仕事ができると思っています。ドラマや映画で当たり前のように共演したいんですよ。「まぜこぜ一座」のように、私が脚本を書いて演出するステージではなくて、オファーをいただいてドラマに出てみたら、私の上司がマメ山田さんで、部下が後藤ひとみさんで、同僚にかんばらけんたさんがいる、なんていう設定。すごく面白いと思う。
海外では実際にそういう風にキャスティングされた映画やドラマがあって、いろいろな人たちが出演しています。海外のドラマを見ていると、普通にLGBTQの設定の役柄がある。主役ではなくて、障害やマイノリティを「克服する」といったテーマでもなくて。社員の一人だったり、近所の住人だったり、学校の生徒の一人とか、そういう方がいる日常が表現されているんです。それこそが多様性ですよね。
日本でもそういうドラマや映画が増えたら、見る側の意識もかなり変わるはず。家族や友達、同僚の間でも、「そういえば、うちの学校・会社にはこういう人がいないよね、なんでだろう」とか、そういう話題が出てほしいと願っています。
――当たり前だと思っていることについて、見直してみるといいんですよね。
東:そうですね。見える人が見えない役を、聞こえる人が聞こえない役を演じるのもいいけれど、実際に聞こえない俳優もいるし、見えないタレントもいるので、チャンスはあった方がいいですよね。
東:新たなことがどんどん出てきますからね。でも、確実に社会はアップデートされています。その半面、分断はまた広がっているというか、生きづらさを抱える人が増えているのが現実です。
私は、芸能界がグレードアップするといいなと思っています。「まぜこぜ一座」を立ち上げたときに、マイノリティの表現者たちのすごいスキルを目の当たりにしました。彼らの才能と努力は素晴らしい、けれども発揮する場が限られている。その才能を広く披露するチャンスがあらかじめ絶たれているという現実があります。
最近気づいたことなんですが、私には、マイノリティの表現者たちに対する「後ろめたさ」もあるのだと思います。私は劇団出身でもないし、偉大な師匠について修行したわけでもない。そういうベースがなくても、芸能界で仕事をさせてもらってきたんですよね。もちろん、努力はしてきましたけどね。
一方でマイノリティの表現者には、プロダクションもなく、活躍できるチャンスがまずない。私にはそれがあったんです、障害がないから。フラットにみんなにチャンスがある方が、私自身も気持ちよく仕事ができると思っています。ドラマや映画で当たり前のように共演したいんですよ。「まぜこぜ一座」のように、私が脚本を書いて演出するステージではなくて、オファーをいただいてドラマに出てみたら、私の上司がマメ山田さんで、部下が後藤ひとみさんで、同僚にかんばらけんたさんがいる、なんていう設定。すごく面白いと思う。
海外では実際にそういう風にキャスティングされた映画やドラマがあって、いろいろな人たちが出演しています。海外のドラマを見ていると、普通にLGBTQの設定の役柄がある。主役ではなくて、障害やマイノリティを「克服する」といったテーマでもなくて。社員の一人だったり、近所の住人だったり、学校の生徒の一人とか、そういう方がいる日常が表現されているんです。それこそが多様性ですよね。
日本でもそういうドラマや映画が増えたら、見る側の意識もかなり変わるはず。家族や友達、同僚の間でも、「そういえば、うちの学校・会社にはこういう人がいないよね、なんでだろう」とか、そういう話題が出てほしいと願っています。
――当たり前だと思っていることについて、見直してみるといいんですよね。
東:そうですね。見える人が見えない役を、聞こえる人が聞こえない役を演じるのもいいけれど、実際に聞こえない俳優もいるし、見えないタレントもいるので、チャンスはあった方がいいですよね。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています