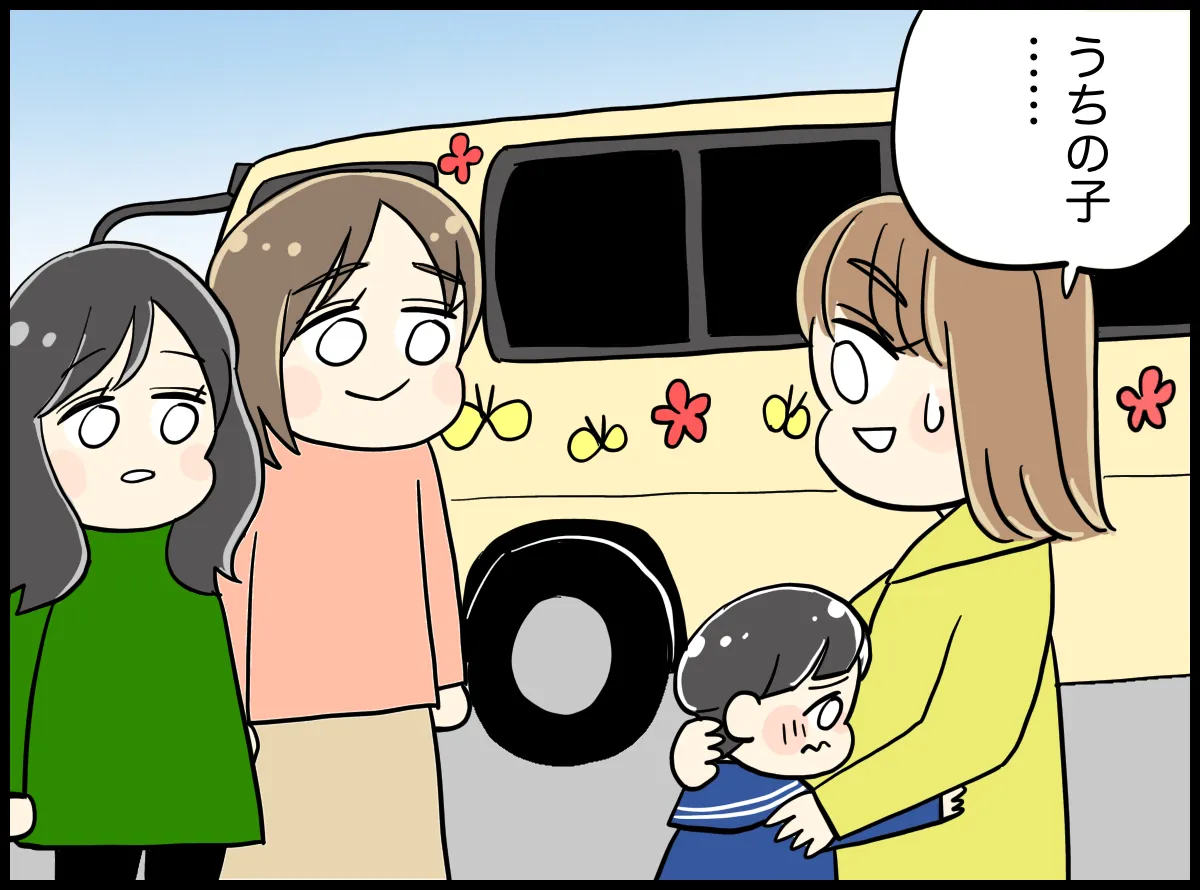「うちの子、自閉症で」息子の障害を出会ったばかりのママ友にカミングアウト!その理由は…【読者体験談】
ライター:ユーザー体験談
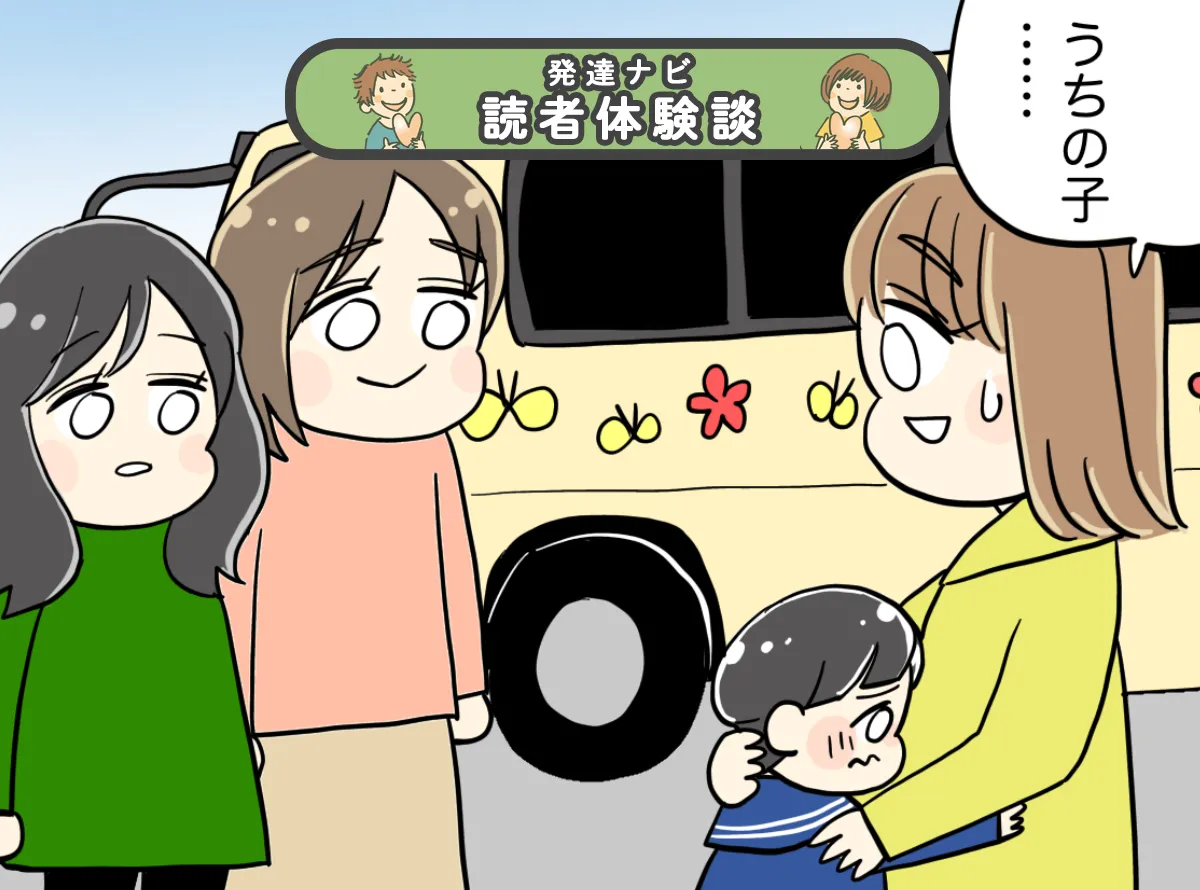
Upload By ユーザー体験談
【発達ナビではユーザーさんからの子育てエピソードを募集中!今回は「ママ友」「カミングアウト」についてのエピソードをご紹介します。】現在小学3年生の息子は、2歳で知的発達症、ASD(自閉スペクトラム症)の診断をうけました。2年間の海外生活後、息子が5歳の時に帰国し日本の幼稚園へ入ったのですが、その時ママ友たちへ息子の障害をすぐカミングアウトしました。私がカミングアウトした理由について、お話させていただきます。

監修: 鈴木直光
筑波こどものこころクリニック院長
1959年東京都生まれ。1985年秋田大学医学部卒。在学中YMCAキャンプリーダーで初めて自閉症児に出会う。同年東京医科歯科大学小児科入局。
1987〜88年、瀬川小児神経学クリニックで自閉症と神経学を学び、栃木県県南健康福祉センターの発達相談で数々の発達障がい児と出会う。2011年、茨城県つくば市に筑波こどものこころクリニック開院。
「うちの子自閉症なので、なかなか気持ちの整理が上手にできなくて」園バスでの大癇癪で、すぐに息子の障害をカミングアウト
現在小学3年生の息子は、2歳で知的発達症、ASD(自閉スペクトラム症)の診断をうけました。
2年間の海外生活から日本へ戻ってきた私たち。当時息子は5歳でした。海外ののびのびした環境から急に帰国、かつ新しい幼稚園に通うことは、誰でもとてもストレスがかかることだと思います。しかも、通うことになった幼稚園は隔日登園、保育時間も短時間で、今までとは異なることだらけ。息子もこの変化を受け止めきれず、癇癪が増えてしまいました。
特に幼稚園が終わって園バスから降りたあとの癇癪が大変。毎日大声で叫んだり泣いたりする日々でした。楽しい園での遊び時間が短すぎて、大好きな先生とのお別れが早過ぎてつらかったのが理由のようです。大きな声で泣き叫ばれたら園バスを待つ他の保護者の方やお子さんたちも驚くでしょうし、不安に思うでしょう。
息子が最初大声を出してしまった時に、私は迷わず、すぐにカミングアウトしました。
「すみません、うちの子自閉症なので、なかなか気持ちの整理が上手にできなくて……新しい幼稚園は短時間なのが理解しづらいみたいです……」
「大きい声ビックリしちゃうよね、ごめんね~。幼稚園大好きすぎて、おうち帰るのがつらいみたい」などと、その場にいるママさんや子どもたちに明るい感じで、息子の気持ちを代弁していました。
カミングアウトをするか迷われる方もいると思いますが、私がすぐ判断できたのは、海外での経験によるものでした。
2年間の海外生活から日本へ戻ってきた私たち。当時息子は5歳でした。海外ののびのびした環境から急に帰国、かつ新しい幼稚園に通うことは、誰でもとてもストレスがかかることだと思います。しかも、通うことになった幼稚園は隔日登園、保育時間も短時間で、今までとは異なることだらけ。息子もこの変化を受け止めきれず、癇癪が増えてしまいました。
特に幼稚園が終わって園バスから降りたあとの癇癪が大変。毎日大声で叫んだり泣いたりする日々でした。楽しい園での遊び時間が短すぎて、大好きな先生とのお別れが早過ぎてつらかったのが理由のようです。大きな声で泣き叫ばれたら園バスを待つ他の保護者の方やお子さんたちも驚くでしょうし、不安に思うでしょう。
息子が最初大声を出してしまった時に、私は迷わず、すぐにカミングアウトしました。
「すみません、うちの子自閉症なので、なかなか気持ちの整理が上手にできなくて……新しい幼稚園は短時間なのが理解しづらいみたいです……」
「大きい声ビックリしちゃうよね、ごめんね~。幼稚園大好きすぎて、おうち帰るのがつらいみたい」などと、その場にいるママさんや子どもたちに明るい感じで、息子の気持ちを代弁していました。
カミングアウトをするか迷われる方もいると思いますが、私がすぐ判断できたのは、海外での経験によるものでした。
私が積極的にカミングアウトをしている理由
息子が年少・年中の2年間、わが家はドイツで暮らしていました。通うことになった幼稚園では、外国人の障害児を受け入れるのは初めてとのこと。私は事前にメールで息子の様子を伝えたり、日本の園での様子を撮影した動画を送ったりして、息子の障害がどの程度なのかを伝えました。
送った動画は以下の2つです。
1.お弁当箱を自分で片づけ、歯磨きをして、先生の指示で順番に動いている様子
2.体育の授業で走り回っている様子
当時の私は、「よし、ちゃんと自分で片づけできているな。これなら幼稚園も受け入れてくれるはず」と思いました。でもドイツの園長先生がその動画を見て私に返してくれた感想は、「全然楽しそうじゃないね。目が笑ってない。単に従わせているだけ」。予想してなかった視点でした。この時、私の視点は息子自身の気持ちに向いてないと気づかされました。
実際ドイツの幼稚園は非常に素晴らしい環境でした。先生方は日々試行錯誤で息子に対峙してくださいました。教室に入れない息子を園長先生は自分のオフィスに連れて行き、ときには膝に抱っこして一緒にパソコンで好きなキャラクターの画像を探して印刷したり、ときにはご自分はお仕事をしながら隣の椅子で息子を自由に遊ばせたり、ときには一緒にスマホで写真を撮って可愛く加工したり、ときには一緒にお散歩をしたりしてくれました。関わってくださった先生方全員、息子に合わせて接してくれました。
この経験のお陰で、息子は人を信じることができるようになり、自分を受け入れてくれる人を探すのが上手になりました。自己肯定感の獲得にも繋がっていると思いましたし、仲の良い友達もできました。
送った動画は以下の2つです。
1.お弁当箱を自分で片づけ、歯磨きをして、先生の指示で順番に動いている様子
2.体育の授業で走り回っている様子
当時の私は、「よし、ちゃんと自分で片づけできているな。これなら幼稚園も受け入れてくれるはず」と思いました。でもドイツの園長先生がその動画を見て私に返してくれた感想は、「全然楽しそうじゃないね。目が笑ってない。単に従わせているだけ」。予想してなかった視点でした。この時、私の視点は息子自身の気持ちに向いてないと気づかされました。
実際ドイツの幼稚園は非常に素晴らしい環境でした。先生方は日々試行錯誤で息子に対峙してくださいました。教室に入れない息子を園長先生は自分のオフィスに連れて行き、ときには膝に抱っこして一緒にパソコンで好きなキャラクターの画像を探して印刷したり、ときにはご自分はお仕事をしながら隣の椅子で息子を自由に遊ばせたり、ときには一緒にスマホで写真を撮って可愛く加工したり、ときには一緒にお散歩をしたりしてくれました。関わってくださった先生方全員、息子に合わせて接してくれました。
この経験のお陰で、息子は人を信じることができるようになり、自分を受け入れてくれる人を探すのが上手になりました。自己肯定感の獲得にも繋がっていると思いましたし、仲の良い友達もできました。
そして私の心境も大きく変化しました。ドイツに行く前も充分に息子の障害受容ができていると自分では思っていたのですが、実際には受容できていなかったことに気がつきました。以前の私はというと、仲の良い人にだけはカミングアウトしているのに、知らない人には息子の変な発言や態度に対して、なるべく障害だと思われないようにフォローすることを無意識にしており、気疲れすることが多かったように思います。ですが、ドイツで生活する中で、私はクラスメイトのママパパ全員に、息子の障害について話すようになっていました。
こういう経験があったので、日本でも私は迷わずカミングアウトをしたのでした。
こういう経験があったので、日本でも私は迷わずカミングアウトをしたのでした。
日本の幼稚園でカミングアウトしたら?
ドイツでそのような経験をしていても、日本ではみんなどういう反応をするんだろう……と不安はありました。ですが、返ってきたのは温かい言葉ばかりでした。
「わかりますー。うちの子も! 大変ですよね……」
「友達のお子さんも発達障害で同じような話よく聞きます」
「うちもグレーです。早く慣れるといいですね」
「知り合いに障害児ママいるから、紹介します」
「大丈夫ですよ」
など、だいたいは笑顔で受け入れてくれ、同じ環境の人を紹介してくれたり、お友達になったりしました。
「わかりますー。うちの子も! 大変ですよね……」
「友達のお子さんも発達障害で同じような話よく聞きます」
「うちもグレーです。早く慣れるといいですね」
「知り合いに障害児ママいるから、紹介します」
「大丈夫ですよ」
など、だいたいは笑顔で受け入れてくれ、同じ環境の人を紹介してくれたり、お友達になったりしました。
その時、「あれ? こんなに理解してくれるんだ。自分だけが周りに迷惑をかけてつらいと思っていたけれど、もしかして意外とみなさん発達障害の子どもというものに慣れているのかもしれない」と思って、急に気持ちが楽になったのを覚えています。
大規模マンションに住んでいるのですが、子どもの数がとても多いため、同じような環境に対する知識や経験のあるママさんたちが多かったのもラッキーでした。そこで繋がった人とは、その後も個別に特別支援学級や放課後等デイサービスの情報交換をしています。
大規模マンションに住んでいるのですが、子どもの数がとても多いため、同じような環境に対する知識や経験のあるママさんたちが多かったのもラッキーでした。そこで繋がった人とは、その後も個別に特別支援学級や放課後等デイサービスの情報交換をしています。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています