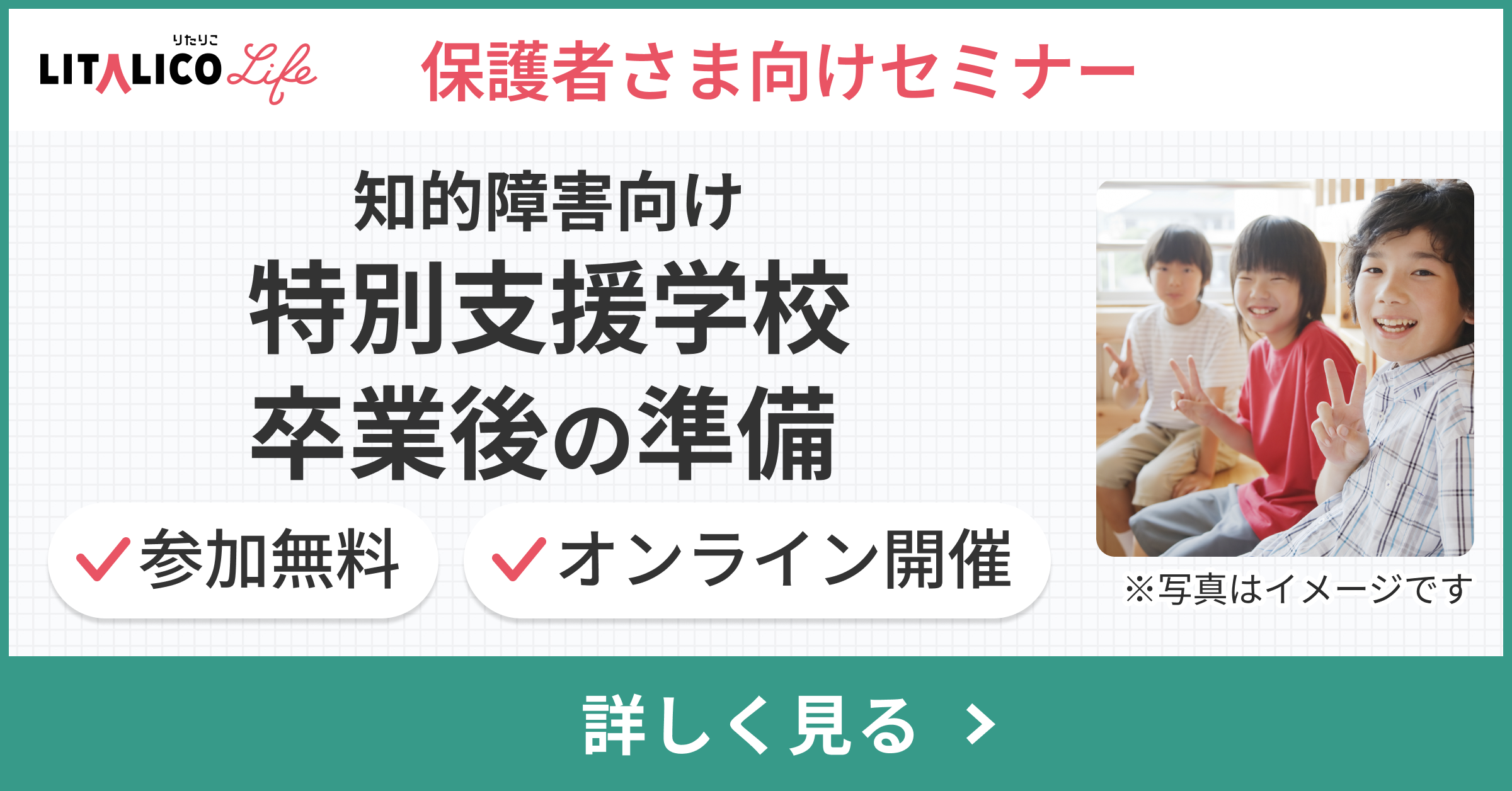ひきこもりが続く自閉症息子。もっと早く出合いたかった「訪問看護」利用までの道のり
ライター:花森はな

Upload By 花森はな
わが家にはASD(自閉スペクトラム症)と強度行動障害のある通信制高校2年生の息子がいます。息子は、小学校3年生の3学期から行き渋りが始まり、5年生には再登校できるようになりましたが、6年生で完全不登校に。特別支援学校中等部に進みましたが、あまり通うことはできませんでした。ひきこもり状態は、通信制高校に進学した今も続いています。今回はそんな息子が利用している訪問看護のお話です。
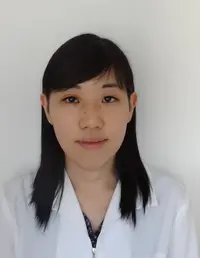
監修: 新美妙美
信州大学医学部子どものこころの発達医学教室 特任助教
2003年信州大学医学部卒業。小児科医師として、小児神経、発達分野を中心に県内の病院で勤務。2010年信州大学精神科・子どものこころ診療部で研修。以降は発達障害、心身症、不登校支援の診療を大学病院及び一般病院専門外来で行っている。グループSST、ペアレントトレーニング、視覚支援を学ぶ保護者向けグループ講座を主催し、特に発達障害・不登校の親支援に力を入れている。
多様な子育てを応援するアプリ「のびのびトイロ」の制作スタッフ。
閉ざされた訪問看護への道
息子が児童精神科に通い始めたのは、小学校3年生の頃でした。不登校をきっかけに受診したのが始まりです。最初の頃は一緒に受診できていたのですが、本人の調子がどんどん悪くなるにつれ、外出自体が困難になりました。そんな状況を心配してくださった特別支援学校の先生が「訪問看護を検討されてはどうですか?」と提案してくださいました。先生ご自身も障害のあるお子さんを育てていらっしゃるので、息子の様子を特に気にしてくださっていました。
しかし当時、子どもが利用できる精神科の訪問看護は圧倒的に少なく、いくつか問い合わせをしてみましたが、子どもは難しいということでほとんどの事業所に断られてしまいました。唯一受け入れてくれると仰ってくださった訪問看護ステーションの方は、ご自分のお子さんがうちの息子と同じ年だということで、かなり親身になって話を聞いてくださいました。
そして、児童精神科の担当医に「訪問看護を利用したい」と相談をしました。先生は「私の方針として、精神科の訪問看護は、お子さんにはお勧めできません。また、息子くんは学校の先生との関わりによる心の傷が深いので、もし訪問看護で新しい人との関わりが生まれ、再び大人への信頼を失うようなことになったら……という危惧もあります」とのことでした。
しかし当時、子どもが利用できる精神科の訪問看護は圧倒的に少なく、いくつか問い合わせをしてみましたが、子どもは難しいということでほとんどの事業所に断られてしまいました。唯一受け入れてくれると仰ってくださった訪問看護ステーションの方は、ご自分のお子さんがうちの息子と同じ年だということで、かなり親身になって話を聞いてくださいました。
そして、児童精神科の担当医に「訪問看護を利用したい」と相談をしました。先生は「私の方針として、精神科の訪問看護は、お子さんにはお勧めできません。また、息子くんは学校の先生との関わりによる心の傷が深いので、もし訪問看護で新しい人との関わりが生まれ、再び大人への信頼を失うようなことになったら……という危惧もあります」とのことでした。
※訪問看護は認知症以外の精神疾患も対象になります。精神科訪問看護を受けるためには、医師の精神科訪問看護指示書が必要です
コロナ禍で増えた?子どもの訪問看護
次に訪問看護を検討することになったのは、それから3年後のことです。息子の状況が大きく変化しました。過度の緊張をすると発作が起きるようになり、心因性非てんかん発作と診断されました。学校どころか、いつ発作が起こるか分からないので日常生活もままならず、私も勤務途中に息子から連絡を受け、大きな発作が起きる度に職場と自宅を何度も往復する日々でした。そして精神科を受診した際、改めて訪問看護の利用について相談してみると、快諾されました。その旨を相談支援の方にお伝えすると、すぐにたくさん資料を持ってきてくださり、すでにいくつかの訪問看護ステーションに問い合わせをしてくれていました。
資料を見て驚いたのは、この3年で子どもが利用できる精神科を専門とする訪問看護ステーションが増え、そして不登校支援も行っているところがかなり多かったことでした。コロナ禍で不登校の子どもが増えたことも原因かもしれません。私たちにとっては渡りに船の状況でした。
相談支援の方から「この訪問看護ステーションは男性の看護師さんがほとんどなので息子くんに合うかもしれません。とても良い事業所ですよ!」と勧められた2つの事業所に問い合わせました。家の近くの事業所は既に利用枠が埋まっていたのですが、最後の事業所は奇跡的に空いていました。すぐに面談と体験利用が決まりました。
資料を見て驚いたのは、この3年で子どもが利用できる精神科を専門とする訪問看護ステーションが増え、そして不登校支援も行っているところがかなり多かったことでした。コロナ禍で不登校の子どもが増えたことも原因かもしれません。私たちにとっては渡りに船の状況でした。
相談支援の方から「この訪問看護ステーションは男性の看護師さんがほとんどなので息子くんに合うかもしれません。とても良い事業所ですよ!」と勧められた2つの事業所に問い合わせました。家の近くの事業所は既に利用枠が埋まっていたのですが、最後の事業所は奇跡的に空いていました。すぐに面談と体験利用が決まりました。
障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施しています。
(厚生労働省|障害のある人に対する相談支援について)
もっと早く出合いたかった……短時間ケアと温かな寄り添い
担当の看護師さんとはすぐに打ち解け、訪問看護がスタートしました。訪問看護の内容は、病院との連携による心身状態の観察や服薬管理、日常生活への助言やサポートなどがあるそうです。息子の場合は服薬は夕食後なのでお願いせず、毎回の検温と血圧測定、そして体調の変化の共有をお願いし、残りの時間は話し相手になっていただきました。以前から利用している週2回のホームヘルパーに加え、週2回の訪問看護を利用することで、息子の日常的な見守りの体制が整いました。
ホームヘルパーの利用は1回1時間で、訪問看護の利用は1回30分と短いのですが、長時間他人と接するのがしんどい息子にはその短さがちょうどよかったようです。その短いようで長い時間を、主にゲームの話をして過ごします。「ゲームが好き」と相談支援の方があらかじめお伝えしてくださったので、ゲームの話ができる看護師さんを派遣してくださったようで、訪問時には「うちで担当している子どもたちはゲーム好きな子が多いので、練習用に事務所にゲーム機を置いてもらえないかなぁ」と話してくださいました。なかなか学校に行けない子どもたちに寄り添ってくれているのが、その言葉からも滲み出ていました。
また、入院した際は退院時のカンファレンスなど一人で悩んでいたことや退院後の生活調整のアドバイスをいただいたことは本当にありがたかったです。こんなことならもっと早く訪問看護を利用したかったなぁ……と思ったりもしました。
ホームヘルパーの利用は1回1時間で、訪問看護の利用は1回30分と短いのですが、長時間他人と接するのがしんどい息子にはその短さがちょうどよかったようです。その短いようで長い時間を、主にゲームの話をして過ごします。「ゲームが好き」と相談支援の方があらかじめお伝えしてくださったので、ゲームの話ができる看護師さんを派遣してくださったようで、訪問時には「うちで担当している子どもたちはゲーム好きな子が多いので、練習用に事務所にゲーム機を置いてもらえないかなぁ」と話してくださいました。なかなか学校に行けない子どもたちに寄り添ってくれているのが、その言葉からも滲み出ていました。
また、入院した際は退院時のカンファレンスなど一人で悩んでいたことや退院後の生活調整のアドバイスをいただいたことは本当にありがたかったです。こんなことならもっと早く訪問看護を利用したかったなぁ……と思ったりもしました。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています