親子の強い味方に!
発達特性のある子どもは、病院が苦手な子も少なくありません。特に外出が困難な子は「病院で受診する」ということの前に「定期的に病院へ行くこと自体の負担」が勝ってしまい、保護者も連れて行くことの困難さや子どもの心身を思うと、軽微な症状であれば受診をためらってしまうことがあります。そんな時、訪問看護を通じて主治医と連携がとれた看護師さんに気軽に相談できるのは本当に心強いです。先日も息子の体調が思わしくなく、病院へ行くほどではないかもしれないと悩んだ際、的確なアドバイスをいただきました。
訪問看護の利用を始めて、もうすぐ半年になりますが、わが家は利用できてよかったと心から思っています。
訪問看護の利用を始めて、もうすぐ半年になりますが、わが家は利用できてよかったと心から思っています。
もっと頼ってもいい!さまざまな選択肢
不登校のお子さんの保護者の方と話していた際、発達障害や精神疾患がある子どもの不登校へのサポートをしてくれる訪問看護ステーションがあることをほとんどの方が知りませんでした。私自身も、息子の調子が再び悪くならなければ、知らなかったことだと思います。
訪問看護は「家族への支援・相談」も行ってくださいます。特性があり、学校生活に困難を感じた子どものサポートは、家族だけでは不可能です。カウンセリングに行くまででもないけれど子どものことで悩んでいる、あまりに環境が違いすぎて周囲の人に相談できない、相談しても否定されてしまうような状況のことでも、医療者として話を聞いてくれる訪問看護はとてもありがたい存在です。障害のある不登校育児はどうしても抱え込んでしまいがちですが、なるべくこういったサービスを積極的に利用して、親子共々心の負担をできるだけ軽く、子どもの長い人生に寄り添っていきたいと思っています。
訪問看護は「家族への支援・相談」も行ってくださいます。特性があり、学校生活に困難を感じた子どものサポートは、家族だけでは不可能です。カウンセリングに行くまででもないけれど子どものことで悩んでいる、あまりに環境が違いすぎて周囲の人に相談できない、相談しても否定されてしまうような状況のことでも、医療者として話を聞いてくれる訪問看護はとてもありがたい存在です。障害のある不登校育児はどうしても抱え込んでしまいがちですが、なるべくこういったサービスを積極的に利用して、親子共々心の負担をできるだけ軽く、子どもの長い人生に寄り添っていきたいと思っています。
執筆/花森はな
(監修:新美先生より)
訪問看護利用についてのエピソードを聞かせてくださりありがとうございます。
訪問看護は、訪問看護師などがご自宅などに訪問して、療養生活を送っている方の看護を行うサービスです。看護師以外に、リハビリスタッフが行う訪問リハビリもあります。医師が治療上必要と判断して、訪問看護ステーションに指示書を出すと、医療保険が適用されるため、負担は病院での診療と同様になります。以前は、小児では医療的ケアが必要な方を中心に利用されてきましたが、近年発達障害や精神疾患があって、在宅で過ごすことの多い不登校、ひきこもり傾向のあるお子さんにも、訪問看護や訪問リハビリを利用すると、お子さんにとってメリットが大きいことが注目されてきて、小児や発達障害の方を対象とする訪問看護ステーションも広まりつつあるようです。とはいえ、このような利用のされ方が広まってまだ日が浅いので、こうした利用の仕方になじみのない地域、発達障害のあるお子さんを対象としていない看護ステーションも多いです。指示を出す医師の方も、経験がなくて戸惑うケースも少なくないかもしれません。
お子さんにとっても、安心安全の拠点であるべき自宅に、慣れない人が来ることで、領域侵犯されたと感じる方もいます。花森さんの場合、担当医の先生が初めは「お勧めしない」とおっしゃったのには、そのように判断されたのかもしれません。
自宅ということや、頻度も比較的多く利用できることから、かえって負担にならないように、利用に際して、担当医や訪問看護ステーションのスタッフと利用の仕方についてはよく話し合い、ご本人の意思をしっかり確認して、また実際に利用してみてからの本人の感触をしっかり聞き取って、よりよいやり方で継続できるといいですね。
訪問看護や訪問リハビリは、不登校・ひきこもり傾向の発達障害のある方にも、相性のよい利用の仕方が見つかると、利用の幅が広くとても使いやすい制度だと思います。どのような利用の仕方があるかのアイデアを、どんどんシェアしていけたらいいなと思います。
訪問看護利用についてのエピソードを聞かせてくださりありがとうございます。
訪問看護は、訪問看護師などがご自宅などに訪問して、療養生活を送っている方の看護を行うサービスです。看護師以外に、リハビリスタッフが行う訪問リハビリもあります。医師が治療上必要と判断して、訪問看護ステーションに指示書を出すと、医療保険が適用されるため、負担は病院での診療と同様になります。以前は、小児では医療的ケアが必要な方を中心に利用されてきましたが、近年発達障害や精神疾患があって、在宅で過ごすことの多い不登校、ひきこもり傾向のあるお子さんにも、訪問看護や訪問リハビリを利用すると、お子さんにとってメリットが大きいことが注目されてきて、小児や発達障害の方を対象とする訪問看護ステーションも広まりつつあるようです。とはいえ、このような利用のされ方が広まってまだ日が浅いので、こうした利用の仕方になじみのない地域、発達障害のあるお子さんを対象としていない看護ステーションも多いです。指示を出す医師の方も、経験がなくて戸惑うケースも少なくないかもしれません。
お子さんにとっても、安心安全の拠点であるべき自宅に、慣れない人が来ることで、領域侵犯されたと感じる方もいます。花森さんの場合、担当医の先生が初めは「お勧めしない」とおっしゃったのには、そのように判断されたのかもしれません。
自宅ということや、頻度も比較的多く利用できることから、かえって負担にならないように、利用に際して、担当医や訪問看護ステーションのスタッフと利用の仕方についてはよく話し合い、ご本人の意思をしっかり確認して、また実際に利用してみてからの本人の感触をしっかり聞き取って、よりよいやり方で継続できるといいですね。
訪問看護や訪問リハビリは、不登校・ひきこもり傾向の発達障害のある方にも、相性のよい利用の仕方が見つかると、利用の幅が広くとても使いやすい制度だと思います。どのような利用の仕方があるかのアイデアを、どんどんシェアしていけたらいいなと思います。

週2回のホームヘルプで叶えられた自閉症息子の願い。居宅介護と移動支援、わが家の利用方法

「学校に行けない呪い」不登校小3息子の葛藤。適応指導教室も合わず…再登校のきっかけになったのは

「お母さんが僕をこんな風にした!」壁を殴る蹴る…荒れる発達障害息子、完全不登校で中学進学は?【読者体験談/専門家アドバイスも】

介護・福祉業界を改革し、利用者、保護者、働く人、みんなが安心できる未来へ!全国介護事業者連盟理事長・斉藤正行さんインタビュー
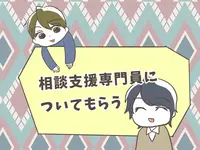
放デイでどんな支援をしてる?相談支援専門員を頼って分かった利用計画作成だけじゃないメリット
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
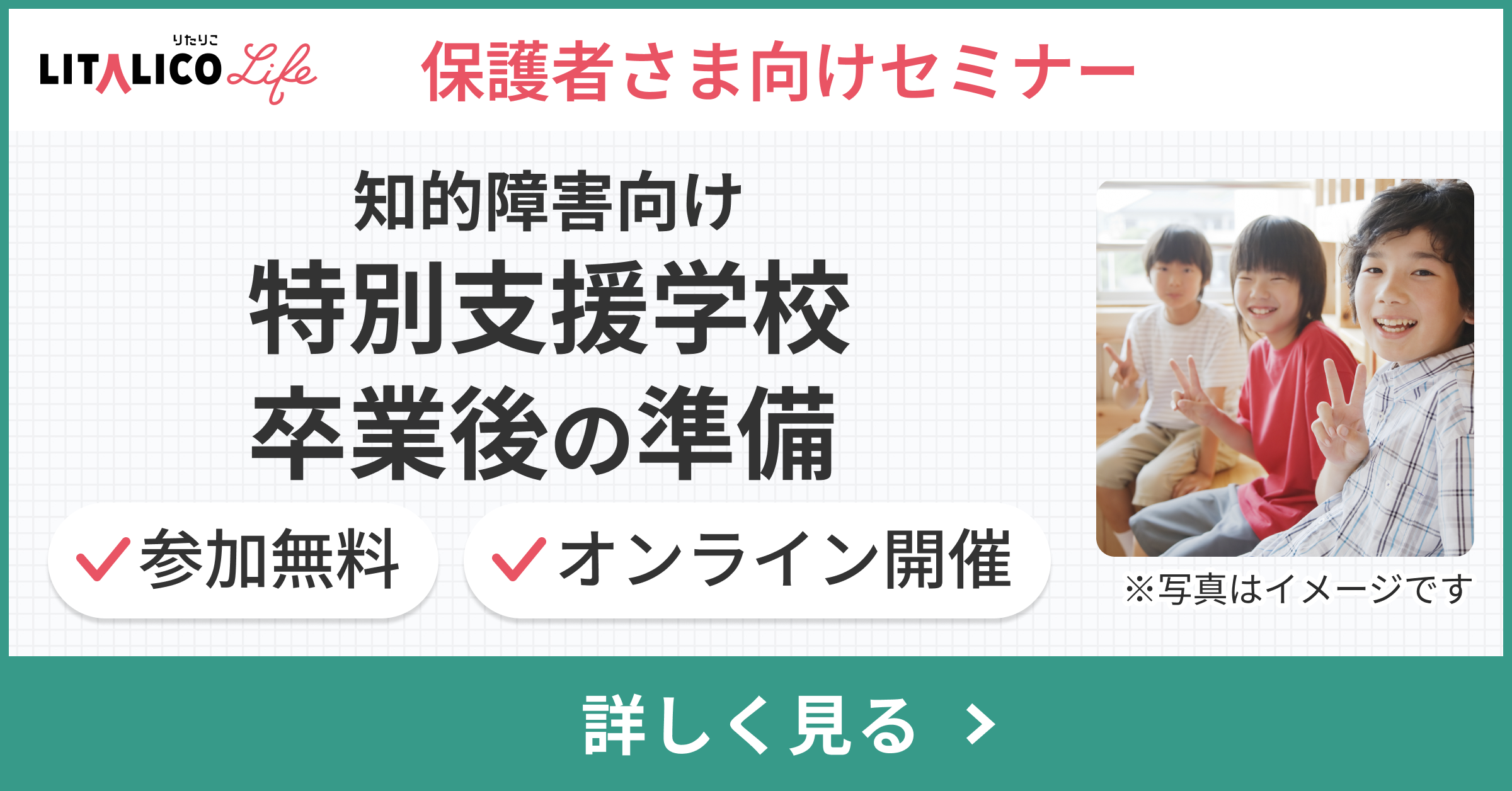
-
 1
1
- 2















