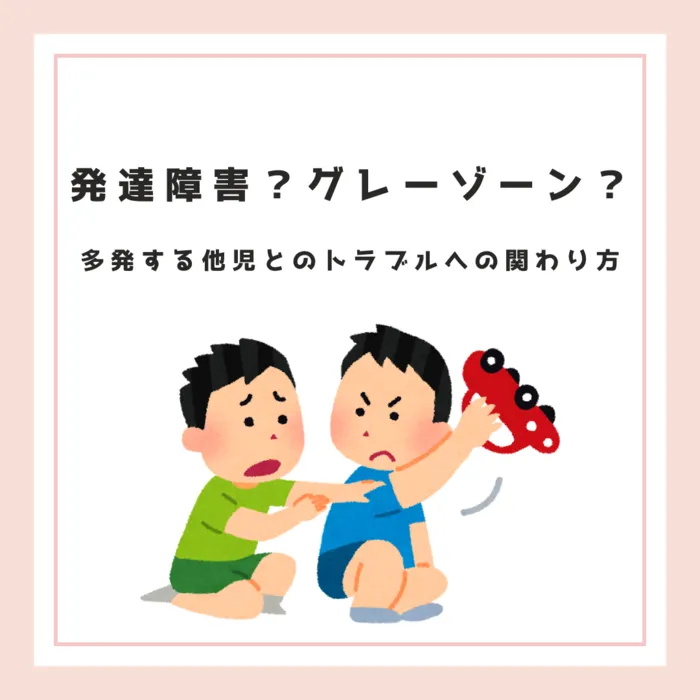
皆さま、こんにちは☺️
横浜市青葉区にあるフォレストキッズこどもの国教室の木山です。
昨年は本当にありがとうございました。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、新年初めての投稿は、幼稚園や保育園で他者とのトラブルが多い際の原因とその改善方法について考えていこうと思います。
幼児期で他者とのトラブルが多い場合には、さまざまな原因が考えられますが、ASD の特性などにより、社会性の部分に難しさを持っていることがあります。(社会性に難しさがあると必ず診断がつくものではありません。)
これは診断の有無やグレーゾーンだからなどは関係なく、社会性に難しさを感じている場合に、まずはその事実を受容し、周囲の環境を整えていくことが何より大事であり、本人が少しでも過ごしやすくなるために重要なポイントになります。
早速、以下に他者トラブルの具体例や対策、原因について記載していきます。
🔷ASDの特性による社会性の問題
🔹抽象的な概念や暗黙の了解の理解が苦手
* ASDの特性があるお子様は、言葉や行動を文字通りに解釈しやすいため、相手の冗談や皮肉、暗黙のルール(例:「人が話しているときは順番を待つ」「感情を表現するときのニュアンス」)がわからないことがあります。このため、「ルールを守らない」「わがまま」と誤解されることがある一方で、本人としては他者の期待が分からずに混乱している場合が多いです。
🔹社会的な合図や雰囲気を読み取ることの困難さ
* 他者の表情や声のトーンから感情を読み取る能力が低いため、相手が怒っている、悲しんでいる、困っているといった感情に気づけないことがあります。その結果、無意識に相手を傷つけたり、相手の怒りを買ったりする場合があります。
🔹感覚の違いによるトラブル
* ASDの特性があるお子様は、感覚過敏や鈍感さを伴うことがあります。例えば、大きな音や強い光に対する過敏さが理由でパニックを起こし、他の子どもたちが驚いたり距離を置いたりする場合があります。
🔷トラブルの具体例と解決方法
🔹トラブルの具体例
1. 遊びのルールを守れない
* 遊びの中で暗黙の了解(順番を守る、柔軟に役割を変えるなど)が守れず、他の子どもたちから「ルール違反」と指摘されることがあります。またASDの特性からくるこだわりなどでマイルールなどを押し付けてしまうことがあります。
2. 相手を傷つける言葉を言ってしまう
* 冗談や皮肉が理解できないため、相手の言葉を文字通りに受け取り、反論したり無神経な言葉を返してしまう場合があります。また相手の立場に立って考えることの難しさや、感情のコントロールなどの難しさにより、暴言などを衝動的に吐いてしまうことがあります。
3. 友達に嫌がられたり拒否されたりする
* 距離感や表情の理解などの理解が難しく、結果的にお友達が嫌がっている行動を継続することで、喧嘩になったり、近くに来られることを嫌がられることがあります。
🔹 トラブルの解決方法
1. 具体的な説明と視覚的サポート
* 抽象的な概念や暗黙のルールを言葉で説明するだけでなく、視覚的なサポート(絵カードやソーシャルストーリー)を使うと理解が進みます。
* 例:「お友だちが悲しいときは、肩に手を置いて『大丈夫?』と言う」といった行動を、絵や写真で示す。「悲しいとき」と言う表現も、涙が出ている時など客観的な情報にすることでより理解がしやすくなる場合があります。
2. 具体的なルールを明示する
* 「順番を守る」「自分の番が来るまで待つ」といった行動を具体的に教え、繰り返し練習することが有効です。後ほど原因についてお話ししますが、抽象的な概念の理解が難しい場合は、成長ともにその特性がなくなるわけではないですが、経験や客観的な事実の積み重ねによって適切な行動ができるよう支援していくことが大切です。
3. 感情の理解をサポートするプログラム
* 表情カード(表情がどの気持ちに属するのを学ぶ)や感情理解プログラム(特定のシチュエーションにおいてどのような気持ちになるかを学ぶ)を活用する。
🔷 医学的な原因
続いては、上記のようなことが起こる原因を医学的な観点から見ていきます。
ASDに関連する研究では、以下の仮説が注目されています。
🔹ミラーニューロン仮説
* ミラーニューロンは、他者の行動や感情を理解するために働く神経細胞です。このニューロンは、自分がある行動をする際だけでなく、他者がその行動をするのを見る際にも活動します。ASDの特性がある場合、このミラーニューロンの働きが弱い可能性があるとされています。このため、他者の行動や感情を自分のことのように感じ取りにくいと考えられており、それが原因で抽象的な概念の理解や、暗黙の了解、雰囲気の読み取りが難しいとされています。
🔹感覚処理の違い
* ASDの人では、脳内の感覚処理の仕組みに違いがあり、それが社会的なシグナルを読み取る困難さにつながっている可能性があります。例えば、顔の表情や声のトーンを処理する脳の部位(側頭葉や前頭葉)の活動が、定型発達の人とは異なるという研究があります。
🔶まとめ
このようにASDの特性により起こりうるトラブルと原因、その解決方法をご説明しましたが、何より、診断の有無やグレーゾーンなど関係なく社会性に難しさを感じている場合、その事実を受容し、周囲の環境整備の徹底を行うことこそが、お子様が少しでも快適に過ごしていくポイントになります。社会性に難しさを感じている場合、お友達や先生に指摘されたり、注意されたりする場面が極端に増えます。
そうなると、社会に対しての不信感や、誰も自分を認めてくれないという自信の喪失による自己肯定感の低下などにつながります。
頑張ってもできないことを理解してもらえないことは、50メートルを5秒で走れと言われてできないと理不尽に否定されて怒られるようなものです。
このような状況は、いわゆる二次障害のような不登校などにつながる可能性が高まるため、まずはお子様の抱えている社会性の難しさなどの事実の理解や受容をすることが大切です。
一般的に見ると問題行動であっても、本人からするとそれが正義であることを理解し、それに共感した上で適切な代替案などを提示することで、僕のこと理解してくれる人がいるんだといった充実感などから自己肯定感を高めていくことがファーストステップになります。
長くなりましたが、社会性に難しさを感じているお子様に対しては、その事実を受容するのを拒んでいると、一番の味方であるはずの保護者様からの理解してもえらず気持ち的な面でネガティブになり、成長や発達を阻害してしまうことにつながるため、まずは自己肯定感を高めるために、その事実を理解し、共感的態度を常に示すことが重要であることを頭に入れて過ごせると良いですね。
横浜市青葉区にあるフォレストキッズこどもの国教室の木山です。
昨年は本当にありがとうございました。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、新年初めての投稿は、幼稚園や保育園で他者とのトラブルが多い際の原因とその改善方法について考えていこうと思います。
幼児期で他者とのトラブルが多い場合には、さまざまな原因が考えられますが、ASD の特性などにより、社会性の部分に難しさを持っていることがあります。(社会性に難しさがあると必ず診断がつくものではありません。)
これは診断の有無やグレーゾーンだからなどは関係なく、社会性に難しさを感じている場合に、まずはその事実を受容し、周囲の環境を整えていくことが何より大事であり、本人が少しでも過ごしやすくなるために重要なポイントになります。
早速、以下に他者トラブルの具体例や対策、原因について記載していきます。
🔷ASDの特性による社会性の問題
🔹抽象的な概念や暗黙の了解の理解が苦手
* ASDの特性があるお子様は、言葉や行動を文字通りに解釈しやすいため、相手の冗談や皮肉、暗黙のルール(例:「人が話しているときは順番を待つ」「感情を表現するときのニュアンス」)がわからないことがあります。このため、「ルールを守らない」「わがまま」と誤解されることがある一方で、本人としては他者の期待が分からずに混乱している場合が多いです。
🔹社会的な合図や雰囲気を読み取ることの困難さ
* 他者の表情や声のトーンから感情を読み取る能力が低いため、相手が怒っている、悲しんでいる、困っているといった感情に気づけないことがあります。その結果、無意識に相手を傷つけたり、相手の怒りを買ったりする場合があります。
🔹感覚の違いによるトラブル
* ASDの特性があるお子様は、感覚過敏や鈍感さを伴うことがあります。例えば、大きな音や強い光に対する過敏さが理由でパニックを起こし、他の子どもたちが驚いたり距離を置いたりする場合があります。
🔷トラブルの具体例と解決方法
🔹トラブルの具体例
1. 遊びのルールを守れない
* 遊びの中で暗黙の了解(順番を守る、柔軟に役割を変えるなど)が守れず、他の子どもたちから「ルール違反」と指摘されることがあります。またASDの特性からくるこだわりなどでマイルールなどを押し付けてしまうことがあります。
2. 相手を傷つける言葉を言ってしまう
* 冗談や皮肉が理解できないため、相手の言葉を文字通りに受け取り、反論したり無神経な言葉を返してしまう場合があります。また相手の立場に立って考えることの難しさや、感情のコントロールなどの難しさにより、暴言などを衝動的に吐いてしまうことがあります。
3. 友達に嫌がられたり拒否されたりする
* 距離感や表情の理解などの理解が難しく、結果的にお友達が嫌がっている行動を継続することで、喧嘩になったり、近くに来られることを嫌がられることがあります。
🔹 トラブルの解決方法
1. 具体的な説明と視覚的サポート
* 抽象的な概念や暗黙のルールを言葉で説明するだけでなく、視覚的なサポート(絵カードやソーシャルストーリー)を使うと理解が進みます。
* 例:「お友だちが悲しいときは、肩に手を置いて『大丈夫?』と言う」といった行動を、絵や写真で示す。「悲しいとき」と言う表現も、涙が出ている時など客観的な情報にすることでより理解がしやすくなる場合があります。
2. 具体的なルールを明示する
* 「順番を守る」「自分の番が来るまで待つ」といった行動を具体的に教え、繰り返し練習することが有効です。後ほど原因についてお話ししますが、抽象的な概念の理解が難しい場合は、成長ともにその特性がなくなるわけではないですが、経験や客観的な事実の積み重ねによって適切な行動ができるよう支援していくことが大切です。
3. 感情の理解をサポートするプログラム
* 表情カード(表情がどの気持ちに属するのを学ぶ)や感情理解プログラム(特定のシチュエーションにおいてどのような気持ちになるかを学ぶ)を活用する。
🔷 医学的な原因
続いては、上記のようなことが起こる原因を医学的な観点から見ていきます。
ASDに関連する研究では、以下の仮説が注目されています。
🔹ミラーニューロン仮説
* ミラーニューロンは、他者の行動や感情を理解するために働く神経細胞です。このニューロンは、自分がある行動をする際だけでなく、他者がその行動をするのを見る際にも活動します。ASDの特性がある場合、このミラーニューロンの働きが弱い可能性があるとされています。このため、他者の行動や感情を自分のことのように感じ取りにくいと考えられており、それが原因で抽象的な概念の理解や、暗黙の了解、雰囲気の読み取りが難しいとされています。
🔹感覚処理の違い
* ASDの人では、脳内の感覚処理の仕組みに違いがあり、それが社会的なシグナルを読み取る困難さにつながっている可能性があります。例えば、顔の表情や声のトーンを処理する脳の部位(側頭葉や前頭葉)の活動が、定型発達の人とは異なるという研究があります。
🔶まとめ
このようにASDの特性により起こりうるトラブルと原因、その解決方法をご説明しましたが、何より、診断の有無やグレーゾーンなど関係なく社会性に難しさを感じている場合、その事実を受容し、周囲の環境整備の徹底を行うことこそが、お子様が少しでも快適に過ごしていくポイントになります。社会性に難しさを感じている場合、お友達や先生に指摘されたり、注意されたりする場面が極端に増えます。
そうなると、社会に対しての不信感や、誰も自分を認めてくれないという自信の喪失による自己肯定感の低下などにつながります。
頑張ってもできないことを理解してもらえないことは、50メートルを5秒で走れと言われてできないと理不尽に否定されて怒られるようなものです。
このような状況は、いわゆる二次障害のような不登校などにつながる可能性が高まるため、まずはお子様の抱えている社会性の難しさなどの事実の理解や受容をすることが大切です。
一般的に見ると問題行動であっても、本人からするとそれが正義であることを理解し、それに共感した上で適切な代替案などを提示することで、僕のこと理解してくれる人がいるんだといった充実感などから自己肯定感を高めていくことがファーストステップになります。
長くなりましたが、社会性に難しさを感じているお子様に対しては、その事実を受容するのを拒んでいると、一番の味方であるはずの保護者様からの理解してもえらず気持ち的な面でネガティブになり、成長や発達を阻害してしまうことにつながるため、まずは自己肯定感を高めるために、その事実を理解し、共感的態度を常に示すことが重要であることを頭に入れて過ごせると良いですね。

