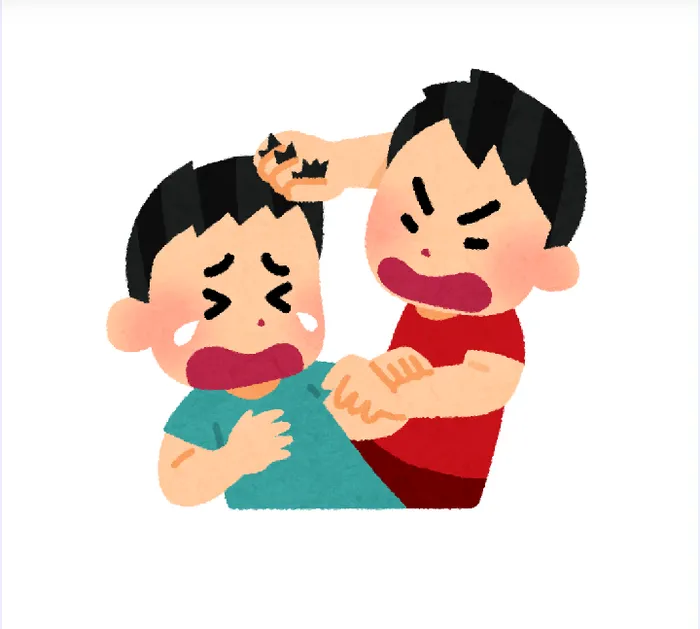
子どもたちが集団で過ごしていると、トラブルはつきものですよね。
他の子があそんでいるおもちゃが欲しくなったとき、
子どもたちはどうするのでしょうか?
「かして」と言えるお子さんは、
言葉で自分の思いを伝えることができ、安心できますよね。
では、発語がまだない(少ない)お子さんは、どうしたら自分の思いを伝えることができるのでしょうか?
ここでひとつ具体例を挙げてお話させていただきます。
A君とB君が一緒にプラレールであそんでいました。
すると突然、A君がB君の肩を何度も強くたたき、体当たりしてぶつかっていったのです。
驚いたB君は大声で泣き出してしましました。
A君は泣いているB君のことを少し気にしながらも、またプラレールであそび出しました。
これは、私が療育中、実際に経験した場面なのですが、A君はどうしてB君に他害をしてしまったのでしょうか?
A君は発語が少なく、自分の思いを言葉にするのが難しいお子さんなので、A君本人から事情を聞くことはできませんでしたが、A君の様子をしばらく見守っていくなかで、A君がB君のことを大好きなことがわかってきました。
そして、それこそが、A君のB君に対する他害の原因でした。
A君の特性として、先ほど挙げさせていただいた発語が少ないということの他に、体の使い方がぎこちなく、力の調整をすることが難しい、という点もありました。
よって、A君がB君にした他害の原因が、大好きなB君とあそびたかったゆえに、
①B君の肩をトントンとたたいて呼びかけようとしたところ、力の調整がうまくできず、叩くようになってしまった。
②B君のとなりに座ろうとしたが、体の使い方がぎこちなく、制御も効かないため、ぶつかってしまった。
ということがわかりました。
目に見える状況だけでなく、その背景になにがあるのかをしっかりと見極めることも、療育をおこなう上でとても大切な要素になります。
上記をふまえ、A君には、
・「いれて」「一緒にあそぼ」など、自分の思いを簡単なことばで伝える練習
・運動の調節ができるように、全身運動をおこなう中で、動⇔静へ動きを切り替える練習
などの療育をおこないました。
『他害』と聞くと、すべてが悪いイメージとして捉えられがちですが、このケースの場合、痛い思いをしたB君のみならず、
『自分の思いをうまく伝えることができなかったA君も辛い思いをしていた』のです。
療育をおこなえばすぐにお困りごとがなくなる、というわけではありません。
療育にはとても時間がかかる、ということも事実です。
ですが、お子さんのご様子をしっかりと見守り、
必要な療育をおこなっていくことで、
お困りごとは必ず少なくなっていきます。
どんな小さなことでも、お子さんに気になるご様子がみられましたら、ほーぷにご相談ください。
お子さんのこれからについて、一緒に考えていきましょう。
他の子があそんでいるおもちゃが欲しくなったとき、
子どもたちはどうするのでしょうか?
「かして」と言えるお子さんは、
言葉で自分の思いを伝えることができ、安心できますよね。
では、発語がまだない(少ない)お子さんは、どうしたら自分の思いを伝えることができるのでしょうか?
ここでひとつ具体例を挙げてお話させていただきます。
A君とB君が一緒にプラレールであそんでいました。
すると突然、A君がB君の肩を何度も強くたたき、体当たりしてぶつかっていったのです。
驚いたB君は大声で泣き出してしましました。
A君は泣いているB君のことを少し気にしながらも、またプラレールであそび出しました。
これは、私が療育中、実際に経験した場面なのですが、A君はどうしてB君に他害をしてしまったのでしょうか?
A君は発語が少なく、自分の思いを言葉にするのが難しいお子さんなので、A君本人から事情を聞くことはできませんでしたが、A君の様子をしばらく見守っていくなかで、A君がB君のことを大好きなことがわかってきました。
そして、それこそが、A君のB君に対する他害の原因でした。
A君の特性として、先ほど挙げさせていただいた発語が少ないということの他に、体の使い方がぎこちなく、力の調整をすることが難しい、という点もありました。
よって、A君がB君にした他害の原因が、大好きなB君とあそびたかったゆえに、
①B君の肩をトントンとたたいて呼びかけようとしたところ、力の調整がうまくできず、叩くようになってしまった。
②B君のとなりに座ろうとしたが、体の使い方がぎこちなく、制御も効かないため、ぶつかってしまった。
ということがわかりました。
目に見える状況だけでなく、その背景になにがあるのかをしっかりと見極めることも、療育をおこなう上でとても大切な要素になります。
上記をふまえ、A君には、
・「いれて」「一緒にあそぼ」など、自分の思いを簡単なことばで伝える練習
・運動の調節ができるように、全身運動をおこなう中で、動⇔静へ動きを切り替える練習
などの療育をおこないました。
『他害』と聞くと、すべてが悪いイメージとして捉えられがちですが、このケースの場合、痛い思いをしたB君のみならず、
『自分の思いをうまく伝えることができなかったA君も辛い思いをしていた』のです。
療育をおこなえばすぐにお困りごとがなくなる、というわけではありません。
療育にはとても時間がかかる、ということも事実です。
ですが、お子さんのご様子をしっかりと見守り、
必要な療育をおこなっていくことで、
お困りごとは必ず少なくなっていきます。
どんな小さなことでも、お子さんに気になるご様子がみられましたら、ほーぷにご相談ください。
お子さんのこれからについて、一緒に考えていきましょう。

