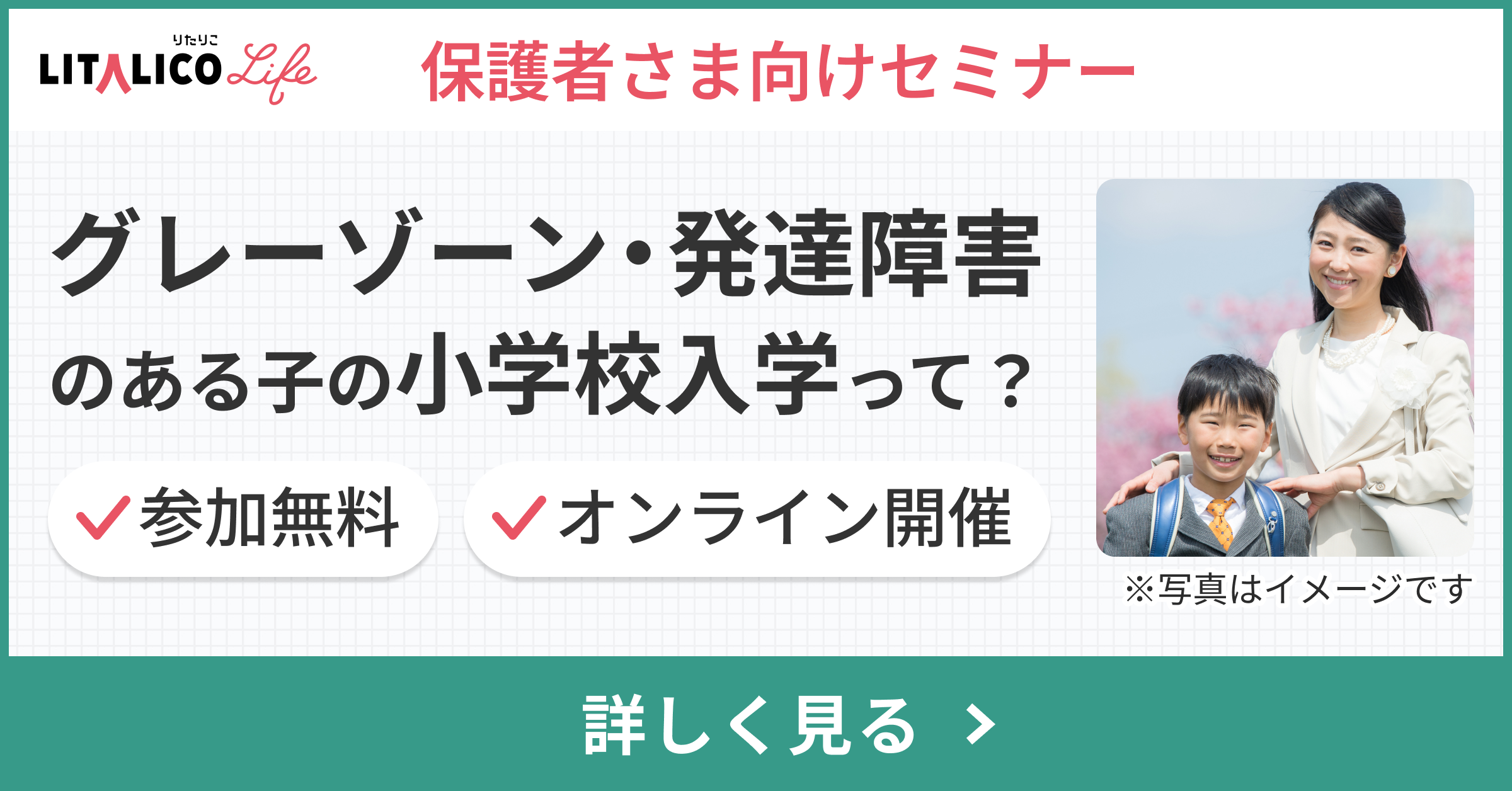あの楽々かあさんでも失敗するの?!支援ツールNG集【特別公開】
ライター:楽々かあさん

Upload By 楽々かあさん
アイデアが出やすい「大人の凸凹さん」の母 ×「健全な凸凹男子」の長男の組み合わせだと、家は毎日実験場と化します。今まで私は数多くの「アイデア支援ツール」を発明してきましたが、その裏では、息子のほうが一枚上手で、一瞬で努力が水の泡になったことも数知れず。今回は、支援ツールを作るコツを交えながら、そんな大失敗のアイデアの一部を、特別公開いたします!
健全な凸凹男子の長男。
「やって」と言われたことを素直にやってくれるのなら、こんなに苦労はしません。
そんな好奇心旺盛で集中力に偏りがあり、興味のあることにはエネルギーを全力投入する彼には、
・本人の興味、関心に合わせる
・できるだけ楽しく、負担の少ない方法にする
・合理的にメリットを説明する
などで、受け容れやすいアイデアをあの手この手で提案しています。
それでも息子のほうが一枚上手で、一瞬で母の努力が水の泡になり上手くいかなかったことは数知れず。
でも、そんな試行錯誤の過程も、結構楽しいと思えるようになりました。
今回は、そんな大失敗のアイデアの一部と、どうしたらめげずに支援ツール作りを続けていけるかのコツをお伝えします。
「やって」と言われたことを素直にやってくれるのなら、こんなに苦労はしません。
そんな好奇心旺盛で集中力に偏りがあり、興味のあることにはエネルギーを全力投入する彼には、
・本人の興味、関心に合わせる
・できるだけ楽しく、負担の少ない方法にする
・合理的にメリットを説明する
などで、受け容れやすいアイデアをあの手この手で提案しています。
それでも息子のほうが一枚上手で、一瞬で母の努力が水の泡になり上手くいかなかったことは数知れず。
でも、そんな試行錯誤の過程も、結構楽しいと思えるようになりました。
今回は、そんな大失敗のアイデアの一部と、どうしたらめげずに支援ツール作りを続けていけるかのコツをお伝えします。
「漢字が覚えられない」長男、あの手この手でやってみるも…
漢字を「書いて覚える」が苦手な長男は、漢字書き取りでどれだけノートに書いても、頭に入りません。
こういったお子さんには、書く以外の方法でアプローチを試してみるといいようです。
例えば・・・
・モールやブロック、粘土などで、立体的に作ってみる
・パーツに分解した漢字カルタや、漢字の足し算など、パズル的にやってみる
・漢字の成り立ち(象形文字)や部首の意味などを、絵や動画で理解する
などなど、いろんな方法が考えられます。
あるとき漢字の再テストが続き、うんざり気味で意気消沈している長男を見て、なんとかしてあげたい親心。
そこで早速、100円shopでカラー粘土を買って来て「これで、漢字作ってみたらいいかもよ?」と、そっと置いておきました。
すると、長男が楽しそうに粘土をこねて文字を作りはじめ、「しめしめ。食いついたな」とほくそ笑み、離れたキッチンから見守る母。
「かあちゃん!見て!超うまくできた!」
自信に溢れて、得意そうな長男。
やった!どれどれ?と、見に行くと…
こういったお子さんには、書く以外の方法でアプローチを試してみるといいようです。
例えば・・・
・モールやブロック、粘土などで、立体的に作ってみる
・パーツに分解した漢字カルタや、漢字の足し算など、パズル的にやってみる
・漢字の成り立ち(象形文字)や部首の意味などを、絵や動画で理解する
などなど、いろんな方法が考えられます。
あるとき漢字の再テストが続き、うんざり気味で意気消沈している長男を見て、なんとかしてあげたい親心。
そこで早速、100円shopでカラー粘土を買って来て「これで、漢字作ってみたらいいかもよ?」と、そっと置いておきました。
すると、長男が楽しそうに粘土をこねて文字を作りはじめ、「しめしめ。食いついたな」とほくそ笑み、離れたキッチンから見守る母。
「かあちゃん!見て!超うまくできた!」
自信に溢れて、得意そうな長男。
やった!どれどれ?と、見に行くと…
コレですよ、コレ。
親の心子知らず。
元気に小学生男子の王道を歩んでいます。
親の心子知らず。
元気に小学生男子の王道を歩んでいます。
移動教室の困りに「行動表」を作成!ところが…
支援級に移ってから、支援級→交流級→実技系の教室など、移動教室がとても多くなった長男。
あるとき教室を間違えてしまい、他のクラスの子達に笑われて悔しかったのだそう。
よっしゃ!かあちゃんがひと肌脱いであげよう!
先の見通しをつけて行動するのが苦手な子や、予定変更が苦手な子には「行動表」を作ってあげるといいようです。
作るポイントは・・・
・始まりから終わりまでの流れを、簡潔に順番に書く
・ゴール(終了時刻や、何をしたら終わりか)を教える
・もし、予定どおりに行かない場合は、どうすればいいかを書く
などの工夫で、落ち着いて行動できると思います。
うちでは過去、運動会の「本人用プログラム」や、家族旅行の「しおり」などでも同様の「行動表」を作って、うまくいっていました。
そこで、今回も学校用の「行動表」で落ち着いて行動できるように、サポートしようと思い立った母。
・小学生は係活動、図書館で本の返却などもあるため、時間割だけでなく、朝/昼/放課後の予定も書ける
・天気の変化に弱いので、その日の天気予報と最高気温/最低気温も書いて心の準備ができるように
・「(前日水筒を持ち帰り忘れた時)古いお茶は飲まないでね」など、母からの伝言メモ欄も
…と、工夫を凝らしたフォーマットを作り、連絡帳を元に母が書いたものを朝、担任の先生にチェックして頂くという連携体制もバッチリ整えています。
無くさないよう行動表には携帯ストラップの紐もつけ、首から下げられるようにしました。
ところが、導入数日後から「行動表」を持ち帰らない長男。
理由を聴くと、衝撃の一言。
「な・く・し・た」
…んだそうです。はあ〜。
おそらく、首にかけるのが煩わしかったのでしょう。
良いアイデアでも、「本人の使い勝手が良くないと、定着しない」という教訓です。
あるとき教室を間違えてしまい、他のクラスの子達に笑われて悔しかったのだそう。
よっしゃ!かあちゃんがひと肌脱いであげよう!
先の見通しをつけて行動するのが苦手な子や、予定変更が苦手な子には「行動表」を作ってあげるといいようです。
作るポイントは・・・
・始まりから終わりまでの流れを、簡潔に順番に書く
・ゴール(終了時刻や、何をしたら終わりか)を教える
・もし、予定どおりに行かない場合は、どうすればいいかを書く
などの工夫で、落ち着いて行動できると思います。
うちでは過去、運動会の「本人用プログラム」や、家族旅行の「しおり」などでも同様の「行動表」を作って、うまくいっていました。
そこで、今回も学校用の「行動表」で落ち着いて行動できるように、サポートしようと思い立った母。
・小学生は係活動、図書館で本の返却などもあるため、時間割だけでなく、朝/昼/放課後の予定も書ける
・天気の変化に弱いので、その日の天気予報と最高気温/最低気温も書いて心の準備ができるように
・「(前日水筒を持ち帰り忘れた時)古いお茶は飲まないでね」など、母からの伝言メモ欄も
…と、工夫を凝らしたフォーマットを作り、連絡帳を元に母が書いたものを朝、担任の先生にチェックして頂くという連携体制もバッチリ整えています。
無くさないよう行動表には携帯ストラップの紐もつけ、首から下げられるようにしました。
ところが、導入数日後から「行動表」を持ち帰らない長男。
理由を聴くと、衝撃の一言。
「な・く・し・た」
…んだそうです。はあ〜。
おそらく、首にかけるのが煩わしかったのでしょう。
良いアイデアでも、「本人の使い勝手が良くないと、定着しない」という教訓です。

連休はイレギュラーの連続!凸凹さんと楽しくお出かけする工夫
苦肉の策。あのひみつ道具を実際にやってみた!
4年生の通常学級の時。
長男のクラスでは、1年間百人一首の暗唱に取り組んでいました。
ところが、3学期になっても一首も暗記できていないのは長男だけ。
先生からは「せめて一首だけでもいいので、がんばって下さい」とのお願いが。
そんなこと言われてもね。
私もこれまで、できることは全部やってみたんですよ。
CD付きの百人一首一式を買って一緒にやってみたり、学習マンガで楽しく内容を理解させてみたり。
身近な例で面白おかしく例えてみても、それでも1年間できなかったんですから…。
良いアイデアが、なんッッッ!!にも思いつかないときは、片っ端から参考になりそうなものをとりあえず丸パクりでもいいので、実際にやってみることも大事です。
そうやっているうちに、うちの子に合った支援のコツを掴んでくるので「アタリ」が増えていきます。
そんな訳で、万策尽きて心折れそうな母はついに、苦肉の策に手を出してしまいました。
暗唱テストのある日の朝食。
もう、私にできるのはこれくらいしか思いつかないのです…
ジャーン!
「暗記パン!!」
長男のクラスでは、1年間百人一首の暗唱に取り組んでいました。
ところが、3学期になっても一首も暗記できていないのは長男だけ。
先生からは「せめて一首だけでもいいので、がんばって下さい」とのお願いが。
そんなこと言われてもね。
私もこれまで、できることは全部やってみたんですよ。
CD付きの百人一首一式を買って一緒にやってみたり、学習マンガで楽しく内容を理解させてみたり。
身近な例で面白おかしく例えてみても、それでも1年間できなかったんですから…。
良いアイデアが、なんッッッ!!にも思いつかないときは、片っ端から参考になりそうなものをとりあえず丸パクりでもいいので、実際にやってみることも大事です。
そうやっているうちに、うちの子に合った支援のコツを掴んでくるので「アタリ」が増えていきます。
そんな訳で、万策尽きて心折れそうな母はついに、苦肉の策に手を出してしまいました。
暗唱テストのある日の朝食。
もう、私にできるのはこれくらいしか思いつかないのです…
ジャーン!
「暗記パン!!」
母「どう?」
長男「うん、フツーにうまいよ。もぐもぐ」
母「覚えた?」
長男「別に」
…で・す・よ・ね~(笑)
時には「ムリなものはムリ!」とスッパリ諦めることも必要です。
そして、支援がなかなかうまくいかない時には、本人の話をじっくり聴いてみることが解決への糸口になります。
そこで、長男本人に「どんなことなら覚えられそう?」と聞いたところ、明解な答えが。
「おれが覚えられるのは、興味のあることと、サバイバルに必要なことと、うまいもの情報。それから、母ちゃんがイヤがりそうなコトだけ!脳みそのメモリ容量は限られているんだから、百人一首は入る場所がないよ」
…とのこと(笑)
がんばっても興味の持てないことは入力自体ができないように、長男の脳はとても合理的にできているのかもしれません。
そして、健全な凸凹男子は母のイヤがりそうなことだけは、本当によく覚えていて、毎日有言実行できるのです。
長男「うん、フツーにうまいよ。もぐもぐ」
母「覚えた?」
長男「別に」
…で・す・よ・ね~(笑)
時には「ムリなものはムリ!」とスッパリ諦めることも必要です。
そして、支援がなかなかうまくいかない時には、本人の話をじっくり聴いてみることが解決への糸口になります。
そこで、長男本人に「どんなことなら覚えられそう?」と聞いたところ、明解な答えが。
「おれが覚えられるのは、興味のあることと、サバイバルに必要なことと、うまいもの情報。それから、母ちゃんがイヤがりそうなコトだけ!脳みそのメモリ容量は限られているんだから、百人一首は入る場所がないよ」
…とのこと(笑)
がんばっても興味の持てないことは入力自体ができないように、長男の脳はとても合理的にできているのかもしれません。
そして、健全な凸凹男子は母のイヤがりそうなことだけは、本当によく覚えていて、毎日有言実行できるのです。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています