【専門家監修】DCD(発達性協調運動症)とは?具体的な特徴や対応法、子どもの体験談
ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
DCD(発達性協調運動症)とは、手と手、目と手、足と手など、複数の身体部位を協力させて行う運動が著しく困難な症状です。キャッチボール(球技)が苦手であったり、転んだ時に手が出ない、消しゴムを使うと紙が破れてしまったりと、日常生活での運動に困難が現れます。この記事では、DCD(発達性協調運動症)について、その定義、症状、原因、年齢別の困りごとの例、相談先、家庭でできることをご紹介します。

監修: 高畑脩平
藍野大学 医療保健学部 作業療法学科 講師
NPO法人はびりす 理事
作業療法士。NPO法人はびりす理事。専門は読み書き障害の子どもへの支援。著書に「子ども理解からはじめる感覚統合遊び 保育者と作業療法士のコラボレーション (クリエイツかもがわ)」ほか。
NPO法人はびりす 理事
DCD(発達性協調運動症)とは?
このコラムで分かること
- DCD(発達性協調運動症)の定義と、「単なる不器用さ」とは異なる日常生活への具体的な影響
- 【年齢別チェック】靴紐が結べない、食べこぼし、板書が苦手など、気づきのきっかけになるサイン
- ADHD(注意欠如多動症)やASD(自閉スペクトラム症)など、併発しやすい他の発達障害との関連性
- 作業療法(OT)や理学療法(PT)による専門的な支援内容と、家庭で楽しみながらできる感覚統合遊び
- 「できないこと」を責めずに道具や環境を工夫し、子どもの自己肯定感を育むためのポジティブな関わり方
DCD(発達性協調運動症/Developmental Coordination Disorder)は、手足など身体の動きをコントロールして行う協調運動が年齢相応に行うことができず、日常生活活動に支障が出る場合に診断されます。運動技能の欠如、知的障害(知的発達症)や視力障害、神経疾患などでは説明できないことを確認したうえで鑑別します。例えば、物をつかんだり、はさみや鉛筆などの道具を使うことが不正確である、書字に困難が生じるといったものが、日常生活活動に困難さを与えている状態です。
※発達性協調運動障害は現在、「発達性協調運動症」という診断名となっていますが、最新版『DSM-5-TR』以前の診断名である「発達性協調運動障害」といわれることも多くあります。この記事では以下、「DCD(発達性協調運動症)」と表記します。
協調運動とは、手と手、手と目、足と手などの個別の動きを一緒に行う運動です。例えば、私たちがキャッチボール(球技)をする時、ボールを目で追いながら、ボールをキャッチするという動作を同時にしていますよね。ほかにも、縄跳びをする時、ジャンプする動作と、縄を回す動作を同時にしなくてはなりません。このような運動を協調運動といいます。
本人の運動能力が期待されるよりどのくらい離れているかは、通常「MABC-2」(Movement Assessment Battery for Children,2nd Edition)や、「JPAN感覚処理行為機能検査」(日本版の感覚統合検査)などにより評価されます。これらの評価結果を参考に、医師がDCD(発達性協調運動症)かどうかを判断します。
人間の運動には大きく分けて、粗大運動と微細運動(巧緻運動)があります。人間は、さまざまな感覚器官から得られた情報をもとに、初めは姿勢を保つことや寝返りといった粗大運動を習得し、次第に段階を踏みながらより細かい微細運動ができるようになります。
※発達性協調運動障害は現在、「発達性協調運動症」という診断名となっていますが、最新版『DSM-5-TR』以前の診断名である「発達性協調運動障害」といわれることも多くあります。この記事では以下、「DCD(発達性協調運動症)」と表記します。
協調運動とは、手と手、手と目、足と手などの個別の動きを一緒に行う運動です。例えば、私たちがキャッチボール(球技)をする時、ボールを目で追いながら、ボールをキャッチするという動作を同時にしていますよね。ほかにも、縄跳びをする時、ジャンプする動作と、縄を回す動作を同時にしなくてはなりません。このような運動を協調運動といいます。
本人の運動能力が期待されるよりどのくらい離れているかは、通常「MABC-2」(Movement Assessment Battery for Children,2nd Edition)や、「JPAN感覚処理行為機能検査」(日本版の感覚統合検査)などにより評価されます。これらの評価結果を参考に、医師がDCD(発達性協調運動症)かどうかを判断します。
人間の運動には大きく分けて、粗大運動と微細運動(巧緻運動)があります。人間は、さまざまな感覚器官から得られた情報をもとに、初めは姿勢を保つことや寝返りといった粗大運動を習得し、次第に段階を踏みながらより細かい微細運動ができるようになります。
粗大運動と微細運動(巧緻運動)
粗大運動とは、感覚器官からの情報をもとに行う、姿勢と移動に関する運動です。
寝返り、這う、歩く、走るといった基本的な運動や、それらを土台に学習される泳ぐ、自転車に乗るなどのスキルも含まれます。
微細運動(巧緻運動)とは、感覚器官や粗大運動で得られた情報をもとに、小さい筋肉(特に指先など)の調整が必要な運動です。
モノをつまんだり、ひっぱったり、指先を使って行う細かな作業、例えば、絵を描く、ボタンをかける、字を書くなどの運動があります。成長と共に、粗大運動から、より細かい微細運動ができるようになります。
DCD(発達性協調運動症)のある人は、粗大運動や微細運動、またはその両方における協調運動が同年代に比べぎこちなく、遅かったり、不正確だったりします。
子どもによって、乳幼児期の粗大運動には全く遅れや苦手はなかったものの、幼稚園や小学校に行くようになり、微細運動を必要とする場面が増え、微細運動の困難さが顕著になる場合もあります。
寝返り、這う、歩く、走るといった基本的な運動や、それらを土台に学習される泳ぐ、自転車に乗るなどのスキルも含まれます。
微細運動(巧緻運動)とは、感覚器官や粗大運動で得られた情報をもとに、小さい筋肉(特に指先など)の調整が必要な運動です。
モノをつまんだり、ひっぱったり、指先を使って行う細かな作業、例えば、絵を描く、ボタンをかける、字を書くなどの運動があります。成長と共に、粗大運動から、より細かい微細運動ができるようになります。
DCD(発達性協調運動症)のある人は、粗大運動や微細運動、またはその両方における協調運動が同年代に比べぎこちなく、遅かったり、不正確だったりします。
子どもによって、乳幼児期の粗大運動には全く遅れや苦手はなかったものの、幼稚園や小学校に行くようになり、微細運動を必要とする場面が増え、微細運動の困難さが顕著になる場合もあります。
DCD(発達性協調運動症)の診断
現在使われている精神疾患の診断基準は、アメリカ精神医学会の『DSM-5-TR』(『精神障害のための診断と統計のマニュアル』第5版テキスト改訂版)と世界保健機関(WHO)の『ICD-10』(『国際疾病分類』第10版)(※)による診断基準があります。
現在、最新の診断基準である『DSM-5-TR』が主流になりつつありますが、医師や医療機関によってどちらの診断基準に準拠しているかは異なります。
『DSM-5-TR』と『ICD-10』では、診断基準に異なる点があります。
『DSM-5-TR』でDCD(発達性協調運動症)は、神経系の発達に不具合があると想定されている「神経発達症群」に入ります。そのため、知的障害(知的発達症)や知能指数との関係ではなく、協調運動が年齢相応に行うことができず、日常生活に支障が出ているかどうかで診断されます。
たとえば、
・物をつかんだり、はさみや鉛筆などの道具を使うことが不正確である
・ボールを投げる、縄跳びを跳ぶなどを行う際に、身体の使い方が極端に不器用である
などによって日常生活に困難がある場合は、DCD(発達性協調運動症)の可能性が高くなります。
なお、こうした症状は幼少期からみられ、運動技能の欠如は知的障害や視力障害、神経疾患などでは説明できないことを確認したうえで鑑別します。
『ICD-10』では、心理発達の障害に分類されるため、精神遅滞と知能指数が重要になります。明らかな精神遅滞(知能指数70以下)の場合、運動の困難さ、不器用さはその精神遅滞が原因によるものと判断されます。
現在ICD-10では診断名は「運動機能の特異的発達障害」となっていますが、ICD-11では「発達性協調運動症」と名称が変更されており、神経発達症群に入っています。
※ICD-10について:2019年5月、世界保健機関(WHO)の総会で、国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)が承認されました。日本国内ではこれから、日本語訳や審議、周知などを経て数年以内に施行される見込みです。WHOでの公表・承認を受けて、各国では翻訳やICD-10/11 変換表の作成、疾病分類表、死因分類表の作成などの作業が進められ、審議、周知などを経て施行されていきます。ICD-11への改訂によって分類コードが変化すると、書類上で要求されるICDコードが変わったり、疾病概念やカテゴリー、名称や診断基準も変更になったりする可能性もあります。
現在、最新の診断基準である『DSM-5-TR』が主流になりつつありますが、医師や医療機関によってどちらの診断基準に準拠しているかは異なります。
『DSM-5-TR』と『ICD-10』では、診断基準に異なる点があります。
『DSM-5-TR』でDCD(発達性協調運動症)は、神経系の発達に不具合があると想定されている「神経発達症群」に入ります。そのため、知的障害(知的発達症)や知能指数との関係ではなく、協調運動が年齢相応に行うことができず、日常生活に支障が出ているかどうかで診断されます。
たとえば、
・物をつかんだり、はさみや鉛筆などの道具を使うことが不正確である
・ボールを投げる、縄跳びを跳ぶなどを行う際に、身体の使い方が極端に不器用である
などによって日常生活に困難がある場合は、DCD(発達性協調運動症)の可能性が高くなります。
なお、こうした症状は幼少期からみられ、運動技能の欠如は知的障害や視力障害、神経疾患などでは説明できないことを確認したうえで鑑別します。
『ICD-10』では、心理発達の障害に分類されるため、精神遅滞と知能指数が重要になります。明らかな精神遅滞(知能指数70以下)の場合、運動の困難さ、不器用さはその精神遅滞が原因によるものと判断されます。
現在ICD-10では診断名は「運動機能の特異的発達障害」となっていますが、ICD-11では「発達性協調運動症」と名称が変更されており、神経発達症群に入っています。
※ICD-10について:2019年5月、世界保健機関(WHO)の総会で、国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)が承認されました。日本国内ではこれから、日本語訳や審議、周知などを経て数年以内に施行される見込みです。WHOでの公表・承認を受けて、各国では翻訳やICD-10/11 変換表の作成、疾病分類表、死因分類表の作成などの作業が進められ、審議、周知などを経て施行されていきます。ICD-11への改訂によって分類コードが変化すると、書類上で要求されるICDコードが変わったり、疾病概念やカテゴリー、名称や診断基準も変更になったりする可能性もあります。
DCD(発達性協調運動症)のある子どもの特徴は?困りごとをチェック
DCD(発達性協調運動症)のある子どもの年齢別の困りごとの傾向を具体的に見ていきます。
DCD(発達性協調運動症)かどうかの判断は、協調運動が本人の年齢や知能に応じて期待されるよりも著しく不正確なのか、困難であるかどうかが重要なポイントとなります。とはいえ、年齢が低ければ低いほど、得意な運動と困難な運動は子どもによって大きく差があり、人それぞれです。ですので、以下の例に当てはまるからといって、必ずしもDCD(発達性協調運動症)であるということではありません。
子どもの様子を見つつ、気になるときは専門家に相談してみましょう。
DCD(発達性協調運動症)かどうかの判断は、協調運動が本人の年齢や知能に応じて期待されるよりも著しく不正確なのか、困難であるかどうかが重要なポイントとなります。とはいえ、年齢が低ければ低いほど、得意な運動と困難な運動は子どもによって大きく差があり、人それぞれです。ですので、以下の例に当てはまるからといって、必ずしもDCD(発達性協調運動症)であるということではありません。
子どもの様子を見つつ、気になるときは専門家に相談してみましょう。
乳児期(1歳未満)の特徴
乳児期は、そもそも基本的な粗大運動を学び、獲得していく段階です。また、子ども一人ひとりの運動機能獲得のスピードは違いますし、できること、できないことも個人差が大きい時期です。そのため、苦手なことがあっても心配する必要がない場合も多いといえます。
ですが、DCD(発達性協調運動症)と診断される子どもは、乳児期に以下のような特徴が共通して見られる傾向があります。
例:母乳やミルクの飲みが悪い・むせやすい、離乳食を食べるとむせる、寝返りがうまくできない、ハイハイがうまくできない など
ですが、DCD(発達性協調運動症)と診断される子どもは、乳児期に以下のような特徴が共通して見られる傾向があります。
例:母乳やミルクの飲みが悪い・むせやすい、離乳食を食べるとむせる、寝返りがうまくできない、ハイハイがうまくできない など
幼児期(1歳以上6歳未満)の特徴
幼児期は、特に5歳を過ぎると、運動能力の個人差が縮まってきます。そのため、この時期にDCD(発達性協調運動症)と診断される場合が比較的多いといえます。DCD(発達性協調運動症)のある幼児は以下のような運動に不正確さや、習得の遅れ、困難さが見られる場合があります。
例:歩行がぎこちない、靴ひもを結べない、ボタンをはめるのが苦手、ファスナーを上げられない、転んだ時に手が出ない、平坦な場所で転ぶ、トイレで上手にお尻をふけない など
例:歩行がぎこちない、靴ひもを結べない、ボタンをはめるのが苦手、ファスナーを上げられない、転んだ時に手が出ない、平坦な場所で転ぶ、トイレで上手にお尻をふけない など
小学生(6歳以上13歳未満)
小学校に上がると日常生活、学習生活でより複雑で繊細な動作を求められる場面が増えます。そのため、微細運動での協調運動の問題が顕著に現れ、不器用さが目につきます。DCD(発達性協調運動症)のある子どもは以下のような運動に不正確さや、習得の遅れ、困難さが見られる場合があります。
例:模型を組み立てたりするのが苦手、ボール(球技)遊びが苦手、字が汚い、文字をますの中に入れて書けない、階段の上り降りがぎこちない、靴ひもを結べない、お箸をうまく使えない、文房具を使った作業が苦手(消しゴムで消すと紙が破れる、定規を押さえられずにずれるなど)、自転車に乗れない など
例:模型を組み立てたりするのが苦手、ボール(球技)遊びが苦手、字が汚い、文字をますの中に入れて書けない、階段の上り降りがぎこちない、靴ひもを結べない、お箸をうまく使えない、文房具を使った作業が苦手(消しゴムで消すと紙が破れる、定規を押さえられずにずれるなど)、自転車に乗れない など
DCD(発達性協調運動症)の特徴のある子どもの体験談
DCD(発達性協調運動症)の特徴のある子どもたちの困りごとについて、実際の体験談を一部紹介します。それぞれ、“工夫”を凝らして困難を乗り越えようとしている様子がうかがえます。
軽度知的障害・ASD・場面緘黙の診断がおりている娘。リボン結びができず、着替えに時間がかかるので、一人で脱ぎ履きするスニーカーは、スリッポン型のような靴紐のないタイプを選んでいます。字を書くことも苦手です。人より苦手なことが多いけれど、『できなかった、私はダメだ』と落ちこまないようにしたいと考えています。努力しても難しいのであれば、やり方や道具を工夫すればいい。コンプレックスを感じることが少なくなるよう環境を整えています。
【参照・一部抜粋】リボン結び、書字、着替えが苦手…軽度知的障害と発達障害のある娘の不器用さ。練習する?工夫する?母として優先したいのは

縄跳びが飛べなくて癇癪!ASD息子が「秘策」で笑顔に!?不器用すぎる息子と母の二人三脚――発達ナビユーザー体験談
自閉スペクトラム症(ASD)の息子は不器用さのため運動が苦手です。そんな息子が特に苦戦していたものが縄跳びです。小1のとき、『できない!もうやだ!』と縄跳びを地面に投げつけて泣いてしまう姿がありました。跳べずに癇癪をおこすため、その日から家で猛特訓。それでもなかなか跳べず、縄跳びの持ち手から縄の部分をはずし、持ち手だけを息子に渡しました。名付けて『エアー縄跳び』!縄がないので絶対に引っかかりません!息子は喜んでエアー縄跳びを手に、縄跳び集会に参加することができました。
【参照・一部抜粋】縄跳びが飛べなくて癇癪!ASD息子が「秘策」で笑顔に!?不器用すぎる息子と母の二人三脚――発達ナビユーザー体験談

リボン結び、書字、着替えが苦手…軽度知的障害と発達障害のある娘の不器用さ。練習する?工夫する?母として優先したいのは
おっとりした性格で、インドア派、発語や言葉の理解などもゆっくりだった娘。小学生の時は運動が大の苦手で、鉄棒も前回りだけ、跳び箱も3段以上は跳べず、プールも25m泳げず、自転車にも乗れず…。ところが中学1年の時に授業で自転車に乗って校外に出かけなければならず、猛練習。なんとか少し走れるようになりました。苦手なこと(他者に言葉で困りごとを伝えるなど)は、娘に合う方法を試行錯誤しながら良い対応方法などを見つけられるようにサポートをしたり、アドバイスをしていけたらと思います。
【参照・一部抜粋】運動苦手な発達グレー中1娘、突然の自転車の試練!クラスメートの前で「乗れるように」と言われたけれど、公道デビューは前途多難で――発達ナビユーザー体験談

運動苦手な発達グレー中1娘、突然の自転車の試練!クラスメートの前で「乗れるように」と言われたけれど、公道デビューは前途多難で――発達ナビユーザー体験談

Sponsored
喧嘩でケガ、不登校で転校…発達障害がある子との毎日を守る意外な方法--月200円で心理士相談までもサポート
DCD(発達性協調運動症)は治せるの?支援や治療方法
作業療法
作業療法は、作業(子どもの場合、主に遊び)を通して、日常生活で必要な動作を獲得できるよう支援を行うものです。運動、身辺処理、学習などの動作をスムーズに行えるようにするために、基本的な動作に加え、動きと動きの統合が必要な協調運動への支援を行います。
DCD(発達性協調運動症)のある子どもは、一つひとつの行動の統合が苦手であることが分かっているので、作業療法は症状の改善に効果があるといわれています。
DCD(発達性協調運動症)のある子どもは、一つひとつの行動の統合が苦手であることが分かっているので、作業療法は症状の改善に効果があるといわれています。

作業療法士の仕事や資格について、発達障害の人にOT・作業療法士が行う支援について紹介【専門家監修】
理学療法
広義には高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある人々に対し、運動機能の維持・改善を目的に運動、温熱、電気、水、光線などの物理的手段を用いて行われる治療法です。
特に運動による理学療法はDCD(発達性協調運動症)の改善に役立つとされています。理学療法士が行う運動を使った療育では、日常生活で必要な運動、行動を訓練し改善していきます。
特に運動による理学療法はDCD(発達性協調運動症)の改善に役立つとされています。理学療法士が行う運動を使った療育では、日常生活で必要な運動、行動を訓練し改善していきます。

理学療法士(PT)とは?仕事内容や資格の取得方法は?理学療法の受け方や発達障害の人への支援内容は?
家庭でもできること
家庭でもできることは多くあります。家庭でさまざまなサポートを行う場合は、まず、「こうするべき、こうあるべき」という先入観を捨て、子どもと一緒に楽しむことが長続きの秘訣です。あくまで遊びの中で取り入れ、”訓練”という位置づけにしないことも大切です。
家庭で見られる困りごとの例としては、以下のような例が挙げられます。
・手先がうまく使えていない
・正しくお箸の使い方を何度も教えても、なかなかお箸をうまく使いこなせない
・服のボタンをうまくはずしたり、かけたりすることができない
・文字を書くときに極端に筆圧が弱い、強い
上記のような困りごとに対して、考えられる不器用さの原因としては、
・手の筋肉の動きをうまく制御できない
・手元に注意が向いてない
・手の動きと視覚の情報の連携が取れていない
などが挙げられます。
これらを踏まえたうえで、手で身体を支える、力いっぱい握る、力の入れ方を調整するなど、さまざまな経験により、多様な手の使い方ができるようになると期待されます。
具体的に家庭でできることとしては、以下のような取り組みが考えられます。
・ブランコやアスレチックで遊び、どのくらいの力で自分の体重を支えられるようになるのかを学ぶ
・コイン遊びを通して、コインを握る、つまむ、入れるという動作を経験する。いろんな指でコインをつかむことで指の力の入れ加減を学ぶ
・粘土で遊び、粘土の形を変形させるなど、細かい作業を行うことで、感覚の加減を学ぶ
ここで紹介した方法はあくまで一例であり、このような考え方をもとに一人一人の子どもに合わせて楽しめるアレンジを加えることが大切です。
繰り返しになりますが、どんなに効果的と思われる訓練も楽しくなければ子どもたちは取り組んでくれません。訓練ではなく、楽しく取り組めることがもっとも重要です。
家庭で見られる困りごとの例としては、以下のような例が挙げられます。
・手先がうまく使えていない
・正しくお箸の使い方を何度も教えても、なかなかお箸をうまく使いこなせない
・服のボタンをうまくはずしたり、かけたりすることができない
・文字を書くときに極端に筆圧が弱い、強い
上記のような困りごとに対して、考えられる不器用さの原因としては、
・手の筋肉の動きをうまく制御できない
・手元に注意が向いてない
・手の動きと視覚の情報の連携が取れていない
などが挙げられます。
これらを踏まえたうえで、手で身体を支える、力いっぱい握る、力の入れ方を調整するなど、さまざまな経験により、多様な手の使い方ができるようになると期待されます。
具体的に家庭でできることとしては、以下のような取り組みが考えられます。
・ブランコやアスレチックで遊び、どのくらいの力で自分の体重を支えられるようになるのかを学ぶ
・コイン遊びを通して、コインを握る、つまむ、入れるという動作を経験する。いろんな指でコインをつかむことで指の力の入れ加減を学ぶ
・粘土で遊び、粘土の形を変形させるなど、細かい作業を行うことで、感覚の加減を学ぶ
ここで紹介した方法はあくまで一例であり、このような考え方をもとに一人一人の子どもに合わせて楽しめるアレンジを加えることが大切です。
繰り返しになりますが、どんなに効果的と思われる訓練も楽しくなければ子どもたちは取り組んでくれません。訓練ではなく、楽しく取り組めることがもっとも重要です。
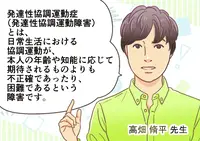
発達性協調運動症(発達性協調運動障害)とは?乳児期から小学生まで、年齢別の困りごと例も【専門家解説】ーーマンガで学ぶDCD
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
















