提出するか悩んだサポートブック
長男けんとが特別支援学級に入学する時は、サポートブックを作成し、学校に提出しました。サポートブックとは、その子の情報や特性、困りごとがあった際に有効な関わり方などを記す資料のことです。私はインターネットで見つけたサポートブックのテンプレートを自分でダウンロードし、印刷して記入しましたが、私の住んでいる地域では、地域の役所で記入できるサポートブックをいただけるようです。
次男ゆうきもサポートブックを作成しようかと思い悩んでいましたが、通っていた児童発達支援施設の先生が、ゆうきの施設での様子を記した資料を作成し、入学前の3月頃、小学校宛てに送ってくださったので、サポートブックの作成はしませんでした。
私からも担任の先生に伝えておきたいことを厳選して……
・ゆうきの困りやすいシーン(失敗したり負けたりすることがとても苦手で、立ち直るまでに時間がかかること……など)
・その場合は、こうやるとうまくいくことが多いという情報(クールダウンが必要になるかも、など)
というような内容を、ご挨拶も含めて1枚の紙にまとめ記入し、入学式の日の帰り際に担任の先生にお渡ししました。
次男ゆうきもサポートブックを作成しようかと思い悩んでいましたが、通っていた児童発達支援施設の先生が、ゆうきの施設での様子を記した資料を作成し、入学前の3月頃、小学校宛てに送ってくださったので、サポートブックの作成はしませんでした。
私からも担任の先生に伝えておきたいことを厳選して……
・ゆうきの困りやすいシーン(失敗したり負けたりすることがとても苦手で、立ち直るまでに時間がかかること……など)
・その場合は、こうやるとうまくいくことが多いという情報(クールダウンが必要になるかも、など)
というような内容を、ご挨拶も含めて1枚の紙にまとめ記入し、入学式の日の帰り際に担任の先生にお渡ししました。
心配性で、見通し不安のある次男のために
次男ゆうきが年長の2~3月頃、図書館で小学校生活について書いてある本を何冊も借りてきて、一緒に読みました。どんな科目があるのか、どんな教室があるのか、どんな行事があるのか……何となくでも見通しがたったほうが安心につながると思ったからです。
長男けんとの時は学校からのご提案で、入学式前日に学校へ見学に行き、入学式の流れを聞いたり実際に座る場所の確認をしたりしてくださいました。次男ゆうきは通常学級ということもあったのでこちらからもお願いしませんでしたが、入学式のだいたいの流れは家庭で説明しました。
次男ゆうきは通常学級に在籍しているので、今でもどこまで学校にお願いしていいのか分からなくなる時があります。悩んだ時は1人で悩まず、次男ゆうきを支えてくださるいろいろな方々に相談をさせていただきながら、これからも成長を見守っていけたらと思っています。
執筆/ゆきみ
長男けんとの時は学校からのご提案で、入学式前日に学校へ見学に行き、入学式の流れを聞いたり実際に座る場所の確認をしたりしてくださいました。次男ゆうきは通常学級ということもあったのでこちらからもお願いしませんでしたが、入学式のだいたいの流れは家庭で説明しました。
次男ゆうきは通常学級に在籍しているので、今でもどこまで学校にお願いしていいのか分からなくなる時があります。悩んだ時は1人で悩まず、次男ゆうきを支えてくださるいろいろな方々に相談をさせていただきながら、これからも成長を見守っていけたらと思っています。
執筆/ゆきみ
(監修:新美先生より)
次男さんの就学に向けた準備について詳しく教えてくださりありがとうございます。
通常学級在籍ということで、どこまで学校側にお願いできるのかを迷いながら進めていかれたことが伝わってきました。地域差もあり一概には言えませんが、通常学級であろうが特別支援学級であろうが、お子さんに必要な合理的配慮は求めていくことはそんなに遠慮しなくてもよいと思います。必要だと思う支援を求めたうえで、学校側との相談、交渉し、過度に負担にならない範囲の合意を得ていくプロセスが合理的配慮には必要ですよね。
とはいえ保護者としては迷うからこそ、記事に出てきたように、保育所等訪問支援を使うのはいい方法ですね。保育所等訪問支援の担当者なら、その地域のほかの学校の状況もある程度把握しているので、その地域のスタンダードを参考にしながら、通常学級内でできる、お子さんに必要な支援を具体的に提案していただけるのではないでしょうか。通常学級だからといって保育所等訪問支援の利用を断られることはあり得ないのでおすすめです。
長男さんの時に書いたサポートブックは次男さんの時には使わず、児童発達支援施設からの資料提出と、保護者の方からは1枚の紙に厳選してまとめてお伝えしたとのことでした。これもすごく重要なポイントで、サポートブックのように情報量が多すぎるとかえってしっかり見てもらえないリスクもあり、特に通常学級と言うことを考えると、1枚の紙にまとめるというのは得策だと思いました。また、入学前に、小学校生活の本を読んだり、入学式も分かる範囲で流れを説明するなど事前の準備もばっちりですね。保育園と小学校では雰囲気ががらりと変わるので、入学初日~始まった当初に面食らってしまわないように、事前にご本人が小学校生活をイメージできるように知らせておくことはとても大切だと思いました。
次男さんの就学に向けた準備について詳しく教えてくださりありがとうございます。
通常学級在籍ということで、どこまで学校側にお願いできるのかを迷いながら進めていかれたことが伝わってきました。地域差もあり一概には言えませんが、通常学級であろうが特別支援学級であろうが、お子さんに必要な合理的配慮は求めていくことはそんなに遠慮しなくてもよいと思います。必要だと思う支援を求めたうえで、学校側との相談、交渉し、過度に負担にならない範囲の合意を得ていくプロセスが合理的配慮には必要ですよね。
とはいえ保護者としては迷うからこそ、記事に出てきたように、保育所等訪問支援を使うのはいい方法ですね。保育所等訪問支援の担当者なら、その地域のほかの学校の状況もある程度把握しているので、その地域のスタンダードを参考にしながら、通常学級内でできる、お子さんに必要な支援を具体的に提案していただけるのではないでしょうか。通常学級だからといって保育所等訪問支援の利用を断られることはあり得ないのでおすすめです。
長男さんの時に書いたサポートブックは次男さんの時には使わず、児童発達支援施設からの資料提出と、保護者の方からは1枚の紙に厳選してまとめてお伝えしたとのことでした。これもすごく重要なポイントで、サポートブックのように情報量が多すぎるとかえってしっかり見てもらえないリスクもあり、特に通常学級と言うことを考えると、1枚の紙にまとめるというのは得策だと思いました。また、入学前に、小学校生活の本を読んだり、入学式も分かる範囲で流れを説明するなど事前の準備もばっちりですね。保育園と小学校では雰囲気ががらりと変わるので、入学初日~始まった当初に面食らってしまわないように、事前にご本人が小学校生活をイメージできるように知らせておくことはとても大切だと思いました。

自閉症の息子、就学時健診でパニック!特別支援学級に行ける?年中から始めた就学相談、サポートブックを書きながら願うこと

園・学校とどう連携する?検査結果共有のポイントを紹介します【LITALICO発達特性検査】

自閉症長男に通常学級は難しい?悩ましい就学問題。小学校見学で決め手になったポイントは

幼稚園で連日の友だちトラブル、気まずいママ友関係に悩み…特別支援学級に就学した今

先生や経験者のアドバイスに心が揺れて。「通常学級か、特別支援学級か」直前まで迷った就学問題【読者体験談】
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
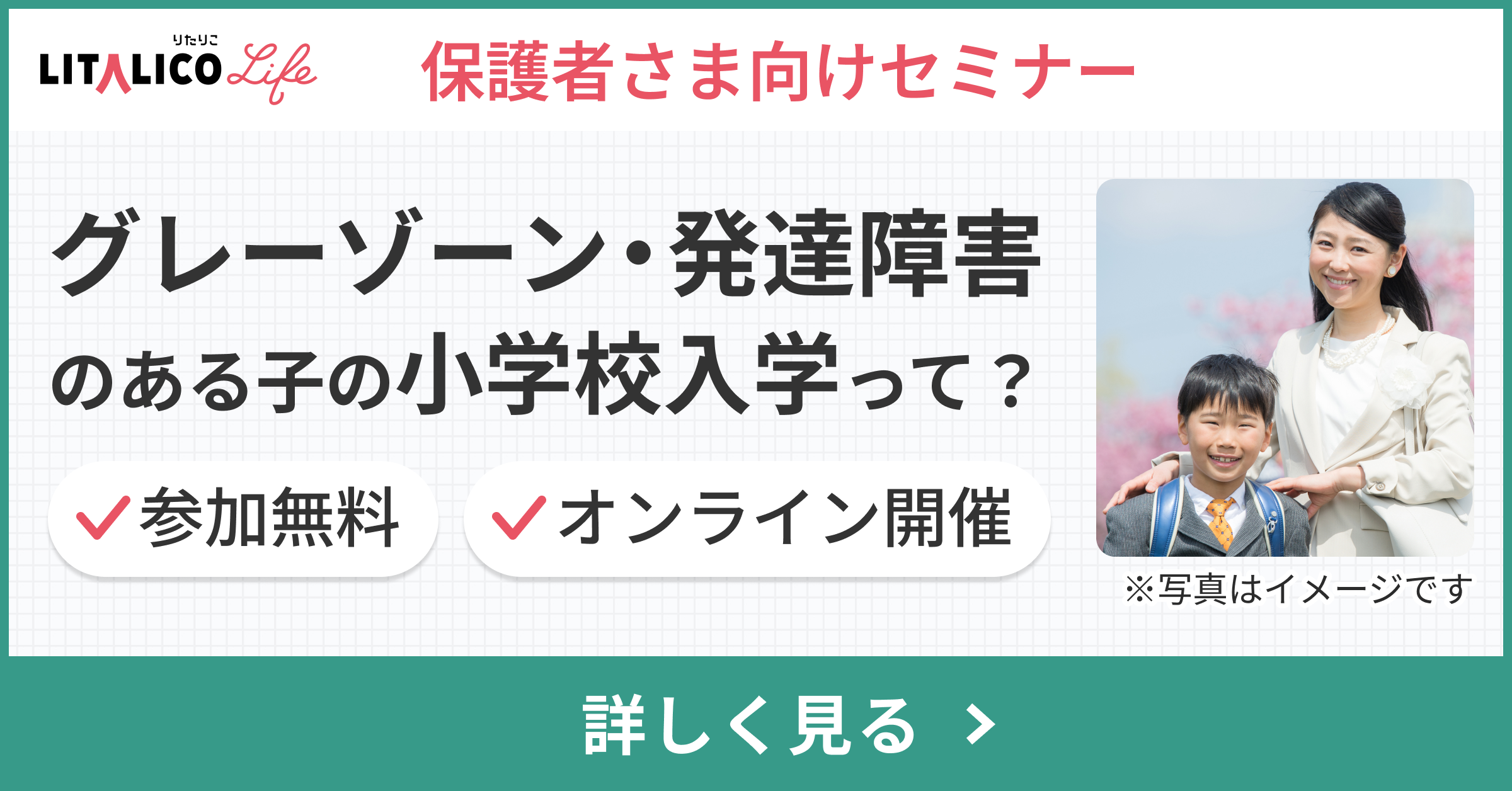
-
 1
1
- 2















