発達ナビでもおなじみの井上雅彦先生の新刊が登場!作業療法士考案の書字ワーク、基礎知識から将来展望まで分かる本も
ライター:発達ナビBOOKガイド
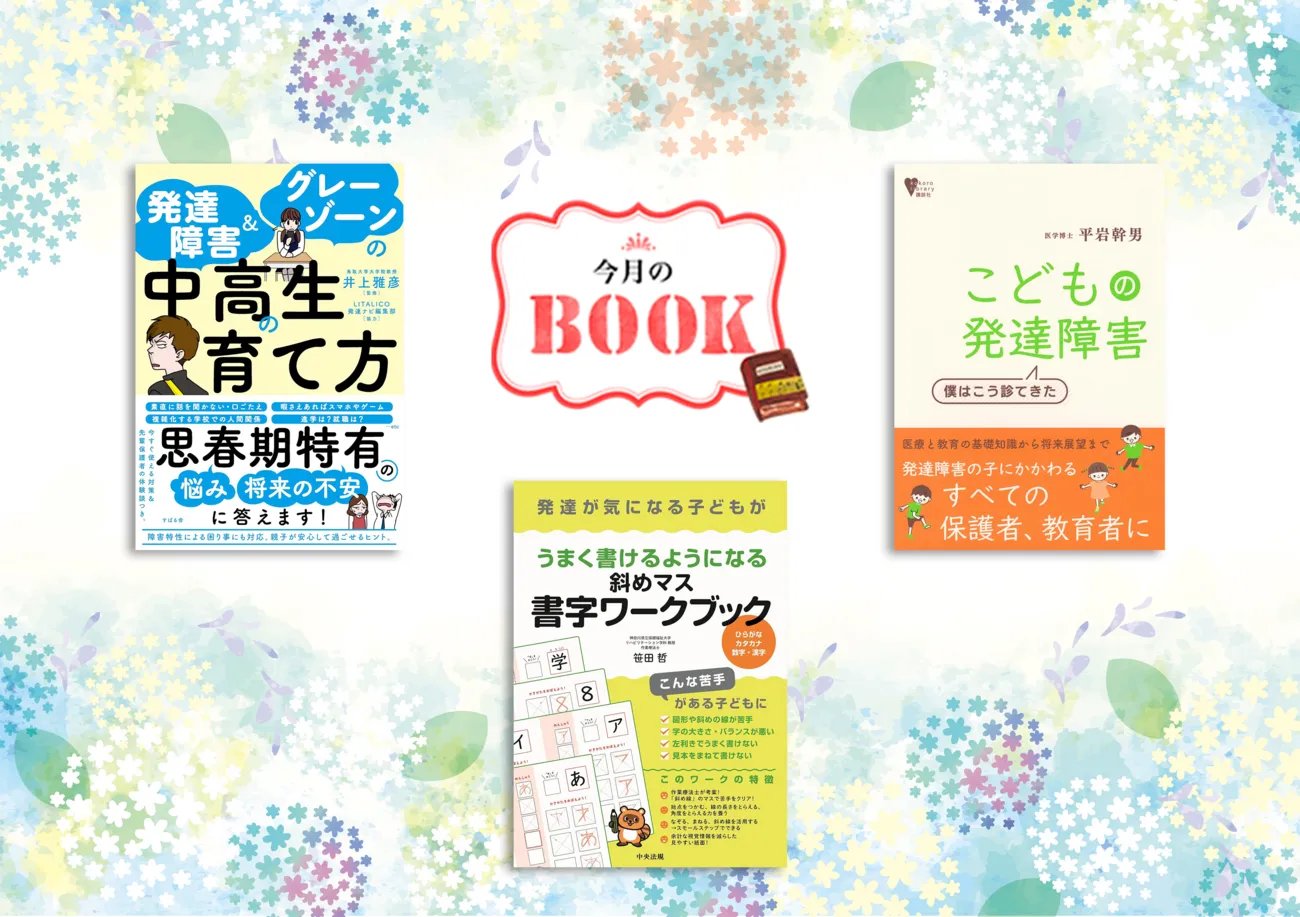
Upload By 発達ナビBOOKガイド
今月は、発達ナビも全面協力した井上雅彦先生の新刊「発達障害&グレーゾーンの中高生の育て方」、書字のお悩みに役立つ作業療法士考案のワークブック、平岩幹男先生の50年の臨床経験が詰まった一冊をご紹介します。
思春期の難しさに寄り添う子育てガイド『発達障害&グレーゾーンの中高生の育て方』
中学生になると、子どもたちは思春期や反抗期を迎え、これまでのような関わり方では通じなくなることが多くなります。発達障害やグレーゾーンのお子さんを持つ保護者の方にとって、この時期の子育てはより一層の戸惑いを感じる時期かもしれません。本書は、そんな中学生以降から18歳頃までのお子さんとの向き合い方を、優しく丁寧に教えてくれるガイドブックです。
この本の魅力は、専門的な知識と実際の子育て経験がバランスよく組み合わされていることです。臨床心理学や応用行動分析学、認知行動療法といった学術的な裏付けがありながらも、発達ナビの連載ライターや読者の皆さんが実際に試してみた工夫やアイデアがたくさん紹介されています。そのため、理論だけでなく「明日からすぐに試せそう」な内容が盛りだくさんです。
発達ナビが行った「中学生以降の子育てアンケート」によると、多くの保護者が「宿題・課題への取り組み」「進路選び」「ゲーム・スマホとの付き合い方」「学校に行きたがらない時の対応」「お友だちとのトラブル」といった悩みを抱えていることが分かりました。本書では、こうした身近な困りごとに対して、さまざまな角度からのアプローチ方法が紹介されています。
中高生になると、小学生の頃に比べて子どもたち自身の考えや意見がはっきりしてきます。それは成長の証でもある一方で、親子のやり取りが以前より複雑になることも意味しています。本書は、そんなお子さんの成長を温かく見守りながら、適切な距離感で支えていく方法を教えてくれます。
思春期特有の課題について、専門家の知見に基づく解決策や先輩保護者の体験談がたくさん詰まった本書は、中高生のお子さんとの関係に悩んでいる保護者の皆さまにとって、きっと心強い味方になってくれることでしょう。
この本の魅力は、専門的な知識と実際の子育て経験がバランスよく組み合わされていることです。臨床心理学や応用行動分析学、認知行動療法といった学術的な裏付けがありながらも、発達ナビの連載ライターや読者の皆さんが実際に試してみた工夫やアイデアがたくさん紹介されています。そのため、理論だけでなく「明日からすぐに試せそう」な内容が盛りだくさんです。
発達ナビが行った「中学生以降の子育てアンケート」によると、多くの保護者が「宿題・課題への取り組み」「進路選び」「ゲーム・スマホとの付き合い方」「学校に行きたがらない時の対応」「お友だちとのトラブル」といった悩みを抱えていることが分かりました。本書では、こうした身近な困りごとに対して、さまざまな角度からのアプローチ方法が紹介されています。
中高生になると、小学生の頃に比べて子どもたち自身の考えや意見がはっきりしてきます。それは成長の証でもある一方で、親子のやり取りが以前より複雑になることも意味しています。本書は、そんなお子さんの成長を温かく見守りながら、適切な距離感で支えていく方法を教えてくれます。
思春期特有の課題について、専門家の知見に基づく解決策や先輩保護者の体験談がたくさん詰まった本書は、中高生のお子さんとの関係に悩んでいる保護者の皆さまにとって、きっと心強い味方になってくれることでしょう。
発達障害&グレーゾーンの中高生の育て方
すばる舎
Amazonで詳しく見る
発達障害&グレーゾーンの中高生の育て方
すばる舎
楽天で詳しく見る
作業療法士考案「斜めマス」で文字が書きやすくなる『発達が気になる子どもがうまく書けるようになる斜めマス書字ワークブック ひらがな・カタカナ・数字・漢字』
「線をまっすぐ書くのが難しい」「文字の形がうまく整わない」「お手本を見ても同じように書けない」「マスからはみ出してしまう」など、文字を書くことで困っているお子さんのためにつくられたワークブックです。ひらがな、カタカナ、数字、小学校1・2年生で習う漢字14文字の練習をすることができます。
本書の大きな特徴は、「斜めマス」という新しいアイデアです。作業療法士である著者が30年以上、子どもたちが文字を書く様子を現場で見つめてきた経験から考案した方法で、マスに斜めの線が入っていることで、どこから書き始めればいいか、どの角度で線を引けばいいか、どのくらいの長さにすればいいか、どんな順番で書けばいいかが、自然と分かるようになります。お手本の文字も、読みやすい「ユニバーサルフォント」という誰もが読みやすい文字を使っています。
最初は斜めマスで練習して、だんだん慣れてきたら少しずつ見本の文字に近づけていけるように、無理のない進め方ができるようになっています。
文字を書くことが嫌になってしまわないように、楽しく続けられることを一番に考えられている本書。「うちの子、文字がうまく書けなくて困っているな」と感じている保護者の方にとって、お子さんの「書けた!」という喜びを一緒に感じられるような工夫が随所に凝らされています。
同じシリーズの『発達が気になる子どもの運筆力・認知力が身につくワークブック』と一緒に使うと、文字を書くのに必要な力を遊びながら楽しく伸ばすことができるので、こちらもおすすめです。
本書の大きな特徴は、「斜めマス」という新しいアイデアです。作業療法士である著者が30年以上、子どもたちが文字を書く様子を現場で見つめてきた経験から考案した方法で、マスに斜めの線が入っていることで、どこから書き始めればいいか、どの角度で線を引けばいいか、どのくらいの長さにすればいいか、どんな順番で書けばいいかが、自然と分かるようになります。お手本の文字も、読みやすい「ユニバーサルフォント」という誰もが読みやすい文字を使っています。
最初は斜めマスで練習して、だんだん慣れてきたら少しずつ見本の文字に近づけていけるように、無理のない進め方ができるようになっています。
文字を書くことが嫌になってしまわないように、楽しく続けられることを一番に考えられている本書。「うちの子、文字がうまく書けなくて困っているな」と感じている保護者の方にとって、お子さんの「書けた!」という喜びを一緒に感じられるような工夫が随所に凝らされています。
同じシリーズの『発達が気になる子どもの運筆力・認知力が身につくワークブック』と一緒に使うと、文字を書くのに必要な力を遊びながら楽しく伸ばすことができるので、こちらもおすすめです。
発達が気になる子どもがうまく書けるようになる斜めマス書字ワークブック ひらがな・カタカナ・数字・漢字
中央法規出版
Amazonで詳しく見る
発達が気になる子どもがうまく書けるようになる斜めマス書字ワークブック ひらがな・カタカナ・数字・漢字
中央法規出版
楽天で詳しく見る
50年の臨床経験と知見が詰まった一冊!『こどもの発達障害 僕はこう診てきた』
「発達障害って何だろう?」「どうやって診断されるの?」「どんな種類があるの?」「医療や教育はどんなふうに行われているの?」そんな疑問を持つ保護者の方に、ぜひ手に取っていただきたい本書。著者である平岩幹男先生が50年近くにわたって子どもたちと向き合ってきた豊富なご経験をもとに、発達障害について分かりやすく教えてくれます。
本書では、発達障害をめぐってさまざまな考え方や対応があることを踏まえながら、今の状況や課題、これからの方向性について丁寧に説明されています。まず、障害や発達障害に対する日本や世界の考え方を整理してから、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動症)、知的障害(知的発達症)、LD・SLD(限局性学習症)、DCD(発達性協調運動症)など、代表的な障害について詳しく解説しています。
特に心強いのは、発達障害のお子さんが使える社会の支援について、年齢に応じてどんな課題があるか、将来をどう考えていけばいいかまで、幅広く紹介されていることです。小学校入学から中学進学、思春期から大人になるまでの成長過程を見据えて、それぞれの時期に大切なことが書かれています。
「僕はこう診てきた」というタイトルに表れているように、専門的な内容を親しみやすい語り口で伝えてくれるところも、大きな魅力の一つです。発達障害について正しく理解したいけれど、専門書は難しそう……と感じる方にも読みやすく、それでいて必要な情報はしっかりと網羅されています。
長年にわたって多くの子どもたちとご家族に寄り添ってきた平岩先生の温かい視点と、確かな専門知識が合わさった本書は、保護者の方にとって、きっと頼りになる一冊となるのではないでしょうか。
本書では、発達障害をめぐってさまざまな考え方や対応があることを踏まえながら、今の状況や課題、これからの方向性について丁寧に説明されています。まず、障害や発達障害に対する日本や世界の考え方を整理してから、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動症)、知的障害(知的発達症)、LD・SLD(限局性学習症)、DCD(発達性協調運動症)など、代表的な障害について詳しく解説しています。
特に心強いのは、発達障害のお子さんが使える社会の支援について、年齢に応じてどんな課題があるか、将来をどう考えていけばいいかまで、幅広く紹介されていることです。小学校入学から中学進学、思春期から大人になるまでの成長過程を見据えて、それぞれの時期に大切なことが書かれています。
「僕はこう診てきた」というタイトルに表れているように、専門的な内容を親しみやすい語り口で伝えてくれるところも、大きな魅力の一つです。発達障害について正しく理解したいけれど、専門書は難しそう……と感じる方にも読みやすく、それでいて必要な情報はしっかりと網羅されています。
長年にわたって多くの子どもたちとご家族に寄り添ってきた平岩先生の温かい視点と、確かな専門知識が合わさった本書は、保護者の方にとって、きっと頼りになる一冊となるのではないでしょうか。
こどもの発達障害 僕はこう診てきた
講談社
Amazonで詳しく見る
こどもの発達障害 僕はこう診てきた
講談社
楽天で詳しく見る
LITALICO発達ナビ無料会員は発達障害コラムが読み放題!
https://h-navi.jp/column
https://h-navi.jp/column

Sponsored
勉強・学校生活・進路…思春期に悩む保護者へ!『発達障害&グレーゾーンの中高生の育て方』井上雅彦先生インタビュー

通信制高校でも週5日通う自閉症息子。一人での外出経験がなく電車通学が心配で待ち伏せしてみると…
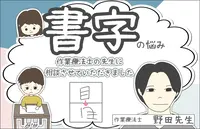
小2自閉症息子、読める字が書けない!テストも不正解…担任に「きれいに書くの諦めます」と言い出せず――作業療法士・野田先生に聞いた「褒めポイント」と「工夫」

【専門家回答】児童発達支援とは?個別支援計画、施設の併用、小集団のメリットなど【アンケート・保護者の声も紹介】

ひきこもりが続く自閉症息子。もっと早く出合いたかった「訪問看護」利用までの道のり
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
SLD(限局性学習症)
LD、学習障害、などの名称で呼ばれていましたが、現在はSLD、限局性学習症と呼ばれるようになりました。SLDはSpecific Learning Disorderの略。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
SLD(限局性学習症)
LD、学習障害、などの名称で呼ばれていましたが、現在はSLD、限局性学習症と呼ばれるようになりました。SLDはSpecific Learning Disorderの略。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

















