子どもの『脳のタイプ』を伝えるには?障害告知のヒント、発達とトラウマ…精神科医・田中康雄先生が選ぶ3冊【発達ナビ・あの人の本棚から】
ライター:発達ナビBOOKガイド
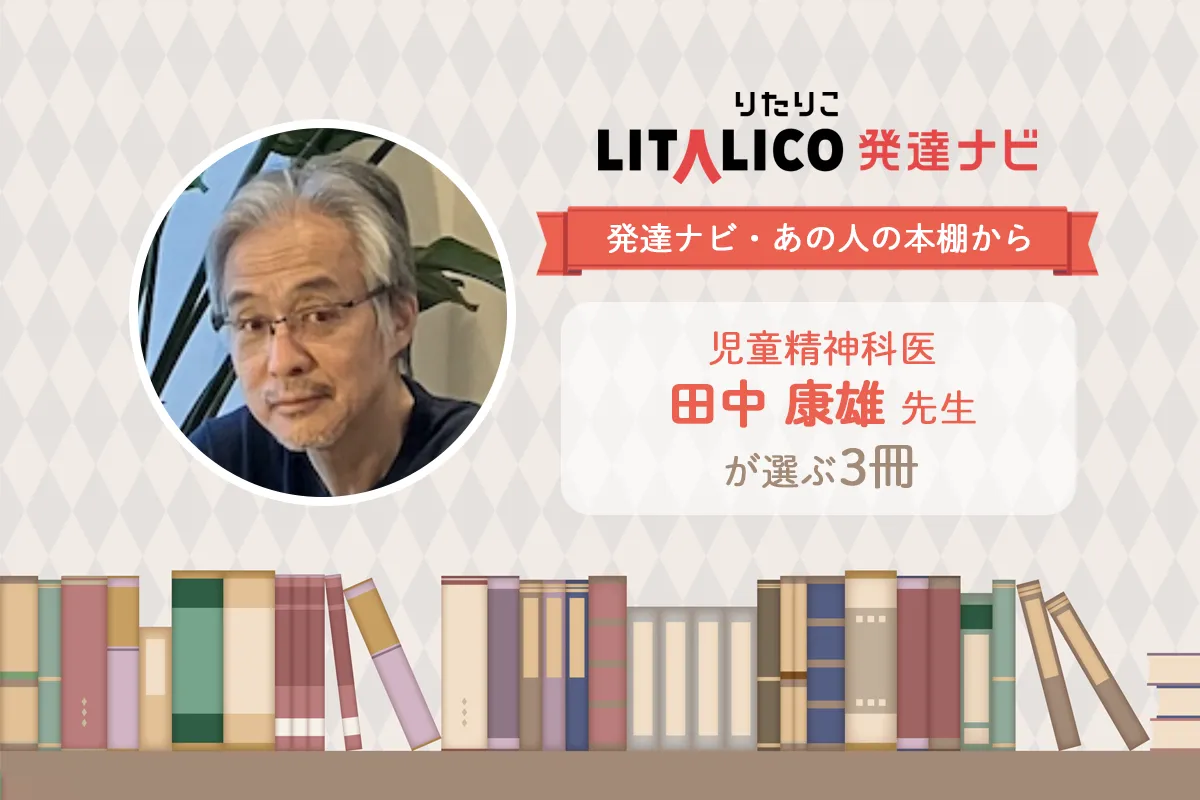
Upload By 発達ナビBOOKガイド
発達ナビでは、発達障害や子育て、教育の分野で活躍する専門家や実践者の皆さんに、「人生を豊かにしてくれた本」「多くの人におすすめしたい本」を紹介していただく連載【発達ナビ・あの人の本棚から】をお届けします。
今回は、長年にわたり発達障害のある子どもたちとその家族に寄り添い続けている精神科医・田中康雄先生に、「保護者向け」「支援者向け」「自著」の3つのカテゴリーから、おすすめの本を選んでいただきました。
田中康雄先生が選ぶ3冊は?
長年にわたり発達障害のある子どもたちとその家族に寄り添い続けてきた精神科医・田中康雄先生。豊富な臨床経験を通じて、子どもたちの困りごとや家族の悩みに向き合い、適切な支援につなげるための実践を重ねてこられました。
今回、そんな田中先生に、発達ナビの連載企画として「保護者の方へ」「支援に携わる方へ」「著者ご自身の作品」という3つの観点から、心からおすすめしたい書籍を選んでいただきました。
今回、そんな田中先生に、発達ナビの連載企画として「保護者の方へ」「支援に携わる方へ」「著者ご自身の作品」という3つの観点から、心からおすすめしたい書籍を選んでいただきました。
田中康雄先生が選ぶ!保護者の方におすすめの1冊『自閉スペクトラム「自分のこと」のおしえ方 増補版 特性説明・診断告知マニュアル』(吉田友子 著)
ロングセラー『自閉症・アスペルガー症候群 「自分のこと」の教え方』の増補改訂版として2023年に発売された本書は、ASD(自閉スペクトラム症)の子どもたちへの「説明という支援」のための実践的なマニュアルです。
子ども自身が自分の特性を理解し、肯定的に考えられるようにするために、いつ、誰が、どのように説明したらよいのか、著者が臨床現場で取り組んできた事例をもとに、説明文例を多数掲載しながら具体的に解説しています。
増補改訂版では、診断名の変更など医学の最新情報を反映し、支援の対象となる「子ども」を大学生にまで広げ、小学生から大学生までの幅広い年齢層をカバー。さらに、本文中で紹介しているひな型(資料・説明文例・勉強会資料など)のPDFデータを、専用のWebサイト
からダウンロードして実際に使える実用性の高い内容となっています。
「欠落ではなく、ひとつの認知スタイルとしての自閉スペクトラム」「強みと苦手は、同じ特徴の表と裏」という視点で、子どもたちが自分らしく生きていくための土台作りを支援します。
子ども自身が自分の特性を理解し、肯定的に考えられるようにするために、いつ、誰が、どのように説明したらよいのか、著者が臨床現場で取り組んできた事例をもとに、説明文例を多数掲載しながら具体的に解説しています。
増補改訂版では、診断名の変更など医学の最新情報を反映し、支援の対象となる「子ども」を大学生にまで広げ、小学生から大学生までの幅広い年齢層をカバー。さらに、本文中で紹介しているひな型(資料・説明文例・勉強会資料など)のPDFデータを、専用のWebサイト
からダウンロードして実際に使える実用性の高い内容となっています。
「欠落ではなく、ひとつの認知スタイルとしての自閉スペクトラム」「強みと苦手は、同じ特徴の表と裏」という視点で、子どもたちが自分らしく生きていくための土台作りを支援します。
【田中康雄先生のおすすめポイント】短所だけでなく、たくさんの長所があるお子さんの「脳のタイプ」を分かりやすく伝えるために
うちの子に、いつ、どんなふうに診断名を伝えたら、「障害告知」をしたらよいのでしょうか?診察室で、何度となく尋ねられる言葉です。
そんなとき、僕は「診断名の説明は僕からします」と伝え、説明文を作ります。それをまず親に見てもらいます。親が読んでみて、違和感があったり、不安に思い言葉があれば、相談して修正します。説明は、障害告知でなく、キミが持っている「脳のタイプ」を分かりやすく伝えることで、短所だけでなく、たくさんの長所もある「脳のタイプ」の持ち主であることを伝えます。
そうです。僕の説明文は、本書にあるひな形をその子の年齢、状況、家族の思いを参考に多少はアレンジしたものです。10年以上お世話になっており、今回さらにバージョンアップした本書は、医師だけでなく家族にとっても役立つ本であることは間違いありません。
そんなとき、僕は「診断名の説明は僕からします」と伝え、説明文を作ります。それをまず親に見てもらいます。親が読んでみて、違和感があったり、不安に思い言葉があれば、相談して修正します。説明は、障害告知でなく、キミが持っている「脳のタイプ」を分かりやすく伝えることで、短所だけでなく、たくさんの長所もある「脳のタイプ」の持ち主であることを伝えます。
そうです。僕の説明文は、本書にあるひな形をその子の年齢、状況、家族の思いを参考に多少はアレンジしたものです。10年以上お世話になっており、今回さらにバージョンアップした本書は、医師だけでなく家族にとっても役立つ本であることは間違いありません。
自閉スペクトラム「自分のこと」のおしえ方 増補版 特性説明・診断告知マニュアル
Gakken
Amazonで詳しく見る
自閉スペクトラム「自分のこと」のおしえ方 増補版 特性説明・診断告知マニュアル
Gakken
楽天で詳しく見る
支援者の方におすすめの1冊:『発達とトラウマから診る精神科臨床』(青木省三 著)
50年近く精神科診療に携わってきた著者が、現在の精神科臨床の変化に着目して書かれた専門書です。統合失調症やうつ病などの典型的な病像が減り、ベースに発達障害(神経発達症)やトラウマのある患者さんが増えてきた現状を踏まえ、新しい臨床アプローチを提案しています。
統合失調症、双極性障害(双極症)、うつ病、不安障害(不安症)などの具体的な症例を通じて、発達特性やトラウマの視点から患者さんを理解し、薬物療法だけでなく環境調整や精神療法の重要性を実践的に解説。「何かに困って(悩んで)いるのではないか」「何か現実に支援できることはないか」と素朴に考える精神医学の大切さを伝えています。
統合失調症、双極性障害(双極症)、うつ病、不安障害(不安症)などの具体的な症例を通じて、発達特性やトラウマの視点から患者さんを理解し、薬物療法だけでなく環境調整や精神療法の重要性を実践的に解説。「何かに困って(悩んで)いるのではないか」「何か現実に支援できることはないか」と素朴に考える精神医学の大切さを伝えています。
【田中康雄先生のおすすめポイント】既存の概念から少し自由になれる本
発達障害、そしてトラウマという言葉が、単発で医療、福祉、教育現場を席巻しています。こうした事柄に関心が向き、深く理解されようとしているのはありがたいと思う反面、猫も杓子も「発達障害」、なんでもかんでも「トラウマ」という状況に向かっていないか、そんな不安ななか、この本が世に出ました。
実は非常に挑戦的な本です。これまでの精神医学体系を崩す面があるからです。
実は非常に当たり前の本です。発達と生活環境を重視しその個体と環境の絡み合いで生じた生きづらさこそが精神症状である、と本書は説いています。
目からうろことはこのことで、既存の概念から少し自由になれる本です。
実は非常に挑戦的な本です。これまでの精神医学体系を崩す面があるからです。
実は非常に当たり前の本です。発達と生活環境を重視しその個体と環境の絡み合いで生じた生きづらさこそが精神症状である、と本書は説いています。
目からうろことはこのことで、既存の概念から少し自由になれる本です。
発達とトラウマから診る精神科臨床
医学書院
Amazonで詳しく見る
発達とトラウマから診る精神科臨床
医学書院
楽天で詳しく見る

















