発達ナビユーザーへおすすめの自著1冊:『僕の児童精神科外来の覚書 子どもと親とともに考え、悩み、実践していること』(田中康雄 著)
児童精神科医として長年の経験を積み重ねてきた著者が、日々の臨床現場で出会った子どもたちや家族との関わりを通じて学んだことを綴った実践記録です。「子どものつまずきや親の苦悩に思いを馳せ、隣でともに考え続ける」という著者の実直かつ真摯な姿勢が、全編を通じて伝わってきます。
本書は、就学前から思春期まで、子どもの発達段階に応じた具体的な支援方法を、豊富な事例とともに解説。「生活障害としてかかわる」「診立てる」「関わりについて」「連携」など、教科書では学べない臨床の極意が詰まっています。
不登校への対応、虐待してしまう親への支援、関係機関との連携など、現場で直面するさまざまな課題についても、著者の経験に基づいた実践的なアプローチを提示。単なる技法の紹介にとどまらず、子どもと親の「育ちを信じて」「刻を味方に」するという、先生の臨床現場での実体験を通じて学べる貴重な一冊です。保護者の方にも、支援者の方にも、そして当事者の方にも、新たな気づきを与えてくれることでしょう。
本書は、就学前から思春期まで、子どもの発達段階に応じた具体的な支援方法を、豊富な事例とともに解説。「生活障害としてかかわる」「診立てる」「関わりについて」「連携」など、教科書では学べない臨床の極意が詰まっています。
不登校への対応、虐待してしまう親への支援、関係機関との連携など、現場で直面するさまざまな課題についても、著者の経験に基づいた実践的なアプローチを提示。単なる技法の紹介にとどまらず、子どもと親の「育ちを信じて」「刻を味方に」するという、先生の臨床現場での実体験を通じて学べる貴重な一冊です。保護者の方にも、支援者の方にも、そして当事者の方にも、新たな気づきを与えてくれることでしょう。
【田中康雄先生から】読者のみなさんへのひとこと
先の2冊に比べて、読み劣りするのは、自著だからです。
3冊のなかに、自著を入れるということで、いちおう最新の本をあげました。クリニックを開いて10年越え、その中で改めて考えた子どもの精神科外来診療に対する僕の個人的な思いです。僕の本の中では、外来での学びというひとつの軸の中で、考えたことをまとめたものです。書いているときは、あれもこれもと思いつつ、書き終えると不足したところばかりに気がついて、日々の臨床と同じく、関わりは「続く」ということになります。
独りよがりのところも多いのですが、現時点で僕が考え実践している報告書であることは間違いありません。これからまた次へ、僕は進みたいとは思っています。
3冊のなかに、自著を入れるということで、いちおう最新の本をあげました。クリニックを開いて10年越え、その中で改めて考えた子どもの精神科外来診療に対する僕の個人的な思いです。僕の本の中では、外来での学びというひとつの軸の中で、考えたことをまとめたものです。書いているときは、あれもこれもと思いつつ、書き終えると不足したところばかりに気がついて、日々の臨床と同じく、関わりは「続く」ということになります。
独りよがりのところも多いのですが、現時点で僕が考え実践している報告書であることは間違いありません。これからまた次へ、僕は進みたいとは思っています。
僕の児童精神科外来の覚書 子どもと親とともに考え、悩み、実践していること
日本評論社
Amazonで詳しく見る
僕の児童精神科外来の覚書 子どもと親とともに考え、悩み、実践していること
日本評論社
楽天で詳しく見る
まとめ
田中康雄先生が選ばれた3冊は、発達障害のある子どもたちとその家族、そして支援者の方々にとって、それぞれ異なる視点から深い学びを提供してくれる本です。これらを通じて、発達障害のある子どもたちの唯一無二の思いに寄り添い、より良い支援につなげていくためのヒントを見つけてみませんか?

「発達障害ではなく、一人ひとりと向き合う」精神科医が伝えたい保護者への思いとは。登校渋りや思春期の親子関係、親なきあともーー田中康雄先生のコラムまとめ

話しかけても良いときかどうか判断をしよう!

精神科医・田中康雄先生、ファザ―リング・ジャパン・橋謙太氏、発達ナビ編集長が「障害がある子どもの自立や保護者のキャリア」まで語り合う。映画『旅立つ息子へ』×LITALICO発達ナビ座談会レポート
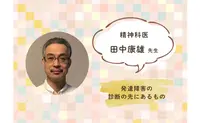
発達が気になる子の「診断」の先にあるものとは。育ちに必要な医師・支援者「協働」への7つの心構えーー精神科医・田中康雄先生

「楽しいこと以外はしない」家事拒否だった発達障害息子が18歳を境に大変身!?転機となったのは
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

-
 1
1
- 2















