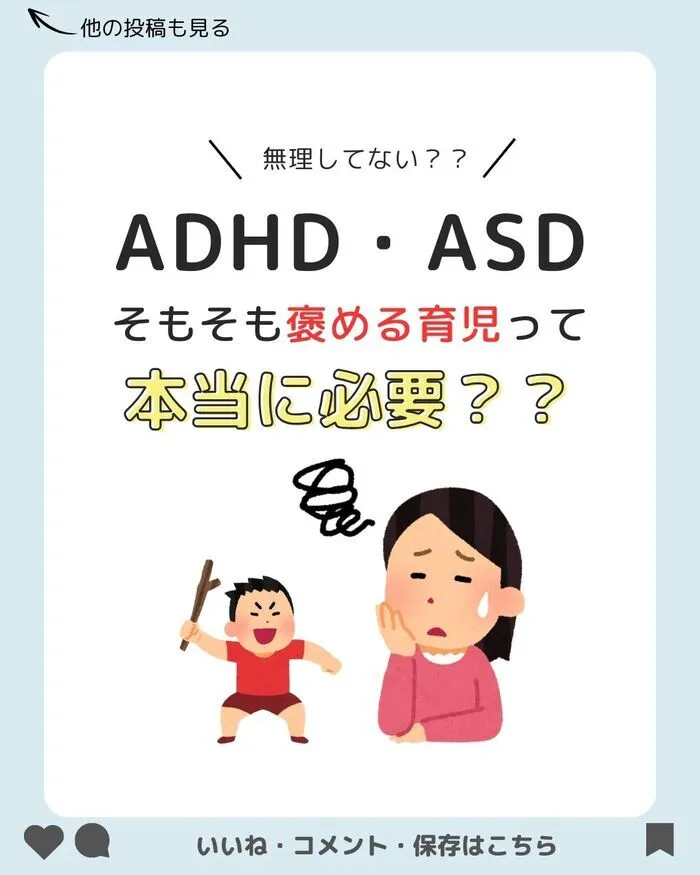
みなさん、こんにちは。
フォレストキッズこどもの国教室です。
本日は前回に引き続き、「褒める育児」についてお話ししようと思います。
褒める育児が大切だとよく言われており、実際に前回の投稿でも褒める育児のポイントについてお話ししましたが、今回は本当に褒める育児は必要なのかといった観点で解説していこうと思います。
今回このようなタイトルにした理由としては、特性のある子の育児の場合、実際問題、指摘することばかりでうまく褒めてあげれないといった内容のご相談をよくいただくからです。
それでは早速、以下にて解説していきます。
そもそも褒める育児とは
褒める育児のメリットは以下のようなものが挙げられます。
・自己肯定感が高まる
・親子の信頼関係が深まる
・ポジティブな行動が増える
また、褒める育児というものは、発達に特性のあるお子様に対しては、更に有効的なケースが多いです。
それは、特性のあるお子様は指摘や失敗経験が重なりやすく、自己肯定感が低下しやすい事や、誰も認めてくれないという認知を予防、改善できる可能性があるからです。
特性のあるお子様への褒めるポイントについては前回の投稿をご確認ください。
さて、本題ですが褒める育児は本当に必要なのでしょうか。特に特性のある子の子育ての場合、現実問題、褒めてあげるどころか、どうしても指摘ばかりしてしまい自己嫌悪感を感じている方も多いのではないでしょうか。
その場合は、むしろ「褒める育児」に囚われすぎないことが重要です。うまく褒めてあげられなくても「適切な指摘」で代替可能です。
そもそも褒める育児の目的は、最初にも挙げたように、自己肯定感の向上や親子の信頼関係を深める事、ポジティブな行動を増やすことが主に挙げられます。これは、「適切な指摘」においても補うことができます。
この「適切な指摘」ですが、それは
共感(肯定)+指摘(代替案の提示)です。
ex)ご飯の時間にお片付けできずに癇癪を起こした
「まだ遊びたかったから、嫌で泣いちゃったんだよね。(共感)+でも今はご飯の時間だから一緒に食べようね(指摘)」といった具合です。
どうしてもしてしまう指摘に共感を入れることで、褒める育児とは異なるアプローチ方法で自己肯定感や信頼関係の構築、ポジティブな行動の強化を目指します。
問題行動には必ずその行動をした背景や理由(特性由来のもの)があるため、共感してもらえる回数が増えると理解してくれている安心感や信頼感関係の構築により言うことを聞いてくれるようになるケースがよくあります。
「共感」をとにかく意識すれば、指摘することもなかなか褒めてあげれないことも問題ない場合が多いです。ただ、もちろん褒めることも大切なので、まずは褒めれずに「指摘」ばかりしてしまうことが悪いことだという認識を少しづつ緩和させ、心の余裕から自然に褒めれるようになると良いですね。
フォレストキッズこどもの国教室です。
本日は前回に引き続き、「褒める育児」についてお話ししようと思います。
褒める育児が大切だとよく言われており、実際に前回の投稿でも褒める育児のポイントについてお話ししましたが、今回は本当に褒める育児は必要なのかといった観点で解説していこうと思います。
今回このようなタイトルにした理由としては、特性のある子の育児の場合、実際問題、指摘することばかりでうまく褒めてあげれないといった内容のご相談をよくいただくからです。
それでは早速、以下にて解説していきます。
そもそも褒める育児とは
褒める育児のメリットは以下のようなものが挙げられます。
・自己肯定感が高まる
・親子の信頼関係が深まる
・ポジティブな行動が増える
また、褒める育児というものは、発達に特性のあるお子様に対しては、更に有効的なケースが多いです。
それは、特性のあるお子様は指摘や失敗経験が重なりやすく、自己肯定感が低下しやすい事や、誰も認めてくれないという認知を予防、改善できる可能性があるからです。
特性のあるお子様への褒めるポイントについては前回の投稿をご確認ください。
さて、本題ですが褒める育児は本当に必要なのでしょうか。特に特性のある子の子育ての場合、現実問題、褒めてあげるどころか、どうしても指摘ばかりしてしまい自己嫌悪感を感じている方も多いのではないでしょうか。
その場合は、むしろ「褒める育児」に囚われすぎないことが重要です。うまく褒めてあげられなくても「適切な指摘」で代替可能です。
そもそも褒める育児の目的は、最初にも挙げたように、自己肯定感の向上や親子の信頼関係を深める事、ポジティブな行動を増やすことが主に挙げられます。これは、「適切な指摘」においても補うことができます。
この「適切な指摘」ですが、それは
共感(肯定)+指摘(代替案の提示)です。
ex)ご飯の時間にお片付けできずに癇癪を起こした
「まだ遊びたかったから、嫌で泣いちゃったんだよね。(共感)+でも今はご飯の時間だから一緒に食べようね(指摘)」といった具合です。
どうしてもしてしまう指摘に共感を入れることで、褒める育児とは異なるアプローチ方法で自己肯定感や信頼関係の構築、ポジティブな行動の強化を目指します。
問題行動には必ずその行動をした背景や理由(特性由来のもの)があるため、共感してもらえる回数が増えると理解してくれている安心感や信頼感関係の構築により言うことを聞いてくれるようになるケースがよくあります。
「共感」をとにかく意識すれば、指摘することもなかなか褒めてあげれないことも問題ない場合が多いです。ただ、もちろん褒めることも大切なので、まずは褒めれずに「指摘」ばかりしてしまうことが悪いことだという認識を少しづつ緩和させ、心の余裕から自然に褒めれるようになると良いですね。

