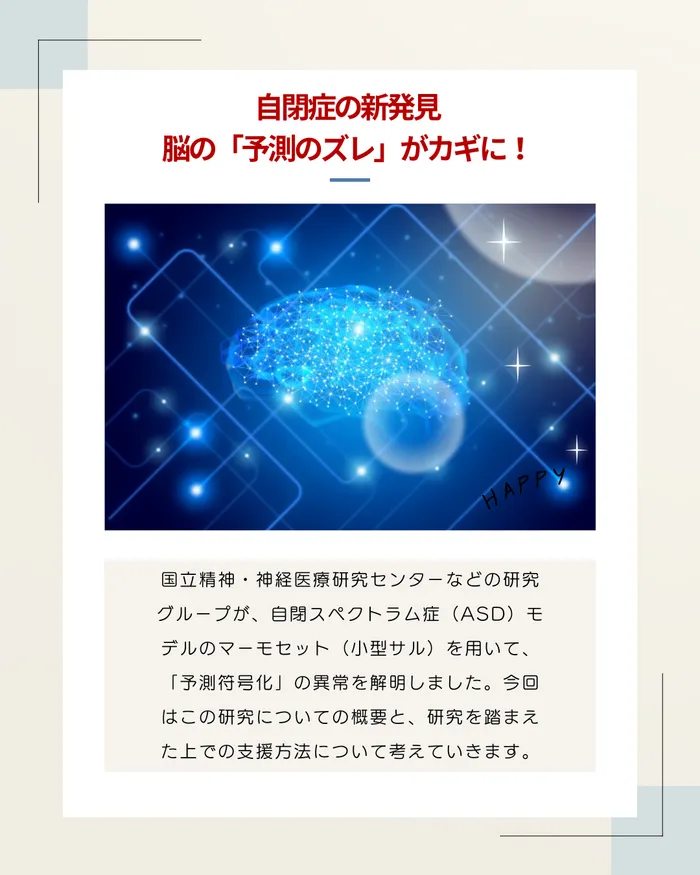
こんにちは🌞
横浜市青葉区にある児童発達支援、フォレストキッズこどもの国教室の木山です🌳🌋
今回はASDの支援について参考になる研究結果と、それを踏まえた上での支援方法ついてご紹介しようと思います。
国立精神・神経医療研究センターなどの研究グループが、自閉スペクトラム症(ASD)モデルのマーモセット(小型サル)を用いて、「予測符号化」の異常を解明しました。
これは、簡単に説明すると脳が過去の経験をもとに次に起こることを予測し、実際の出来事と比較してズレ(予測エラー)を修正する仕組みに関する研究です。
本研究成果は日本時間2024年7月12日に、米国のオンライン総合学術雑誌「Communications Biology」にon-line掲載されています。
予測符号化とは
例として、都会でクマのシルエットを見ると「はくせい」と予測し、山奥では「ほんもの」と予測するように、環境や経験により予測は変わります。そのため、都会でクマが動けば大きな予測エラーが生じ、山奥で動けば予測通りでエラーは小さくなります。このように、脳は必要に応じて予測を素早く適切に変更していきます。
ASDの脳は、上述した予測と現実のズレ(予測エラー)を調整するのが難しく、以下のような困難に繋がることが本研究で示唆されました。
🔸 感覚過敏・鈍感 → 予測が当たらないと常に「驚き」を感じる。
🔸 空気が読めない → 相手の表情や状況の変化を予測しづらい。
🔸 こだわり・繰り返し行動 → 予測しやすい状況を好む傾向。
研究結果のまとめ
自閉症の脳では、繰り返し与えられる刺激に対して、健常な脳のように慣れていくことが難しいことが分かりました。また、脳の中で行われる予測も不安定で、精度が低いことが明らかになりました。ある自閉症の脳では、予測に引き込まれすぎてしまい、実際の感覚情報よりも予測を重視しすぎてしまうことがありました。一方で、別の自閉症の脳では、予測をうまく取り込めず、予測と実際の感覚情報を適切に組み合わせることが難しいようでした。
ASD傾向のお子様の感覚のズレやこだわり行動は、脳の予測エラーの調整が難しいことが背景にあるかもしれません。
今回の研究と、早期療育により柔軟な行動ができるようになるケースが多いという個人的な臨床経験から今後のASDへの関わり方について考えていきます。
脳の可塑性による変化の可能性
早期療育により柔軟性が高まるケースは、脳の可塑性による影響が大きいと考えられます。
特に、ポジティブな強化(褒められる・安心する経験)が積み重なることで、「変化への不安感」より「柔軟な行動への心地よさ」が上回るケースも多いです。
結果として、この段階では、こだわりの強さそのものが低減したというより、「変化しても大丈夫」という認知の変容が起き、柔軟な行動が可能になったと考えられます。
根本的な予測困難さの課題は残る
しかし、研究が示唆するように、ASDの特性として「予測信号のズレ」が根底にあり、根本的に予測精度を改善するのは難しいと考えられます。
そのため、柔軟な行動が身についても、「予測エラーが少ない環境」のほうが安定感を保てるのは変わりません。特に成長とともに社会的状況が複雑になると、柔軟性が身についていても、予測困難な状況でのストレスは続くことがあります。
結果としては、柔軟性が向上しても、「常に柔軟であること」を求めるのではなく、適応しやすい環境整備の重要性は変わりません。
結論
結論:両者のバランスが鍵になります。
✅ 幼少期の柔軟性のトレーニングは、認知変容とポジティブな強化により、柔軟な行動を受け入れやすくするメリットがあります。
✅ しかし、「予測しやすい環境」の整備も引き続き必要です。
👉 最適な支援方針:
「柔軟性を育むトレーニング」と「環境の予測可能性の向上」を両輪で進めることで、本人にとって最もストレスの少ない状態を目指すのが理想だと考えます。
■引用
https://www.ncnp.go.jp/topics/detail.php?@uid=FQXLBn0iArHTXrPD
■原著論文情報 ・ 論文名
Erroneous predictive coding across brain hierarchies in a non-human primate model of autism spectrum disorder ・ 著者名 Zenas Chao, Misako Komatsu, Madoka Matsumoto, Kazuki Iijima, Keiko Nakagaki, Noritaka Ichinohe ・ 掲載誌: Communications Biology ・ doi: 10.1038/s42003-024-06545-3 ・ https: https://www.nature.com/articles/s42003-024-065453?utm_source=rct_congratemailt&utm_medium=email&utm_campaign=oa_20240712&utm_content =10.1038/s42003-024-06545-3
■研究グループ
国立精神・神経医療研究センター 神経研究所微細構造研究部 一戸紀孝、中垣慶子 精神保健研究所 児童・予防精神医学研究部 松元まどか(現:京都大学 医学研究科附属脳機能総合研究センター 臨床脳生理学分野 特定准教授)、飯島和樹 (現:玉川大学) ・ 東京大学 国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN) Zenas Chao ・ 東京工業大学 科学技術創成研究院 小松三佐子 (理化学研究所 脳神経科学研究センター 触知覚生理学研究チーム 客員研究員)
横浜市青葉区にある児童発達支援、フォレストキッズこどもの国教室の木山です🌳🌋
今回はASDの支援について参考になる研究結果と、それを踏まえた上での支援方法ついてご紹介しようと思います。
国立精神・神経医療研究センターなどの研究グループが、自閉スペクトラム症(ASD)モデルのマーモセット(小型サル)を用いて、「予測符号化」の異常を解明しました。
これは、簡単に説明すると脳が過去の経験をもとに次に起こることを予測し、実際の出来事と比較してズレ(予測エラー)を修正する仕組みに関する研究です。
本研究成果は日本時間2024年7月12日に、米国のオンライン総合学術雑誌「Communications Biology」にon-line掲載されています。
予測符号化とは
例として、都会でクマのシルエットを見ると「はくせい」と予測し、山奥では「ほんもの」と予測するように、環境や経験により予測は変わります。そのため、都会でクマが動けば大きな予測エラーが生じ、山奥で動けば予測通りでエラーは小さくなります。このように、脳は必要に応じて予測を素早く適切に変更していきます。
ASDの脳は、上述した予測と現実のズレ(予測エラー)を調整するのが難しく、以下のような困難に繋がることが本研究で示唆されました。
🔸 感覚過敏・鈍感 → 予測が当たらないと常に「驚き」を感じる。
🔸 空気が読めない → 相手の表情や状況の変化を予測しづらい。
🔸 こだわり・繰り返し行動 → 予測しやすい状況を好む傾向。
研究結果のまとめ
自閉症の脳では、繰り返し与えられる刺激に対して、健常な脳のように慣れていくことが難しいことが分かりました。また、脳の中で行われる予測も不安定で、精度が低いことが明らかになりました。ある自閉症の脳では、予測に引き込まれすぎてしまい、実際の感覚情報よりも予測を重視しすぎてしまうことがありました。一方で、別の自閉症の脳では、予測をうまく取り込めず、予測と実際の感覚情報を適切に組み合わせることが難しいようでした。
ASD傾向のお子様の感覚のズレやこだわり行動は、脳の予測エラーの調整が難しいことが背景にあるかもしれません。
今回の研究と、早期療育により柔軟な行動ができるようになるケースが多いという個人的な臨床経験から今後のASDへの関わり方について考えていきます。
脳の可塑性による変化の可能性
早期療育により柔軟性が高まるケースは、脳の可塑性による影響が大きいと考えられます。
特に、ポジティブな強化(褒められる・安心する経験)が積み重なることで、「変化への不安感」より「柔軟な行動への心地よさ」が上回るケースも多いです。
結果として、この段階では、こだわりの強さそのものが低減したというより、「変化しても大丈夫」という認知の変容が起き、柔軟な行動が可能になったと考えられます。
根本的な予測困難さの課題は残る
しかし、研究が示唆するように、ASDの特性として「予測信号のズレ」が根底にあり、根本的に予測精度を改善するのは難しいと考えられます。
そのため、柔軟な行動が身についても、「予測エラーが少ない環境」のほうが安定感を保てるのは変わりません。特に成長とともに社会的状況が複雑になると、柔軟性が身についていても、予測困難な状況でのストレスは続くことがあります。
結果としては、柔軟性が向上しても、「常に柔軟であること」を求めるのではなく、適応しやすい環境整備の重要性は変わりません。
結論
結論:両者のバランスが鍵になります。
✅ 幼少期の柔軟性のトレーニングは、認知変容とポジティブな強化により、柔軟な行動を受け入れやすくするメリットがあります。
✅ しかし、「予測しやすい環境」の整備も引き続き必要です。
👉 最適な支援方針:
「柔軟性を育むトレーニング」と「環境の予測可能性の向上」を両輪で進めることで、本人にとって最もストレスの少ない状態を目指すのが理想だと考えます。
■引用
https://www.ncnp.go.jp/topics/detail.php?@uid=FQXLBn0iArHTXrPD
■原著論文情報 ・ 論文名
Erroneous predictive coding across brain hierarchies in a non-human primate model of autism spectrum disorder ・ 著者名 Zenas Chao, Misako Komatsu, Madoka Matsumoto, Kazuki Iijima, Keiko Nakagaki, Noritaka Ichinohe ・ 掲載誌: Communications Biology ・ doi: 10.1038/s42003-024-06545-3 ・ https: https://www.nature.com/articles/s42003-024-065453?utm_source=rct_congratemailt&utm_medium=email&utm_campaign=oa_20240712&utm_content =10.1038/s42003-024-06545-3
■研究グループ
国立精神・神経医療研究センター 神経研究所微細構造研究部 一戸紀孝、中垣慶子 精神保健研究所 児童・予防精神医学研究部 松元まどか(現:京都大学 医学研究科附属脳機能総合研究センター 臨床脳生理学分野 特定准教授)、飯島和樹 (現:玉川大学) ・ 東京大学 国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN) Zenas Chao ・ 東京工業大学 科学技術創成研究院 小松三佐子 (理化学研究所 脳神経科学研究センター 触知覚生理学研究チーム 客員研究員)

