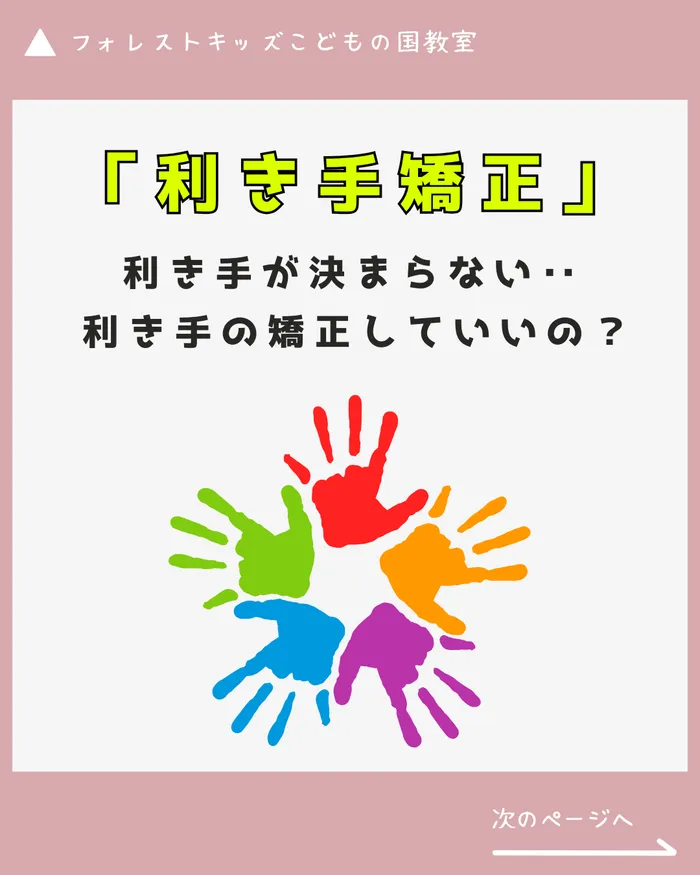
こんにちは🌞
横浜市青葉区にある児童発達支援、フォレストキッズこどもの国教室の木山です🌳🌋
本日は、お子様の発達過程の中で、よくご質問をいただく「利き手」の問題についてです。
いまだにメカニズムが解明されていない「利き手」について、基本的な知識に加えて利き手矯正、利き手の固定、利き手がなかなか決まらない場合の3つの観点で話を進めていきます。
どうして利き手が決まるの?
🧠 利き手は、脳の発達や遺伝、生活環境、文化的背景などが複雑に絡まりあって選択されるとされています。
脳の発達の観点では、
左脳が優位=言語能力が優位=右手を選択
右脳が優位=空間・情報処理が優位=左手を選択
とされています。
矯正ってしてもいいの?
そこで左利きの場合によくある質問ですが、利き手は矯正していいの?ということに触れていきます。
【メリット】
・右利き社会に適応しやすい(文具、マナーなど)
【デメリット】
・本来の脳の回路と違う使い方になり混乱する
・集中力や言語発達に悪影響を及ぼすことがある
・左右失認や左右盲、吃音症などを発症するリスクがある
このようにデメリットを考えると、矯正はしない方が良いというのが一般的な見解になりますが、脳内科医の加藤俊徳先生によれば左利きの才能を最大限発揮するためにも、右手を使って左脳を刺激することを推奨しています。
どうやって矯正すれば良いの?
では、結局矯正しても良いのかという疑問ですが、小学校中学年(9〜10歳)以降であれば矯正を考えても安心です。
幼児期は【意識づけはOK】【強制はNG】
→遊びの中でよく使う手を“優先”して使わせてみましょう。
利き手が「ある程度決まっている」場合は?
ここまで矯正は良くないというお話をしましたが、どちらかの手をよく使っているなら、その手を優先して使う習慣をつけると良いです。
【利き手を明確にすると…】
・書く・食べるなどの動作がスムーズに!
・脳の指令が一貫して、効率がUP!
・言語や運動の発達が安定しやすい
👉中途半端に「なんでも両手」でかえって効率が悪くなることや、一本化する方が脳の処理が楽になることがあります。
逆に利き手がなかなか決まらない場合は?
特に発達に特性のあるお子様の場合、固有覚や前庭覚の未熟さにより、利き手がなかなか決まらないことがあります。(利き手が決まるのが遅いと発達障害であるというものではありません。)
固有覚が未熟:固有覚はボディイメージや力加減を調整する感覚です。固有覚の鈍麻などから右手・左手の認識が難しい事などが考えられます。
前庭覚が未熟:前庭覚は体幹の安定性やバランス感覚を司る重要な感覚です。前庭覚の発達を促す活動を通して、脳の機能分担が促進され、利き手が確立されるのに役立ちます。
そのため、固有覚や前庭覚を養う感覚統合のトレーニングなどが有効的です。
まとめ
・ 利き手は2〜4歳ごろに自然に決まり始める
・ 片手が優位なら、はっきり決めるのが◎
・ 矯正をするなら10歳前後から
・利き手が決まらないのは固有覚と前庭覚が関係しているかも?
・子どもの発達をよく観察して、自然な形でサポートを🌱
定期的に情報を発信しておりますので、是非フォローしてください✨
参考文献:https://diamond.jp/articles/-/286267
横浜市青葉区にある児童発達支援、フォレストキッズこどもの国教室の木山です🌳🌋
本日は、お子様の発達過程の中で、よくご質問をいただく「利き手」の問題についてです。
いまだにメカニズムが解明されていない「利き手」について、基本的な知識に加えて利き手矯正、利き手の固定、利き手がなかなか決まらない場合の3つの観点で話を進めていきます。
どうして利き手が決まるの?
🧠 利き手は、脳の発達や遺伝、生活環境、文化的背景などが複雑に絡まりあって選択されるとされています。
脳の発達の観点では、
左脳が優位=言語能力が優位=右手を選択
右脳が優位=空間・情報処理が優位=左手を選択
とされています。
矯正ってしてもいいの?
そこで左利きの場合によくある質問ですが、利き手は矯正していいの?ということに触れていきます。
【メリット】
・右利き社会に適応しやすい(文具、マナーなど)
【デメリット】
・本来の脳の回路と違う使い方になり混乱する
・集中力や言語発達に悪影響を及ぼすことがある
・左右失認や左右盲、吃音症などを発症するリスクがある
このようにデメリットを考えると、矯正はしない方が良いというのが一般的な見解になりますが、脳内科医の加藤俊徳先生によれば左利きの才能を最大限発揮するためにも、右手を使って左脳を刺激することを推奨しています。
どうやって矯正すれば良いの?
では、結局矯正しても良いのかという疑問ですが、小学校中学年(9〜10歳)以降であれば矯正を考えても安心です。
幼児期は【意識づけはOK】【強制はNG】
→遊びの中でよく使う手を“優先”して使わせてみましょう。
利き手が「ある程度決まっている」場合は?
ここまで矯正は良くないというお話をしましたが、どちらかの手をよく使っているなら、その手を優先して使う習慣をつけると良いです。
【利き手を明確にすると…】
・書く・食べるなどの動作がスムーズに!
・脳の指令が一貫して、効率がUP!
・言語や運動の発達が安定しやすい
👉中途半端に「なんでも両手」でかえって効率が悪くなることや、一本化する方が脳の処理が楽になることがあります。
逆に利き手がなかなか決まらない場合は?
特に発達に特性のあるお子様の場合、固有覚や前庭覚の未熟さにより、利き手がなかなか決まらないことがあります。(利き手が決まるのが遅いと発達障害であるというものではありません。)
固有覚が未熟:固有覚はボディイメージや力加減を調整する感覚です。固有覚の鈍麻などから右手・左手の認識が難しい事などが考えられます。
前庭覚が未熟:前庭覚は体幹の安定性やバランス感覚を司る重要な感覚です。前庭覚の発達を促す活動を通して、脳の機能分担が促進され、利き手が確立されるのに役立ちます。
そのため、固有覚や前庭覚を養う感覚統合のトレーニングなどが有効的です。
まとめ
・ 利き手は2〜4歳ごろに自然に決まり始める
・ 片手が優位なら、はっきり決めるのが◎
・ 矯正をするなら10歳前後から
・利き手が決まらないのは固有覚と前庭覚が関係しているかも?
・子どもの発達をよく観察して、自然な形でサポートを🌱
定期的に情報を発信しておりますので、是非フォローしてください✨
参考文献:https://diamond.jp/articles/-/286267

