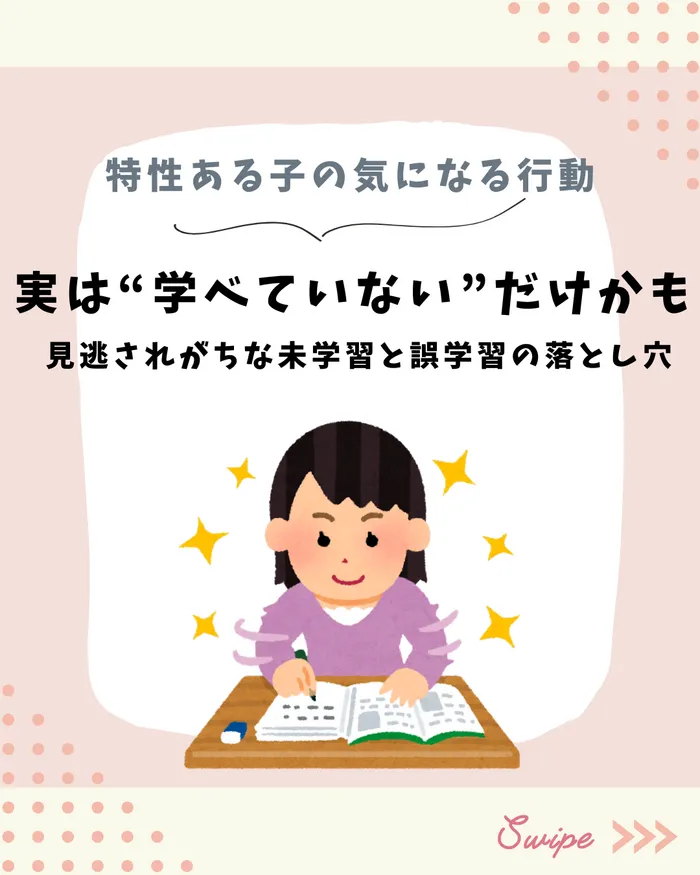
こんにちは🌞
横浜市青葉区にある児童発達支援、フォレストキッズこどもの国教室の木山です🌳🌋
本日は、特性のあるお子様はなぜ問題行動が頻繁に起こるのかという課題に対して、発達特性と学習がミスマッチであるという視点からお話ししようと思います。
特性ある子の学習の仕方を理解する
「教えたのに、なんでわからないの?」
そう感じたことはありませんか?
発達障害の特性をもつ子どもたちは、 一見「わざとやっている」「聞いていない」ように見える行動の裏に、 実は“学べていない”=未学習や “違う形で覚えてしまった”=誤学習があることが多くあります。
◆ たとえば、こんな場面…
【事例①未学習:こだわりで話を聞けなかったケース】
お友だちと遊ぶときに、「順番を守ろうね」と伝えたが、何度言っても割り込んでしまう。
➡ この子はお気に入りのおもちゃに強いこだわりがあり、 そのおもちゃを目にした瞬間、他の情報(順番を守るなど)は入ってこなかった。
➡ 結果として、順番を守るという社会的に大切な場面を経験しているはずなのに学べていない=未学習の状態が考えられます。
【事例②誤学習:誤学習が起こったケース】
レストランで待てずに泣き出したとき、すぐにスマホ動画を見せて落ち着かせた。
➡ すると子どもは「泣けば動画が見られる」と覚えてしまい、 次も同じように泣く行動をとるようになる。
➡ これは、“こうすればうまくいく”と誤って覚えてしまった=誤学習の状態が考えられます。
◆ 背景にある発達障害の特性
これらの「未学習」「誤学習」が起こる背景には、以下のような特性があります。
* 感覚過敏やこだわり:特定の刺激や自身の興味関心に強く反応し、他の情報が入らない
* 多動性や衝動性:その場で落ち着いて話を聞くのが難しい
* 視覚優位:言葉だけの指示が頭に入らず、目に見えるものに気を取られる
* 予測困難性:次に何が起こるかがわからず、不安や混乱が強くなる
これらの影響で、「その場にいたのに、学んでいない」状態になりやすく、 その結果として、行動が定着しにくい、または誤った形で定着してしまうのです。
◆ 大切なのは「理解」と「学び直し」
子どもの行動には必ず理由があります。 表面的な行動だけで判断せず、 「なぜこの行動が出たのか?」という、子供がどのようにその行動を学習しているのかの視点をもつことがとても大切です。
未学習や誤学習が起きている背景を理解したうえで、 その子の特性に合った方法で、もう一度丁寧に伝え直すことが、 行動改善の第一歩になります。
◆ 最後に
困った行動の裏には、「困っている子ども」がいます。 一人で悩まず、まずは「見方」を変えることから始めてみませんか?
横浜市青葉区にある児童発達支援、フォレストキッズこどもの国教室の木山です🌳🌋
本日は、特性のあるお子様はなぜ問題行動が頻繁に起こるのかという課題に対して、発達特性と学習がミスマッチであるという視点からお話ししようと思います。
特性ある子の学習の仕方を理解する
「教えたのに、なんでわからないの?」
そう感じたことはありませんか?
発達障害の特性をもつ子どもたちは、 一見「わざとやっている」「聞いていない」ように見える行動の裏に、 実は“学べていない”=未学習や “違う形で覚えてしまった”=誤学習があることが多くあります。
◆ たとえば、こんな場面…
【事例①未学習:こだわりで話を聞けなかったケース】
お友だちと遊ぶときに、「順番を守ろうね」と伝えたが、何度言っても割り込んでしまう。
➡ この子はお気に入りのおもちゃに強いこだわりがあり、 そのおもちゃを目にした瞬間、他の情報(順番を守るなど)は入ってこなかった。
➡ 結果として、順番を守るという社会的に大切な場面を経験しているはずなのに学べていない=未学習の状態が考えられます。
【事例②誤学習:誤学習が起こったケース】
レストランで待てずに泣き出したとき、すぐにスマホ動画を見せて落ち着かせた。
➡ すると子どもは「泣けば動画が見られる」と覚えてしまい、 次も同じように泣く行動をとるようになる。
➡ これは、“こうすればうまくいく”と誤って覚えてしまった=誤学習の状態が考えられます。
◆ 背景にある発達障害の特性
これらの「未学習」「誤学習」が起こる背景には、以下のような特性があります。
* 感覚過敏やこだわり:特定の刺激や自身の興味関心に強く反応し、他の情報が入らない
* 多動性や衝動性:その場で落ち着いて話を聞くのが難しい
* 視覚優位:言葉だけの指示が頭に入らず、目に見えるものに気を取られる
* 予測困難性:次に何が起こるかがわからず、不安や混乱が強くなる
これらの影響で、「その場にいたのに、学んでいない」状態になりやすく、 その結果として、行動が定着しにくい、または誤った形で定着してしまうのです。
◆ 大切なのは「理解」と「学び直し」
子どもの行動には必ず理由があります。 表面的な行動だけで判断せず、 「なぜこの行動が出たのか?」という、子供がどのようにその行動を学習しているのかの視点をもつことがとても大切です。
未学習や誤学習が起きている背景を理解したうえで、 その子の特性に合った方法で、もう一度丁寧に伝え直すことが、 行動改善の第一歩になります。
◆ 最後に
困った行動の裏には、「困っている子ども」がいます。 一人で悩まず、まずは「見方」を変えることから始めてみませんか?

