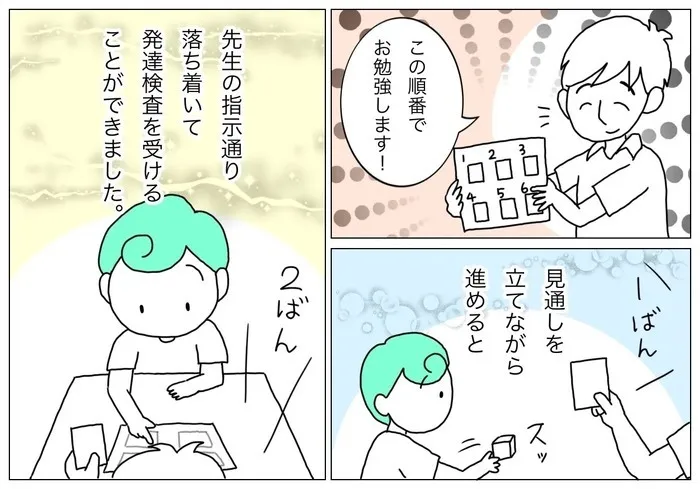
こんにちは(^^♪『かみか企画』です☆
タイトルの結論から言うと個人的には見つけやすくなったんだと思います。
✅ なぜ「増えた」と感じるのか?主な理由は3つ
① 発達障害についての理解・認知が広がった
• 昔は「性格」「しつけ」「親の育て方」で片づけられていた
• 今は特徴を理解し、早期に専門機関や支援につながりやすい
→ 「診断を受ける人」が増えた
② 診断基準が拡大・整備された
• DSM(診断基準)の改訂で ASD/ADHD の捉え方が変わり、グレーゾーンも支援対象になった
• 女の子の特性も見逃されにくくなった
→ 診断される範囲が広がった
③ 現代の環境で困りが目立ちやすくなった
昔と比べて、子どもの特性が表面化しやすい環境になっています。
昔 遊びの中で自然に感覚や体の使い方を学べた
今 室内遊び・デジタル化で発達の偏りが出やすい
昔 集団の中で多少の凸凹は許容されやすかった
今 「空気を読む・協調性」など社会性の要求が高い
昔 家族・地域が子育てを分担
今 核家族化で親の負担が増え、困りが見えやすい
→ 診断されなくても「生きづらさ」を感じやすい時代💦
📊 では、本当に発達障害は増えている?
医学的に“発生率そのものが増えた”という確定的証拠はないとされています。
しかし一部では、以下が影響している可能性も議論されています:
• 出生年齢の上昇(高齢出産)
• 未熟児の生存率向上
• 生活環境や刺激の変化
• 化学物質・食生活の変化(研究中で結論なし)
まだ科学的に断定できる段階ではありません。
✨結論(わかりやすく)
項目 発達障害という特性を持つ人そのもの
増えた? ✅明確には増えたとは言えない
項目 診断される人
増えた? ⬆大幅に増えている
項目 支援が必要と感じる子
増えた? ⬆時代の変化で増えている
必要なのは、
「増えたかどうか」より
💡特性があっても暮らしやすい社会にすること💡と僕は思います(^_
タイトルの結論から言うと個人的には見つけやすくなったんだと思います。
✅ なぜ「増えた」と感じるのか?主な理由は3つ
① 発達障害についての理解・認知が広がった
• 昔は「性格」「しつけ」「親の育て方」で片づけられていた
• 今は特徴を理解し、早期に専門機関や支援につながりやすい
→ 「診断を受ける人」が増えた
② 診断基準が拡大・整備された
• DSM(診断基準)の改訂で ASD/ADHD の捉え方が変わり、グレーゾーンも支援対象になった
• 女の子の特性も見逃されにくくなった
→ 診断される範囲が広がった
③ 現代の環境で困りが目立ちやすくなった
昔と比べて、子どもの特性が表面化しやすい環境になっています。
昔 遊びの中で自然に感覚や体の使い方を学べた
今 室内遊び・デジタル化で発達の偏りが出やすい
昔 集団の中で多少の凸凹は許容されやすかった
今 「空気を読む・協調性」など社会性の要求が高い
昔 家族・地域が子育てを分担
今 核家族化で親の負担が増え、困りが見えやすい
→ 診断されなくても「生きづらさ」を感じやすい時代💦
📊 では、本当に発達障害は増えている?
医学的に“発生率そのものが増えた”という確定的証拠はないとされています。
しかし一部では、以下が影響している可能性も議論されています:
• 出生年齢の上昇(高齢出産)
• 未熟児の生存率向上
• 生活環境や刺激の変化
• 化学物質・食生活の変化(研究中で結論なし)
まだ科学的に断定できる段階ではありません。
✨結論(わかりやすく)
項目 発達障害という特性を持つ人そのもの
増えた? ✅明確には増えたとは言えない
項目 診断される人
増えた? ⬆大幅に増えている
項目 支援が必要と感じる子
増えた? ⬆時代の変化で増えている
必要なのは、
「増えたかどうか」より
💡特性があっても暮らしやすい社会にすること💡と僕は思います(^_

