ADHD(注意欠如多動症)の原因は?遺伝する確率は?【専門家監修】
ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
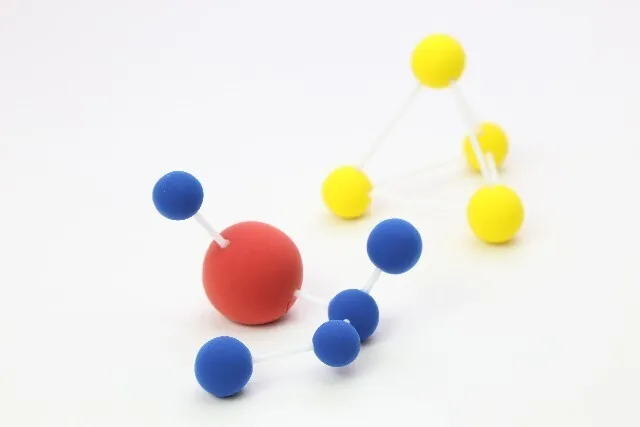
Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
ADHD(注意欠如多動症)は「多動」「衝動」「不注意」の3つの特徴がみられる発達障害です。ADHDは先天性の障害と言われていますが、原因にはどのようなものがあるのでしょうか?また、遺伝との関係性はあるのでしょうか。

監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ADHD(注意欠如多動症)とは?発言時期は分かっているの?
ADHD(注意欠如多動症)は、話を集中して聞けない、作業が不正確、なくしものが多いといった「不注意」、体を絶えず動かす、離席する、おしゃべり、順番を待てないなどの「多動性」「衝動性」の特性があり、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。特性のあらわれ方によって多動・衝動性の傾向が強いタイプ、不注意の傾向が強いタイプ、多動・衝動性と不注意が混在しているタイプなど主に3つに分けられ、これらの症状が12歳になる前に出現します。特性の多くは幼い子どもにみられる特徴と重なり、それらと区別することが難しいため、幼児期にADHD(注意欠如多動症)であると診断することは難しく、就学期以降に診断されることが多いといわれています。また、個人差はありますが、年齢と共に多動性が弱まるなど、特性のあらわれ方が成長に伴って変化することもあります。

【専門家監修】ADHD(注意欠如多動症)の3つのタイプとは?「不注意」「多動・衝動性」「混合」それぞれの特徴を解説
ADHD(注意欠如多動症)の原因は?
ADHD(注意欠如多動症)の症状が起こる確かな原因はまだ解明されていません。主に「遺伝的要因による脳の機能障害説」と「環境的要因の説」があり議論や研究が重ねられています。現在有力だとされている素因は脳の前頭野部分の機能異常です。近年の研究から、ADHD(注意欠如多動症)の人は、行動等をコントロールしている神経系に機能異常があるのではないかと考えられています。
前頭葉は脳の前部分にあり、物事を整理整頓したり論理的に考えたりする働きをします。この部位は注意を持続させたり行動などをコントロールさせたりします。ADHD(注意欠如多動症)の人は、この部分の働きに何らかのかたよりや異常があり、前頭葉がうまく働いていないのではないかと考えられています。
前頭葉が働くためには、神経伝達物質のドーパミンがニューロンによって運ばれなくてはいけません。しかしADHD(注意欠如多動症)の人の場合ニューロンによってドーパミンがうまく運べず、前頭葉の働きが弱くなってしまうと考えられています。それが原因で「多動」「衝動」「不注意」の3つの特徴が現れます。
ADHD(注意欠如多動症)の人は五感からの刺激を敏感に感じ取ってしまう傾向がありますが、それも前頭葉の働きが弱いからだと言われています。思考よりも五感からの刺激を敏感に感じ取ってしまい感覚を過剰に感じてしまうので、論理的に考えたり集中するのが苦手となる傾向があります。
また、最近の研究では、遺伝的要因とともに、胎児期・発育期の環境的要因も相互に影響を及ぼすといわれています。様々な関連の可能性について、研究が進められていますが、まだはっきりとした因果関係についての結論は出ていません。
まだ明確な原因の解明には至っていませんが、ADHD(注意欠如多動症)には複数の関連遺伝子が素因としてあり、それらが様々な道筋をたどって、このような特有の脳機能の偏りを引き起こし、ADHD(注意欠如多動症)の症状につながるのではないかと言われています。つまり、先天的な遺伝的要因による脳の機能異常があり、それが様々な環境的要因と相互に影響し合ってADHD(注意欠如多動症)の症状となると考えられるので、以前言われていたような親の育て方やしつけが直接の原因という説は誤解です。(※1)
前頭葉は脳の前部分にあり、物事を整理整頓したり論理的に考えたりする働きをします。この部位は注意を持続させたり行動などをコントロールさせたりします。ADHD(注意欠如多動症)の人は、この部分の働きに何らかのかたよりや異常があり、前頭葉がうまく働いていないのではないかと考えられています。
前頭葉が働くためには、神経伝達物質のドーパミンがニューロンによって運ばれなくてはいけません。しかしADHD(注意欠如多動症)の人の場合ニューロンによってドーパミンがうまく運べず、前頭葉の働きが弱くなってしまうと考えられています。それが原因で「多動」「衝動」「不注意」の3つの特徴が現れます。
ADHD(注意欠如多動症)の人は五感からの刺激を敏感に感じ取ってしまう傾向がありますが、それも前頭葉の働きが弱いからだと言われています。思考よりも五感からの刺激を敏感に感じ取ってしまい感覚を過剰に感じてしまうので、論理的に考えたり集中するのが苦手となる傾向があります。
また、最近の研究では、遺伝的要因とともに、胎児期・発育期の環境的要因も相互に影響を及ぼすといわれています。様々な関連の可能性について、研究が進められていますが、まだはっきりとした因果関係についての結論は出ていません。
まだ明確な原因の解明には至っていませんが、ADHD(注意欠如多動症)には複数の関連遺伝子が素因としてあり、それらが様々な道筋をたどって、このような特有の脳機能の偏りを引き起こし、ADHD(注意欠如多動症)の症状につながるのではないかと言われています。つまり、先天的な遺伝的要因による脳の機能異常があり、それが様々な環境的要因と相互に影響し合ってADHD(注意欠如多動症)の症状となると考えられるので、以前言われていたような親の育て方やしつけが直接の原因という説は誤解です。(※1)
ADHD(注意欠如多動症)は親から子どもへ遺伝するの?
親からの遺伝によって子どもがADHD(注意欠如多動症)になる可能性はあるのでしょうか?
ADHD(注意欠如多動症)は、遺伝的要因と環境要因が複雑に影響して発現するといわれています。そのため、親から子どもにADHD(注意欠如多動症)が100%遺伝するわけではありません。また、しつけや育て方は原因にはなりません。
ADHD(注意欠如多動症)は、遺伝的要因と環境要因が複雑に影響して発現するといわれています。そのため、親から子どもにADHD(注意欠如多動症)が100%遺伝するわけではありません。また、しつけや育て方は原因にはなりません。
脳の機能障害には、遺伝的要因が関連するという研究結果もあります。現段階では親からの遺伝が原因となって発現する可能性を確率によって表すことはできませんが、ゼロであるとは言い切れないと考えられています。また、現在進められている中に、家族性についての研究があります。
「家族性」とは、ADHD(注意欠如多動症)のある人がいる家系の場合、ない家系より発現しやすい傾向があるということですが、これもまだ研究段階ではっきりと確率が出ているわけではありません。
家族間では遺伝による体質と、生育環境が似ているため、このような傾向が出るのではないかと考えられていますが、ADHD(注意欠如多動症)は体質や環境要因が相互にかつ複雑に影響して発現します。また、遺伝子が一致する一卵性双生児でも100%の確率で発現しないことから、単純に親がADHD(注意欠如多動症)だからといって、子どもにADHD(注意欠如多動症)が遺伝するということではありません。
「家族性」とは、ADHD(注意欠如多動症)のある人がいる家系の場合、ない家系より発現しやすい傾向があるということですが、これもまだ研究段階ではっきりと確率が出ているわけではありません。
家族間では遺伝による体質と、生育環境が似ているため、このような傾向が出るのではないかと考えられていますが、ADHD(注意欠如多動症)は体質や環境要因が相互にかつ複雑に影響して発現します。また、遺伝子が一致する一卵性双生児でも100%の確率で発現しないことから、単純に親がADHD(注意欠如多動症)だからといって、子どもにADHD(注意欠如多動症)が遺伝するということではありません。
















