ADHD(注意欠如多動症)の治療法・療育法は?治療薬は効果的なの?【専門家監修】
ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
ADHD(注意欠如多動症)の治療法にはどんなものがあるのでしょうか?またどのような療育法が適しているのでしょうか?ADHD(注意欠如多動症)の治療薬の効果や副作用、薬以外の治療法としての療育などについてご紹介します。様々な治療法のメリット・デメリットを知り、本人が生きやすい環境を作るように心がけましょう。

監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ADHD(注意欠如多動症)の治療はいつから始めるべきなの?
どのような症状であれば治療が必要?
ADHD(注意欠如多動症)は、話を集中して聞けない、作業が不正確、なくしものが多いといった「不注意」、体を絶えず動かす、離席する、おしゃべり、順番を待てないなどの「多動性」「衝動性」の特性があり、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。特性のあらわれ方によって多動・衝動性の傾向が強いタイプ、不注意の傾向が強いタイプ、多動・衝動性と不注意が混在しているタイプなど主に3つに分けられ、これらの症状が12歳になる前に出現します。特性の多くは幼い子どもにみられる特徴と重なり、それらと区別することが難しいため、幼児期にADHD(注意欠如多動症)であると診断することは難しく、就学期以降に診断されることが多いといわれています。また、個人差はありますが、年齢と共に多動性が弱まるなど、特性のあらわれ方が成長に伴って変化することもあります。
小さい子どものうちは、ADHD(注意欠如多動症)がなくても「不注意」「多動性」「衝動性」のような行動をとることもありますが、このような特徴が年齢や発達に不釣り合いなほど過度に見られ、社会的な活動や学業に支障が出る場合には、保健センターや子育て支援センター、児童発達支援事業所などの専門機関に相談することをおすすめします。
大人の場合には、同じミスばかり繰り返したり、大事な約束を頻繁に忘れてしまったり、整理整頓ができないなど、社会生活や日常生活に支障をきたす症状がある場合には、発達障害者支援センターなどの専門機関や精神科などの医療機関で相談してみましょう。
小さい子どものうちは、ADHD(注意欠如多動症)がなくても「不注意」「多動性」「衝動性」のような行動をとることもありますが、このような特徴が年齢や発達に不釣り合いなほど過度に見られ、社会的な活動や学業に支障が出る場合には、保健センターや子育て支援センター、児童発達支援事業所などの専門機関に相談することをおすすめします。
大人の場合には、同じミスばかり繰り返したり、大事な約束を頻繁に忘れてしまったり、整理整頓ができないなど、社会生活や日常生活に支障をきたす症状がある場合には、発達障害者支援センターなどの専門機関や精神科などの医療機関で相談してみましょう。
治療を始める年齢は何歳?
治療には、療育や教育といった心理・社会的アプローチと、薬物療法などの医療的なアプローチがあります。
ADHD(注意欠如多動症)は先天性の発達障害ですが、診断は症状が出てからとなるため、治療や療育をはじめる年齢はまちまちです。一般的には療育や教育は年齢には関係なく、いつからでも受けることができますが、困りごとが出てきたり、障害に気づいた時点で早めに取り組むことが大切です。
ADHD(注意欠如多動症)は先天性の発達障害ですが、診断は症状が出てからとなるため、治療や療育をはじめる年齢はまちまちです。一般的には療育や教育は年齢には関係なく、いつからでも受けることができますが、困りごとが出てきたり、障害に気づいた時点で早めに取り組むことが大切です。
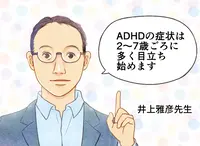
ADHD(注意欠如多動症)の特徴とは?2歳ごろから現れる?チェックリストも【専門家監修】
療育によるADHD(注意欠如多動症)の治療
ADHD(注意欠如多動症)の根本的な完治は現在の医療では難しいですが、ADHD(注意欠如多動症)の症状を緩和させるために療育という手法を取ることができます。療育とは、社会的な自立をめざしてスキルを習得したり、環境を整えるアプローチのことです。療育法で学ぶことは主に環境調整、ソーシャルスキルトレーニング、ペアレントトレーニングの3つです。今回はこの3つの具体的な内容をお伝えします。
■環境調整
この環境は、教育現場や家庭における環境をさします。たとえば集中が難しい場合は、机の周りに無駄な刺激物を置かないようにするなど、教室や身の回りの環境を調整します。片付けが苦手な子の場合に、元の位置に物を戻しやすいようにおもちゃ箱を工夫する、視覚過敏がある子の場合、照明を工夫する、などがあげられます。
■ソーシャルスキルトレーニング(SST)
ソーシャルスキルトレーニングは、略してSSTとも呼ばれます。ここでは様々な特性をもつ本人が社会や生活での適切な行動をうまくできるようにトレーニングしていきます。対人関係をうまく行うための社会生活技能を身につけるためのトレーニングを遊びなどを用いたロールプレイを通じて行います。
■ペアレントトレーニング
保護者が障害のある子どもとの関わり方や、子育ての工夫の仕方を学ぶプログラムです。注意の仕方、子どもの行動に対するアドバイスの仕方、本人の自己肯定感を育む褒め方など、子どもとの接し方を中心に学びます。
このような療育は、発達障害専門の病院や公立・民間の「児童発達支援」「放課後等デイサービス」などで学ぶことができます。療育によって、本人の生きづらさを緩和し、また良い部分を磨いていくことができます。
■環境調整
この環境は、教育現場や家庭における環境をさします。たとえば集中が難しい場合は、机の周りに無駄な刺激物を置かないようにするなど、教室や身の回りの環境を調整します。片付けが苦手な子の場合に、元の位置に物を戻しやすいようにおもちゃ箱を工夫する、視覚過敏がある子の場合、照明を工夫する、などがあげられます。
■ソーシャルスキルトレーニング(SST)
ソーシャルスキルトレーニングは、略してSSTとも呼ばれます。ここでは様々な特性をもつ本人が社会や生活での適切な行動をうまくできるようにトレーニングしていきます。対人関係をうまく行うための社会生活技能を身につけるためのトレーニングを遊びなどを用いたロールプレイを通じて行います。
■ペアレントトレーニング
保護者が障害のある子どもとの関わり方や、子育ての工夫の仕方を学ぶプログラムです。注意の仕方、子どもの行動に対するアドバイスの仕方、本人の自己肯定感を育む褒め方など、子どもとの接し方を中心に学びます。
このような療育は、発達障害専門の病院や公立・民間の「児童発達支援」「放課後等デイサービス」などで学ぶことができます。療育によって、本人の生きづらさを緩和し、また良い部分を磨いていくことができます。
ADHD(注意欠如多動症)の薬物療法は?
治療薬でのADHD(注意欠如多動症)の治療は、不注意・多動性・衝動性の症状を緩和する効果があります。しかし、この効果は服薬している間にとどまります。薬の効き方は個人によって違いがあり、また副作用の出方もまた同様です。そのため、医師と相談しながら使用する必要があります。
ADHD(注意欠如多動症)で使われる主な治療薬は以下の3種類があります。
■ストラテラ(アトモキセチン)
ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(NRI)です。日本でADHD(注意欠如多動症)に効果効能があるとして承認されている薬のひとつで、効き目が出るまで約1ヶ月かかりますが、24時間効果が持続します。副作用としては食欲不振があると言われています。
■コンサータ(メチルフェニデート)
中枢神経を刺激して、脳内の神経伝達物質であるドーパミンやノルアドレナリンの調節をする薬です。飲んで2時間後ぐらいから効果を感じることができ、効き目は12時間程度持続します。副作用としては、頭痛・寝つきが悪くなる・食欲不振などがあると言われています。しかし服用を続けて薬に慣れてくると、副作用が軽減することもあるそうです。
■インチュニブ
症状に応じて、上記以外の薬が処方される場合があります。人によって合う合わないもあり、副作用が見られこともあります。薬に頼りすぎたり、また自己判断で服用をやめたりしないようにしましょう。医師としっかり治療方針を相談した上で、用法用量を守って使用することが大切です。また、薬物療法のみで子どもを落ち着かせるのでははく、環境調整や落ち着いている時にスキルトレーニングなどを行っていきましょう。(※1)
ADHD(注意欠如多動症)で使われる主な治療薬は以下の3種類があります。
■ストラテラ(アトモキセチン)
ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(NRI)です。日本でADHD(注意欠如多動症)に効果効能があるとして承認されている薬のひとつで、効き目が出るまで約1ヶ月かかりますが、24時間効果が持続します。副作用としては食欲不振があると言われています。
■コンサータ(メチルフェニデート)
中枢神経を刺激して、脳内の神経伝達物質であるドーパミンやノルアドレナリンの調節をする薬です。飲んで2時間後ぐらいから効果を感じることができ、効き目は12時間程度持続します。副作用としては、頭痛・寝つきが悪くなる・食欲不振などがあると言われています。しかし服用を続けて薬に慣れてくると、副作用が軽減することもあるそうです。
■インチュニブ
症状に応じて、上記以外の薬が処方される場合があります。人によって合う合わないもあり、副作用が見られこともあります。薬に頼りすぎたり、また自己判断で服用をやめたりしないようにしましょう。医師としっかり治療方針を相談した上で、用法用量を守って使用することが大切です。また、薬物療法のみで子どもを落ち着かせるのでははく、環境調整や落ち着いている時にスキルトレーニングなどを行っていきましょう。(※1)
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています















