小児期崩壊性障害とは?【専門家監修】
ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
小児期崩壊性障害とは、かつての診断基準であるDSM-Ⅳに記載されている診断名であり2歳頃まではコミュニケーションや適応行動において発達的な遅れがみられなかったのに突然、成長の過程で覚えた言葉や排泄能力などを失い、最終的には知的障害を伴った自閉スペクトラム症のような状態になる障害です。この記事ではその特徴や原因、類似している障害との比較を紹介します。

監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
小児期崩壊性障害とは?
小児期崩壊性障害には、少なくとも2歳頃までは社会的コミュニケーションや対人関係、遊びや適応行動において発達的な遅れがみられなかったが、2歳以降(10歳まで)に獲得されたはずの発達期相応のスキルを失ってしまうという特徴があります。具体的には、話せていた言葉が話せなくなる、できていたはずのコミュニケーションをとれなくなる、トイレで排泄できていたのにできなくなる、おままごとなどのごっこ遊びのバリエーションが乏しくなる、運動能力の低下などです。なお小児期崩壊性障害は、かつての診断基準であるDSM-Ⅳに記載されている診断名であり、「対人関係や社会的コミュニケーションの困難」および常同的な行動や、「特定のものや行動における反復性やこだわり」という特性を持つため、現在の診断基準であるDSM-5-TRでは「ASD(自閉スペクトラム症)」という名称に包括されています。
※ASD(自閉スペクトラム症)の診断基準については以下のコラムで解説しています。
※ASD(自閉スペクトラム症)の診断基準については以下のコラムで解説しています。
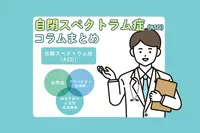
自閉スペクトラム症の特徴、原因、治療方法、併存しやすい疾患とは?自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、高機能自閉症とは何が違うの?【保存版!発達ナビASDコラム一覧/専門家監修】
小児期崩壊性障害の原因
小児期崩壊性障害の原因は現段階では解明されていません。
現状では、脂質代謝異常や結節性硬化症など、さまざまな疾患と関連があるのではないかと考えられています。
現状では、脂質代謝異常や結節性硬化症など、さまざまな疾患と関連があるのではないかと考えられています。
小児期崩壊性障害と似ている障害
小児期崩壊性障害と似ている障害として、小児統合失調症や認知症などが挙げられます。
・小児統合失調症
統合失調症は妄想や幻覚などの症状が続く疾患です。ほとんどが思春期以降の発症ですが、まれに幼いころに発症することがあります。小児統合失調症の症状にも感情的な反応の欠如が見られるなど、小児期崩壊性障害と似ている症状が見られることがあります。
・認知症
小児期崩壊性障害と似ている障害として、成人期における認知症があげられます。しかし、小児期崩壊性障害は、頭部外傷などの身体的な要因が原因ではないこと、技能喪失の後ある程度の回復がみられること、自閉スペクトラム症に典型的にみられる特徴がみられることなどの点において認知症とは異なっています。
・小児統合失調症
統合失調症は妄想や幻覚などの症状が続く疾患です。ほとんどが思春期以降の発症ですが、まれに幼いころに発症することがあります。小児統合失調症の症状にも感情的な反応の欠如が見られるなど、小児期崩壊性障害と似ている症状が見られることがあります。
・認知症
小児期崩壊性障害と似ている障害として、成人期における認知症があげられます。しかし、小児期崩壊性障害は、頭部外傷などの身体的な要因が原因ではないこと、技能喪失の後ある程度の回復がみられること、自閉スペクトラム症に典型的にみられる特徴がみられることなどの点において認知症とは異なっています。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
















