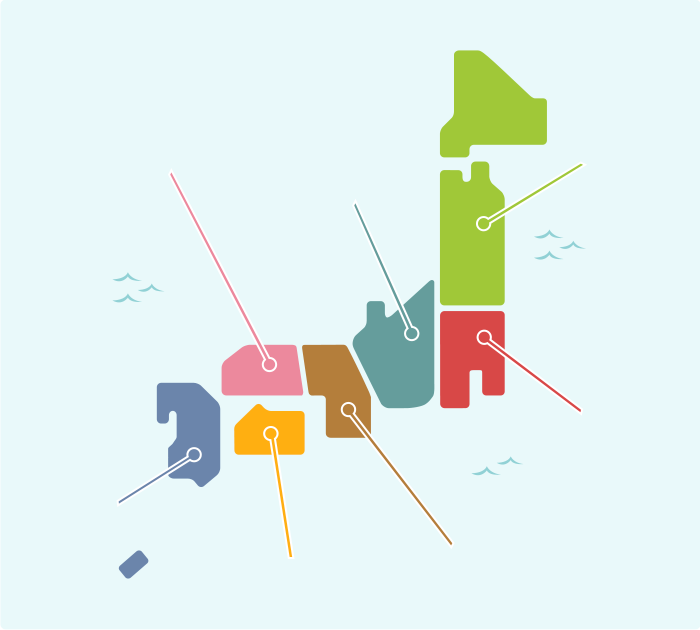稽古中、セリフにつまづいて黙ってしまう役者を褒めます。その訳は…
編:役者さんとは普段どのようなコミュニケーションをとりながら稽古をしているのですか?
松:「嘘はつかないでほしい」と、まず最初に言っています。セリフがあるからって言わないでほしい、言えないのに言わないでほしいと言っています。
セリフを覚えてないわけでなく、うまく出なかった。そんな時には立ち止まって、なぜ出なかったのかを考えてほしいと伝えています。なんでその演技ができないのかということを考えてほしいんです。とりあえずで無理やり話を進めないで、セリフを言うきっかけを探してほしいって言っています。
ピンとこないセリフがあったら、じゃあ今どんな気持ちになっているのかを共有して前段階から演技を考えていきます。なるべくお互いにごまかさない、その代わり稽古なんだから失敗していきましょうと。そう伝えると、ホントにセリフ言わない人も出てくるんですよ。
そこからは、この人物がセリフを言う動機はどこにあるのか、どれくらいのイメージを持ってやっているのか、お互いのイメージをすり合わせるようにして進めていきます。
編:松澤さんが今のような演出スタイルをとることになったきっかけはなんですか?
松:そうですね。人はそれぞれ違う、という意識がそうさせたかもしれません。自分と他者という違いに少しずつ気付いてきた時期があって。
昔は男主人公でやっていましたが、一挙手一投足が気になりすぎてしまって、役者にも細かく指摘し過ぎてしまうんですね。だんだん、「このままじゃ駄目だ」と思うようになって、女主人公の芝居にチャレンジしたんです。そしたら、女性のしぐさに対してなかなか想像が及ばず、わからないことだらけだったんです。
そこで気づいたんです。そもそも演出家も役者も、芝居に挑むバックボーンが違うし、みんなバラバラの意思や体を持っているのだということに。でもそれは、一緒に芝居を作っていく上では、実は大した問題ではないんですよね。
大事なのは同じ目標を持って、ひとつのことに向かうこと。そこに至るまでに各々が違う役割を全うすればいいだけ。そこから今のような演出スタイルや、役者とのコミュニケーション方法が築かれていきました。
編:人はみんなバラバラで、違った意思を持っている。当たり前のことなのに、人はつい自分の信念や、一般的な社会通念にとらわれてしまう…発達障害のある人の中には、そんな周囲からのプレッシャーに苦しんでいる人も少なくないと思います。
演出家、役者、監修者、一人ひとりの「ちがい」を前提として芝居をつくりあげていくスタイルは、きっとこのテーマにぴったりの手法なのだと感じました。
松:「嘘はつかないでほしい」と、まず最初に言っています。セリフがあるからって言わないでほしい、言えないのに言わないでほしいと言っています。
セリフを覚えてないわけでなく、うまく出なかった。そんな時には立ち止まって、なぜ出なかったのかを考えてほしいと伝えています。なんでその演技ができないのかということを考えてほしいんです。とりあえずで無理やり話を進めないで、セリフを言うきっかけを探してほしいって言っています。
ピンとこないセリフがあったら、じゃあ今どんな気持ちになっているのかを共有して前段階から演技を考えていきます。なるべくお互いにごまかさない、その代わり稽古なんだから失敗していきましょうと。そう伝えると、ホントにセリフ言わない人も出てくるんですよ。
そこからは、この人物がセリフを言う動機はどこにあるのか、どれくらいのイメージを持ってやっているのか、お互いのイメージをすり合わせるようにして進めていきます。
編:松澤さんが今のような演出スタイルをとることになったきっかけはなんですか?
松:そうですね。人はそれぞれ違う、という意識がそうさせたかもしれません。自分と他者という違いに少しずつ気付いてきた時期があって。
昔は男主人公でやっていましたが、一挙手一投足が気になりすぎてしまって、役者にも細かく指摘し過ぎてしまうんですね。だんだん、「このままじゃ駄目だ」と思うようになって、女主人公の芝居にチャレンジしたんです。そしたら、女性のしぐさに対してなかなか想像が及ばず、わからないことだらけだったんです。
そこで気づいたんです。そもそも演出家も役者も、芝居に挑むバックボーンが違うし、みんなバラバラの意思や体を持っているのだということに。でもそれは、一緒に芝居を作っていく上では、実は大した問題ではないんですよね。
大事なのは同じ目標を持って、ひとつのことに向かうこと。そこに至るまでに各々が違う役割を全うすればいいだけ。そこから今のような演出スタイルや、役者とのコミュニケーション方法が築かれていきました。
編:人はみんなバラバラで、違った意思を持っている。当たり前のことなのに、人はつい自分の信念や、一般的な社会通念にとらわれてしまう…発達障害のある人の中には、そんな周囲からのプレッシャーに苦しんでいる人も少なくないと思います。
演出家、役者、監修者、一人ひとりの「ちがい」を前提として芝居をつくりあげていくスタイルは、きっとこのテーマにぴったりの手法なのだと感じました。
自分のフィルターは、視点が異なる他者との密なかかわりで、外していける
編:今回の作品の話に戻りますが、創作していくうえで、松澤さんの築いたスタイルはどう生かされましたか?役者さんにとっては、発達障害のことや心理士の仕事は未知の世界でしょうし、イメージしにくいところからのスタートだと思うのですが。
松:初演の稽古の際、きっかけになったできごとがあります。
くまさんがいて、うさぎさんがいて、箱にビー玉を入れるという、子どもへの発達検査のシーンでのことです。
最初は、検査で子どもが間違えてしまったことで生じた、発達障害の可能性に対して、両親が失望するという台本にしていたのです。しかし、父親役の役者の意見からは「間違えてしまった子どものことは、僕には正常に見えた。子どもだから複雑な指示に従えないのは当たり前だと思います」といったのです。
そこで活路が見えました。こうなるから、こう とこだわらず、なるべく自分のフィルターをはずして、バラバラにして組み立てていくようにしたんです。実際に演じる役者さん、監修をしてくれた心理士、自分と視点が異なる他者の視点を取り入れていくことで、リアリティが生まれていきました。
そんななかで、たとえば観客席の最後列から聞くと声が聞き取れない役なども出てきました。登場人物のテンションもそれぞれ違うので、役ごとにバラツキをもたせたのです。普通のお芝居だと、なるべくはっきり、後ろまで声が通るようにしますよね。でも今回、それをやらなかった。
あと、余談ですがうちは円陣も組みません。そしたら同じテンションになっちゃうから。それではリアリティを消してしまいます。そこまですると演出がバラバラに見えることもあるかもしれません。しかし、現実では同じテンションはありえないんです。揃えてしまうことではリアリティは生み出せないことになります。
なるべく誰かのペースに巻き込まれないでと、役者には言ってます。ストーリーばかりを勝手に進めないようにと。正しいと思ってなくても言ってほしい。自信のなさでもいいので、なるべく決めつけずに進めてほしい。だから達成感がない芝居だと役者から言われることもあるんですけどね(笑)。
松:初演の稽古の際、きっかけになったできごとがあります。
くまさんがいて、うさぎさんがいて、箱にビー玉を入れるという、子どもへの発達検査のシーンでのことです。
最初は、検査で子どもが間違えてしまったことで生じた、発達障害の可能性に対して、両親が失望するという台本にしていたのです。しかし、父親役の役者の意見からは「間違えてしまった子どものことは、僕には正常に見えた。子どもだから複雑な指示に従えないのは当たり前だと思います」といったのです。
そこで活路が見えました。こうなるから、こう とこだわらず、なるべく自分のフィルターをはずして、バラバラにして組み立てていくようにしたんです。実際に演じる役者さん、監修をしてくれた心理士、自分と視点が異なる他者の視点を取り入れていくことで、リアリティが生まれていきました。
そんななかで、たとえば観客席の最後列から聞くと声が聞き取れない役なども出てきました。登場人物のテンションもそれぞれ違うので、役ごとにバラツキをもたせたのです。普通のお芝居だと、なるべくはっきり、後ろまで声が通るようにしますよね。でも今回、それをやらなかった。
あと、余談ですがうちは円陣も組みません。そしたら同じテンションになっちゃうから。それではリアリティを消してしまいます。そこまですると演出がバラバラに見えることもあるかもしれません。しかし、現実では同じテンションはありえないんです。揃えてしまうことではリアリティは生み出せないことになります。
なるべく誰かのペースに巻き込まれないでと、役者には言ってます。ストーリーばかりを勝手に進めないようにと。正しいと思ってなくても言ってほしい。自信のなさでもいいので、なるべく決めつけずに進めてほしい。だから達成感がない芝居だと役者から言われることもあるんですけどね(笑)。
伝わりにくい「生きにくさ」の正体。観客に「いたたまれない…」と思わせる、ぎりぎりの表現を生み出すには
編:テーマにかかげてある「生きにくさ」を身体表現と会話劇で繰り広げるのは大変だと思いますが、どういう点で苦労しましたか?
松:一般的には芝居って筋書きが決まっているものなので、稽古すればできるようになるじゃないですか。出来不出来はともかく、とりあえずストーリーは追えると思うんですよ。でも、それだけでは安定してしまう。だからぎりぎりを攻めてほしいと、役者さんに伝え続けました。
セリフをとちってほしいというわけではないんですが、ぎりぎりまで忘れているんだけどぽろっとセリフが出てくる、それぐらいの状態でいてほしいと。そこでリアリティがでてくるので。
矛盾と戦い続けることで出来るようになっていくことですよね。稽古していることを稽古していないことのようにやること。100回練習したことをはじめてやるかのようにやる。「生きにくさ」とは、「うまくいかなさ」ですからね。
たとえば、ここで突然御二方(発達ナビ編集部員)に怒られたとするじゃないですか。
インタビュー受けなきゃよかったな、早く帰りたいなぁ、言ったこと間違ってたのかなという気持ちになって、ここにいにくくなると思うんです。「いたたまれなさ」です。そのあり様をそのまま舞台上に、その気持ちで立ってもらいたいと思っています。
やっぱりお芝居って、自分の出番で自信を持って体を大きく動かしてセリフをバシッということができるほうが気持ちいいんですよ。自分も役者だったんでわかるんです。そっちのほうがある種の安心感があるというか。でも目指すのはそっちじゃない。
ここ全然うまくいってない、相手との掛け合いがうまくいってない、っていうときほど「今日よかったですね」って僕は言いますし、逆に役者が「今日は調子いいぞ」と思っているときほど駄目で、「今日は予定調和でした」と言いますね。
演劇によっていろいろなジャンルがあるので、秒単位で筋書きが決まってるようなものでこういうことをやるのは駄目ですが、「わたしの、領分」のようにありのままを見せるような芝居では、その人自身がちゃんと傷ついてその場にいたくないという気持ちになることが大切だと思ってます。心のどこかで本当に「ここにいたくない」と思うことが大事なんです。
そういうところが身体表現の大事なところなんじゃないかと思います。
いるとき、いなくちゃいけないときの境目を分けてふるまうことも大事です。いなくていいときはすぐ舞台上から去ることも大切ですね。
編:戸惑うお客さんもいるんでしょうね。
松:芝居に親しんできた人は斬新にみえるらしいですね。
現代口語演劇の延長線でやってきているので、それに親しんでいる人は受け入れられると思います。アンケートで、「私がいつも観ている帝国劇場より声がでてない」とか(笑)、「結論がない、結論を出せ」といわれることもあります。
もともとある価値観を変えることはなかなかむずかしいし、それこそ多様性を認めろというのも押しつけでありエゴでもあります。
でもこういう人がいるんだということを知るというのはいいと思っています。登場人物にどこか自分と共通した変なところが見えてくるといいと思います。
たとえば、作中に登場する心理士も変な人が多くて、ちょっとずれてるところを持っていることが多いように描きました。
登場人物の荻野もシャーペンのカチカチする音がきらいで、年の離れたドクターにおもわず切れてしまうことがあったり。それをお客さんもみて「ここわかる」「ここわからない」と自分の中にもある変わったところと重ねながら観てもらえたらと考えています。
松:一般的には芝居って筋書きが決まっているものなので、稽古すればできるようになるじゃないですか。出来不出来はともかく、とりあえずストーリーは追えると思うんですよ。でも、それだけでは安定してしまう。だからぎりぎりを攻めてほしいと、役者さんに伝え続けました。
セリフをとちってほしいというわけではないんですが、ぎりぎりまで忘れているんだけどぽろっとセリフが出てくる、それぐらいの状態でいてほしいと。そこでリアリティがでてくるので。
矛盾と戦い続けることで出来るようになっていくことですよね。稽古していることを稽古していないことのようにやること。100回練習したことをはじめてやるかのようにやる。「生きにくさ」とは、「うまくいかなさ」ですからね。
たとえば、ここで突然御二方(発達ナビ編集部員)に怒られたとするじゃないですか。
インタビュー受けなきゃよかったな、早く帰りたいなぁ、言ったこと間違ってたのかなという気持ちになって、ここにいにくくなると思うんです。「いたたまれなさ」です。そのあり様をそのまま舞台上に、その気持ちで立ってもらいたいと思っています。
やっぱりお芝居って、自分の出番で自信を持って体を大きく動かしてセリフをバシッということができるほうが気持ちいいんですよ。自分も役者だったんでわかるんです。そっちのほうがある種の安心感があるというか。でも目指すのはそっちじゃない。
ここ全然うまくいってない、相手との掛け合いがうまくいってない、っていうときほど「今日よかったですね」って僕は言いますし、逆に役者が「今日は調子いいぞ」と思っているときほど駄目で、「今日は予定調和でした」と言いますね。
演劇によっていろいろなジャンルがあるので、秒単位で筋書きが決まってるようなものでこういうことをやるのは駄目ですが、「わたしの、領分」のようにありのままを見せるような芝居では、その人自身がちゃんと傷ついてその場にいたくないという気持ちになることが大切だと思ってます。心のどこかで本当に「ここにいたくない」と思うことが大事なんです。
そういうところが身体表現の大事なところなんじゃないかと思います。
いるとき、いなくちゃいけないときの境目を分けてふるまうことも大事です。いなくていいときはすぐ舞台上から去ることも大切ですね。
編:戸惑うお客さんもいるんでしょうね。
松:芝居に親しんできた人は斬新にみえるらしいですね。
現代口語演劇の延長線でやってきているので、それに親しんでいる人は受け入れられると思います。アンケートで、「私がいつも観ている帝国劇場より声がでてない」とか(笑)、「結論がない、結論を出せ」といわれることもあります。
もともとある価値観を変えることはなかなかむずかしいし、それこそ多様性を認めろというのも押しつけでありエゴでもあります。
でもこういう人がいるんだということを知るというのはいいと思っています。登場人物にどこか自分と共通した変なところが見えてくるといいと思います。
たとえば、作中に登場する心理士も変な人が多くて、ちょっとずれてるところを持っていることが多いように描きました。
登場人物の荻野もシャーペンのカチカチする音がきらいで、年の離れたドクターにおもわず切れてしまうことがあったり。それをお客さんもみて「ここわかる」「ここわからない」と自分の中にもある変わったところと重ねながら観てもらえたらと考えています。