心のケアも、アプリでグッと手軽に!AIの活用も!?大人のASDの私が見つけた社会を生き抜くスキル【ITでセルフケア編】
ライター:宇樹義子
複数回に分けてお届けしている、「発達障害者のためのITを活用した生きるスキル」についての記事。今回はセルフケア編です。セルフケアもITを活用すると想像以上に多くのことができます。
認知行動療法や、過集中のコントロール、AIの活用まで。使いやすい無料アプリも紹介。
ITを活用したメンタルケア
最近はメンタルケア用のアプリが豊富に出揃ってきています。
このごろ、病院での治療や家でのメンタルセルフケアに認知行動療法を使うことが普及してきています。スマホ向けのアプリと認知行動療法は相性が良いようで、メンタルケアの分野では特に認知行動療法系のアプリが多くみられます。
このごろ、病院での治療や家でのメンタルセルフケアに認知行動療法を使うことが普及してきています。スマホ向けのアプリと認知行動療法は相性が良いようで、メンタルケアの分野では特に認知行動療法系のアプリが多くみられます。
認知行動療法アプリ
認知行動療法の感情日記を再現した感情ログ機能や、心のバランスをとるためのマインドフルネス瞑想のガイド音声が揃った、しっかりした内容のアプリとして「Awarefy」があります。
これまでも、感情ログ単体のアプリや、瞑想用のガイド音声単体のアプリはあったのですが、Awarefyのように総合的に認知行動療法を行える、充実した無料の日本語アプリは今までにありませんでした。
感情の記録やマインドフルネス瞑想といった、少し敷居の高いセルフケアの敷居を下げてくれます。私はこのアプリを使い始めてから、感情ログと瞑想をかなり習慣化することができました。
ガイド音声はわかりやすく、不安をどうにかしたいときや深く眠りたいときなど、シーン別にたくさん用意されています。子どもが落ち着かないときなど、一緒に音声を聴いてリラックスすることに誘ってみるのもいいかもしれません。
感情ログは感情を色で分けてグラフ化してくれるのでぱっと見てわかりやすく、一週間ごとの総合レポートも出してくれて、振り返りに便利です。
これまでも、感情ログ単体のアプリや、瞑想用のガイド音声単体のアプリはあったのですが、Awarefyのように総合的に認知行動療法を行える、充実した無料の日本語アプリは今までにありませんでした。
感情の記録やマインドフルネス瞑想といった、少し敷居の高いセルフケアの敷居を下げてくれます。私はこのアプリを使い始めてから、感情ログと瞑想をかなり習慣化することができました。
ガイド音声はわかりやすく、不安をどうにかしたいときや深く眠りたいときなど、シーン別にたくさん用意されています。子どもが落ち着かないときなど、一緒に音声を聴いてリラックスすることに誘ってみるのもいいかもしれません。
感情ログは感情を色で分けてグラフ化してくれるのでぱっと見てわかりやすく、一週間ごとの総合レポートも出してくれて、振り返りに便利です。
AIとの会話でメンタルセルフケア
AIを搭載した会話アプリとして「SELF」もあります。AIというと冷たく不自然そうな印象がある人も多いと思いますが、会話してみるとかなり丁寧に作り込まれていて、会話していくうちに想像以上に気持ちが落ち着いていくことも多いです。
会話相手のAIは、情報提供系、癒し系、悩み相談系、猫など複数揃っています。使っていくうちにデータがたまっていって、「悩んでるって言ってたけど最近はどう?」とか聞いてくれたりします。
一日や一週間の振り返りを手伝ってくれたり、性格分析の機能もあったりします。本人がAIとの会話だけでどうにもならない悩みや状況を抱えていることがわかった場合、適切な専門家や助けにつながるように促してくれることも。
すでにカウンセラーや精神科医師とつながっているけれど、きょう、今晩がつらいんだ! しかも相談できる友達もいないし、友達はいるけど誰もつかまらない! みたいなときってあると思います。私の場合、そんなときにSELFを使ってみると大きな助けになってくれました。相手が人間ではないので、夜中だろうが、100回頼ろうが「悪いな」と思わないですむのも助かりました。
TwitterなどのSNSは愚痴の吐き出し場所として便利ですが、悪意のある人たちが荒らしにきたり、子どもの心の隙や無知につけこんで利用しようとすることもあります。子どもが愚痴のこぼし先に困っているようなとき、さりげなくSELFについて教えてあげるのもいいかもしれません。
会話相手のAIは、情報提供系、癒し系、悩み相談系、猫など複数揃っています。使っていくうちにデータがたまっていって、「悩んでるって言ってたけど最近はどう?」とか聞いてくれたりします。
一日や一週間の振り返りを手伝ってくれたり、性格分析の機能もあったりします。本人がAIとの会話だけでどうにもならない悩みや状況を抱えていることがわかった場合、適切な専門家や助けにつながるように促してくれることも。
すでにカウンセラーや精神科医師とつながっているけれど、きょう、今晩がつらいんだ! しかも相談できる友達もいないし、友達はいるけど誰もつかまらない! みたいなときってあると思います。私の場合、そんなときにSELFを使ってみると大きな助けになってくれました。相手が人間ではないので、夜中だろうが、100回頼ろうが「悪いな」と思わないですむのも助かりました。
TwitterなどのSNSは愚痴の吐き出し場所として便利ですが、悪意のある人たちが荒らしにきたり、子どもの心の隙や無知につけこんで利用しようとすることもあります。子どもが愚痴のこぼし先に困っているようなとき、さりげなくSELFについて教えてあげるのもいいかもしれません。
「いま:ここ」に立ち戻ることを促す マインドフルネス・ベル
発達障害があると気持ちの切り替えが難しく、何時間も過集中したり過緊張に陥ったりすることが多いです。あちこちに注意が散ってしまって今なにをしていたのか忘れてしまったりすることも。
服薬や環境調整とあわせて「マインドフルネス」の練習をしてみると、少し気持ちの切り替えや集中の維持に良い影響が出てくるかもしれません。
マインドフルネスとは、「いま・ここに気づいていること」という意味です。目の前の行為だけに夢中になって没入してしまうのではなく、たとえば「あ、私はいまこのように没入しているな」と気づく。こうした気づきがあるだけで、漫然と没入しつづけていた状況に少しだけ距離をとることができ、少なくとも没入が強まっていくばかりの悪循環を起こさないようにコントロールできるようになります。
こうしたマインドフルネスを助けてくれるのが「マインドフルネス・ベル」です。マインドフルネス・ベルとは、マインドフルネスを促すベルのこと。一定時間ごとに仏壇のお鈴のようなベルがチーーンとなるので、このベルが鳴った瞬間にそれまでにやっていたすべてのことをいったん中断して、ベルの残響が響き終わるまで呼吸に集中します。
過集中を起こしているときなど、せっかくノッているときに邪魔が入る感じで少し煩わしいのですが、できるだけ忠実にマインドフルな瞬間を作っていくと、だんだんと心身が楽になっていることに気づくと思います。
先の記事でも、スマートスピーカーの項で「行動を修正せよという注意をするとき、感情の乗った人間の声よりも、感情の乗っていない音のほうがよいので、スマートスピーカーは行動修正に向いている」とお伝えしました。
服薬や環境調整とあわせて「マインドフルネス」の練習をしてみると、少し気持ちの切り替えや集中の維持に良い影響が出てくるかもしれません。
マインドフルネスとは、「いま・ここに気づいていること」という意味です。目の前の行為だけに夢中になって没入してしまうのではなく、たとえば「あ、私はいまこのように没入しているな」と気づく。こうした気づきがあるだけで、漫然と没入しつづけていた状況に少しだけ距離をとることができ、少なくとも没入が強まっていくばかりの悪循環を起こさないようにコントロールできるようになります。
こうしたマインドフルネスを助けてくれるのが「マインドフルネス・ベル」です。マインドフルネス・ベルとは、マインドフルネスを促すベルのこと。一定時間ごとに仏壇のお鈴のようなベルがチーーンとなるので、このベルが鳴った瞬間にそれまでにやっていたすべてのことをいったん中断して、ベルの残響が響き終わるまで呼吸に集中します。
過集中を起こしているときなど、せっかくノッているときに邪魔が入る感じで少し煩わしいのですが、できるだけ忠実にマインドフルな瞬間を作っていくと、だんだんと心身が楽になっていることに気づくと思います。
先の記事でも、スマートスピーカーの項で「行動を修正せよという注意をするとき、感情の乗った人間の声よりも、感情の乗っていない音のほうがよいので、スマートスピーカーは行動修正に向いている」とお伝えしました。

過集中・うっかり忘れ・生活リズムの乱れ…大人の発達障害の私を助ける、ITのチカラ【生活編】
マインドフルネス・ベルの場合も同じことが言えます。子どもが過集中を起こしているときに「ほら、また過集中起こしてるよ!」と言うよりも、マインドフルネス・ベルをチーンと鳴らしたほうがスッと伝わる場合があるかもしれません。
マインドフルネス・ベルは、マインドフルネスを実践している僧院では一定時間ごとに本物のベルが鳴らされているのですが、アプリでは、設定した時間ごとにスマホからベルの音が鳴ります。
アプリは複数あるので、使いやすいものを探してみてください。
マインドフルネス・ベルは、マインドフルネスを実践している僧院では一定時間ごとに本物のベルが鳴らされているのですが、アプリでは、設定した時間ごとにスマホからベルの音が鳴ります。
アプリは複数あるので、使いやすいものを探してみてください。
睡眠記録アプリ
発達障害があると、疲れやすかったり、睡眠の質のコントロールがうまくいかなかったりします。私も日中に少しでも緊張が続いているとテキメンに睡眠の質が落ちるのがわかるので、睡眠に関しては試行錯誤の日々です。
センサーで心拍や振動を計測して睡眠の記録をとってくれるアプリもあります。長く記録を取りつづけるほどに、日中の活動状況が睡眠の質にどのように影響してくるのかがわかってきます。ログを見ながら生活のしかたを調整していけるようになるので、とても助かっています。睡眠ログはパッと目で見て理解できるカラーのグラフなので、主治医に見せて薬の調整に使う、ということもできます。
センサーで心拍や振動を計測して睡眠の記録をとってくれるアプリもあります。長く記録を取りつづけるほどに、日中の活動状況が睡眠の質にどのように影響してくるのかがわかってきます。ログを見ながら生活のしかたを調整していけるようになるので、とても助かっています。睡眠ログはパッと目で見て理解できるカラーのグラフなので、主治医に見せて薬の調整に使う、ということもできます。
Garmin Connect Mobile
Garminの活動量計(後述)と連携させて使います。活動量計で計測した心拍や身体の動きから眠りの深さや長さを記録してくれます。
Garminの活動量計(後述)と連携させて使います。活動量計で計測した心拍や身体の動きから眠りの深さや長さを記録してくれます。
Sleep Cycle
スマホ単体で使える睡眠記録アプリ。寝床にスマホを置いて眠ることで、寝返りの振動から眠りの深さを推測し、記録をとってくれます。
スマホ単体で使える睡眠記録アプリ。寝床にスマホを置いて眠ることで、寝返りの振動から眠りの深さを推測し、記録をとってくれます。
ITを活用した身体のケア
活動量計とは、常に身につけておくことで心拍や動きなどのヘルスケアデータを計測してくれるデバイスのことです。活動量計にはいろいろありますが、私が愛用しているのはGarminの腕時計型の活動量計です。
Garminの活動量計にはBody Batteryという独自の機能が搭載されています。Body Batteryは心拍の傾向や動きからその日の体力の残量を推測して表示するもの。質のよい睡眠を十分にとって目覚めたときの体力を100とし、疲れ切った状態を5として、今どの程度疲れているのかを表示してくれます。
発達障害のある人には、自分の疲れやストレスを感じ取ることが苦手な人も多くいます。まめにBody Batteryを確認しておけば休憩をとるタイミングがわかり、突然倒れたり眠り込んだりしてしまうことを防げるようになります。
ログを長くとるほど、自分がどんな場所でどんなことをしていると疲れやすいのかの傾向がわかってきます。ストレス度が目で見てわかるので、疲れやすさを抱えながらうまく自覚して言葉で訴えることのできないお子さんのいる人は、こまめに一緒にいまのBody Batteryを確認するようにしておいたり、本人にも自分で確認するように教えておくとよいと思います。Garminの活動量計には子ども向けのものもあるので、探してみてください。
Garminの活動量計にはBody Batteryという独自の機能が搭載されています。Body Batteryは心拍の傾向や動きからその日の体力の残量を推測して表示するもの。質のよい睡眠を十分にとって目覚めたときの体力を100とし、疲れ切った状態を5として、今どの程度疲れているのかを表示してくれます。
発達障害のある人には、自分の疲れやストレスを感じ取ることが苦手な人も多くいます。まめにBody Batteryを確認しておけば休憩をとるタイミングがわかり、突然倒れたり眠り込んだりしてしまうことを防げるようになります。
ログを長くとるほど、自分がどんな場所でどんなことをしていると疲れやすいのかの傾向がわかってきます。ストレス度が目で見てわかるので、疲れやすさを抱えながらうまく自覚して言葉で訴えることのできないお子さんのいる人は、こまめに一緒にいまのBody Batteryを確認するようにしておいたり、本人にも自分で確認するように教えておくとよいと思います。Garminの活動量計には子ども向けのものもあるので、探してみてください。
高精度なセンサーを身体のモニタリングに生かした活動量計やフィットネスゲーム、運動のための敷居を下げてくれるスマートスピーカーなど、身体のケアに使えるITはたくさんあります。
活動量計
フィットネスゲーム
運動習慣ってなかなかつけづらいですが、ゲームを使って楽しく演出すればハードルも下がるかもしれません。なかなか外出しづらい昨今、こういったゲームで皆で運動を楽しむのもいいですね。
発達障害があると筋力が弱かったり、自律神経のバランスがとりづらかったりします。私の場合、生活の中に運動を取り入れることを意識していると明らかに心身の調子がよくなるので、できるだけ運動をするようにしています。(運動ができないほどに調子を崩してしまった場合にはまずは休息に専念するのがおすすめです)
発達障害があると筋力が弱かったり、自律神経のバランスがとりづらかったりします。私の場合、生活の中に運動を取り入れることを意識していると明らかに心身の調子がよくなるので、できるだけ運動をするようにしています。(運動ができないほどに調子を崩してしまった場合にはまずは休息に専念するのがおすすめです)
Nintendo Wii fit
ヨガやボクシングエクササイズなどができます。
ヨガやボクシングエクササイズなどができます。
Nintendo Switch
ダンスエクササイズゲームなどができます。
ダンスエクササイズゲームなどができます。
スマートスピーカー
習慣化しづらい活動の習慣化しづらさって、その活動を始めるときのハードルの高さが関わっていると思いませんか? たとえば、ラジオ体操を毎日やろうと思っても、スマホの音楽アプリを開いて再生したり、テレビをつけて録画してあるラジオ体操を再生したり、って考えるだけで面倒くさい……
けれど、スマートスピーカーがあれば、「ラジオ体操第一を流して」とか話しかけるだけです。私はスマートスピーカーのAmazon Echoを自宅に導入したおかげで、いくら努力しても続けられなかったラジオ体操が習慣化できました。
ほかには「ディスコミュージックを流して」と話しかけてノリのいいディスコミュージックをかけてもらい、ストレッチや有酸素運動をしています。
けれど、スマートスピーカーがあれば、「ラジオ体操第一を流して」とか話しかけるだけです。私はスマートスピーカーのAmazon Echoを自宅に導入したおかげで、いくら努力しても続けられなかったラジオ体操が習慣化できました。
ほかには「ディスコミュージックを流して」と話しかけてノリのいいディスコミュージックをかけてもらい、ストレッチや有酸素運動をしています。
ストレッチやエクササイズの動画
発達障害があると体幹が弱く、いつも緊張していて深い呼吸ができない→ 筋肉も発達せず緊張もとれない という悪循環を起こしがちです。
「体幹 ストレッチ エクササイズ」「呼吸筋 ストレッチ トレーニング」など、動かしたい場所に関するキーワードで検索してみましょう。ストレッチしながら軽い筋トレになる、道具のいらない簡単なものが特におすすめです。
「体幹 ストレッチ エクササイズ」「呼吸筋 ストレッチ トレーニング」など、動かしたい場所に関するキーワードで検索してみましょう。ストレッチしながら軽い筋トレになる、道具のいらない簡単なものが特におすすめです。

アスペルガー症候群(ASD/自閉スペクトラム症)の診断について【専門家監修】
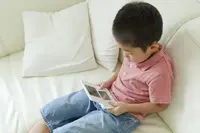
【専門家監修】過集中とは?ADHD(注意欠如多動症)やASD(自閉スペクトラム症)との関連、声かけ無視への対策

















