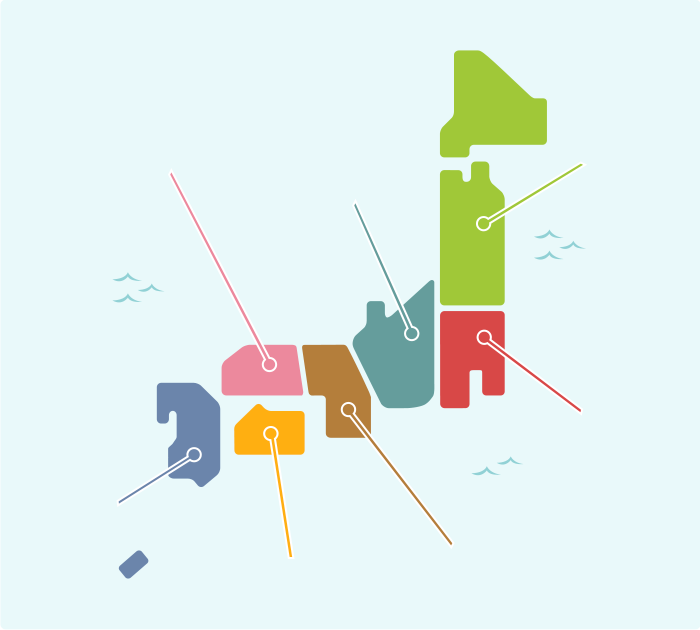映画『梅切らぬバカ』監督・脚本の和島香太郎さん、自閉症の「忠さん」を好演した塚地武雅さんを取材。当事者、地域の人々、双方の視点で描いた背景や想いとは?
ライター:発達ナビ【編集部Eye】

Upload By 発達ナビ【編集部Eye】
11月12日に全国ロードショー公開される映画「梅切らぬバカ」。自閉スペクトラム症の50歳の男性とシングルマザー、2人暮らしの親子の日常を描いたストーリー。親子の愛情や絆といったテーマに加えて、引っ越してきたお隣さんとの関係や、グループホームと地域の関係といった、障害者が地域の中で暮らすということについても、考えさせられる映画です。監督・脚本の和島香太郎さんと、息子役の「忠(ちゅう)さん」を好演した塚地武雅さんに、この映画への思いを伺いました。
映画「梅切らぬバカ」のストーリー
11月12日に全国ロードショー公開される映画「梅切らぬバカ」。自閉スペクトラム症の50歳の男性とシングルマザーの母子2人の日常を描いた作品。親子の愛情や絆といったテーマに加えて、障害のある人が地域の中で暮らすということについても考えさせられる映画です。
閑静な住宅地、大きな梅の木がある古い一軒家に暮らす、山田珠子(加賀まりこ)と50歳の息子、山田忠男こと忠(ちゅう)さん(塚地武雅)。珠子は占い師として生計を立てるシングルマザー、忠さんは自閉スペクトラム症、几帳面で馬が好き。毎日決まった時刻に起き、朝食をとり、作業所に通う忠さんと母の穏やかな暮らしに、変化が訪れる。隣家に越してきた里村家は、思い付きで行動しがちな父・茂(渡辺いっけい)、明るい母・英子(森口瑤子)、小学生の草太(斎藤汰鷹)の3人家族。あるとき、忠さんがぎっくり腰になったことを機に「親なきあと」を考えた珠子は、忠さんをグループホームに入居させることを考え始める。ところが、そのグループホームには、近隣からの反対運動が起こっていた――。タイトルは「桜伐る馬鹿梅伐らぬ馬鹿」ということわざから。木によって剪定のしかたが違うように、それぞれの人の特性によって向き合い方があるという意味。
閑静な住宅地、大きな梅の木がある古い一軒家に暮らす、山田珠子(加賀まりこ)と50歳の息子、山田忠男こと忠(ちゅう)さん(塚地武雅)。珠子は占い師として生計を立てるシングルマザー、忠さんは自閉スペクトラム症、几帳面で馬が好き。毎日決まった時刻に起き、朝食をとり、作業所に通う忠さんと母の穏やかな暮らしに、変化が訪れる。隣家に越してきた里村家は、思い付きで行動しがちな父・茂(渡辺いっけい)、明るい母・英子(森口瑤子)、小学生の草太(斎藤汰鷹)の3人家族。あるとき、忠さんがぎっくり腰になったことを機に「親なきあと」を考えた珠子は、忠さんをグループホームに入居させることを考え始める。ところが、そのグループホームには、近隣からの反対運動が起こっていた――。タイトルは「桜伐る馬鹿梅伐らぬ馬鹿」ということわざから。木によって剪定のしかたが違うように、それぞれの人の特性によって向き合い方があるという意味。

50歳の自閉症息子がグループホームへ。老いた母の葛藤、不寛容な社会への働きかけが起こす変化とはーー加賀まりこ・塚地武雅出演 映画「梅切らぬバカ」が11月12日公開
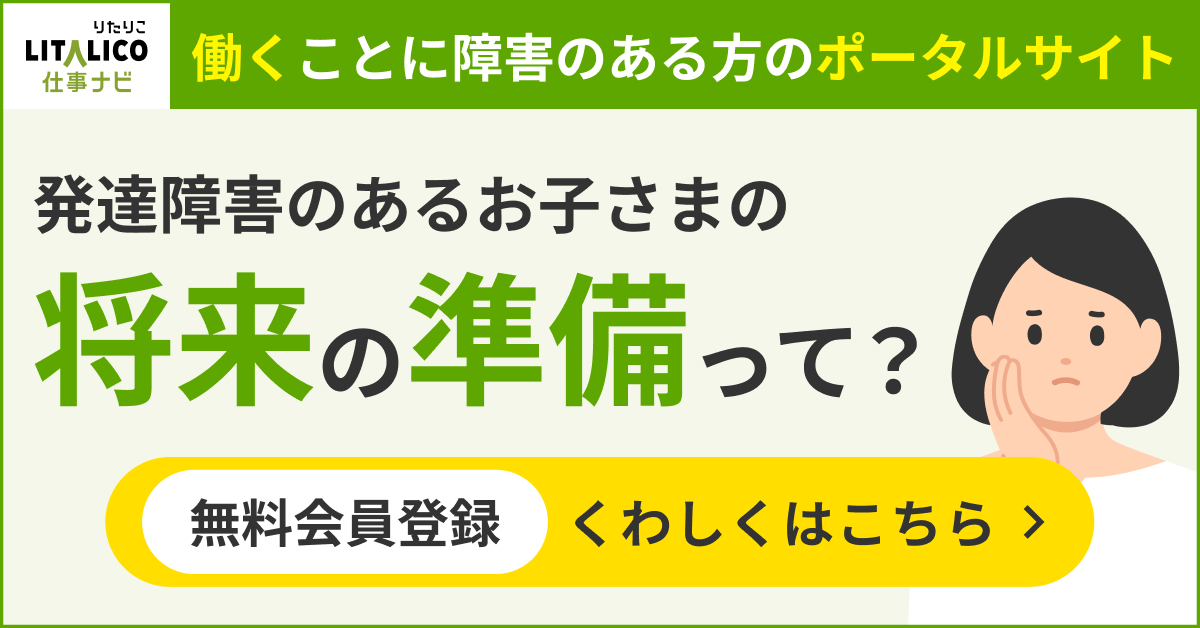
障害者の側と、その近隣の人々、両方の視点を同時に描く
映画「梅切らぬバカ」監督・脚本の和島香太郎さんと、息子役の「忠(ちゅう)さん」を好演した塚地武雅さんに、LITALICO発達ナビ編集長・牟田が、この映画への思いを伺いました。
LITALICO発達ナビ 牟田暁子編集長(以下――) はじめに、この映画を撮ろうと思われたきっかけから、教えてください。
和島香太郎監督(以下、和島):数年前、障害のある男性の一人暮らしを描いたドキュメンタリー映画に、編集として携わっていたことがこの映画を撮るきっかけになっています。そのドキュメンタリー映画では、主人公の男性は広汎性発達障害(※)と診断されていて、親御さんが残された家に一人暮らしを続けていました。福祉のサービスや親族の助けを借りて、どうにかギリギリ自立生活をされている、その様子を記録したドキュメンタリーでした。
編集をするということは、すべての撮影してきた素材映像を確認することになります。その男性と近隣住民との関係がよくなかったために、画面上に近隣住民が映らないように編集する作業もありました。最初はあまり気にしていなかったんですが、こうせざるをえない状況があるんだな…と思うようになっていきました。
そのドキュメンタリーの完成後、主人公の彼がおかれた状況を知ってもらうために、近隣の人たちに見ていただく機会があり、そのあとに長い手紙をもらいました。内容をまとめると、「障害者を肯定的に描きすぎているんじゃないか、近所に住む者としては彼の言動によって不安な思いもしている、憤りもある」というようなことが書かれていたのです。
私たちが撮影を通じて見ていた彼は、とてもユーモアのある、やさしいおじさんでした。でも、近隣の人にはまた別の視点がある。そこまで全部ひっくるめて描くことができたら、と思ったんです。
ただ、ドキュメンタリーでは近隣の人たちにカメラを向けることができない。フィクションであればできるかもしれないと、脚本を書いたのです。
※編集部注:診断当時の名称。現在は自閉スペクトラム症と称される
――ハッピーエンドになりすぎない、救いのない感じでもないという絶妙なストーリーですが、そこも意識して脚本を書かれたのでしょうか。
和島:取材する中で、自閉症のある方のお母さんにもたくさんお会いして、いろいろなお話を伺いました。こういう題材を扱った映画において、奇跡が起きたり、ハッピーエンドだったりすることに違和感を持たれている方も少なくありませんでした。問題の解決を描くことは映画を観に来た人に気持ちよく帰ってもらうためなのかもしれません。けれど、現実ではギリギリのところで心の折り合いをつけながら、暮らしている方々がいます。その姿を映画のために歪めないことを意識して、悩みながら、着地した脚本になります。
LITALICO発達ナビ 牟田暁子編集長(以下――) はじめに、この映画を撮ろうと思われたきっかけから、教えてください。
和島香太郎監督(以下、和島):数年前、障害のある男性の一人暮らしを描いたドキュメンタリー映画に、編集として携わっていたことがこの映画を撮るきっかけになっています。そのドキュメンタリー映画では、主人公の男性は広汎性発達障害(※)と診断されていて、親御さんが残された家に一人暮らしを続けていました。福祉のサービスや親族の助けを借りて、どうにかギリギリ自立生活をされている、その様子を記録したドキュメンタリーでした。
編集をするということは、すべての撮影してきた素材映像を確認することになります。その男性と近隣住民との関係がよくなかったために、画面上に近隣住民が映らないように編集する作業もありました。最初はあまり気にしていなかったんですが、こうせざるをえない状況があるんだな…と思うようになっていきました。
そのドキュメンタリーの完成後、主人公の彼がおかれた状況を知ってもらうために、近隣の人たちに見ていただく機会があり、そのあとに長い手紙をもらいました。内容をまとめると、「障害者を肯定的に描きすぎているんじゃないか、近所に住む者としては彼の言動によって不安な思いもしている、憤りもある」というようなことが書かれていたのです。
私たちが撮影を通じて見ていた彼は、とてもユーモアのある、やさしいおじさんでした。でも、近隣の人にはまた別の視点がある。そこまで全部ひっくるめて描くことができたら、と思ったんです。
ただ、ドキュメンタリーでは近隣の人たちにカメラを向けることができない。フィクションであればできるかもしれないと、脚本を書いたのです。
※編集部注:診断当時の名称。現在は自閉スペクトラム症と称される
――ハッピーエンドになりすぎない、救いのない感じでもないという絶妙なストーリーですが、そこも意識して脚本を書かれたのでしょうか。
和島:取材する中で、自閉症のある方のお母さんにもたくさんお会いして、いろいろなお話を伺いました。こういう題材を扱った映画において、奇跡が起きたり、ハッピーエンドだったりすることに違和感を持たれている方も少なくありませんでした。問題の解決を描くことは映画を観に来た人に気持ちよく帰ってもらうためなのかもしれません。けれど、現実ではギリギリのところで心の折り合いをつけながら、暮らしている方々がいます。その姿を映画のために歪めないことを意識して、悩みながら、着地した脚本になります。
最初から最後までフラットに忠さんとして演じた
――塚地さんは、監督のそうした思いをどのように感じられていましたか?
塚地武雅さん(以下、塚地):完成した台本を見せていただいたときに、監督が言わんとしていることが詰まった内容だと感じました。大きく奇跡が起こるということではなく、日常を切り取った話だけれど、「あ、私も考えなきゃな」と思えるような脚本でしたね。
僕自身は、身近に障害のある方がいるわけではありません。子どものころには、たとえば、同じバスに自閉症の方が乗ってきたときに、ちょっとこわいと身構えたこともありました。だから、映画で描かれている近隣の人たちの気持ちもわかるんです。
実際のグループホームを見学したり、監督からいただいた多くの資料映像で家族の方々の姿を見たりするうちに、「こわい」存在ではないとわかってきます。でも踏み込まないとわからないとも感じています。
――忠さんを演じてみて、どんな感じでしたか?
塚地:ほんとに最初から最後まで変わらずに「忠さん」として、演じていたんですよね。通常の映画やドラマでは、クライマックスに向けて気合を入れて演じる場面があるというか、「ここで感動してもらおう!」というスイッチを入れるところがあるんです。でも今回、そうしたことは一切なく、フラットにただ忠さんとして演じられたのは、脚本に深みがあったからだと思っています。
――たしかに自然でした。がんこな忠さんの心が少しずつ落ち着いていく様子が見られますが、そのあたりも自然でリアルだなと思いました。
塚地武雅さん(以下、塚地):完成した台本を見せていただいたときに、監督が言わんとしていることが詰まった内容だと感じました。大きく奇跡が起こるということではなく、日常を切り取った話だけれど、「あ、私も考えなきゃな」と思えるような脚本でしたね。
僕自身は、身近に障害のある方がいるわけではありません。子どものころには、たとえば、同じバスに自閉症の方が乗ってきたときに、ちょっとこわいと身構えたこともありました。だから、映画で描かれている近隣の人たちの気持ちもわかるんです。
実際のグループホームを見学したり、監督からいただいた多くの資料映像で家族の方々の姿を見たりするうちに、「こわい」存在ではないとわかってきます。でも踏み込まないとわからないとも感じています。
――忠さんを演じてみて、どんな感じでしたか?
塚地:ほんとに最初から最後まで変わらずに「忠さん」として、演じていたんですよね。通常の映画やドラマでは、クライマックスに向けて気合を入れて演じる場面があるというか、「ここで感動してもらおう!」というスイッチを入れるところがあるんです。でも今回、そうしたことは一切なく、フラットにただ忠さんとして演じられたのは、脚本に深みがあったからだと思っています。
――たしかに自然でした。がんこな忠さんの心が少しずつ落ち着いていく様子が見られますが、そのあたりも自然でリアルだなと思いました。