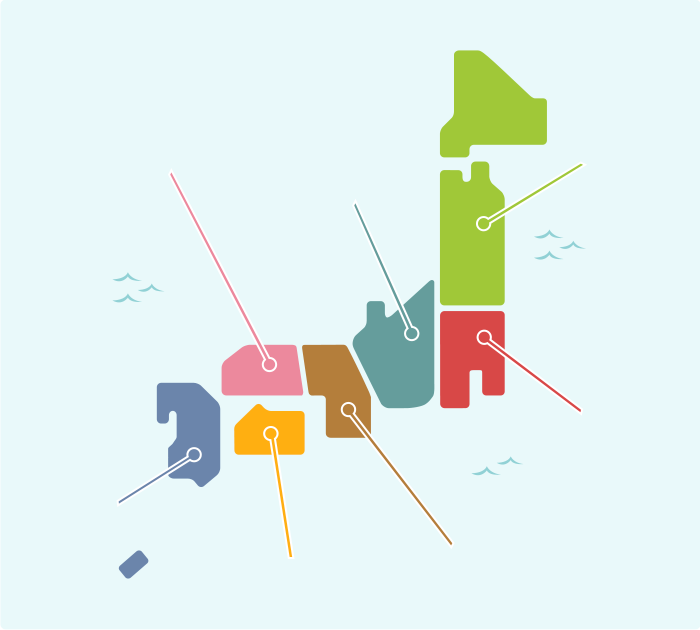小3で「忘れ物の女王」、片づけが苦手で夫から罵倒、離婚も。ADHD当事者が目指す「否定しない社会」――発達障害を描いたCMプロデューサーが聞く【見えない障害と生きる】
ライター:桑山 知之

Upload By 桑山 知之
本連載は、発達障害を描いたドキュメンタリーCM『見えない障害と生きる。』でプロデューサーを務めた東海テレビの桑山知之が聞き手となり、さまざまな発達障害の当事者やその家族らと対談するコラムである。16回目となる今回は、ADHDとASDの当事者で、NPO法人「DDAC」代表・広野ゆいさん(49)に話を聞いた。

監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
小3でついたアダ名は「忘れ物の女王」
筆者と広野さんとの出会いは2019年に遡る。ドキュメンタリーCM『見えない障害と生きる。』の取材のため、連絡を取ったのがきっかけだった。底抜けに明るい性格について触れると、広野さんは「このくらいじゃないと生きていけない」と笑い飛ばした。その言葉の重みに、筆者の胸が苦しくなったのを今でも覚えている。
広野さんは幼少期から、目の前にあるもの以外はすぐに忘れてしまう子どもだった。小学校に入ってからは管理しなければいけないものが増え、何かをこなすことは「全く無理だった」。宿題を出され、その場ではやる気でいても、家に帰れば宿題を出されたことすら忘れている。翌日提出を求められて初めて思い出す。小学校2年生の通知表に「忘れ物が多い」とはっきり書かれ、3年になると周囲からは「忘れ物の女王」とアダ名をつけられた。
「どうしてみんなができるのか分からないんですよ。頑張らなきゃいけないんだけど、どう頑張ったらいいのか分からない。困るんですよね、『ちゃんとやって』って言われると。ちゃんとやっているつもりなので。一人だけ違うことしてたりするんですけど、それを問題だとも思っていない。だから怒られますよね」(広野さん)
学校のあちこちには、広野さんの持ち物が散らばっていたという。5年生ぐらいのころには、遠足で河原に行った際、飯盒炊飯でカレーをみんなでつくって食べるとき、広野さんは肉を持ってくる係だったが、肉を忘れてしまい、広野さんの班だけベジタブルカレーになってしまったこともあった。成績や勉強よりも「生きていくこと自体が難しかった」といい、時間に遅れないようにするなど社会生活に食らいつくのに必死だった。
片づけできず夫から罵倒…「私はいても意味ない」
地元の中学を経て静岡県内の高校を卒業後、青山学院大学に進学。当初は国語の教員になろうと思っていたが、LD(学習障害)の傾向があるのか、時折、字が正確に書けないことがあった。ずっと続けて文字を書いていると、例えば「春」の横棒が四本になってしまうことがあるらしい。「これでは黒板の字が不正確になってしまう」と思い、教師の夢を諦めた。落ち込んでいたところ、ゼミの教授の紹介で、都内の大学病院の教授の秘書になった。しかし、当時は自身がADHDとは知らず、自分のスケジュールの管理も難しく、何より察して動くことが全くできず、とんちんかんなことばかりしてしまい、周囲から「使えない」と言われ、思い悩むことも多かったという。
「若いときは、できなくても頑張らなきゃいけないとか、頑張ったらできるかもしれないとか、そういう気持ちが強かったんです。でも半年でおかしくなっちゃって。電車に乗っていられなくなったり、起きたら午後だったり、色々できなくなっていきました。生きていてもしょうがないと、思いつめていました……」(広野さん)
生きることもできず、死ぬこともできず、「しんどい」毎日を過ごしていたが、23歳で当時交際していた男性と“デキ婚”。実家の両親からサポートを受けながら家事や育児に勤しんでいたが、やはり片づけがどうにも苦手だった。家の中は物で溢れかえり、食卓には書類などが大量に積まれ、食事を摂ることもままならなかった。そして29歳のころ、鬱病と診断された。
「旦那からは『こんな家に帰ってくる俺の気持ちになってみろ』とか『お前、一日家にいて何してるんだ』とか言われて。そのときは診断も受けていなかったので、『私はいても意味ないな』ってどんどん落ち込んでいきましたね。頑張って専業主婦をしていたときが一番つらかったです」(広野さん)
そんな中、2000年に刊行された『片づけられない女たち』(WAVE出版/サリ・ソルデン著)を読み、驚いた。自分によく似た人がこんなにいる。そして、対処方法がある。そこから、発達障害というものがあることを知り、同じ悩みを抱える人とともに当事者グループをつくって理解を深めた。「最初は自分がとにかく喋りたいからつくった」と笑うが、家庭の悩みなどを打ち明けられる居場所ができたのだった。
片づけられない女たち
WAVE出版
Amazonで詳しく見る
「言い訳だ」夫から度重なる暴力、そして離婚
30歳を過ぎてからADHDと診断を受けた広野さん。発達障害のことを夫に打ち明け、「家事を一緒にやってほしい」「手伝ってほしい」と伝えたが、「そんなのは言い訳だ」と理解してもらえなかった。むしろ、診断を打ち明けたことをきっかけに、夫との関係は余計に悪化。物を投げられ、時には暴力を受け、外に出られないぐらいひどいあざが顔面にできることもあった。
「自分が(夫の)ストレスの捌け口になっていたんだと思います。私が反論するようになって、ストレス解消ができないから、手が出るようになったのかなって。でも自分の両親はサポートしてくれたし、ママ友たちも『子どもの迎え忘れているよ』とか教えてくれるようになって、すごく助かりましたね。私自身も、ADHDがあると分かってからは、子どもに怒らないようになりました」(広野さん)
夫と別居するために2年ほど準備期間を経て、娘2人とともに小学校の校区の端から端に引っ越した。すぐに弁護士を立て、34歳で離婚に踏み切った。別居するとすぐさま、ストレスから解放された気分になった。そして2008年、「発達障害をもつ大人の会(現・NPO法人DDAC)」を立ち上げた。
「こんな感じでも今NPO法人の代表をしていたりとか、全部ができないわけじゃないんですよね。発達障害はできることできないことにものすごく差があるけれども、できないことばかりではないということを知ってもらいたいです。あと、周りの人は何でもできるようにさせようとするじゃないですか。それをやられると、みんなだめになっていくんです。二次障害を引き起こしたりとか。何でもできる人間にならなくていいんです」(広野さん)
現在広野さんは、キャリアカウンセラーとして同じ悩みを抱える若者や仕事を探している人への就労支援を行っている。発達障害があるかもしれない人や、障害者手帳を取るかどうか悩んでる人、仕事を何回も辞めさせられたり、仕事が長続きしない人など、広野さんのもとにはあらゆる相談が舞い込んでくる。
「とにかく“フツウになろうとしない”ことをオススメします。自分なりの生き方、生活の仕方を編み出していくのが必要なので、落ち込みすぎずにうまく周りに助けてもらいながらできることをやっていく。私も20代のころは『どうやったらうまく死ねるのかな』とか思っていたんですけど、今はこの人生も割と悪くないと思っていて。発達障害があっても楽しく生きていけるような生き方をみんなにもしてほしいと思います」(広野さん)
新型コロナウイルス対策で、在宅勤務やリモート授業などが推進され、家族が一緒にいる時間が増えた。発達障害のある人にとって、毎日決まった時間に通勤・通学することの煩雑さを感じなくていいのは非常に楽だと広野さんは言う。ただし、「家の環境が良くないと地獄」とも指摘している。