「様子を見ましょう」発達診断で確定診断が出ない、支援につながらず悩む人へーー『発達障害「グレーゾーン」その正しい理解と克服法』
ライター:発達ナビBOOKガイド
Sponsored
SBクリエイティブ株式会社
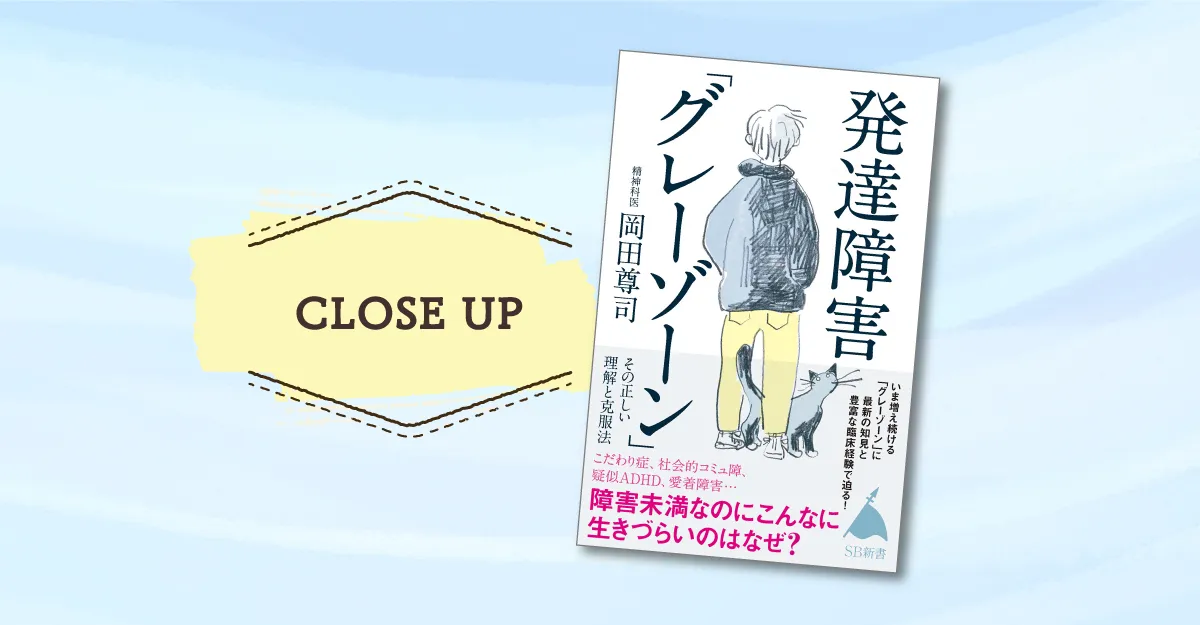
Upload By 発達ナビBOOKガイド
発達相談で「様子を見ましょう」と言われ、発達診断に行っても確定的な診断が出なかった…、発達障害の「グレーゾーン」と呼ばれる状況はこうして生まれます。そもそも脳の働き、発達段階はグラデーション(連続的)です。だとしたら、このグレーのところにいる人たちは、何も支援がないままでよいのでしょうか。さまざまな事例と共に「発達障害グレーゾーン」について考える本『発達障害「グレーゾーン」その正しい理解と克服法』(岡田尊司著 SBクリエイティブ)をご紹介します。
診断がないために支援が受けづらい「発達障害グレーゾーン」とは
もし、わが子が「発達障害グレーゾーン」だとしたら。保護者からすると気になるところがたくさんあるし、どう育てていいか分からないと感じることが多くあることでしょう。しかし、「発達障害」という診断はないので、いわゆる療育などの支援が受けられない場合もあります。
精神科医の岡田尊司先生による『発達障害「グレーゾーン」その正しい理解と克服法』(SBクリエイティブ)には、こうしたグレーゾーンにいる子どもと大人の特性理解と、どうしたら克服できるのかについて、豊富な事例を用いて分かりやすく丁寧に書かれています。
境界域にいる子どもは、医師にかかったときの、本人の状況などによって、(発達障害の)診断がつかない場合もあります。ですので、後に発達障害だと診断されるケースもあります。本書は各章ごとに、その特性についてどういう場合に「グレーゾーン」とされるのか、また、本人や家族が困っている特性についての原因を考察して克服法を考えていきます。各特性については、こだわり、コミュニケーション障害、共感が苦手、学習障害など多岐にわたります。
精神科医の岡田尊司先生による『発達障害「グレーゾーン」その正しい理解と克服法』(SBクリエイティブ)には、こうしたグレーゾーンにいる子どもと大人の特性理解と、どうしたら克服できるのかについて、豊富な事例を用いて分かりやすく丁寧に書かれています。
境界域にいる子どもは、医師にかかったときの、本人の状況などによって、(発達障害の)診断がつかない場合もあります。ですので、後に発達障害だと診断されるケースもあります。本書は各章ごとに、その特性についてどういう場合に「グレーゾーン」とされるのか、また、本人や家族が困っている特性についての原因を考察して克服法を考えていきます。各特性については、こだわり、コミュニケーション障害、共感が苦手、学習障害など多岐にわたります。
「グレーゾーンは症状が軽いから問題ない」とはいえない
ご存じの方も多いかもしれませんが、発達障害の診断には時間も手間もかかります。たくさんのチェック項目があることに加えて、特に子どもの場合は自分で自分の気持ちや状態をうまく説明できないために、医師と面談してもすぐにはその子の特性が分からないことがあります。初めて会った医師の前では、子どもは普段と同じような様子でいられないし、ふだんの様子が分かったとしても、その背景にあるものは生育歴も合わせて見ないと分からないからでもあります。診断はグラデーション(連続的)で、特定の数値だから確定できるというものではありません。
そして、子どもの場合には「様子を見ましょう」と言われることがよくあります。
そして、子どもの場合には「様子を見ましょう」と言われることがよくあります。
どうして「グレーゾーン」とされてしまうの?
本書には、ウェクスラー式知能検査についても書かれています。ウェクスラー式では、知能指数意外に、「言語理解」「知覚統合(知覚推理)」「作動記憶(ワーキングメモリ)」「処理速度」の4つの能力についての指数が算出されるというもの。この4つのバランスによって、その人の発達の偏りが分かると考えられています。この偏り方をどう見るかによって、発達障害の診断はつかず、グレーゾーンだとされるケースもある、ということなのです。
グレーゾーンと診断されたために、適切な時期に支援を受けられなかったことによって、成長するにつれて困難を抱え、障害ゾーンに傾いてしまう、というケースもあります。子どもの場合、「様子を見ましょう」と言われることはよくありますが、ただ見ていればいいだけではありません。
グレーゾーンと診断されたために、適切な時期に支援を受けられなかったことによって、成長するにつれて困難を抱え、障害ゾーンに傾いてしまう、というケースもあります。子どもの場合、「様子を見ましょう」と言われることはよくありますが、ただ見ていればいいだけではありません。
「グレーゾーン」は決して様子を見ればいい状態ではなく、細やかな注意と適切なサポートが必要な状態 (p25より)
ということを忘れてはいけないでしょう。
では、「グレーゾーン」の人は、子どものころにケアを受けなかったために、大人になるにつれて困難を抱えるようになっていくというものなのでしょうか。実はそこにはさまざまなケースがあるといいます。大人のADHDについてはニュージーランドのコホート研究の結果によると、子どものADHDとは抱える困難さが異なることも多いと分かってきました。
では、「グレーゾーン」の人は、子どものころにケアを受けなかったために、大人になるにつれて困難を抱えるようになっていくというものなのでしょうか。実はそこにはさまざまなケースがあるといいます。大人のADHDについてはニュージーランドのコホート研究の結果によると、子どものADHDとは抱える困難さが異なることも多いと分かってきました。
大人のADHDは、本来のADHDに比べると神経学的な障害は軽度であるにもかかわらず、生きづらさや生活上で感じている困難は、本来のADHDをもった人よりも強いという
(p30より)
発達障害の「グレーゾーン」についても、「軽度だから様子を見ていて大丈夫」ということを意味するのではなく、実はさまざまな困難を抱えている可能性があるのです。また、子どものころに診断されなくても、大人になって困難を抱える場合もあるのです。
さまざまな症状があり、人の数だけ原因となることは複雑に異なる
発達障害のグレーゾーンには、具体的にはどのような特性と克服法があるのでしょうか。本書では第2章から第9章まで8つのパターンを事例と共に紹介しています。タイトルを眺めると、どのような人たちが、どのような発達障害のグレーゾーンに当たるのかが見えてきます。
第2章 同じ行動を繰り返す人たち――こだわり症・執着症
第3章 空気が読めない人たち――社会的コミュニケーション障害
第4章 イメージできない人たち――ASDタイプと文系脳タイプ
第5章 共感するのが苦手な人たち――理系脳タイプとSタイプ
第6章 ひといちばい過敏な人たち――HSPと不安型愛着スタイル
第7章 生活が混乱しやすい人たち――ADHDと疑似ADHD
第8章 動きがぎこちない人たち――発達性協調運動障害
第9章 勉強が苦手な人たち――学習障害と境界知能
この中から、いくつかの例をピックアップしてみましょう。
第2章 同じ行動を繰り返す人たち――こだわり症・執着症
第3章 空気が読めない人たち――社会的コミュニケーション障害
第4章 イメージできない人たち――ASDタイプと文系脳タイプ
第5章 共感するのが苦手な人たち――理系脳タイプとSタイプ
第6章 ひといちばい過敏な人たち――HSPと不安型愛着スタイル
第7章 生活が混乱しやすい人たち――ADHDと疑似ADHD
第8章 動きがぎこちない人たち――発達性協調運動障害
第9章 勉強が苦手な人たち――学習障害と境界知能
この中から、いくつかの例をピックアップしてみましょう。
第2章 同じ行動を繰り返す人たち――こだわり症・執着症
自閉スペクトラム症(ASD)によく見られる「こだわり」。「いつもと同じ」であることへのこだわりが強くあることから、いつも通りにしたいのに邪魔が入ったり、突発的な予定が入ったりするとどうしていいか分からなくなってしまいます。
ただ、この「こだわり」にもさまざまな種類があるといいます。1.同じパターンの運動や所作を繰り返し行う常同運動障害 2.特定の行動・思考パターンへのこだわり…1の常同運動障害よりも、少し複雑な一連の行動を繰り返すことへのこだわり 3.電車などの特定の対象への強い執着といったことが挙げられます。
この中には、「正しさ」へのこだわりもあります。自分がやっていることが正しいと思うあまり、周りの人がゆるせないということも起こります。実は自分が正しいと思ってきたことはそうではないのかも?と気づくことで周りの人とのトラブルから抜け出すことができた、というある研究者の事例も紹介されています。
とらわれている物事や行動から脱出するためには、
ただ、この「こだわり」にもさまざまな種類があるといいます。1.同じパターンの運動や所作を繰り返し行う常同運動障害 2.特定の行動・思考パターンへのこだわり…1の常同運動障害よりも、少し複雑な一連の行動を繰り返すことへのこだわり 3.電車などの特定の対象への強い執着といったことが挙げられます。
この中には、「正しさ」へのこだわりもあります。自分がやっていることが正しいと思うあまり、周りの人がゆるせないということも起こります。実は自分が正しいと思ってきたことはそうではないのかも?と気づくことで周りの人とのトラブルから抜け出すことができた、というある研究者の事例も紹介されています。
とらわれている物事や行動から脱出するためには、
言葉で考えすぎるのをやめて、イメージや身体感覚を活性化したり楽しんだりする取り組みを増やすとよいようだ。(p62より)
また、今いる自分の状況から視点を変えて、部分でものを見るのではなく全体像を見るようにしてみること、つまり知覚統合を行うことが、こだわりから抜け出すヒントだとも書かれています。
第3章 空気が読めない人たち――社会的コミュニケーション障害
社会的コミュニケーションは、実はそれだけでは発達障害があるとは診断されません。そこにはさまざまな研究上の理由があります。
「社会的コミュニケーション障害」は、言葉のやりとりや非言語的なサインを通して、言外の意味やニュアンスを察しながら、その場にふさわしい会話を交わし、気もちや意図や情報を共有することがスムーズにできない状態(p71)
コミュニケーションに課題がある、と言うと、言語能力が低いイメージがありますが、意外にも、「言語能力が高くてもコミュニケーション能力が高いとは限らない」(p75)と書かれています。それは、コミュニケーションには、相互性がとても重要だから。おしゃべりは得意でなくても楽しそうに友だちと過ごしている子どもと、ことば巧みに自分の主張ばかりを言う子ども。どちらがコミュニケーション力としては高いか、と問われれば前者でしょう。「社会的コミュニケーションの能力とは、平たくいうと、人に慣れ親しむ能力」とも岡田先生は書いています。
このほかにも、グレーゾーンとされるのは、
・話は面白いし、積極的だが、人の気もちが分からない
・人とのちょうどいい距離感がつかめない人
・コミュニケーション能力はあるのに人づき合いを避けてしまう人
・人と親しめない「非社会性タイプ」と「回避性タイプ」
といった傾向がある人たちであるといわれています。
このほかにも、グレーゾーンとされるのは、
・話は面白いし、積極的だが、人の気もちが分からない
・人とのちょうどいい距離感がつかめない人
・コミュニケーション能力はあるのに人づき合いを避けてしまう人
・人と親しめない「非社会性タイプ」と「回避性タイプ」
といった傾向がある人たちであるといわれています。
勉強が苦手なケースには、知的障害とのボーダーラインである場合のほかに、学習障害があります。
知的障害は、境界知能を知能指数70~80(85とする場合)とされ、2割程度の人にみられるといいます。ある程度の年齢までは、なんとか努力で追いつくことができても、努力では補いきれなくなったときに、周りの期待とのギャップで苦しむことになるケースもあります。
また、いわゆる学習障害には、1.文字の読み、2.文の理解を合わせた読字障害、3.綴字の困難、4.作文の困難を合わせた書字表出障害、5.数字の理解や計算の困難、6.数学的推論の困難を合わせた算数障害のように分類されます。学校の学習や実生活の中で、困ることが起こるのはこうした学習障害があるからかもしれません。
ここで大切なのは、発達障害はグラデーションであることを忘れない、ということでしょう。
知的障害は、境界知能を知能指数70~80(85とする場合)とされ、2割程度の人にみられるといいます。ある程度の年齢までは、なんとか努力で追いつくことができても、努力では補いきれなくなったときに、周りの期待とのギャップで苦しむことになるケースもあります。
また、いわゆる学習障害には、1.文字の読み、2.文の理解を合わせた読字障害、3.綴字の困難、4.作文の困難を合わせた書字表出障害、5.数字の理解や計算の困難、6.数学的推論の困難を合わせた算数障害のように分類されます。学校の学習や実生活の中で、困ることが起こるのはこうした学習障害があるからかもしれません。
ここで大切なのは、発達障害はグラデーションであることを忘れない、ということでしょう。
早く知的障害の存在に気づかれた場合は、さまざまな支援を受けられるので、障害はあっても、その子なりのペースで発達していけると言える。むしろ問題は、知的障害の存在がわからないまま、普通学級で無理を強いられた場合や、知的障害というほどではない境界レベルの場合だ。(p191より)
支援が必要かどうかは、どこかでスパッと切り分けられるものではありません。そして、どんな子どもにとっても学校での学習の体験は、好奇心を満たして、分からないことがわかる楽しさにあるはず。それが、できないことを叱責されて自信をなくす場になっていないでしょうか。
学習障害にしろ、ほかのタイプの発達障害にしろ、失敗と𠮟 責の積み重ねが、その子の自信を打ち砕き、コンプレックスと自己否定を植えつけていく。そうなると、できるはずのこともできなくなってしまう。(p214より)
このことは、学習障害に限らず、ほかのグレーゾーンの子どもにも当てはまることでしょう。「イメージできない」「共感するのが苦手」「過敏」「生活が混乱」「動きがぎこちない」といった場合も、深く掘り下げてみると原因はさまざまです。発達障害ではなく、愛着障害である場合もあるし、環境によるものの場合もあるし、その両方の場合もあるということが、本書を読むとよく分かります。
まとめ
本書が伝えている事例は、どれも「一筋縄」では理解も克服も難しいものです。それは人の脳の働きは一人ずつ違うからであり、それが個性であり障害にもなりうるということだからです。グレーゾーンと一括りにされてしまうことで必要な支援に出合えず、本人も保護者も苦労するということがよく分かります。
克服法というと、それぞれの能力を少しでも高めるトレーニング方法のように感じられるかもしれません。でも、一番大事なことは、その人がその人らしくあって、幸せでいることです。何を伸ばして、どこを補ってあげたらいいのかを見ながら育てることなのでしょう。診断がある・ないにかかわらず、その子・その人自身を見ることによって、その人の困りごとを解決する糸口は見つかっていくということを、『発達障害「グレーゾーン」その正しい理解と克服法』は教えてくれるようです。
文/関川香織
克服法というと、それぞれの能力を少しでも高めるトレーニング方法のように感じられるかもしれません。でも、一番大事なことは、その人がその人らしくあって、幸せでいることです。何を伸ばして、どこを補ってあげたらいいのかを見ながら育てることなのでしょう。診断がある・ないにかかわらず、その子・その人自身を見ることによって、その人の困りごとを解決する糸口は見つかっていくということを、『発達障害「グレーゾーン」その正しい理解と克服法』は教えてくれるようです。
文/関川香織
発達障害「グレーゾーン」 その正しい理解と克服法
SBクリエイティブ
Amazonで詳しく見る
発達障害「グレーゾーン」 その正しい理解と克服法
SBクリエイティブ
楽天で詳しく見る

黒板を写せない、漢字や計算が苦手…「頑張ってもできない」子どもたちの背景に「認知機能」の弱さがある?――児童精神科医・宮口幸治先生

「認知の力」は学習の土台に!5つの認知機能をパズルやナゾトキで鍛える『コグトレ』とは――児童精神科医・宮口幸治先生

発達障害におけるグレーゾーンとは?特徴や注意すべきポイントなどを紹介します!【専門家監修】













