1歳でASD(自閉スペクトラム症)は分かる?発達障害の兆候や特徴、チェックリストも【小児科医監修】
ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
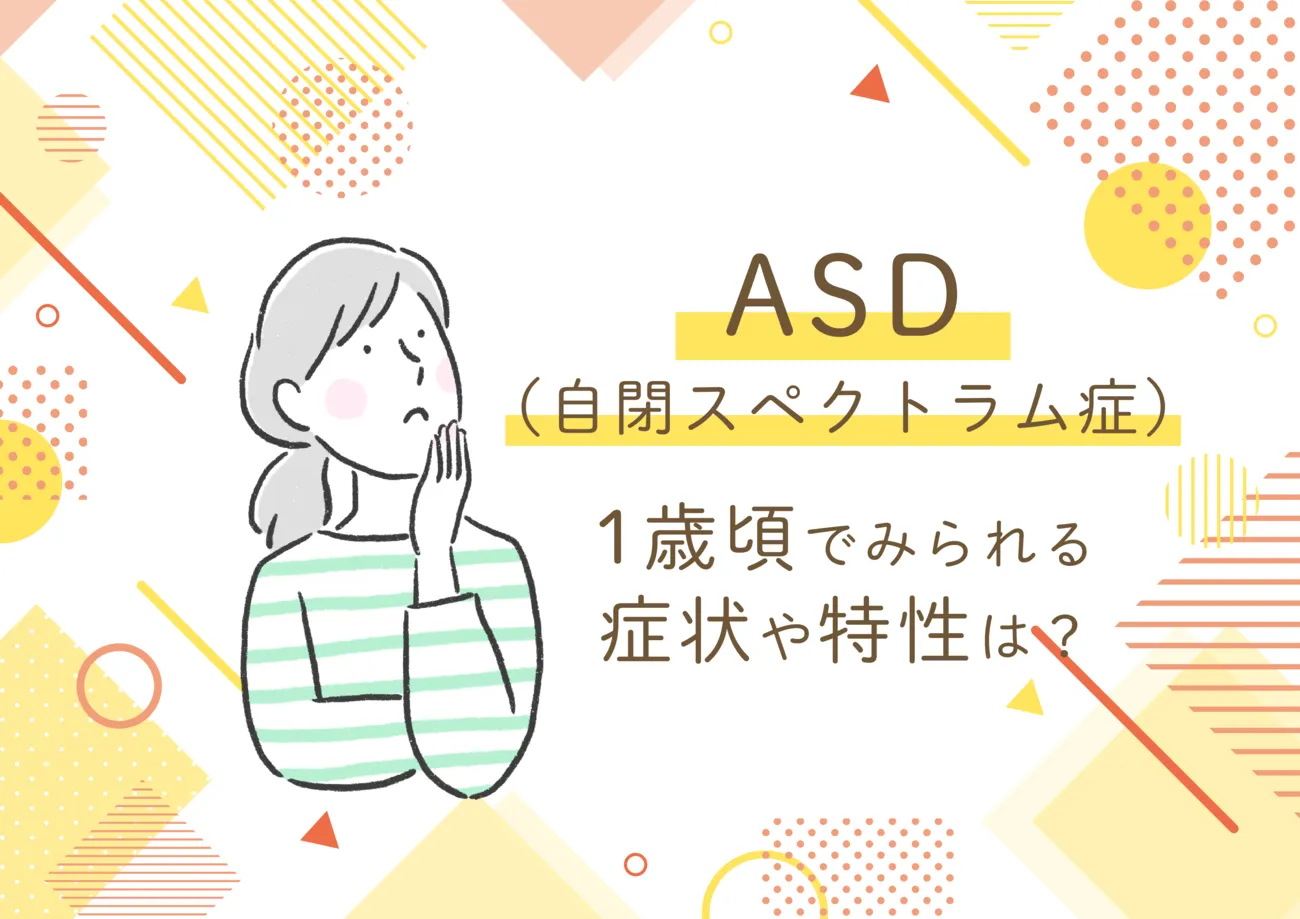
Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
1歳児は成長の個人差がとても大きい時期ですが、ASD(自閉スぺクトラム症)がある場合、目が合いにくい、「指さし」や「他者の顔を見てほほえむ」が出にくいなどの特徴がみられることがあります。ただし、1歳児は発達の個人差が大きいため、気になる場合には自治体の子育て相談窓口に相談しつつ、様子を見ながらおおらかな気持ちで接することも大切です。
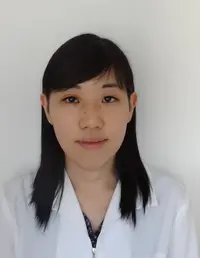
監修: 新美妙美
信州大学医学部子どものこころの発達医学教室 特任助教
2003年信州大学医学部卒業。小児科医師として、小児神経、発達分野を中心に県内の病院で勤務。2010年信州大学精神科・子どものこころ診療部で研修。以降は発達障害、心身症、不登校支援の診療を大学病院及び一般病院専門外来で行っている。グループSST、ペアレントトレーニング、視覚支援を学ぶ保護者向けグループ講座を主催し、特に発達障害・不登校の親支援に力を入れている。
多様な子育てを応援するアプリ「のびのびトイロ」の制作スタッフ。
自閉スペクトラム症(ASD)とは?
ASD(自閉スペクトラム症)は、社会的コミュニケーションや対人関係の構築が難しい、また常同的・反復的行動が多くみられる、乳幼児期に出現する精神発達の障害です。普段と違うことを嫌がる、大きな音や光などへの感覚の過敏さがあるなど、「強いこだわり、感覚の過敏さまたは鈍麻さ」という特性もあり、知的障害(知的発達症)を伴うこともあります。
症状の程度はそれぞれの人によって差があるため、スペクトラム(spectrum:範囲や連続体など幅を持った分布の意味)として診断されるようになりました。
症状の程度はそれぞれの人によって差があるため、スペクトラム(spectrum:範囲や連続体など幅を持った分布の意味)として診断されるようになりました。
遺伝との関係はある?
ASD(自閉スペクトラム症)は生まれつきの脳障害で、脳内の情報処理の仕方に障害があるといわれていますが、その原因はまだ分かっていません。
1歳児にみられることの多いASD(自閉スペクトラム症)の症状とは
この時期の成長や発達には大きな個人差がありますが、1歳でASD(自閉スペクトラム症)であると診断される指標として、
などがあげられます。
- 共同注意場面において「指さし」や「(他者の)指さし方向に顔を向ける」行動が出にくい
- 「他者の顔を見てほほえむ」などの社会的行動が出にくい
- 定型発達の1歳児にみられる「関心の共有」に興味を持ちにくい
などがあげられます。
発達ナビのQ&Aコーナーでは、1歳児のわが子の発達が気になる、対応方法が知りたいという保護者の声も寄せられています。
一歳9ヶ月男児です。最近あったことです。
公園に家族で行きましたが、最近小石を拾うのが子どものはやり。遊びを一旦終えてランチ、のとき抱っこしてました、するとおもむろにわたしのマスクを下げてくる(これは普段からやります)のでありのままにしてたら、息子の手いっぱい位ある大きな石を私の口に当ててきました。食べさせようとしたのでしょうか?私もびっくりして、思わずその石を取り上げてダメだよと叱ったのですが、叱ってる最中に今度は指で私の目を突いてきました。ついに息子を芝生に立たせて強め叱りました。えーんと大声で泣きましたが、、私の叱りも正しい対応だったか感情的過ぎたかな?と思い返してましたが、、大きい石をママの口に当てたり、目を突くとか、、ご経験あるかたいますか?こんな質問ですみません!専門家に相談した方がいいのかなと、このサイトに行き当たりました。
1歳9か月の発達障がいの子供がいます。言葉の理解がまだ難しいのですが、何でも投げることに困っています。癇癪や出来ない、イヤという意思表示で投げるならわかるのですが、そうではなく、食事のとき細かくしたハンバーグやウインナーなど、とりあえず一個ずつ全部投げる。拾って戻すと普通に食べたり、また投げたりします。あとは、おもちゃを一回使ったら投げる、拾いに行ってまたやって投げるなどです。リアクションしないようにしていましたが、おもちゃは投げたものが危なかったり、食事は毎回なのでイライラしてきてしまい、投げないで!と言ってしまったりします。言葉もわからないようなので、どういう対処をしたらいいでしょうか?よろしくお願いします。
1歳児の発達の目安やASD(自閉スペクトラム症)の特徴について、次章以降で詳しく紹介します。

1歳児の発達の目安って?
一般的に1歳頃の発達の目安としては、
などがあげられます。
- 歩き始め、手を使い、言葉を話すようになる
- 身近な人や身の回りの物に自発的に働きかけていく
- 歩く、押す、つまむ、めくるなど、さまざまな運動機能の発達や新しい行動の獲得により、環境に働きかける意欲を一層高める
- 物をやり取りしたり、取り合ったりする
- おもちゃ等を実物に見立てるなどの象徴機能が発達し、人や物との関わりが強まる
- 大人の言葉を理解するようになり、自分の意思を親しい大人に伝えたいという欲求が高まる
- 指さし、身振り、片言などを盛んに使うようになり、二語文を話し始める
などがあげられます。
ASD(自閉スペクトラム症)の特性は1歳児でも表れる?--違和感や発達の遅れ、気になるサインやチェックリスト
1歳児は言葉の表出がまだまだ乏しいため、日常の中で気になる行動を見逃さないことが大切です。1歳頃に表れる、気になる発達の遅れやサインとは、どのようなものがあるのでしょうか。
1歳児に表れることの多いASD(自閉スペクトラム症)の特性・特徴
1歳児の気になる発達の遅れ、1歳児に表れやすいASD(自閉スペクトラム症)の特性や特徴として、
などがあげられます。
- 目が合いにくい、呼ばれても反応しない
- 社会性、言葉の発達(喋るのが遅い)などが表れやすい傾向
- 睡眠の問題(寝つきが悪い、途中で目が覚める、夜泣き)
- 人見知りがなさすぎる、あるいは人見知りが強すぎる、場所見知りが強い
などがあげられます。
診断のポイントは?チェックリストの例も
子どもにASD(自閉スペクトラム症)があるかどうかの診断において、厚生労働省は1歳6ヶ月児健診でM-CHATという質問紙を使用した「スクリーニング検査」を推奨しています。対人(対象物)関係や行動面(こだわりや常同行動など)、日常生活における反応や行動を、保護者から聞き取ります。
など、実に20項目にわたり、将来において社会性の重要な基盤となる「非言語の対人コミュニケーション行動」を確認します。
成長は個人差が大きいこともあり、M-CHATでASD(自閉スペクトラム症)の可能性が高いとされた1歳児のすべてがASD(自閉スペクトラム症)と診断されるわけではありません。
また、基本的にM-CHATは保健師などがチェックするものであり、保護者自身がチェックするものではありません。
- ほかの子どもに興味がありますか?
- 何かに興味を持った時、指をさして伝えようとしますか?
- あなたのすることをまねしますか?(バイバイや拍手など)
- 名前を呼ぶと、反応しますか?
など、実に20項目にわたり、将来において社会性の重要な基盤となる「非言語の対人コミュニケーション行動」を確認します。
成長は個人差が大きいこともあり、M-CHATでASD(自閉スペクトラム症)の可能性が高いとされた1歳児のすべてがASD(自閉スペクトラム症)と診断されるわけではありません。
また、基本的にM-CHATは保健師などがチェックするものであり、保護者自身がチェックするものではありません。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています















