「臨機応変」が苦手な知的障害息子、就労移行支援事業所のサポートで起きた3つの変化とは?【18歳の壁/立石美津子 第4回】
ライター:立石美津子
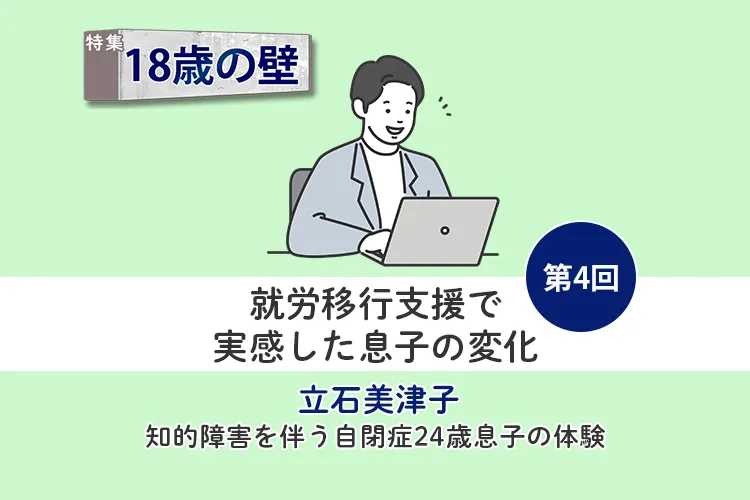
Upload By 立石美津子
就労移行支援は、障害のある方が一般企業への就職を目指すための訓練やサポートを受けることができる福祉サービスです。24歳になる息子は知的障害(知的発達症)を伴うASD(自閉スペクトラム症)、企業で契約社員として働いて4年目になります。
前回は、14か所の就労移行支援事業所を見学し、息子に合った事業所、H事業所を見つけた経緯をお話ししました。今回はH事業所に通ったことで息子に見られた変化についてお話しします【第4回(全6回)】

監修: 渡部伸
行政書士
親なきあと相談室主宰
社会保険労務士
慶應義塾大学法学部卒後、出版社勤務を経て、行政書士、社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能士などの資格を取得。現在、渡部行政書士社労士事務所代表。自身も知的障害の子どもを持ち、知的障害の子どもをもつ親に向けて「親なきあと」相談室を主宰。著作、講演など幅広く活動中。
親なきあと相談室主宰
社会保険労務士
「場面に応じて判断を変える」ことができない息子
息子はその特性から「場面に応じて判断を変える」ことできません。H事業所に通い始めてからも、そのことによる問題を感じ、私は心配になっていました。
帽子のマナー指導から生まれた混乱
H事業所に通い出したある日のことです。通っていた通所施設で、帽子をかぶったまま室内に入った息子は、支援員さんから「マナー違反ですよ。建物の中に入るときは帽子を取りましょう」と注意を受けました。
それからしばらく経った土砂降りの日、事業所へ向かう息子に長靴と履き替え用の靴を持たせ、「事業所に入ったら履き替えてね」と伝えました。ところが息子は、「マナー違反!靴は外で履き替える!コンビニの前で履き替える!」と強く言い張ったのです。以前の「帽子は外で脱ぐ」という指導を、今回の"靴"に応用したようでした。
しかし、彼の言う「外」は道路沿いのコンビニの前。土砂降りの中、道路で靴を履き替える姿に、通行人はきっとぎょっとしたことでしょう。「それはおかしいよ。靴は建物に入ってから履き替えようね」と伝えると、息子は混乱し、ついにはパニックを起こして自傷行為にまで至ってしまいました。
それからしばらく経った土砂降りの日、事業所へ向かう息子に長靴と履き替え用の靴を持たせ、「事業所に入ったら履き替えてね」と伝えました。ところが息子は、「マナー違反!靴は外で履き替える!コンビニの前で履き替える!」と強く言い張ったのです。以前の「帽子は外で脱ぐ」という指導を、今回の"靴"に応用したようでした。
しかし、彼の言う「外」は道路沿いのコンビニの前。土砂降りの中、道路で靴を履き替える姿に、通行人はきっとぎょっとしたことでしょう。「それはおかしいよ。靴は建物に入ってから履き替えようね」と伝えると、息子は混乱し、ついにはパニックを起こして自傷行為にまで至ってしまいました。
ルールを優先したティッシュ事件
さらに、別の日、H事業所へ通うため、いつも通り9時に家を出た息子が、なんと20分後に戻ってきました。電車に乗ったあと、ティッシュペーパーを忘れたことに気づき、わざわざ降りて戻ってきたのです。
事業所への遅刻連絡は9時30分〜10時の間に本人が電話する決まりでした。ティッシュを取りに戻ったせいで、駅に戻ると電話をかけられない時間帯になってしまいます。そこで息子がとった行動は、「さらに遅刻してでも、家に帰って家から電話してから向かう」というものでした。
遅刻そのものよりも、"決められた時間に自分で電話すること"を優先したのです。彼にとって「柔軟な対応」こそが最も難しいことのようでした。
これらのことを親である私が伝えても、息子は頭にきた様子を見せ聞いてくれません。
私は(こんな状態で、息子はH事業所で大丈夫なのか)と常に気になっていました。しかし、息子は事業所であった出来事などを教えてはくれないため、私はやきもきするばかり。
そこで、H事業所へこれらのことを伝え、困っていることを連携したのでした。
事業所への遅刻連絡は9時30分〜10時の間に本人が電話する決まりでした。ティッシュを取りに戻ったせいで、駅に戻ると電話をかけられない時間帯になってしまいます。そこで息子がとった行動は、「さらに遅刻してでも、家に帰って家から電話してから向かう」というものでした。
遅刻そのものよりも、"決められた時間に自分で電話すること"を優先したのです。彼にとって「柔軟な対応」こそが最も難しいことのようでした。
これらのことを親である私が伝えても、息子は頭にきた様子を見せ聞いてくれません。
私は(こんな状態で、息子はH事業所で大丈夫なのか)と常に気になっていました。しかし、息子は事業所であった出来事などを教えてはくれないため、私はやきもきするばかり。
そこで、H事業所へこれらのことを伝え、困っていることを連携したのでした。

息子の特性に合わせた指導が開始
H事業所と連携を始めると、息子の特性に合わせた、まさに「痒いところに手が届く」ようなきめ細やかな指導が始まったのです。
例えば、息子はビジネスマナーとしてどんな暑くてもブレザーを脱がない状態でした、これについて、支援員さんは「上着の脱ぎ着」について、なぜ脱ぐ必要があるのか、脱いだらどうなるのかを息子自身に考えてもらうシートを作成してくれました。
シートには以下の項目があり、それぞれについて息子の意見をヒアリングし書きこんでいただいた跡がありました。
・上着の脱ぎ着について
事業所に来る途中で、汗が出てきたり、頭がぼーっとしてきたり、手すりを握ると手すりがぬれたりしてきました。さぁ、どうしますか?
その他にも、いろいろなシートなどを作っていただき、丁寧に指導してくれたおかげで息子は3年で大きく成長しました。
例えば、息子はビジネスマナーとしてどんな暑くてもブレザーを脱がない状態でした、これについて、支援員さんは「上着の脱ぎ着」について、なぜ脱ぐ必要があるのか、脱いだらどうなるのかを息子自身に考えてもらうシートを作成してくれました。
シートには以下の項目があり、それぞれについて息子の意見をヒアリングし書きこんでいただいた跡がありました。
・上着の脱ぎ着について
事業所に来る途中で、汗が出てきたり、頭がぼーっとしてきたり、手すりを握ると手すりがぬれたりしてきました。さぁ、どうしますか?
- 1、上着を脱がない理由は何ですか?
- 2、上着を脱ぎましょうと言われるとどんな気持ちがしますか?
- 3、なぜ、職員やお母さんは、上着を脱ぐように言ってくるのでしょうか?
- 4、上着を脱いだら、職員やお母さんは、何と言うと思いますか?
- 5、寒かったら着る、汗が出てきたら脱ぐ、ということができたら職員やお母さん、企業の棚や机がない所で、リュックをどのようにしたら上着を脱いだり着たりできるでしょうか?
その他にも、いろいろなシートなどを作っていただき、丁寧に指導してくれたおかげで息子は3年で大きく成長しました。
就労移行支援事業所がもたらした3つの大きな変化
H事業所に通い始めたことで、息子は成長しました。
H事業所で作成してもらった「よく使うセリフの表」を活用することで、ビジネス面のコミュニケーションも取れるようになってきました。
- 変化その1:コミュニケーション面の成長
H事業所で作成してもらった「よく使うセリフの表」を活用することで、ビジネス面のコミュニケーションも取れるようになってきました。
- 変化その2:作業スキルの習得
H事業所は、多岐にわたる職業訓練が行われていました。息子は「作業のお手本」をじっくり見て学ぶことで、着実に作業スキルを向上させていったようです。
特にパソコン訓練をやっていたため、タイピングのスピードアップやテンキータイピングとを頑張ったようです。
- 変化その3:3年間頑張った自信
息子は、H事業所卒業の際に3年間についてまとめたスライドを作りました。
そのスライドでは、事業所で楽しかったこととして「土曜開所」や「コミュニケーション活動」が挙げられていました。コミュニケーションを楽しめるようになったのは、親として本当に感慨深いものがありました。一方大変だったことは「話しかけられた時」「相手への報告」「作業の確認」。大変だったと就職前に実際に経験できたことは大きいと思います。
さらに、「就職してから頑張りたいこと」として「スキャニング」「返事」「質問」といった具体的な目標を掲げていたのにも成長を感じました。
さらに、「就職してから頑張りたいこと」として「スキャニング」「返事」「質問」といった具体的な目標を掲げていたのにも成長を感じました。

















