就労移行支援で乗り越えた「18歳の壁」。就職後の支援は?継続勤労者表彰を受けた息子の今【18歳の壁/立石美津子 第6回】
ライター:立石美津子
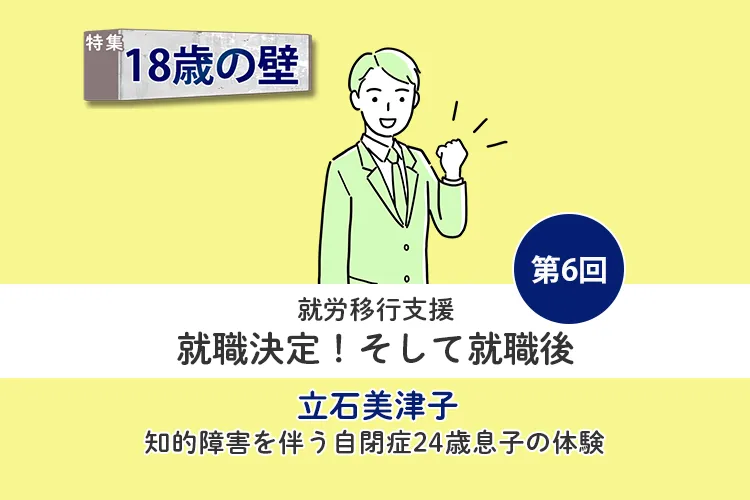
Upload By 立石美津子
これまでお届けしてきた「18歳の壁」シリーズも、最終回となります。今回は、就職までの道のりと、働き始めてからの息子の成長、そして親としての想いをお伝えします。【最終回(全6回)】

監修: 渡部伸
行政書士
親なきあと相談室主宰
社会保険労務士
慶應義塾大学法学部卒後、出版社勤務を経て、行政書士、社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能士などの資格を取得。現在、渡部行政書士社労士事務所代表。自身も知的障害の子どもを持ち、知的障害の子どもをもつ親に向けて「親なきあと」相談室を主宰。著作、講演など幅広く活動中。
親なきあと相談室主宰
社会保険労務士
就職までの崖っぷちの道のり
就労継続支援事業所を利用している時にコロナ禍となった影響もあり、息子は特例として3年間利用しました。就労継続支援事業所の本来の利用期間は2年間なので、1年の猶予があった形です。
息子には「ここに入りたい」という企業が1社だけありました。3年目に入り、念願の企業での実習が叶いましたが、結果は無情にも「受け入れ不可」評価。刻一刻と3月31日の利用期間終了が迫り、「4月1日から行き先がなくなるかもしれない」という現実に、親子共々追い込まれていきました。
年が明けた1月、再度同じ企業で実習の機会をいただきました。事業所で2ヶ月間努力を重ねた成果が認められ、評価は「△」に上がったものの、採用には至りません。そして、いよいよ最後の望みを託す3週間の「最終実習」が3月に組まれました。
もし、ここで不採用となれば、息子は本当に社会から孤立してしまうのかもしれない……。その恐怖から、私は必死で「保険」をかけることにしました。区の障害福祉課のケースワーカーさんや相談支援事業所の担当者さんと連携し、万が一の場合に備えてB型作業所の実習を企業実習と並行して進めることにしたのです。
もちろん、B型作業所も簡単に入れるわけではありません。特別支援学校の新卒者が優先される上、新卒者の受け入れ先はすでに決定している状況。3月末に申し込みして4月から入所するというのは極めて困難な状況でした。それでもダメ元で近所の事業所にお願いし、事情を正直にお話ししました。
「もし企業に採用されたら、こちらにお世話になることはできません。保険をかけるような形で申し訳ありません」
そう伝えた私に、施設長さんは「そういう方はたくさんいますよ。空きもあるので大丈夫です」と温かい言葉をかけてくださり、どれほど救われたか分かりません。この一言で、私たちは安心して最後の挑戦に臨むことができました。
そして迎えた、運命の最終実習。
結果は、「採用決定」でした。
契約社員という形ではありますが、息子は自らの力で社会への扉をこじ開けたのです。
息子には「ここに入りたい」という企業が1社だけありました。3年目に入り、念願の企業での実習が叶いましたが、結果は無情にも「受け入れ不可」評価。刻一刻と3月31日の利用期間終了が迫り、「4月1日から行き先がなくなるかもしれない」という現実に、親子共々追い込まれていきました。
年が明けた1月、再度同じ企業で実習の機会をいただきました。事業所で2ヶ月間努力を重ねた成果が認められ、評価は「△」に上がったものの、採用には至りません。そして、いよいよ最後の望みを託す3週間の「最終実習」が3月に組まれました。
もし、ここで不採用となれば、息子は本当に社会から孤立してしまうのかもしれない……。その恐怖から、私は必死で「保険」をかけることにしました。区の障害福祉課のケースワーカーさんや相談支援事業所の担当者さんと連携し、万が一の場合に備えてB型作業所の実習を企業実習と並行して進めることにしたのです。
もちろん、B型作業所も簡単に入れるわけではありません。特別支援学校の新卒者が優先される上、新卒者の受け入れ先はすでに決定している状況。3月末に申し込みして4月から入所するというのは極めて困難な状況でした。それでもダメ元で近所の事業所にお願いし、事情を正直にお話ししました。
「もし企業に採用されたら、こちらにお世話になることはできません。保険をかけるような形で申し訳ありません」
そう伝えた私に、施設長さんは「そういう方はたくさんいますよ。空きもあるので大丈夫です」と温かい言葉をかけてくださり、どれほど救われたか分かりません。この一言で、私たちは安心して最後の挑戦に臨むことができました。
そして迎えた、運命の最終実習。
結果は、「採用決定」でした。
契約社員という形ではありますが、息子は自らの力で社会への扉をこじ開けたのです。

社会人としての第一歩と、親の「丸投げ」という覚悟
就職後の息子の勤務は、月曜から金曜の10時から16時。障害基礎年金も受給していたため、収入面では新卒の正社員と同じくらいの額を得ることができました(年金は収入とは言えませんが、生活を支える大きな助けになりました)。
息子の社会人生活を支えるため、私たちは「就労定着支援制度」を利用しました。月に一度、卒業した就労移行支援事業所の担当者が会社を訪問し、その様子は会社、事業所、相談支援員の三者で共有され、書面で私の手元にも届きます。
しかし、私は会社に同行することも、仕事の様子を見学することもしませんでした。
息子も25歳。親がいつまでも前に出るのは過保護だと感じ、「とにかく専門家の方々に丸投げしよう」と心を決めました。
トラブルが起きたとしても、プロフェッショナルにお任せする。それが、息子の自立のために親ができる最善のサポートだと考えたのです。
この就労定着支援も3年6ヶ月で一区切りとなりますが、その後は「障害者就業・生活支援センター」へと支援が引き継がれます。
何かあればいつでも相談できる場所がある。障害のある人にとって、こうした「切れ目のない支援」がいかに重要か、改めて実感しています。
息子の社会人生活を支えるため、私たちは「就労定着支援制度」を利用しました。月に一度、卒業した就労移行支援事業所の担当者が会社を訪問し、その様子は会社、事業所、相談支援員の三者で共有され、書面で私の手元にも届きます。
しかし、私は会社に同行することも、仕事の様子を見学することもしませんでした。
息子も25歳。親がいつまでも前に出るのは過保護だと感じ、「とにかく専門家の方々に丸投げしよう」と心を決めました。
トラブルが起きたとしても、プロフェッショナルにお任せする。それが、息子の自立のために親ができる最善のサポートだと考えたのです。
この就労定着支援も3年6ヶ月で一区切りとなりますが、その後は「障害者就業・生活支援センター」へと支援が引き継がれます。
何かあればいつでも相談できる場所がある。障害のある人にとって、こうした「切れ目のない支援」がいかに重要か、改めて実感しています。
【制度のご紹介】「就労定着支援制度」と「障害者就業・生活支援センター」とは?
- 就労定着支援制度
就労移行支援などを利用して一般就労した障害のある方が、就労に伴って生じる生活面の課題に対し、長く働き続けられるように支援する障害福祉サービスです。
就職後6ヶ月を経過した時点から利用でき、1年ごとに利用を更新しながら最長3年間、支援が受けられます。支援員が月に1回以上、本人との面談や職場訪問を行い、生活リズムや体調管理に関する助言、また会社や医療機関など関係機関との連絡調整を行います。
- 障害者就業・生活支援センター
障害のある方の身近な地域にあって、就業面と生活面における一体的な相談・支援を行う機関です。全国に設置されており、「なかぽつ」や「しゅうぽつ」とも呼ばれています。
●就業支援: 就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん)、就職活動の支援、職場定着に向けた支援のほか、事業主に対して障害特性を踏まえた雇用管理に関する助言などを行います。
●生活支援: 健康管理、金銭管理といった日常生活に関する自己管理への助言や、住居や年金など地域生活に関する相談に応じます。
ハローワークや福祉事務所、医療機関などさまざまな関係機関と連携しており、就労定着支援の利用期間が終了した後の継続的な相談先としての役割も担っています。
3年間継続勤労者の表彰イベントで見た息子の成長
先日、息子が卒業した就労移行支援事業所から、「3年間継続勤労者の表彰イベント」のご案内をいただきました。
イベント後の交流会では、息子の大きな成長を目の当たりにしました。
後輩にあたる現在の訓練生たちとのグループワークでは、終始笑顔で、とても楽しそうに参加していました。それだけでなく、自ら進んで意見を述べ、議論をリードする姿に、私はただただ感心するばかりでした。
訓練生から「職場で気をつけていることは?」と質問された息子は、こう答えていました。
「気になったときに(意図せず)笑ってしまわないように、深呼吸をしています」
自分の特性を理解し、具体的な対処法を身につけ、それを自分の言葉で後輩に伝えられる。慌てて就職を目指すのではなく、3年間じっくりと自分と向き合い、訓練を積んだからこそ辿り着けたのだと思いました。
このイベントでは、うれしい光景ばかりではありませんでした。そこには企業に就職したものの、うまくいかず再び事業所に戻り、訓練生として通っている仲間の姿もありました(2年間の通所期間は分けて利用することもできます)。
数ヶ月の通所を経てスピーディに就労したとしても、十分な訓練ができていなかったり自分に合わない職場だった場合は、就労を継続することは難しく、離職につながることもあるのでしょう……。
イベント後の交流会では、息子の大きな成長を目の当たりにしました。
後輩にあたる現在の訓練生たちとのグループワークでは、終始笑顔で、とても楽しそうに参加していました。それだけでなく、自ら進んで意見を述べ、議論をリードする姿に、私はただただ感心するばかりでした。
訓練生から「職場で気をつけていることは?」と質問された息子は、こう答えていました。
「気になったときに(意図せず)笑ってしまわないように、深呼吸をしています」
自分の特性を理解し、具体的な対処法を身につけ、それを自分の言葉で後輩に伝えられる。慌てて就職を目指すのではなく、3年間じっくりと自分と向き合い、訓練を積んだからこそ辿り着けたのだと思いました。
このイベントでは、うれしい光景ばかりではありませんでした。そこには企業に就職したものの、うまくいかず再び事業所に戻り、訓練生として通っている仲間の姿もありました(2年間の通所期間は分けて利用することもできます)。
数ヶ月の通所を経てスピーディに就労したとしても、十分な訓練ができていなかったり自分に合わない職場だった場合は、就労を継続することは難しく、離職につながることもあるのでしょう……。















