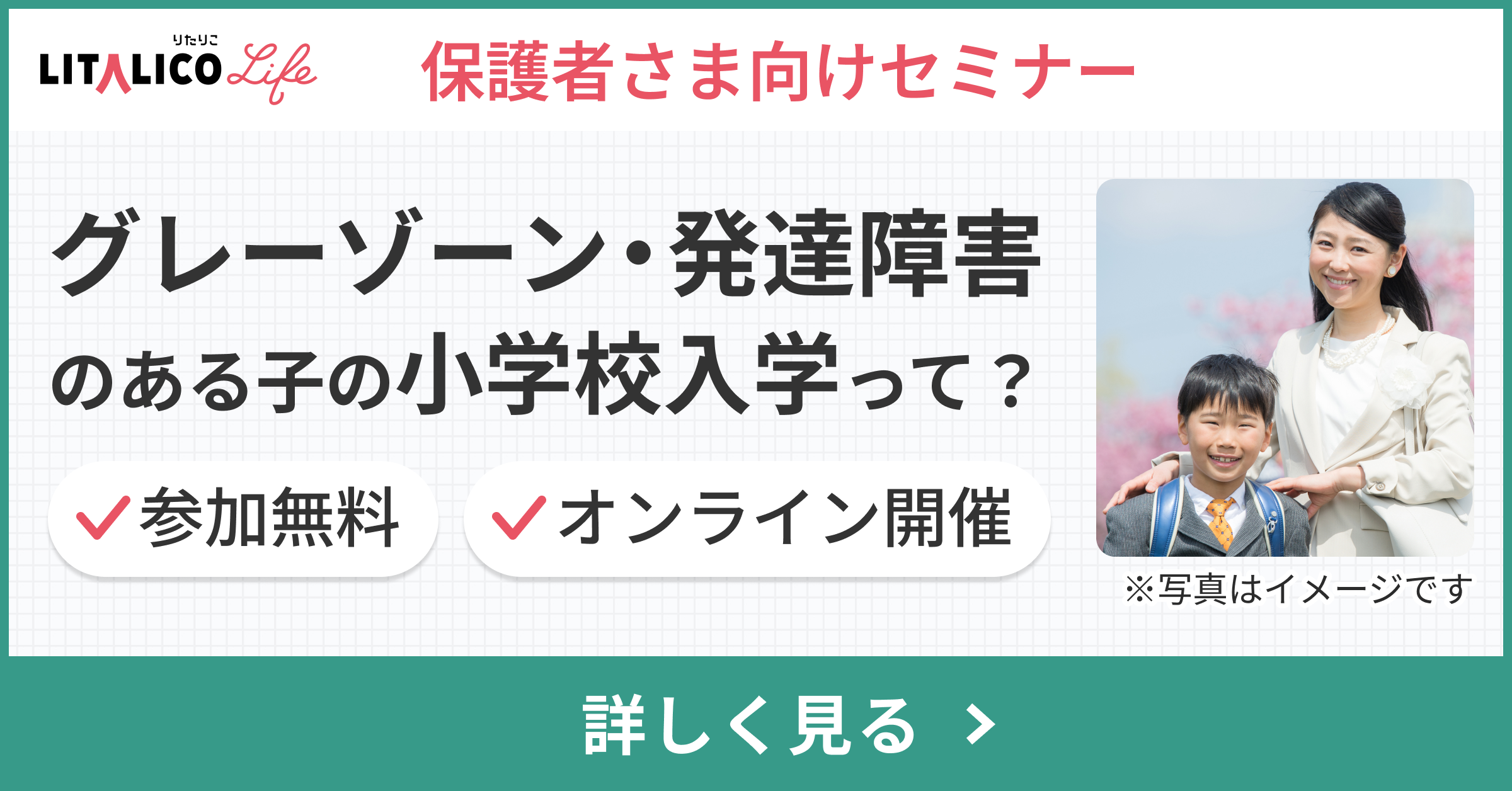切り替えベタな子どもにピッタリ!お家で出来るタイマー活用術
ライター:楽々かあさん
気持ちの切り替えの苦手な子、夢中になると周りに気づきにくい子、時間感覚の弱い子なども、視覚的に時間が分かる楽しいタイマーやアラームを活用して、親の段階的な声かけなどを併用すれば、「始めること」「やめること」が、ぐんと取り組みやすくなります。我が家の工夫を紹介します!
なかなか時間通りに動けない子どもたち
我が家には、夢中になるとなかなか「やめられない」長男、ゆっくりマイペースでなかなか「始められない」次男、時計がまだ「読めない」幼稚園の長女がいます。
そうすると、時間通りに動くには工夫が必要。今日は、そんな我が家の工夫をご紹介します。
そうすると、時間通りに動くには工夫が必要。今日は、そんな我が家の工夫をご紹介します。
時間が見えれば分かりやすい!
時間という目に見えないもの。
その時間の経過が「見える」ように工夫されているタイマーや時計があります。視覚情報を受け取りやすい子や、時間感覚の弱い子にはとってもおススメです。
市販の「タイムタイマー」や、スマホのタイマーアプリは色のついたゲージが減ることで、残り時間がわかるような工夫がされています。
その時間の経過が「見える」ように工夫されているタイマーや時計があります。視覚情報を受け取りやすい子や、時間感覚の弱い子にはとってもおススメです。
市販の「タイムタイマー」や、スマホのタイマーアプリは色のついたゲージが減ることで、残り時間がわかるような工夫がされています。
タイムタイマー(TIME TIMER) 勉強タイマー 5分 プラス ハンドル付き 学習アラーム TT05-W
Amazonで詳しく見る
それからアナログな「砂時計」や「オイル時計」など良いですよね。見ていて楽しい、視覚的なタイマーになります。
時計の針が目印になる
また、壁掛け時計に工夫をして、手動の紙時計や電池を抜いた学習時計などを組み合わせるのもおススメです。開始と終了の目標時刻を見せることができます。
「時計の針がこの形になったら、始めようね」という声かけをすれば、時計のまだ読めない子でも大丈夫です。
「時計の針がこの形になったら、始めようね」という声かけをすれば、時計のまだ読めない子でも大丈夫です。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています