ハーネスが使えない時、外出時の安全確保に役立つテクニックとは?
ライター:松本太一

Upload By 松本太一
外出時にお子さんの安全を確保する上で、手つなぎやハーネスは大切です。しかしお子さんがこうした方法を嫌がることもあります。その場合に役立つ「目線のコントロール」というテクニックを解説します。
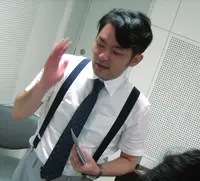
執筆: 松本太一
アナログゲーム療育アドバイザー
放課後等デイサービスコンサルタント
NPO法人グッド・トイ委員会認定おもちゃインストラクター
東京学芸大学大学院障害児教育専攻卒業(教育学修士)
フリーランスの療育アドバイザー。カードゲームやボードゲームを用いて、発達障害のある子のコミュニケーション力を伸ばす「アナログゲーム療育」を開発。各地の療育機関や支援団体で、実践・研修を行っている。
放課後等デイサービスコンサルタント
NPO法人グッド・トイ委員会認定おもちゃインストラクター
東京学芸大学大学院障害児教育専攻卒業(教育学修士)
手つなぎやハーネスが使えないときは・・・?
アナログゲーム療育アドバイザーの松本太一です。
発達障害の中でもADHDのあるお子さんは、衝動性と不注意の問題から、道路への飛び出しなど危険な行動をとる場合があります。
そこで、外を歩くときはお子さんと手をつないだり、下記の記事で紹介されているハーネスを用いたりして安全を確保することが大切です。
発達障害の中でもADHDのあるお子さんは、衝動性と不注意の問題から、道路への飛び出しなど危険な行動をとる場合があります。
そこで、外を歩くときはお子さんと手をつないだり、下記の記事で紹介されているハーネスを用いたりして安全を確保することが大切です。

賛否両論!?そのアイテムはわが子にとって「命綱」でした
しかし、小学生以上になると、恥ずかしがって親と手をつなぐことを拒否されてしまったり、ハーネスは体重制限を越えて着用できなかったりする等の理由で、こうした安全確保の手段が取れないことが少なくありません
かといって、外出時の危険がなくなるわけではなく、悩ましいところです。
幼児期のように一瞬でも目を離した隙にいなくなってしまうことは少なくなってきますが、代わりに大人が予期できない動きをすることが増えます。
たとえば、道路を渡ろうとして赤信号を待っている時、信号が青になった瞬間に周囲を確認せずパッと走りだし、強引に通過しようとスピードをあげてきた車にひかれそうになる、といったことがあります。
かといって、外出時の危険がなくなるわけではなく、悩ましいところです。
幼児期のように一瞬でも目を離した隙にいなくなってしまうことは少なくなってきますが、代わりに大人が予期できない動きをすることが増えます。
たとえば、道路を渡ろうとして赤信号を待っている時、信号が青になった瞬間に周囲を確認せずパッと走りだし、強引に通過しようとスピードをあげてきた車にひかれそうになる、といったことがあります。
「目線のコントロールで安全を確保する」
一定以上の年齢で手つなぎやハーネスの使用に抵抗があるお子さんに対して、
外出時の安全確保のために私が用いるのが「視線のコントロール」というテクニックです。
飛び出しの危険があるお子さんは、自分が目指す方向だけに注目しており、左右後方に注意を払っていないことがほとんどです。
そこで、信号待ちの場面などでは、お子さんと同じ目線に立ち、やってくる車や自転車を指差して注目を促します。
指差しだけで注目が難しい時は、お子さんの肩を優しく持ち、車がやってくる方向に向けてあげましょう。
お子さんがやってくる車に注目さえできれば、不注意で飛び出してに車にはねられる危険はほとんどないと言えます
外出時の安全確保のために私が用いるのが「視線のコントロール」というテクニックです。
飛び出しの危険があるお子さんは、自分が目指す方向だけに注目しており、左右後方に注意を払っていないことがほとんどです。
そこで、信号待ちの場面などでは、お子さんと同じ目線に立ち、やってくる車や自転車を指差して注目を促します。
指差しだけで注目が難しい時は、お子さんの肩を優しく持ち、車がやってくる方向に向けてあげましょう。
お子さんがやってくる車に注目さえできれば、不注意で飛び出してに車にはねられる危険はほとんどないと言えます

指差しに加え、お子さんの肩を抱いて危険の来る方向に体を向けてあげる
常に「肩を抱ける位置」に立つ
こうした「目線のコントロール」ができるためには、大人の立ち位置が重要です。
私は発達障害のあるお子さんと外出する場合、「お子さんの肩が抱ける位置」に常に立つ事を心がけています。
この位置に立つことで、肩をすぐに抱くことができ、車や自転車などの方向に身体を向けてあげることで、注目を促せます。
また、この位置なら急にお子さんが走りだそうとした時、手を前に出すことでお子さんを制止することもできます。
私は発達障害のあるお子さんと外出する場合、「お子さんの肩が抱ける位置」に常に立つ事を心がけています。
この位置に立つことで、肩をすぐに抱くことができ、車や自転車などの方向に身体を向けてあげることで、注目を促せます。
また、この位置なら急にお子さんが走りだそうとした時、手を前に出すことでお子さんを制止することもできます。

こちらはNG。大人がお子さんの後につく形になっており、危険が迫っても制止できない

















