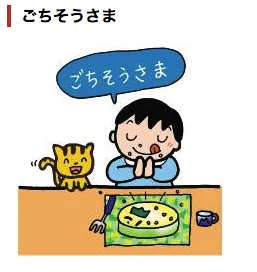
こんにちは。
児童発達支援事業所STELLA KID(ステラキッド )鶴ヶ峰教室です。
今回はSST(ソーシャルスキルトレーニング)についてお話をしたいと思います。
ソーシャルスキル(社会?技術?)などと聞くと「職業訓練」のような印象を持たれ「うちの子には早い」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、実は幼児期にもソーシャルスキルは大切で、早い時期から訓練を必要とするものなのです。
ーSST(ソーシャルスキルトレーニング)とはー
SST(ソーシャルスキルトレーニング)とは、
『社会で暮らしていくために必要なマナーやコミュニケーションの取り方、日常生活において必要な生活習慣など人が社会の中で生きていくために必要な技術の獲得を目指す訓練のこと』をいいます。
例えば、
・人と出会った時にかわす挨拶(おはようございます・こんにちはなど)
・人との適切な距離感(身内とそうでない人との距離の違いなど)
・感謝や謝罪の方法(ありがとう・すみません・ごめんなさい・お辞儀をする)
・お願いをしたり断ったりする方法(おねがいします・すみません〜でできません)
・場面に適した声の大きさを調整すること(公共の場では小さな声でなど)
・身だしなみ(服装・髪型など)
・体を清潔に保つこと(入浴・手洗い・うがいなど)
など、その内容は実に多様です。
こうした多様なソーシャルスキルをその方の年齢やとりまく環境、
または苦手としている技術に合わせてトレーニングを行なっていくことがSSTとなります。
ーSSTの対象は?ー
社会で生きていくために必要な技術はとりまく環境で変化していくため、あらゆる年齢の方が対象となります。
幼稚園児には幼稚園児の、小学生には小学生の、社会人には社会人のソーシャルスキルが存在するのです。
ただし、社会人がそれまでの必要なあいさつやみだしなみなどのソーシャルスキルを身につけないまま、「飲み会の断り方」だけを身につけるということも現実的ではありませんよね。
そこにはやはり獲得すべき基礎となるソーシャルスキルが存在し、段階を踏んで習得していく必要があります。
ここではその基礎ともいうべき幼児期のSSTについて簡単に触れてみたいとおもいます。
ー幼児期のSSTー
上野一彦・岡田智 編著の『ソーシャルスキル マニュアル』によると、ソーシャルスキルの指導方法には
・「教示」:言葉や絵カードを見せて覚える
・「モデリング」:手本を見て学ぶ
・「リハーサル」:実践してみる
・「フィードバック」:振り返る
・「般化」:どんな場面や状況でも使えるようになる
といった方法が挙げられており,それらの方法を組み合わせたり反復練習をすることが効果的であると述べています。
では具体的にどのような訓練があるのでしょうか?
【具体的なSST】
絵カード/ワークなどの教材(教示)
絵カードやイラストを用いることでSSTのイメージの具体化を促します。
(例)
「いただきます」の絵カードを見る(教示)+先生がお手本を見せる(モデリング)
+自宅で取り組んでみる(リハーサル)
などの練習を反復することでスキルの獲得を促すことができます。
ごっこ遊び
ごっこ遊びは日常生活で目にしている大人の仕草や好きなテレビ番組のキャラクターを模倣する遊びですが、それらを見ている日常生活の中に「モデリング」の要素が含まれ、遊びの中で実践する(=「リハーサル」)ことによって、遊びを通しながらスキルを獲得していきます。
小さなお子さん同士でもできますし、先生など大人が混じることでさらなるモデルを示すこともできます。
ゲーム
「遊び」が幼児期のお子さんにとって社会性を培うために大切であるということを当教室ブログにてお話しさせていただきました。
ゲーム性の高い遊びが増えてくると、ルールやペナルティなど社会のあり方がそのまま縮小化した世界を楽しみながら学べるようになります。
また、仲良く遊ぶことで団結力、時には意見が噛み合わずに喧嘩になることで自分の意見を主張する力、相手の意見を聞く力、お互いの意見を調整する力なども培われます。
大人と一緒にいろいろな人に出会う/いろいろな場所にいく
いろいろな人に出会ったり、いろいろな場所にいく経験を積むことは、特に大きな効果が期待されます。
(例)
大人と一緒に誰かと出会う
→大人が交わす挨拶のことばや仕草を見聞きする(モデリング)
→その場で模倣したり、別の場面で再現する(リハーサル・般化)
(例)
色々な場所に行く
→公共の場での声量やマナーを見聞きする(モデリング)
→その場その場に見合った声量やマナーを実践する(リハーサル・般化) など
いかがだったでしょうか。
SSTは人(=社会)と関わる上で大切なスキルの獲得であり、生まれた瞬間から始まっていると言っても過言ではありません。
また、特に乳幼児期の小さいお子さんは
生活=遊び=学び
であるため、いたるところにSSTのきっかけが点在しています。
私たち大人は、そのお子さんに見合ったソーシャルスキルは何かを考え、学びのチャンスを発見あるいは用意してあげることで、お子さんの発達を支えていく姿勢が大切になってきます。
また、学びのあとには「褒める」を忘れないようにすることも大切です。
**********************************************************************
当教室では
・じっとしていられない
・こだわりが強い
・感情の調整が難しい
・人の気持ちを読むことが難しい
・お友達とのトラブルが多い
・言葉の遅れを感じる
・抽象的な表現が苦手
・発達に心配がある
・不器用
・視線が合わない
・幼稚園、保育園、小学校への就学が不安だ
などの保護者の方々・お子さんの困り感をサポートいたします。
※自治体の助成により無料もしくは低額にて療育が受けられます。
まずは市役所/相談支援事業所/当事業所にご相談ください。
※児童発達支援事業は、放課後等デイサービス(放デイ)と同じく障害児通所支援事業に属する療育施設であり、「児発」などの略称で呼ばれる場合もあります。
児童発達支援事業所 STELLA KID 鶴ヶ峰教室のホームページはこちら
→https://www.stellakid.com
一般社団法人KID-Gのホームページはこちら
→http://www.kid-g.com/
住所:横浜市旭区白根5−10−1 AOKIYA BLD 1階
関連ワード:児童発達支援・放課後等デイサービス・療育・療育センター・通級教室・特別支援教育総合支援センター・小学校が不安・勉強が苦手・運動神経が悪い・保育園・幼稚園・障害・発達障害・自閉症スペクトラム・ASD・注意欠陥多動性障害・ADHD・学習障害・LD・知的障害・グレーゾーン・視線が合わない・先の見通しがないと不安・視覚優位・聴覚優位・感覚過敏・距離が近い・いきしぶり・気持ちが読めない・表情が読めない・空気が読めない・不器用・体幹が弱い・筆圧が弱い・言葉のキャチボール・マイペース・好きなことだけ話す・語彙が少ない・言葉の遅れ・勝ち負けにこだわる・一番じゃないとだめ・癇癪・感情の調整・クールダウン・アンガーマネジメント・こだわり・友達ができない・チック・おねしょ・偏食・暴力・手が出る・おちつきがない・座っていられない・話を聞けない・忘れ物が多い・儀式的な行動・声の大きさ・個別支援級・特別支援級・自傷
児童発達支援事業所STELLA KID(ステラキッド )鶴ヶ峰教室です。
今回はSST(ソーシャルスキルトレーニング)についてお話をしたいと思います。
ソーシャルスキル(社会?技術?)などと聞くと「職業訓練」のような印象を持たれ「うちの子には早い」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、実は幼児期にもソーシャルスキルは大切で、早い時期から訓練を必要とするものなのです。
ーSST(ソーシャルスキルトレーニング)とはー
SST(ソーシャルスキルトレーニング)とは、
『社会で暮らしていくために必要なマナーやコミュニケーションの取り方、日常生活において必要な生活習慣など人が社会の中で生きていくために必要な技術の獲得を目指す訓練のこと』をいいます。
例えば、
・人と出会った時にかわす挨拶(おはようございます・こんにちはなど)
・人との適切な距離感(身内とそうでない人との距離の違いなど)
・感謝や謝罪の方法(ありがとう・すみません・ごめんなさい・お辞儀をする)
・お願いをしたり断ったりする方法(おねがいします・すみません〜でできません)
・場面に適した声の大きさを調整すること(公共の場では小さな声でなど)
・身だしなみ(服装・髪型など)
・体を清潔に保つこと(入浴・手洗い・うがいなど)
など、その内容は実に多様です。
こうした多様なソーシャルスキルをその方の年齢やとりまく環境、
または苦手としている技術に合わせてトレーニングを行なっていくことがSSTとなります。
ーSSTの対象は?ー
社会で生きていくために必要な技術はとりまく環境で変化していくため、あらゆる年齢の方が対象となります。
幼稚園児には幼稚園児の、小学生には小学生の、社会人には社会人のソーシャルスキルが存在するのです。
ただし、社会人がそれまでの必要なあいさつやみだしなみなどのソーシャルスキルを身につけないまま、「飲み会の断り方」だけを身につけるということも現実的ではありませんよね。
そこにはやはり獲得すべき基礎となるソーシャルスキルが存在し、段階を踏んで習得していく必要があります。
ここではその基礎ともいうべき幼児期のSSTについて簡単に触れてみたいとおもいます。
ー幼児期のSSTー
上野一彦・岡田智 編著の『ソーシャルスキル マニュアル』によると、ソーシャルスキルの指導方法には
・「教示」:言葉や絵カードを見せて覚える
・「モデリング」:手本を見て学ぶ
・「リハーサル」:実践してみる
・「フィードバック」:振り返る
・「般化」:どんな場面や状況でも使えるようになる
といった方法が挙げられており,それらの方法を組み合わせたり反復練習をすることが効果的であると述べています。
では具体的にどのような訓練があるのでしょうか?
【具体的なSST】
絵カード/ワークなどの教材(教示)
絵カードやイラストを用いることでSSTのイメージの具体化を促します。
(例)
「いただきます」の絵カードを見る(教示)+先生がお手本を見せる(モデリング)
+自宅で取り組んでみる(リハーサル)
などの練習を反復することでスキルの獲得を促すことができます。
ごっこ遊び
ごっこ遊びは日常生活で目にしている大人の仕草や好きなテレビ番組のキャラクターを模倣する遊びですが、それらを見ている日常生活の中に「モデリング」の要素が含まれ、遊びの中で実践する(=「リハーサル」)ことによって、遊びを通しながらスキルを獲得していきます。
小さなお子さん同士でもできますし、先生など大人が混じることでさらなるモデルを示すこともできます。
ゲーム
「遊び」が幼児期のお子さんにとって社会性を培うために大切であるということを当教室ブログにてお話しさせていただきました。
ゲーム性の高い遊びが増えてくると、ルールやペナルティなど社会のあり方がそのまま縮小化した世界を楽しみながら学べるようになります。
また、仲良く遊ぶことで団結力、時には意見が噛み合わずに喧嘩になることで自分の意見を主張する力、相手の意見を聞く力、お互いの意見を調整する力なども培われます。
大人と一緒にいろいろな人に出会う/いろいろな場所にいく
いろいろな人に出会ったり、いろいろな場所にいく経験を積むことは、特に大きな効果が期待されます。
(例)
大人と一緒に誰かと出会う
→大人が交わす挨拶のことばや仕草を見聞きする(モデリング)
→その場で模倣したり、別の場面で再現する(リハーサル・般化)
(例)
色々な場所に行く
→公共の場での声量やマナーを見聞きする(モデリング)
→その場その場に見合った声量やマナーを実践する(リハーサル・般化) など
いかがだったでしょうか。
SSTは人(=社会)と関わる上で大切なスキルの獲得であり、生まれた瞬間から始まっていると言っても過言ではありません。
また、特に乳幼児期の小さいお子さんは
生活=遊び=学び
であるため、いたるところにSSTのきっかけが点在しています。
私たち大人は、そのお子さんに見合ったソーシャルスキルは何かを考え、学びのチャンスを発見あるいは用意してあげることで、お子さんの発達を支えていく姿勢が大切になってきます。
また、学びのあとには「褒める」を忘れないようにすることも大切です。
**********************************************************************
当教室では
・じっとしていられない
・こだわりが強い
・感情の調整が難しい
・人の気持ちを読むことが難しい
・お友達とのトラブルが多い
・言葉の遅れを感じる
・抽象的な表現が苦手
・発達に心配がある
・不器用
・視線が合わない
・幼稚園、保育園、小学校への就学が不安だ
などの保護者の方々・お子さんの困り感をサポートいたします。
※自治体の助成により無料もしくは低額にて療育が受けられます。
まずは市役所/相談支援事業所/当事業所にご相談ください。
※児童発達支援事業は、放課後等デイサービス(放デイ)と同じく障害児通所支援事業に属する療育施設であり、「児発」などの略称で呼ばれる場合もあります。
児童発達支援事業所 STELLA KID 鶴ヶ峰教室のホームページはこちら
→https://www.stellakid.com
一般社団法人KID-Gのホームページはこちら
→http://www.kid-g.com/
住所:横浜市旭区白根5−10−1 AOKIYA BLD 1階
関連ワード:児童発達支援・放課後等デイサービス・療育・療育センター・通級教室・特別支援教育総合支援センター・小学校が不安・勉強が苦手・運動神経が悪い・保育園・幼稚園・障害・発達障害・自閉症スペクトラム・ASD・注意欠陥多動性障害・ADHD・学習障害・LD・知的障害・グレーゾーン・視線が合わない・先の見通しがないと不安・視覚優位・聴覚優位・感覚過敏・距離が近い・いきしぶり・気持ちが読めない・表情が読めない・空気が読めない・不器用・体幹が弱い・筆圧が弱い・言葉のキャチボール・マイペース・好きなことだけ話す・語彙が少ない・言葉の遅れ・勝ち負けにこだわる・一番じゃないとだめ・癇癪・感情の調整・クールダウン・アンガーマネジメント・こだわり・友達ができない・チック・おねしょ・偏食・暴力・手が出る・おちつきがない・座っていられない・話を聞けない・忘れ物が多い・儀式的な行動・声の大きさ・個別支援級・特別支援級・自傷

