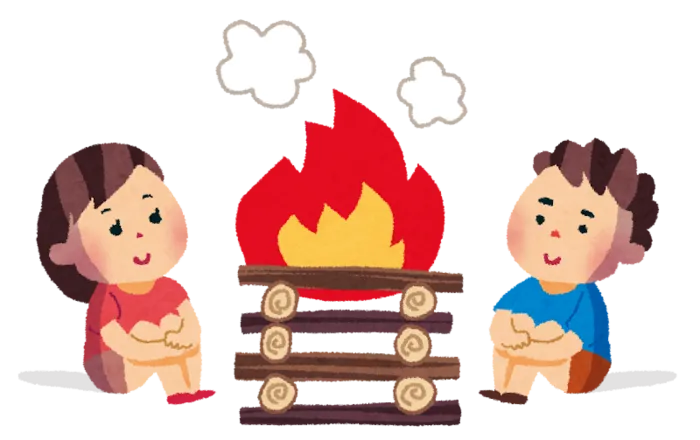
こんにちは!保育士のたくまです。突然ですが、皆さんは「オープンダイアローグ」という言葉をご存じでしょうか?
「なんだか難しそう」「カウンセリング?心理療法?」そんな声が聞こえてきそうですが、実はこの手法、支援の現場でもとても有効に使える「対話の魔法」なのです。
今回は、「オープンダイアローグ」を、日々の子どもたちへの支援や保護者さま対応にどう活かせるのか?そのエッセンスと具体例をお届けします!
そもそもオープンダイアローグとは、フィンランドで生まれた精神的な困りごとを抱える人たちの支援に使われてきた手法のこと。特徴はとにかく「対話」です。
すぐに答えを出そうとしない、その場にいる全員の声を「対等に」聞く、対話を重ねながら、自然と「変化」が起こるのを待つ、といった、まるで「会話のキャンプファイヤー」のように、みんなで輪になって、ゆっくり温めるような支援になります。
これらを踏まえて、ユリシスの現場で実際に起こった例をもとに、子どもの支援にどう使うの?といったところを考えてみましょう。
ある日、Aくんが突然、遊んでいる最中に友だち(Cくん)のブロックを壊してしまいました。職員のBさんは「あれ、何があったんだろう」と思いながら、本人を叱るのではなく、こんなふうに声をかけました。
Bさん:「Aくん、何かあってびっくりしたのかな。教えてくれる?」
Aくん:「Cくんに名前をからかわれて、すごく嫌だったの」
その場にいたAくん、そしてCくんも加わり、責めずに「Aくんがどう感じたか」「Cくんはなぜそう言ったのか」「2人がどうしたら安心できるか」を、ゆっくり話し合いました。
すると、子どもたち同士で「次からは名前のことは言わないようにするね」「嫌な気持ちはすぐ伝えよう」と自然に決まりごとが生まれたのです。
子ども同士の「声」を拾い、「一方的な指導」ではなく「共同の気づき」で問題をほどいていくことが、支援のポイントと言えます。
さらに、保護者との「モヤモヤ」にもこの手法は有効的です。
「なかなか他の子と関われなくて心配です」あるお母さんのつぶやき。以前なら「少しずつ慣れてきますよ〜」と「励まし」で返していた職員のDさん。でも今回は違いました。
Dさん:「その心配って、どんなときに強く感じますか?」
お母さん:「周りがどんどん成長していくように見えて、焦るんです」
Dさん:「なるほど。焦りがあるんですね。どうしてそこに焦りを感じるんでしょう?」
話していくうちに、お母さん自身の子ども時代の「周囲と比べられた経験」が浮かび上がってきたのです。
「どうすればいいか」ではなく、お母さんが「どう感じているか」を深堀りする。感情の共有から、モヤモヤの原因はお母さん自身の「心の持ちよう」にあったのです。
このオープンダイアローグの手法を、支援の現場で実践するために大事なのは「すぐに結論を出さないクセをつける」こと。
「〜しよう」「〜しなさい」よりも、まず「どう思った?」「それを聞いてどう感じた?」と投げかけてみることが必要だと感じています。子どもの暴言ひとつとっても、感情的に叱らずに「どうしてそう思ったの?」とまずは理由を聞く。
オープンダイアローグは、特別な技術や資格が必要なものではありません。必要なのは、「答えを急がず、相手の声に耳をすます」こと。
療育は、支援者・子ども・保護者が一緒に「日常の小さな物語」を紡ぐ場だと思っています。その物語に深みを与えるのが、「対話の力」。
今日も、静かに、じんわりと。子どもたちの声に耳をすませてみませんか?
「なんだか難しそう」「カウンセリング?心理療法?」そんな声が聞こえてきそうですが、実はこの手法、支援の現場でもとても有効に使える「対話の魔法」なのです。
今回は、「オープンダイアローグ」を、日々の子どもたちへの支援や保護者さま対応にどう活かせるのか?そのエッセンスと具体例をお届けします!
そもそもオープンダイアローグとは、フィンランドで生まれた精神的な困りごとを抱える人たちの支援に使われてきた手法のこと。特徴はとにかく「対話」です。
すぐに答えを出そうとしない、その場にいる全員の声を「対等に」聞く、対話を重ねながら、自然と「変化」が起こるのを待つ、といった、まるで「会話のキャンプファイヤー」のように、みんなで輪になって、ゆっくり温めるような支援になります。
これらを踏まえて、ユリシスの現場で実際に起こった例をもとに、子どもの支援にどう使うの?といったところを考えてみましょう。
ある日、Aくんが突然、遊んでいる最中に友だち(Cくん)のブロックを壊してしまいました。職員のBさんは「あれ、何があったんだろう」と思いながら、本人を叱るのではなく、こんなふうに声をかけました。
Bさん:「Aくん、何かあってびっくりしたのかな。教えてくれる?」
Aくん:「Cくんに名前をからかわれて、すごく嫌だったの」
その場にいたAくん、そしてCくんも加わり、責めずに「Aくんがどう感じたか」「Cくんはなぜそう言ったのか」「2人がどうしたら安心できるか」を、ゆっくり話し合いました。
すると、子どもたち同士で「次からは名前のことは言わないようにするね」「嫌な気持ちはすぐ伝えよう」と自然に決まりごとが生まれたのです。
子ども同士の「声」を拾い、「一方的な指導」ではなく「共同の気づき」で問題をほどいていくことが、支援のポイントと言えます。
さらに、保護者との「モヤモヤ」にもこの手法は有効的です。
「なかなか他の子と関われなくて心配です」あるお母さんのつぶやき。以前なら「少しずつ慣れてきますよ〜」と「励まし」で返していた職員のDさん。でも今回は違いました。
Dさん:「その心配って、どんなときに強く感じますか?」
お母さん:「周りがどんどん成長していくように見えて、焦るんです」
Dさん:「なるほど。焦りがあるんですね。どうしてそこに焦りを感じるんでしょう?」
話していくうちに、お母さん自身の子ども時代の「周囲と比べられた経験」が浮かび上がってきたのです。
「どうすればいいか」ではなく、お母さんが「どう感じているか」を深堀りする。感情の共有から、モヤモヤの原因はお母さん自身の「心の持ちよう」にあったのです。
このオープンダイアローグの手法を、支援の現場で実践するために大事なのは「すぐに結論を出さないクセをつける」こと。
「〜しよう」「〜しなさい」よりも、まず「どう思った?」「それを聞いてどう感じた?」と投げかけてみることが必要だと感じています。子どもの暴言ひとつとっても、感情的に叱らずに「どうしてそう思ったの?」とまずは理由を聞く。
オープンダイアローグは、特別な技術や資格が必要なものではありません。必要なのは、「答えを急がず、相手の声に耳をすます」こと。
療育は、支援者・子ども・保護者が一緒に「日常の小さな物語」を紡ぐ場だと思っています。その物語に深みを与えるのが、「対話の力」。
今日も、静かに、じんわりと。子どもたちの声に耳をすませてみませんか?

