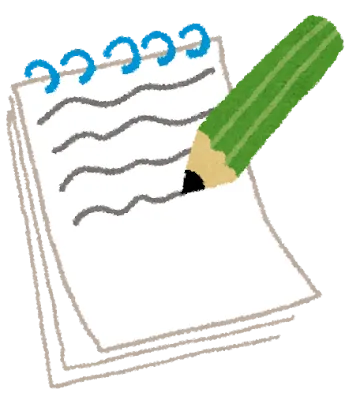
こんにちは!保育士のたくまです。みなさん、「ワーキングメモリ」という言葉をご存知でしょうか?
発達検査(WISCなど)でも出てくる項目のひとつですが、実は子どもの生活や学習を支える「頭の中のメモ帳」 のような働きを担っているんです。
今日はこのワーキングメモリについて、保護者のみなさんにも分かりやすくお伝えできたらいいなと思います。
そもそもワーキングメモリとは、簡単にいうと、「情報を一時的に覚えておきながら、同時にそれを使って作業する力」のこと。
たとえば、「3+5=?」と聞かれて、頭の中で数を覚えながら計算する、「2階に行ってハンカチを持ってきてね」と言われてそのまま行動する、黒板を見てノートに正しく書き写す、などなど、こうした場面で活躍しているのがワーキングメモリです。
ワーキングメモリに苦手さがあると、日常でこんな様子が見られます。
・指示を聞いても途中で忘れてしまう
・計算の途中で数を間違えてしまう
・黒板の長い文章を一気に書き写せない
・本を読んでも、前の内容を覚えていなくて理解が追いつかない
こう列挙してみると、自分のことを言われているようでなんだか胸が痛い(笑)。すぐ忘れるんですよね。とにかくすぐ忘れる。新聞は同じ記事を、理解するまで毎朝何度も読み返します。
脳内のメモ帳のキャパが驚くほど小さいのか、片っ端から忘れていくんです。
決して「やる気がない」のではなく、気づくと頭のメモ帳の容量がいっぱいになってしまっているんですよね。
でも、ワーキングメモリは練習や工夫で補うことができるんです。日常生活でできる工夫をいくつか紹介しますね。
指示は短く・区切って伝える
→「お風呂に入って、服を片づけて、歯を磨いてね」よりも、「まずお風呂に入ろう。そのあと服を片づけてね」と順番に伝える。
視覚的な手がかりを使う
→予定表ややることリストを絵や文字で提示すると見通しが立ち安心して行動できる。
繰り返しを活用する
→一度で覚えられなくてもOK!同じことを繰り返し伝えることで定着します。
楽しく遊びながらトレーニング
→「しりとり」「神経衰弱」「後出しジャンケン」など、遊びの中でワーキングメモリを鍛えることができます。
ワーキングメモリは目に見えない力ですが、子どもの学びや生活の土台になります。「うちの子、忘れっぽいな」と思っても、それは能力のせいではなく情報処理のスタイルの違いかもしれません。
保護者の方がちょっとした工夫でサポートすることで、子どもは安心して力を発揮できるようになります。ユリシスでも、一人ひとりの特性に合わせて支援していきますので、ご家族の方と一緒に長い目で見守っていけたらいいなと思います。
発達検査(WISCなど)でも出てくる項目のひとつですが、実は子どもの生活や学習を支える「頭の中のメモ帳」 のような働きを担っているんです。
今日はこのワーキングメモリについて、保護者のみなさんにも分かりやすくお伝えできたらいいなと思います。
そもそもワーキングメモリとは、簡単にいうと、「情報を一時的に覚えておきながら、同時にそれを使って作業する力」のこと。
たとえば、「3+5=?」と聞かれて、頭の中で数を覚えながら計算する、「2階に行ってハンカチを持ってきてね」と言われてそのまま行動する、黒板を見てノートに正しく書き写す、などなど、こうした場面で活躍しているのがワーキングメモリです。
ワーキングメモリに苦手さがあると、日常でこんな様子が見られます。
・指示を聞いても途中で忘れてしまう
・計算の途中で数を間違えてしまう
・黒板の長い文章を一気に書き写せない
・本を読んでも、前の内容を覚えていなくて理解が追いつかない
こう列挙してみると、自分のことを言われているようでなんだか胸が痛い(笑)。すぐ忘れるんですよね。とにかくすぐ忘れる。新聞は同じ記事を、理解するまで毎朝何度も読み返します。
脳内のメモ帳のキャパが驚くほど小さいのか、片っ端から忘れていくんです。
決して「やる気がない」のではなく、気づくと頭のメモ帳の容量がいっぱいになってしまっているんですよね。
でも、ワーキングメモリは練習や工夫で補うことができるんです。日常生活でできる工夫をいくつか紹介しますね。
指示は短く・区切って伝える
→「お風呂に入って、服を片づけて、歯を磨いてね」よりも、「まずお風呂に入ろう。そのあと服を片づけてね」と順番に伝える。
視覚的な手がかりを使う
→予定表ややることリストを絵や文字で提示すると見通しが立ち安心して行動できる。
繰り返しを活用する
→一度で覚えられなくてもOK!同じことを繰り返し伝えることで定着します。
楽しく遊びながらトレーニング
→「しりとり」「神経衰弱」「後出しジャンケン」など、遊びの中でワーキングメモリを鍛えることができます。
ワーキングメモリは目に見えない力ですが、子どもの学びや生活の土台になります。「うちの子、忘れっぽいな」と思っても、それは能力のせいではなく情報処理のスタイルの違いかもしれません。
保護者の方がちょっとした工夫でサポートすることで、子どもは安心して力を発揮できるようになります。ユリシスでも、一人ひとりの特性に合わせて支援していきますので、ご家族の方と一緒に長い目で見守っていけたらいいなと思います。

