Q3. 勉強が苦手で宿題に時間がかかる場合の解決策とは?
勉強が苦手で、宿題にすごく時間がかかってしまう小学生がいます。親や先生にいろいろとサポートしてもらってもうまくいかず、鉛筆を持つことさえ嫌になってしまいました。子どももストレスを抱え、親や先生もイライラするようになってきています。どんな解決策があるのでしょうか?
A1. 親も疲れてしまうので口出しをやめて、本人のペースを見守る
A2. 難しすぎるので親が手伝う
A3. 宿題が多すぎるので、親から先生に「減らしてほしい」と相談する
A1. 親も疲れてしまうので口出しをやめて、本人のペースを見守る
A2. 難しすぎるので親が手伝う
A3. 宿題が多すぎるので、親から先生に「減らしてほしい」と相談する
宿題の量を減らす
おすすめの対応は3です。
この場合、子どもはなにも悪くありません。宿題の設定の仕方に課題があります。宿題が適切な量や難易度で出ていれば、子どもは30分もかからずにパパッと済ませられるでしょう。宿題に時間がかかり、鉛筆を持つことさえ嫌になるということは、宿題の設定を見直すべき状態です。3のような形で先生に宿題を減らしてもらうか、それが難しければ、親が宿題の量を調整することも考えましょう。
私はそもそも子どもたち全員に同じ量の宿題を出すことは意味がないと思っています。勉強が好きであれば、宿題がなくても自分から勉強するでしょう。勉強が嫌いならば、宿題が負担で勉強がさらに嫌いになってしまうかもしれません。
この場合、子どもはなにも悪くありません。宿題の設定の仕方に課題があります。宿題が適切な量や難易度で出ていれば、子どもは30分もかからずにパパッと済ませられるでしょう。宿題に時間がかかり、鉛筆を持つことさえ嫌になるということは、宿題の設定を見直すべき状態です。3のような形で先生に宿題を減らしてもらうか、それが難しければ、親が宿題の量を調整することも考えましょう。
私はそもそも子どもたち全員に同じ量の宿題を出すことは意味がないと思っています。勉強が好きであれば、宿題がなくても自分から勉強するでしょう。勉強が嫌いならば、宿題が負担で勉強がさらに嫌いになってしまうかもしれません。
まずは身のまわりのことを
「宿題はいらない」という解説を読んで、みなさんは「そうは言っても勉強はしっかりさせなくては」「宿題で学習習慣をつけることは大事」と感じたかもしれません。確かに、常識的に考えればそうでしょう。「着替えや食事のようなことはあとで学んでいけるけれど、勉強で遅れが出てしまっては将来に響く」と考える人もいるかもしれません。しかし私はそのような考え方を聞くと、「まずは身のまわりのことを教える必要がある」と思います。
子どもにとってもっとも大切なのは、基本的な生活習慣です。発達障害のある子どもの場合、生活習慣は特に大事です。着替えや食事などの基本的な生活習慣を自分なりにできるようになっていかないと、それこそ将来に響くと考えています。
子どもにとってもっとも大切なのは、基本的な生活習慣です。発達障害のある子どもの場合、生活習慣は特に大事です。着替えや食事などの基本的な生活習慣を自分なりにできるようになっていかないと、それこそ将来に響くと考えています。
発達障害のある子どもにとって、一番大事なこと
クイズと解説のなかには「給食に手が出てしまうなら別室で待機する」「宿題が嫌なら量を減らす」といった、やや極端な対応法も紹介しました。そんな極端に思える対応の根底にあるのは「子どもを主役にする」という考え方です。
発達障害のある子どもには、さまざまな特性があります。大多数の子どもたちと同じやり方をしていては、うまくいかないこともあります。そんなとき、親や先生が常識的なやり方や、大人がよいと思うやり方を優先して、子どもに無理をさせていては、その子どもはいつまでたっても自分らしいやり方を見つけられないのではないでしょうか。
発達障害のある子どもの個性はさまざまです。このような解説を参考にしながら、使えそうなアイデアをピックアップしてみてください。
発達障害のある子どもには、さまざまな特性があります。大多数の子どもたちと同じやり方をしていては、うまくいかないこともあります。そんなとき、親や先生が常識的なやり方や、大人がよいと思うやり方を優先して、子どもに無理をさせていては、その子どもはいつまでたっても自分らしいやり方を見つけられないのではないでしょうか。
発達障害のある子どもの個性はさまざまです。このような解説を参考にしながら、使えそうなアイデアをピックアップしてみてください。
本田秀夫先生の著書
子どもの発達障害 子育てで大切なこと、やってはいけないこと
SBクリエイティブ
Amazonで詳しく見る
子どもの発達障害 子育てで大切なこと、やってはいけないこと
SBクリエイティブ
楽天で詳しく見る

ソーシャルスキルトレーニング(SST)とは?支援の対象、方法、気をつけたいポイントについて【専門家監修】
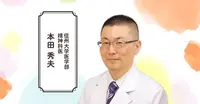
「せめてこれくらい…」が子どもを潰す?発達障害の専門医が語る、発達グレーを白にしようとしないでほしい理由

発達障害のある子には「インクルーシブ教育」が良いのか?誤解されやすい「みんなで一緒に」の落とし穴
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
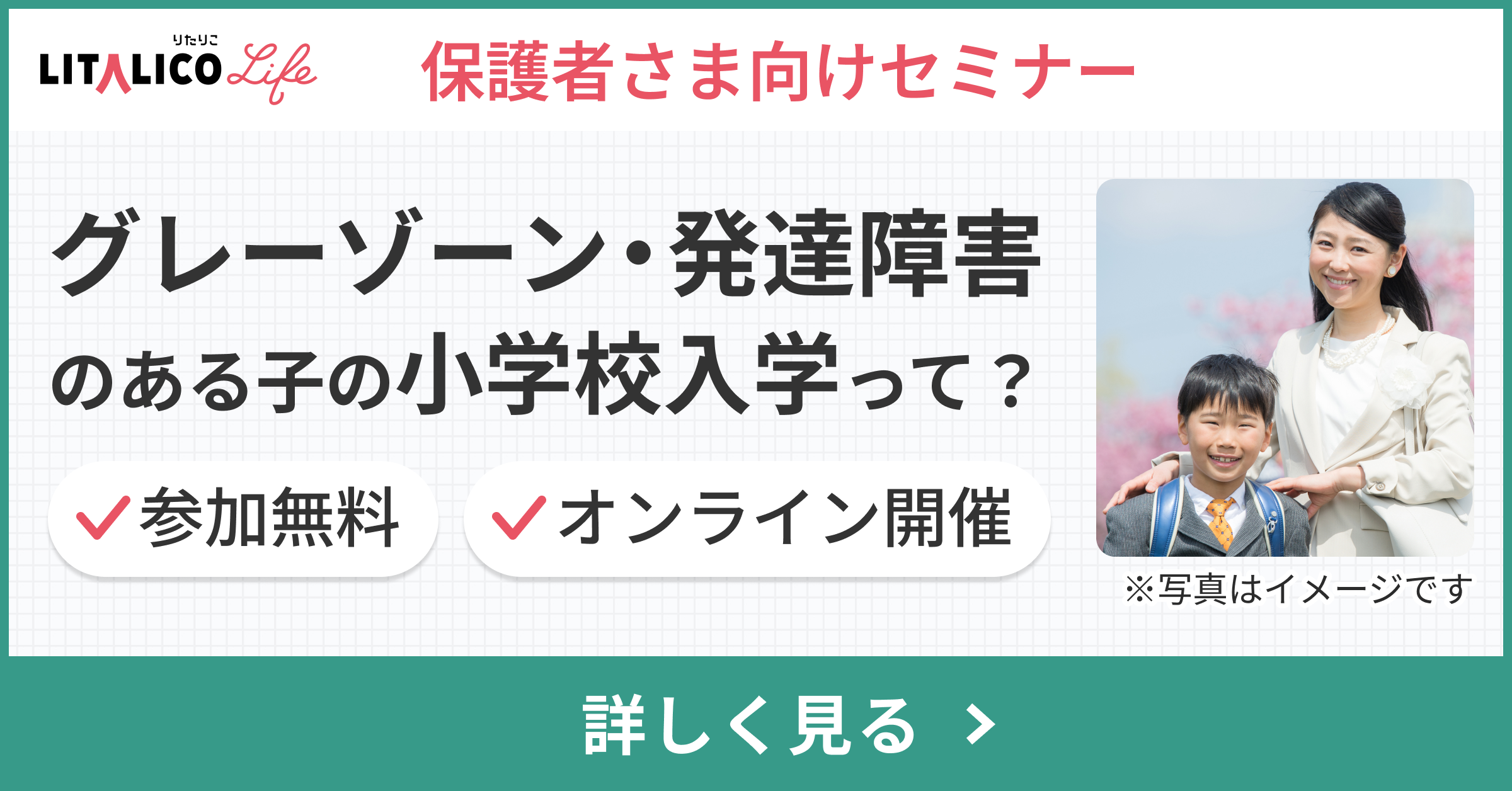
-
 1
1
- 2















