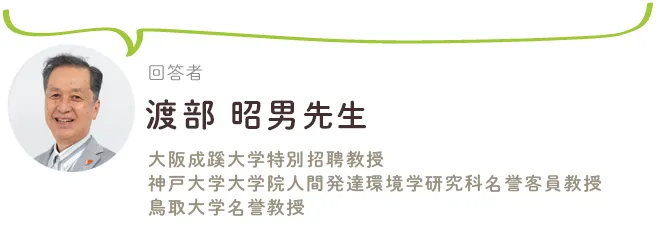特別支援学校に通う子どもと地域のつながり、どう作る?鳥取県の居住地校交流の事例も紹介【教育行政の専門家にきく】
ライター:専門家インタビュー
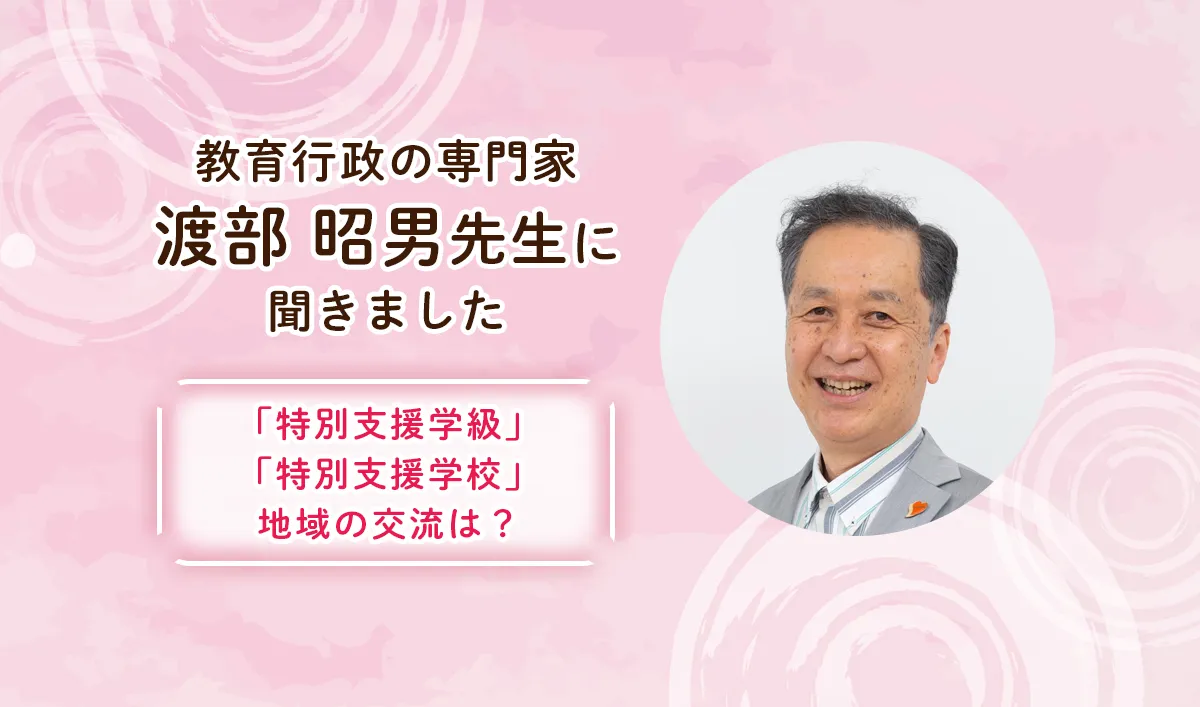
Upload By 専門家インタビュー
「特別支援学校」や「特別支援学級」に通う子どもたちは一体どのように地域と交流をしていったらよいでしょうか。
このコラムでは、そんな「居住地交流」について、鳥取県での取り組みなどを例に出しながら、教育行政を専門とする渡部昭男先生に分かりやすく教えていただきます。(取材/LITALICO発達ナビ編集部)

監修: 渡部昭男
大阪成蹊大学特別招聘教授
神戸大学大学院人間発達環境学研究科名誉客員教授
鳥取大学名誉教授
「この子らを世の光に」「人格発達の権利の徹底的保障」「ひとと生まれて人間となる」などの糸賀一雄(1914-68)の思想と実践を、教育行政学・特別ニーズ教育・発達保障論の立場から21世紀の日本、さらには世界に広く発信している。
神戸大学大学院人間発達環境学研究科名誉客員教授
鳥取大学名誉教授
Q:「特別支援学校」「特別支援学級」に通うわが子。地域とどのように交流していったらよいでしょうか。
A:「豊かな連携」づくりの一環として「居住地校交流」という方法もあります。
居住地校交流とは「同じ地域の学校・学級の仲間」との交流
居住地校交流とは「同じ地域の学校・学級の仲間」との交流です。
一般的に居住地域との結びつきが弱いとされている特別支援学校。学校内では問題なくても、居住地に帰れば独りぼっちという状況は容易に解消されません。
これに対して「同じ地域の学校・学級の仲間」であると位置づけた「居住地校交流」は特別支援学校とおのおのの居住他校との日常的な連携を生み出すものとなっています。
一般的に居住地域との結びつきが弱いとされている特別支援学校。学校内では問題なくても、居住地に帰れば独りぼっちという状況は容易に解消されません。
これに対して「同じ地域の学校・学級の仲間」であると位置づけた「居住地校交流」は特別支援学校とおのおのの居住他校との日常的な連携を生み出すものとなっています。
鳥取県での取り組み
例えば、鳥取県でこの方式を最初に実現したある子どもの取り組みとして(『改訂新版 障がいのある子の就学・進学ガイドブック』pp.91-93の「クミちゃん」参照)
・特別支援学校に通う児童との交流のために、児童が通っていた保育所、同じ町内の障害児の保護者たち、障害児の親の会などの応援により特別支援学校、地域の小学校両方の入学式に出席することができた
・普段は特別支援学校に通っているが、地域の小学校にも教室にその生徒の机が用意され、毎日出席の確認もとっている(特別支援学校に行っている場合はクラスメイトが「特別支援学校です」と返事をする)
・月1~2回の交流学習
などの実績があります。
このような取り組みにより、小学部時代だけでなく中学部・高等部時代を経ても地域とのつながりは保たれていきます。そして、卒業後の地域での生活づくりや福祉・就労サービスの利用にも活きていきます。
※「居住地校交流」を含めて「障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めること」は2004年の障害者基本法の一部改正でも定められています(『改訂新版 障がいのある子の就学・進学ガイドブック』p.102の「障害者基本法」参照)。
・特別支援学校に通う児童との交流のために、児童が通っていた保育所、同じ町内の障害児の保護者たち、障害児の親の会などの応援により特別支援学校、地域の小学校両方の入学式に出席することができた
・普段は特別支援学校に通っているが、地域の小学校にも教室にその生徒の机が用意され、毎日出席の確認もとっている(特別支援学校に行っている場合はクラスメイトが「特別支援学校です」と返事をする)
・月1~2回の交流学習
などの実績があります。
このような取り組みにより、小学部時代だけでなく中学部・高等部時代を経ても地域とのつながりは保たれていきます。そして、卒業後の地域での生活づくりや福祉・就労サービスの利用にも活きていきます。
※「居住地校交流」を含めて「障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めること」は2004年の障害者基本法の一部改正でも定められています(『改訂新版 障がいのある子の就学・進学ガイドブック』p.102の「障害者基本法」参照)。
改訂新版 障がいのある子の就学・進学ガイドブック
日本標準
Amazonで詳しく見る

Sponsored
進路選びに迷ったときに知っておきたい法制度の知識とその活用法とは。教育行政の専門家による「改訂新版 障がいのある子の就学・進学ガイドブック」【著者インタビュー】

接し方で大きく変わる!学習障害・限局性学習症のある子への関わり方とは?具体的な手立ても専門家が解説--マンガでまなぶLD・SLD

特性がある、不登校…進路に迷う家庭の選択肢とは!?体験談や「通信制高校がわかる」特集サイトも紹介【進路特集コラムまとめ】

通常学級?特別支援学級?特別支援学校?それとも私立!?発達が気になるわが子の小・中学校入学に向けて――「進路選び」体験コラムまとめ

好きなことがしたい!ADHD息子が普通科以外の進路選択を考えるきっかけになったのは?
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています