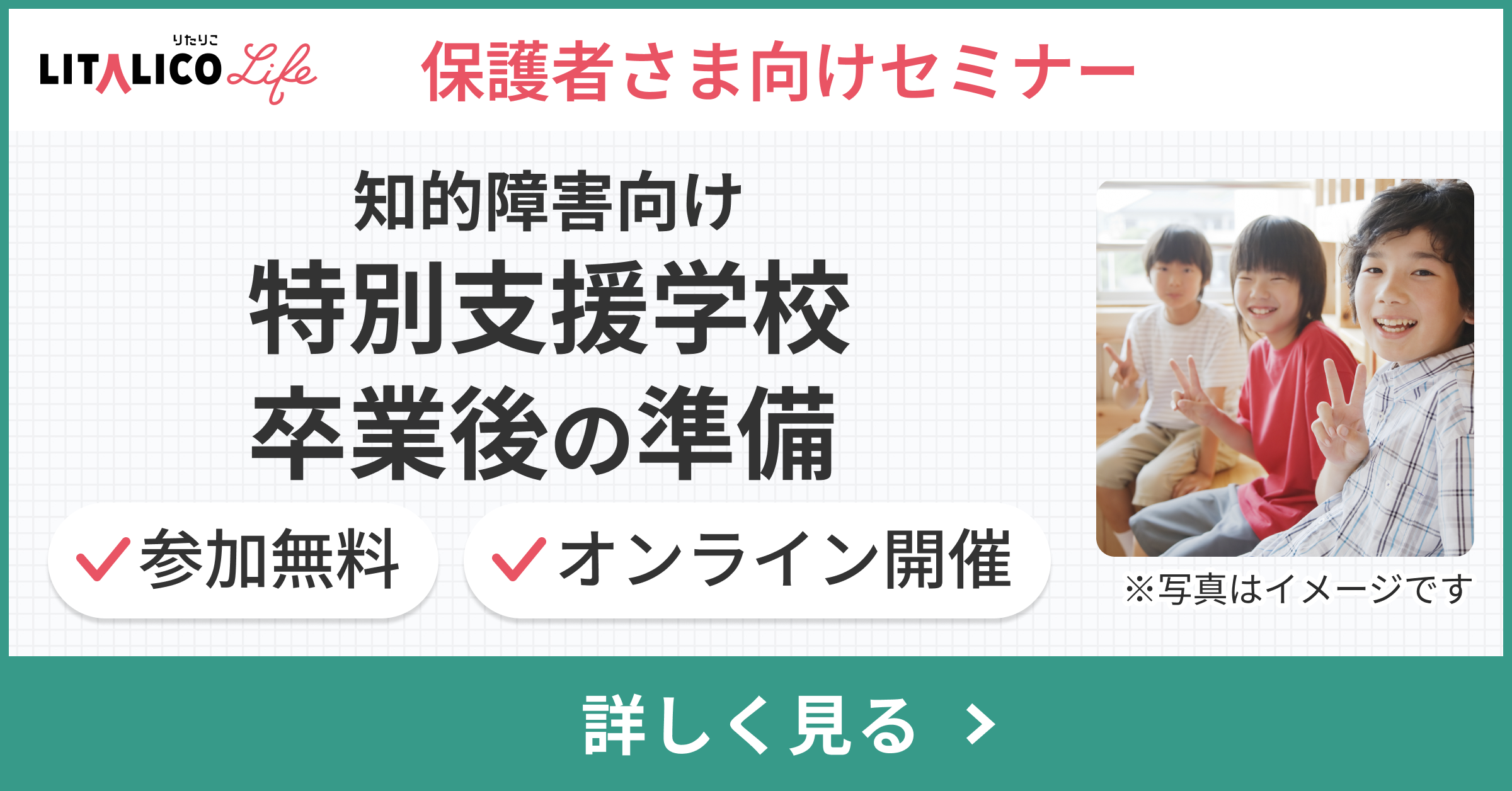発達障害がある子の不登校「ゲーム依存にならない?」「勉強はさせていい?」「反抗期の関わり方」保護者の質問へのアドバイス【臨床心理士が回答】
ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
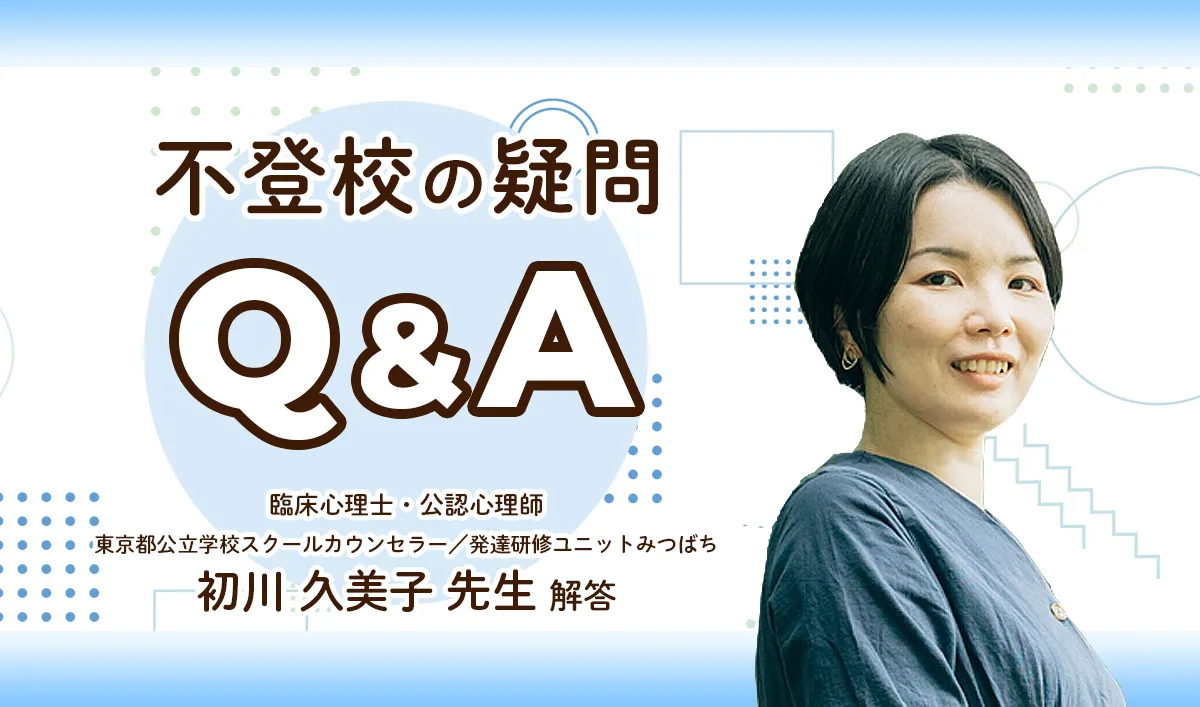
Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
LITALICO発達ナビでは2023年1月に「発達障害のある子の不登校サポートセミナー」を開催し、臨床心理士・公認心理師であり、東京都内のスクールカウンセラーも務めていらっしゃる初川久美子先生に、不登校サポートに関してお話いただきました。このコラムでは不登校生セミナーでの講演から一部を紹介し、さらにあらたな質問と回答を加え「発達障害のある子どもの特性のふまえ方、自宅での過ごし方、学習のすすめ方」を中心にご紹介します。

監修: 初川久美子
臨床心理士・公認心理師
東京都公立学校スクールカウンセラー/発達研修ユニットみつばち
臨床心理士・公認心理師。早稲田大学大学院人間科学研究科修了。在学中よりスクールカウンセリングを学び、臨床心理士資格取得後よりスクールカウンセラーとして勤務。児童精神科医の三木崇弘とともに「発達研修ユニットみつばち」を結成し、教員向け・保護者向け・専門家向け研修・講演講師も行っている。都内公立教育相談室にて教育相談員兼務。
東京都公立学校スクールカウンセラー/発達研修ユニットみつばち
目次
- 発達障害のある子どもの不登校。特性のふまえ方は?
- Q.不登校になり家でゲームをずっとやっている息子。依存症にならないか心配
- Q.ルーティンがあるほうが安心して過ごせるようだが、時間の感覚が苦手な場合、どうしたらいい?
- Q.発達障害があり、服薬をしている娘が最近になりこだわりも増え毎日学校に遅刻。薬の増量をお願いしたほうがいい?思春期特有のパワー不足?
- Q.不登校の息子は自分の気持ちを表現するのが苦手、思春期で接し方も難しい。関わり方のコツは?
- Q.きょうだいそろって不登校。対応の注意点やアドバイスは?
- Q.小5息子の休んだ分の勉強のフォローはどうしたらいい?無理にやらせないほうがいい?
- Q.長期化した不登校。親はどこまで関わっていいもの?
- 発達障害のある子どもの不登校。特性はおおまかな指針であり、大切なのは子どもの状態に合わせた対応
発達障害のある子どもの不登校。特性のふまえ方は?
不登校の小中学生は年々増加傾向にあります。発達障害のある子どもの場合、「学校」という枠組みや「標準」とよばれるようなものにフィットしづらい傾向があり、困りごとを抱えている中で不登校につながることがあります。
そこでLITALICO発達ナビでは2023年1月に「発達障害のある子の不登校サポートセミナー」を開催し、臨床心理士・公認心理師であり、東京都内でスクールカウンセラーも務めていらっしゃる初川久美子先生に、不登校サポートに関してお話いただきました。このコラムでは不登校生セミナーでの講演から一部を紹介し、さらにあらたな質問と回答を加え「発達障害のある子どもの特性のふまえ方、自宅での過ごし方、学習のすすめ方」を中心にご紹介します。
そこでLITALICO発達ナビでは2023年1月に「発達障害のある子の不登校サポートセミナー」を開催し、臨床心理士・公認心理師であり、東京都内でスクールカウンセラーも務めていらっしゃる初川久美子先生に、不登校サポートに関してお話いただきました。このコラムでは不登校生セミナーでの講演から一部を紹介し、さらにあらたな質問と回答を加え「発達障害のある子どもの特性のふまえ方、自宅での過ごし方、学習のすすめ方」を中心にご紹介します。
「学校に行きたくない」は子どもからの「SOS」。大切にしたい「心の休養」と「保護者も頑張りすぎないこと」
子どもが「学校に行きたくない」と言い出したときは、子ども自身がさんざん悩みに悩んだ結果のうえで、それでもどうにもならなかったから出している「SOS」であり、問題を解決するよりも先に、まず休養をとることが最優先と考えましょう。
保護者の方自身も悩み、サポートしていくうちに疲れてしまうという声も多く耳にします。大人自身が不安な気持ちを信頼できる人に話したり、今や将来への情報を集めてみる(想像より選択肢は多く不安が少し解消されるかもしれません)、そして保護者が自分自身を休める時間をつくることが大切です。
保護者の方自身も悩み、サポートしていくうちに疲れてしまうという声も多く耳にします。大人自身が不安な気持ちを信頼できる人に話したり、今や将来への情報を集めてみる(想像より選択肢は多く不安が少し解消されるかもしれません)、そして保護者が自分自身を休める時間をつくることが大切です。

【臨床心理士に聞く】不登校は子どもの最終手段?子どもへの対応や学校連携のヒント、発達障害特性と不登校の関係や、回復への必要なステップとは
発達障害のある子どもの不登校。その特性のふまえ方と対応について
発達障害のある子どもの場合、「学校」という枠組みや「標準」とよばれるようなものにフィットしづらい傾向があります。能力として「できる/できない」以前に、学校生活を送るだけで消耗しやすい状態になりやすく、自分自身のコンディションによって思うような行動ができずに困りごとを抱えてしまうことも多く、不登校や行き渋りにつながることがあります。
では、発達障害のある子どもの特性のふまえ方はどう考えたらよいのでしょうか。
発達障害には主に3つのグループがあります。
では、発達障害のある子どもの特性のふまえ方はどう考えたらよいのでしょうか。
発達障害には主に3つのグループがあります。
しかし、「自閉スペクトラム症のある子どもの不登校には○○をしたら正解」「ADHDのある子どもの不登校は、このようにサポートしたらうまくいく」「学習障害のある子どもの不登校の対応はこれ」などといった、型の決まった解決方法というものは、残念ながら存在しません。
発達障害は、その子の一部分でしかないため、お子さんの状態は「特性によるもの、性格によるもの、環境によるもの」などさまざまです。そのため特性にだけ焦点をあてて対応するのではなく、特性による対応は「大まかな方針」として考えるとよいと思います。
では、以下でそれぞれの特性のふまえ方の例をご紹介します。
発達障害は、その子の一部分でしかないため、お子さんの状態は「特性によるもの、性格によるもの、環境によるもの」などさまざまです。そのため特性にだけ焦点をあてて対応するのではなく、特性による対応は「大まかな方針」として考えるとよいと思います。
では、以下でそれぞれの特性のふまえ方の例をご紹介します。
例1、ルーティンがあるほうがよいか
ルーティンを取り入れられるのであれば、家での過ごし方の”大まかなスケジュール”をお子さんとの話し合いで決めてもよいと思います。例えば「午前中は本を読んで、ゲームは午後からにしよう」「1日1ページは漢字ドリルをやろう」など。
また、何をしていいかわからないと困ってしまい「ルーティンがあったほうが過ごしやすい」というお子さんもいるので、その場合は何かルーティンがあることで、「今日も一日中何もしなかった」「つまらなかった」などとなることを防ぐことができるかもしれません。
例2、学校を休むことに罪悪感が強い場合
学校に行くのはつらいけれど、休むことへの罪悪感が強いお子さんもいます。その場合は、学校との関わり方を模索するとよいでしょう。
詳しくはこちらのコラムをご覧ください。
ルーティンを取り入れられるのであれば、家での過ごし方の”大まかなスケジュール”をお子さんとの話し合いで決めてもよいと思います。例えば「午前中は本を読んで、ゲームは午後からにしよう」「1日1ページは漢字ドリルをやろう」など。
また、何をしていいかわからないと困ってしまい「ルーティンがあったほうが過ごしやすい」というお子さんもいるので、その場合は何かルーティンがあることで、「今日も一日中何もしなかった」「つまらなかった」などとなることを防ぐことができるかもしれません。
例2、学校を休むことに罪悪感が強い場合
学校に行くのはつらいけれど、休むことへの罪悪感が強いお子さんもいます。その場合は、学校との関わり方を模索するとよいでしょう。
詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

【臨床心理士に聞く】不登校は子どもの最終手段?子どもへの対応や学校連携のヒント、発達障害特性と不登校の関係や、回復への必要なステップとは
例3、どこでどう過ごすか
「家で静かに過ごすだけなのは苦痛」というお子さんもいらっしゃると思います。例えば「放課後の校庭開放に行ってみよう」「放課後は友達と遊ぼう」「朝など、保護者と一緒にジョギングしよう」など、少し広い場所などで活動する時間をつくるとよい場合があります。自治体の適応指導教室の利用を考えてもいいかもしれません。
例4、最低限、守ることを決めたほうがよい場合
自分がやりたいことに対して制御できないというお子さんもいると思います。保護者の方もこのままではルールがなし崩しになってしまって危険と感じるようなとき、最低限のルールを決めることは必要だと思います。例えば「ゲームを始めると歯止めが利かず、いつまでもやり続けてしまう」などの場合は「ゲームの終わりの時間を決める」「夜はゲームをしない」「寝る時間を決める」「夕食は家族と一緒に食べる」など、(すべてを制限するのではなく)ルールを厳選して持つことが必要かもしれません。
「家で静かに過ごすだけなのは苦痛」というお子さんもいらっしゃると思います。例えば「放課後の校庭開放に行ってみよう」「放課後は友達と遊ぼう」「朝など、保護者と一緒にジョギングしよう」など、少し広い場所などで活動する時間をつくるとよい場合があります。自治体の適応指導教室の利用を考えてもいいかもしれません。
例4、最低限、守ることを決めたほうがよい場合
自分がやりたいことに対して制御できないというお子さんもいると思います。保護者の方もこのままではルールがなし崩しになってしまって危険と感じるようなとき、最低限のルールを決めることは必要だと思います。例えば「ゲームを始めると歯止めが利かず、いつまでもやり続けてしまう」などの場合は「ゲームの終わりの時間を決める」「夜はゲームをしない」「寝る時間を決める」「夕食は家族と一緒に食べる」など、(すべてを制限するのではなく)ルールを厳選して持つことが必要かもしれません。
ここからは、子どもが不登校になったとき保護者はどうしたらよいのか、学校との連携についてなど寄せられた質問に初川先生に具体例を交えてご回答いただきます。
Q.不登校になり家でゲームをずっとやっている息子。依存症にならないか心配
【質問】
不登校の小4の息子(自閉スペクトラム症/ADHD)がいます。ゲームが大好きで延々やっていても楽しそうです。無制限で徹夜でやりたがります。それでも許可してよいのでしょうか。依存にならないか心配です
不登校の小4の息子(自閉スペクトラム症/ADHD)がいます。ゲームが大好きで延々やっていても楽しそうです。無制限で徹夜でやりたがります。それでも許可してよいのでしょうか。依存にならないか心配です
A.自分でコントロールできないお子さんの場合、ざっくりとしたルールを設定の検討を。頭ごなしに禁止するのではなく、お子さんと話し合いができるとよいでしょう
【回答】
許可しない方がいいと思います。息子さんの特性的な面を考えると、ゲームのような楽しいものから離れづらい(自らおしまいにすることが苦手な)面があるのではと感じます。子どもは、好きなものには飛びつきやすく、生活リズムや体調管理、そして家族との生活(一人で生きているわけではない)を考慮して自らの行動をコントロールすることについては、まだまだ未熟、未発達な面があります。そういった意味で、家庭としてルールは設定してあげたほうがよい場合があります。息子さんの場合はそうだと思います。その設定の仕方はお子さんの特性や状態と家庭の考え方によるとは思います。終わりの時間を定めるだけにするか、始まりの時間も定めるか(不登校のお子さんのご家庭でよくあるのは「ゲームは午後から」や「ゲームは学校が終わった時間から」ですね)、食事は家族と一緒に取ることも追加するか、そのあたりはお子さんとも話し合ってご家庭の方針でと思います。
不登校なり始めの際に、「学校に行っていないのだから、ゲームは禁止」とされるご家庭があると思います。また、「学校を休んでいるなら、寝ているか勉強しているか、あるいはお手伝いするかのどれかじゃないとだめ」と考える保護者の方もいらっしゃるように感じます。学校に行けないことの罰として、お子さんの好きなものを取り上げてしまうような対応をすると、お子さんは学校に行けないのもよくないと分かっているのに、さらに家でも苦しい状況に陥ってしまいます。また、休みはじめは疲れ切っていたり、好きなことすらやる気が湧かないような状態のこともあります。そういう場合は、お子さんの好きな活動や遊びをする時間をうまく取り入れていくことはとても意味のある大事なことになります。
子どもは遊びから元気をもらう場合が多くあります。ただ、だからといって、際限なくさせるというのはまた違う話です。結果としてお子さんが一時的に昼夜逆転になることは多くのケースでありますが、昼夜逆転を引き起こすような設定をする(際限なく動画やゲームを許可する)のはちょっと違うと感じます。お子さんが落ち着いて話せそうなときに、生活のルールについて話し合うことは大切です。ただ、それがあまりにも細かすぎるとそこにもお子さんが疲弊してしまうので、ざっくりとしたルール(消灯時間やゲーム・動画の終わり時間を定めるなど)でよいように感じます。
許可しない方がいいと思います。息子さんの特性的な面を考えると、ゲームのような楽しいものから離れづらい(自らおしまいにすることが苦手な)面があるのではと感じます。子どもは、好きなものには飛びつきやすく、生活リズムや体調管理、そして家族との生活(一人で生きているわけではない)を考慮して自らの行動をコントロールすることについては、まだまだ未熟、未発達な面があります。そういった意味で、家庭としてルールは設定してあげたほうがよい場合があります。息子さんの場合はそうだと思います。その設定の仕方はお子さんの特性や状態と家庭の考え方によるとは思います。終わりの時間を定めるだけにするか、始まりの時間も定めるか(不登校のお子さんのご家庭でよくあるのは「ゲームは午後から」や「ゲームは学校が終わった時間から」ですね)、食事は家族と一緒に取ることも追加するか、そのあたりはお子さんとも話し合ってご家庭の方針でと思います。
不登校なり始めの際に、「学校に行っていないのだから、ゲームは禁止」とされるご家庭があると思います。また、「学校を休んでいるなら、寝ているか勉強しているか、あるいはお手伝いするかのどれかじゃないとだめ」と考える保護者の方もいらっしゃるように感じます。学校に行けないことの罰として、お子さんの好きなものを取り上げてしまうような対応をすると、お子さんは学校に行けないのもよくないと分かっているのに、さらに家でも苦しい状況に陥ってしまいます。また、休みはじめは疲れ切っていたり、好きなことすらやる気が湧かないような状態のこともあります。そういう場合は、お子さんの好きな活動や遊びをする時間をうまく取り入れていくことはとても意味のある大事なことになります。
子どもは遊びから元気をもらう場合が多くあります。ただ、だからといって、際限なくさせるというのはまた違う話です。結果としてお子さんが一時的に昼夜逆転になることは多くのケースでありますが、昼夜逆転を引き起こすような設定をする(際限なく動画やゲームを許可する)のはちょっと違うと感じます。お子さんが落ち着いて話せそうなときに、生活のルールについて話し合うことは大切です。ただ、それがあまりにも細かすぎるとそこにもお子さんが疲弊してしまうので、ざっくりとしたルール(消灯時間やゲーム・動画の終わり時間を定めるなど)でよいように感じます。
Q.ルーティンがあるほうが安心して過ごせるようだが、時間の感覚が苦手な場合、どうしたらいい?
【質問】
子どもは「ルーティン」は好きなのですが、 時間感覚に少し苦手があるのか、 時間で決めるとうまくいかない場合が多く、親子共に困ることがあります。 時間感覚に少し苦手な場合のルーティンづくりのコツがありましたら教えていただけると幸いです
子どもは「ルーティン」は好きなのですが、 時間感覚に少し苦手があるのか、 時間で決めるとうまくいかない場合が多く、親子共に困ることがあります。 時間感覚に少し苦手な場合のルーティンづくりのコツがありましたら教えていただけると幸いです
A.ルーティンがあるほうがよい子どもの場合も、細かく決めすぎるのは負担に。臨機応変に対応できる「ゆるめのルーティン」を検討しましょう
【回答】
ここはぜひご本人とも話し合っていただきたいのですが、時間管理を細かく決めすぎるとせっかくの過ごしやすいはずのルーティンがそうではなくなってしまいます。まずは親子で工夫を考えていただければと思います。私は基本的には時間は決めすぎない方がよいと思っていて、日によって多少ずれるのは自然なことだと思います(コンディションがいいからたくさん何かをやる日もあれば、やる気がどうにも出なくて少しゆるく過ごしたくなる日もあるのは自然です)。そういう意味で、帳尻を合わせるところをむしろ考えたらよいのではと思います。夕食は何時から(多少幅を持たせておいた方が苦しくはならないと思います)、寝る時間は何時といったざっくりさ。あるいは、午前中の間にこれとこれをする、くらいのざっくりさ。本人とどこで帳尻を合わせるか、つまり、優先順位の高い時間のルールはどこかを定めるという話し合いをぜひしていただければと思います。保護者が声をかけるのはその決めたところだけでいいのか、そのほかもリマインダーとして声をかけてほしいのか、そのあたりも相談できるといいと思います。
ルーティンによって安心がもらえるタイプの方は、ぜひルーティンによって心穏やかに過ごせることを受け取ってほしいと思うので、だからこそルーティンに振り回されないことが大事になります。また、大人になってゆくことを考えると、ルーティンと自分自身のコンディションとを考慮できるようになっていくことも大事なことにはなります。例えば今日は疲れているから今日はこれはやらない、という多少の臨機応変さです。今そこまでできずとも、ゆくゆくそうした臨機応変を入れても大丈夫なだけの余白は残しておきたいという意味で、ゆるめのルーティンを一緒に検討しておくという準備が今からできるのではと思います。
ここはぜひご本人とも話し合っていただきたいのですが、時間管理を細かく決めすぎるとせっかくの過ごしやすいはずのルーティンがそうではなくなってしまいます。まずは親子で工夫を考えていただければと思います。私は基本的には時間は決めすぎない方がよいと思っていて、日によって多少ずれるのは自然なことだと思います(コンディションがいいからたくさん何かをやる日もあれば、やる気がどうにも出なくて少しゆるく過ごしたくなる日もあるのは自然です)。そういう意味で、帳尻を合わせるところをむしろ考えたらよいのではと思います。夕食は何時から(多少幅を持たせておいた方が苦しくはならないと思います)、寝る時間は何時といったざっくりさ。あるいは、午前中の間にこれとこれをする、くらいのざっくりさ。本人とどこで帳尻を合わせるか、つまり、優先順位の高い時間のルールはどこかを定めるという話し合いをぜひしていただければと思います。保護者が声をかけるのはその決めたところだけでいいのか、そのほかもリマインダーとして声をかけてほしいのか、そのあたりも相談できるといいと思います。
ルーティンによって安心がもらえるタイプの方は、ぜひルーティンによって心穏やかに過ごせることを受け取ってほしいと思うので、だからこそルーティンに振り回されないことが大事になります。また、大人になってゆくことを考えると、ルーティンと自分自身のコンディションとを考慮できるようになっていくことも大事なことにはなります。例えば今日は疲れているから今日はこれはやらない、という多少の臨機応変さです。今そこまでできずとも、ゆくゆくそうした臨機応変を入れても大丈夫なだけの余白は残しておきたいという意味で、ゆるめのルーティンを一緒に検討しておくという準備が今からできるのではと思います。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています