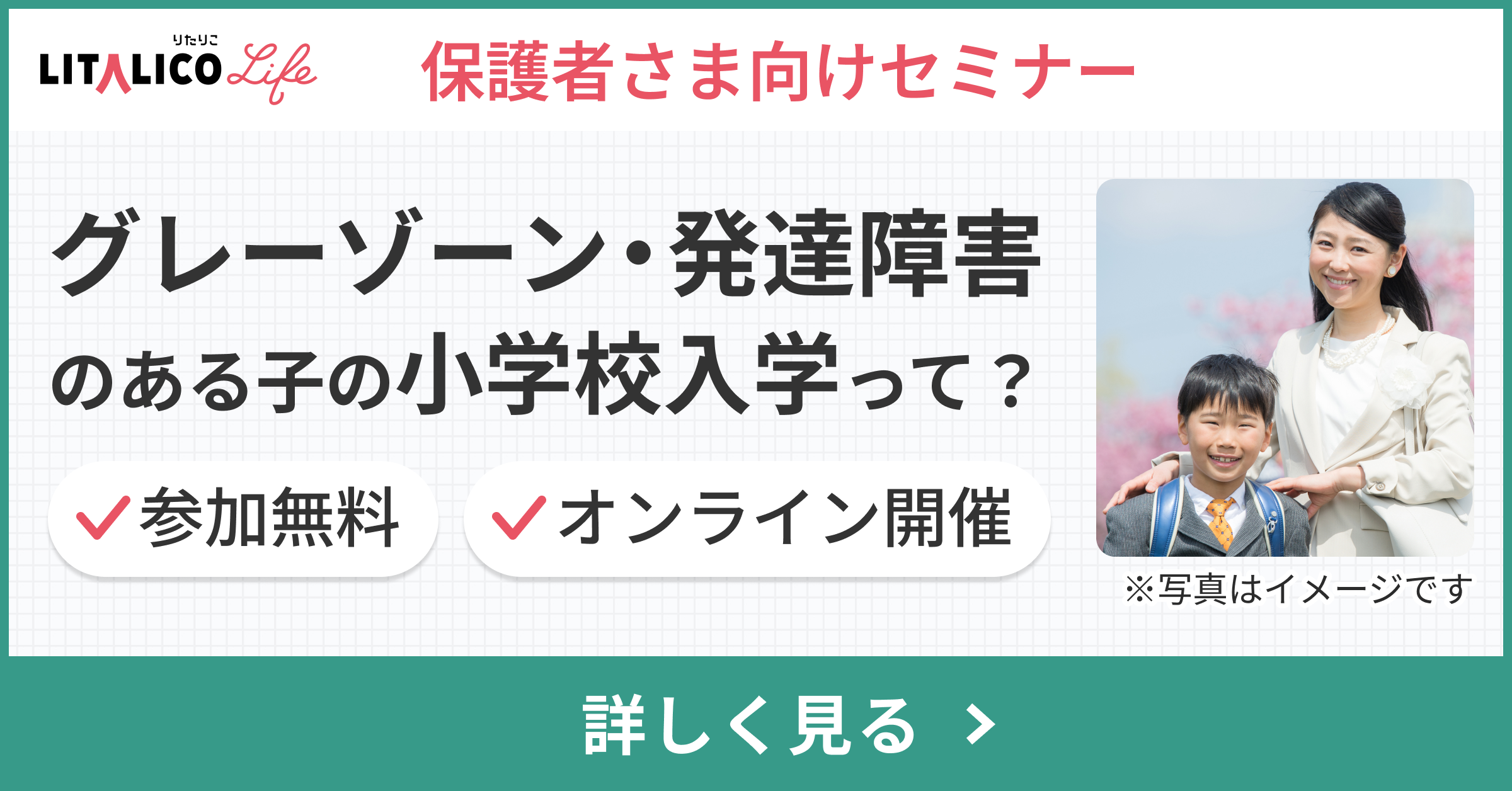Q.小5息子の休んだ分の勉強のフォローはどうしたらいい?無理にやらせないほうがいい?
【質問】
小学5年生の息子(自閉スペクトラム症)が11月から行き渋りが始まり、午前中の途中から登校しています。勉強が分からない、授業がつまらないと言うので、休んだ分家で勉強のフォローをしようと思うのですが、あまりやりたがりません。今は無理に勉強させないほうがよいのでしょうか?
小学5年生の息子(自閉スペクトラム症)が11月から行き渋りが始まり、午前中の途中から登校しています。勉強が分からない、授業がつまらないと言うので、休んだ分家で勉強のフォローをしようと思うのですが、あまりやりたがりません。今は無理に勉強させないほうがよいのでしょうか?
A.「無理に勉強させて」いいことはあまりない。「本人がどうしたいか」に合わせて対応の検討を
【回答】
午前中の途中から登校しているとのこと、本人にとって良きペースであれば何よりです。小学5年生の勉強は難しいですね。授業を毎回出ていても難しいと感じるお子さんが増え始めるのが小学4年生の後半以降だなと感じるので、小学5年生はなおのこと難しいと思います。授業が飛び飛びになると、より一層難しく感じられる(抜けた分を想像しながら聞かないといけない)のはありそうですね。ただ、その前からもしかしたらつまずきがあり、1日6時間分の授業を受けることがつらいから朝から学校行く元気が湧かない…というお子さんもいるようにも感じます。
「勉強が分からないなら、その分を家でフォローしたらいいのでは」とおっしゃるのは、ごもっともだと思います。分からない授業を聞くのは「つまらない」ので授業が分かるようにしよう。ただ、それがうまくいくのは、そこにコミットして解決してまで学校の授業に参加したいという強い気持ちがある場合だけだろうなと感じます。また、家で保護者と学習をする際には、保護者が一生懸命になるあまり、子どもと喧嘩になることが多いように感じます。小学校高学年以降の親子での学習は、保護者が熱くなりすぎないよう注意も必要です。
「無理に勉強させて」いいことはあまりありません。「勉強したくなったら一緒にやるよ、分からないところは教えるよ」くらいのスタンスでいいように思います。ここから先はお子さんの学習意欲にもよりますが、親子で喧嘩しながら勉強したいとは思わないけれど、少しは取り組んでみたいと思うなら、通信教材の活用や、今は動画で単元ごとに配信されているものもあります。そういうものを使って取り組んでみる。分からないところは保護者やあるいは担任の先生に聞くということができるといいでしょう。今まさに授業でやっている内容につまずきがある場合に、その前の内容からつまずいていたらそちらの復習が先になるでしょう。小数のかけ算でつまずいているなら、まず簡単なかけ算からやって、「そうだった」「できるできる」を取り戻しながら取り組めるといいでしょう。昔のドリルや問題集をやってみたり、ネットで無料の問題もシェアされています。学校から配布されているタブレットにもタブレットで回答できるドリルが入っている場合もあります。本人に合っていて、やってみたいと思うものをやってみてもいいかもしれません。あまり多くはないですが、勉強は保護者や学校の先生ではない、勉強を教えてくれる専門の人に教わりたいと思うお子さんもいます。塾や家庭教師の先生とだとできる場合もあるので、そうしたことも検討してみてもいいかもしれません。
さまざま書いてきましたが、大事なのは本人がどうしたいかです。こうしたいという気持ちがあれば、それに合わせてさまざま提案することはできると思います。ただ、何もしたくないというときはそれを尊重するのも1つです。午前中の途中から登校することの、本人にとっての良さはなんでしょうか。誰かと会える、給食が食べられる、休み時間遊べる、勉強ができる、放課後に遊ぶ約束ができる、家でゲームができる。いろいろあると思いますが、それと登校スタイルと、そして学習と。負荷がかかりすぎず、それなりにどれも得られるバランスを探っていただければと思います。そしてそのバランスはときどき変わってくると思います。一度決めたやり方にとらわれすぎず、本人の気持ちとコンディションに合わせて、適宜変更を加えながら進めていただければと思います。
午前中の途中から登校しているとのこと、本人にとって良きペースであれば何よりです。小学5年生の勉強は難しいですね。授業を毎回出ていても難しいと感じるお子さんが増え始めるのが小学4年生の後半以降だなと感じるので、小学5年生はなおのこと難しいと思います。授業が飛び飛びになると、より一層難しく感じられる(抜けた分を想像しながら聞かないといけない)のはありそうですね。ただ、その前からもしかしたらつまずきがあり、1日6時間分の授業を受けることがつらいから朝から学校行く元気が湧かない…というお子さんもいるようにも感じます。
「勉強が分からないなら、その分を家でフォローしたらいいのでは」とおっしゃるのは、ごもっともだと思います。分からない授業を聞くのは「つまらない」ので授業が分かるようにしよう。ただ、それがうまくいくのは、そこにコミットして解決してまで学校の授業に参加したいという強い気持ちがある場合だけだろうなと感じます。また、家で保護者と学習をする際には、保護者が一生懸命になるあまり、子どもと喧嘩になることが多いように感じます。小学校高学年以降の親子での学習は、保護者が熱くなりすぎないよう注意も必要です。
「無理に勉強させて」いいことはあまりありません。「勉強したくなったら一緒にやるよ、分からないところは教えるよ」くらいのスタンスでいいように思います。ここから先はお子さんの学習意欲にもよりますが、親子で喧嘩しながら勉強したいとは思わないけれど、少しは取り組んでみたいと思うなら、通信教材の活用や、今は動画で単元ごとに配信されているものもあります。そういうものを使って取り組んでみる。分からないところは保護者やあるいは担任の先生に聞くということができるといいでしょう。今まさに授業でやっている内容につまずきがある場合に、その前の内容からつまずいていたらそちらの復習が先になるでしょう。小数のかけ算でつまずいているなら、まず簡単なかけ算からやって、「そうだった」「できるできる」を取り戻しながら取り組めるといいでしょう。昔のドリルや問題集をやってみたり、ネットで無料の問題もシェアされています。学校から配布されているタブレットにもタブレットで回答できるドリルが入っている場合もあります。本人に合っていて、やってみたいと思うものをやってみてもいいかもしれません。あまり多くはないですが、勉強は保護者や学校の先生ではない、勉強を教えてくれる専門の人に教わりたいと思うお子さんもいます。塾や家庭教師の先生とだとできる場合もあるので、そうしたことも検討してみてもいいかもしれません。
さまざま書いてきましたが、大事なのは本人がどうしたいかです。こうしたいという気持ちがあれば、それに合わせてさまざま提案することはできると思います。ただ、何もしたくないというときはそれを尊重するのも1つです。午前中の途中から登校することの、本人にとっての良さはなんでしょうか。誰かと会える、給食が食べられる、休み時間遊べる、勉強ができる、放課後に遊ぶ約束ができる、家でゲームができる。いろいろあると思いますが、それと登校スタイルと、そして学習と。負荷がかかりすぎず、それなりにどれも得られるバランスを探っていただければと思います。そしてそのバランスはときどき変わってくると思います。一度決めたやり方にとらわれすぎず、本人の気持ちとコンディションに合わせて、適宜変更を加えながら進めていただければと思います。
Q.長期化した不登校。親はどこまで関わっていいもの?
【質問】
不登校が長期になってきた場合の家での過ごし方(中学生)どこまで親が関わればいいのか知りたいです
不登校が長期になってきた場合の家での過ごし方(中学生)どこまで親が関わればいいのか知りたいです
A.生活のリズムは、どこで折り合いをつけるかがポイントに。将来に向けて中3ごろから自分で動き始める子どもも。保護者は、進路情報などを集めておくとよいでしょう
【回答】
中学生で、しかも長期にわたると生活リズムを一定に保つことも難しいことが多くなります。多くの子どもたちが学校で過ごす時間帯、明るい時間帯にたとえ家であっても心穏やかに過ごすことが(自覚の有無は人それぞれですが)つらく感じられたり、家族が寝静まった夜中だと過ごしやすい気がしたり。日中動かないがゆえに自然と眠くなることも少なく、寝ようと思ってもあまりすぐに寝つけなくなっていたり。ネット上などに友達がいる場合は、そうした仲間たちがネットに集まるのが夜間であることも多く、生活時間帯が後ろ倒しになりやすいです。ネットやスマホは○時までとルールを定めたり、あるいは家庭全体夜間はWi-fiを切ったりなどさまざま工夫される保護者の方もいらっしゃいます。そうしたルールや枠組みでうまくいく場合はそれでいいと思いますが、そこで喧嘩したり、ぎすぎすしたりといったこともよくある話ではあります。どこで折り合いをつけるかはケースバイケースだと感じます(単にそうしたものを取り上げるだけだと、お子さんにとって心のよりどころも失うことになる可能性もあるので、ゼロか100かというよりも、折り合いのつけ方なのだと感じます)。
ただ、家族として同じ家で生活をしているので、お子さんの過ごし方が目に余ると保護者としてイライラしてくるのも自然なことだと思います。そういう意味でも、お子さんと家での過ごし方や学習の仕方、あるいは家庭以外での過ごし方(学校に部分登校できるか、適応指導教室やフリースクールに通えるか、相談機関に通えるか)を話し合い、大方の過ごし方について決めて、そこが維持されていればそれ以上は口は出さないという線を決めたいところです。
実際のところでいえば、「高校に(は)行きたい」と考えているお子さんが多く、中学3年生の春夏ごろから高校の見学や説明会に出向くなど動き始めるお子さんは結構います。逆に言うと、そこまでは動きが見られない場合も多いです。動き出す時期のために、進路情報を保護者が集めておく(集めた情報を本人に知らせるかどうかは慎重にと思います。機が熟すのを待つほうがいい気がします)ことなどをしておきましょう。
中学3年の秋以降は志望校に合わせた準備に取り組むこともよく見られます。どのような高校の種類があり、お子さんにはどんな学校が合っていそうかということは、担任の先生や進路の先生、地域のそうした情報に詳しい適応指導教室や教育支援センター、教育相談室などで聞いてみるのもいいと思います。情報は集めつつも、あくまでも本人が通いたいという意志を見せた学校に進学すること、そのために何校か見学すること。保護者はその手伝いをするということ。それを本人にも折々に伝えていただければと思います。
中学生で、しかも長期にわたると生活リズムを一定に保つことも難しいことが多くなります。多くの子どもたちが学校で過ごす時間帯、明るい時間帯にたとえ家であっても心穏やかに過ごすことが(自覚の有無は人それぞれですが)つらく感じられたり、家族が寝静まった夜中だと過ごしやすい気がしたり。日中動かないがゆえに自然と眠くなることも少なく、寝ようと思ってもあまりすぐに寝つけなくなっていたり。ネット上などに友達がいる場合は、そうした仲間たちがネットに集まるのが夜間であることも多く、生活時間帯が後ろ倒しになりやすいです。ネットやスマホは○時までとルールを定めたり、あるいは家庭全体夜間はWi-fiを切ったりなどさまざま工夫される保護者の方もいらっしゃいます。そうしたルールや枠組みでうまくいく場合はそれでいいと思いますが、そこで喧嘩したり、ぎすぎすしたりといったこともよくある話ではあります。どこで折り合いをつけるかはケースバイケースだと感じます(単にそうしたものを取り上げるだけだと、お子さんにとって心のよりどころも失うことになる可能性もあるので、ゼロか100かというよりも、折り合いのつけ方なのだと感じます)。
ただ、家族として同じ家で生活をしているので、お子さんの過ごし方が目に余ると保護者としてイライラしてくるのも自然なことだと思います。そういう意味でも、お子さんと家での過ごし方や学習の仕方、あるいは家庭以外での過ごし方(学校に部分登校できるか、適応指導教室やフリースクールに通えるか、相談機関に通えるか)を話し合い、大方の過ごし方について決めて、そこが維持されていればそれ以上は口は出さないという線を決めたいところです。
実際のところでいえば、「高校に(は)行きたい」と考えているお子さんが多く、中学3年生の春夏ごろから高校の見学や説明会に出向くなど動き始めるお子さんは結構います。逆に言うと、そこまでは動きが見られない場合も多いです。動き出す時期のために、進路情報を保護者が集めておく(集めた情報を本人に知らせるかどうかは慎重にと思います。機が熟すのを待つほうがいい気がします)ことなどをしておきましょう。
中学3年の秋以降は志望校に合わせた準備に取り組むこともよく見られます。どのような高校の種類があり、お子さんにはどんな学校が合っていそうかということは、担任の先生や進路の先生、地域のそうした情報に詳しい適応指導教室や教育支援センター、教育相談室などで聞いてみるのもいいと思います。情報は集めつつも、あくまでも本人が通いたいという意志を見せた学校に進学すること、そのために何校か見学すること。保護者はその手伝いをするということ。それを本人にも折々に伝えていただければと思います。
発達障害のある子どもの不登校。特性はおおまかな指針であり、大切なのは子どもの状態に合わせた対応
発達障害がある子どもが不登校になったとき、その子どもの特性に焦点をあてて解決の糸口を探ることは多くあると思います。しかし、発達障害はその子どもの一部にしかすぎず、特性だけに焦点をあてても状況がよくならないことも多くあります。特性のふまえ方を大まかな指針として、それぞれのお子さんの特性、性格、環境、こころの状態などを見ながら対応しましょう。
そして何より、子どもも保護者も学校の先生も途中で疲れ切ってしまわないように持続可能なペースでサポートしていくことが大切です。
そして何より、子どもも保護者も学校の先生も途中で疲れ切ってしまわないように持続可能なペースでサポートしていくことが大切です。

【臨床心理士に聞く】不登校は子どもの最終手段?子どもへの対応や学校連携のヒント、発達障害特性と不登校の関係や、回復への必要なステップとは
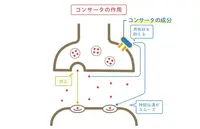
ADHD(注意欠如多動症)のある人に処方される薬コンサータの効果や副作用、コンサータとストラテラ違いも解説【精神科医監修】
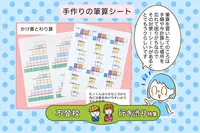
不登校の小3発達障害息子「お母さんだけはあきらめないで!」親子で挑んだ家庭学習の結果は!?2年目で見えてきたわが家の学習スタイル

ASD息子が不登校になったら?小学校入学前から夫婦で話し合った「学習」と「社会性」の育み方
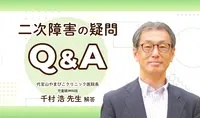
発達障害の二次障害とは?症状や原因の探り方、特性との関連、6つの事例別のギモンにも回答【児童精神科医Q&A】
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如・多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如・多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
SLD(限局性学習症)
LD、学習障害、などの名称で呼ばれていましたが、現在はSLD、限局性学習症と呼ばれるようになりました。SLDはSpecific Learning Disorderの略。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
知的発達症
知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如・多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如・多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
SLD(限局性学習症)
LD、学習障害、などの名称で呼ばれていましたが、現在はSLD、限局性学習症と呼ばれるようになりました。SLDはSpecific Learning Disorderの略。

子どもの癇癪(かんしゃく)とは?癇癪を起こす原因や発達障害との関連は?しんどいときの対応方法、相談先まとめ【専門家監修】
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています