ハジュの成長と親としての喜び
しかし、そんなハジュも少しずつ変わってきています。以前は、準備が間に合わないと感情を爆発させることが多かったのですが、最近では「水筒をお願いします」と頼んだり、「着替えがないから自分で選ぶの?」と言えたりと、柔軟に対応できるようになりました。私自身も、ハジュができることが増えたおかげで、気持ちに余裕が持てるようになりました。朝の準備がスムーズに進むことで、私のHP(体力)も削られずに済んでいます(笑)。ハジュが少しずつ自立に向かって進んでいる姿に親としての喜びを感じます。
ちなみに、長女や次女は…
長女も実は自分のルーティンをしっかり持っています。順番が狂うと、その日はスイッチOFFになってしまうこともありましたが、成長する中で、自分のペースを守るコツや、崩されないための秘技(?)を自分なりに編み出したようです。最近では、もし順番が崩れても「まあ、なんとかなるか……」と自分で気持ちを立て直せるように。成長したなぁ、と感心しています。
それでも体調不良などの“イレギュラーイベント”が発生する時は、私が「今日はいつもとちょっと違うから、これを先にやるね」と事前にアナウンスを入れておきます。すると「うん。いいよ」と落ち着いて対処できるので、事前の見通しって大事だなぁと実感します。
一方、次女はと言えば……そういう順番とかルールとか、まったく気にしません!(笑)。とても自由にやってくれるので、その気ままさにたまに振り回されることもありますが、それが彼女の個性なんだなと微笑ましく見守っています。
それでも体調不良などの“イレギュラーイベント”が発生する時は、私が「今日はいつもとちょっと違うから、これを先にやるね」と事前にアナウンスを入れておきます。すると「うん。いいよ」と落ち着いて対処できるので、事前の見通しって大事だなぁと実感します。
一方、次女はと言えば……そういう順番とかルールとか、まったく気にしません!(笑)。とても自由にやってくれるので、その気ままさにたまに振り回されることもありますが、それが彼女の個性なんだなと微笑ましく見守っています。
ハジュの朝のルーティンは、単なる習慣ではありません。それは彼が安心して一日をスタートするための大切な基盤であり、私たち親子の絆を深める時間でもあります。これからも彼のペースに合わせながら、一緒に成長していきたいと思っています。
執筆/スパ山
執筆/スパ山
(監修:森先生より)
スパ山さん、お子さんのルーティンについての体験談をありがとうございます。 ルーティンを日々こなす中でも、ルーティンが変化していったり、思わぬアクシデントが起きることで、かえってお子さんの成長が感じられてうれしいですね。
さて、「ルーティンをこなすと安心する」というのは、誰しもあることかと思います。 たとえば「野球選手が試合前に素振りをして精神を統一する」とか、「受験生が毎回テスト前に深呼吸する」というようなことですね。 落ち着くための、いわばおまじないのようなルーティンを持っている方は多いのではないでしょうか。
特に発達障害の傾向のあるお子さんでは、日々のルーティンが決まっていることも多いですね。学校に行って小さな社会に触れることは、お子さんにとっては大冒険です。外の世界では何が起きるか分かりませんから、安心して過ごせる家庭の中で「決まった手順」を踏むことで、外の世界に出る心の準備をしているのかもしれません。
お子さんのルーティンを尊重することは、お子さんの気持ちを尊重することです。できる限りルーティンを守ってあげると結果的に準備がスムーズに進むことが多いでしょう。 とはいえ、保護者の方の生活もありますし、時間や体力、天候などもろもろの状況がルーティンを許さないこともあり得ます。 お子さんの求めに必ず毎回応えられるわけではないですよね。「ルーティンが崩れても大丈夫だった」という成功体験を積むと、お子さんはさらに自信を持って成長します。ルーティンをうまく使いながら、無理なく子育てをしていきましょう。
これからもスパ山さんとお子さんが一緒に成長していけることを願っております。
スパ山さん、お子さんのルーティンについての体験談をありがとうございます。 ルーティンを日々こなす中でも、ルーティンが変化していったり、思わぬアクシデントが起きることで、かえってお子さんの成長が感じられてうれしいですね。
さて、「ルーティンをこなすと安心する」というのは、誰しもあることかと思います。 たとえば「野球選手が試合前に素振りをして精神を統一する」とか、「受験生が毎回テスト前に深呼吸する」というようなことですね。 落ち着くための、いわばおまじないのようなルーティンを持っている方は多いのではないでしょうか。
特に発達障害の傾向のあるお子さんでは、日々のルーティンが決まっていることも多いですね。学校に行って小さな社会に触れることは、お子さんにとっては大冒険です。外の世界では何が起きるか分かりませんから、安心して過ごせる家庭の中で「決まった手順」を踏むことで、外の世界に出る心の準備をしているのかもしれません。
お子さんのルーティンを尊重することは、お子さんの気持ちを尊重することです。できる限りルーティンを守ってあげると結果的に準備がスムーズに進むことが多いでしょう。 とはいえ、保護者の方の生活もありますし、時間や体力、天候などもろもろの状況がルーティンを許さないこともあり得ます。 お子さんの求めに必ず毎回応えられるわけではないですよね。「ルーティンが崩れても大丈夫だった」という成功体験を積むと、お子さんはさらに自信を持って成長します。ルーティンをうまく使いながら、無理なく子育てをしていきましょう。
これからもスパ山さんとお子さんが一緒に成長していけることを願っております。

ルールやルーティンにこだわる自閉症息子、通学路変更でトラブル多発、パニックに…!?【読者体験談】

わが子の発達特性に合わせたサポート法は?自宅ですぐできる「LITALICO発達特性検査」活用法まとめ

イヤイヤ期が来ぬまま小4に…自閉症息子、自己主張よりルーティン優先だった幼少期

ASD兄とADHD妹との毎朝の攻防戦!?癇癪阻止、声かけで登園前から母疲弊…わが家の朝ルーティン

自閉症中1娘、「話す」「察する」「弟の世話」は苦手だけど「ルーティン」のこだわりを活かして家庭で母より大活躍!?
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
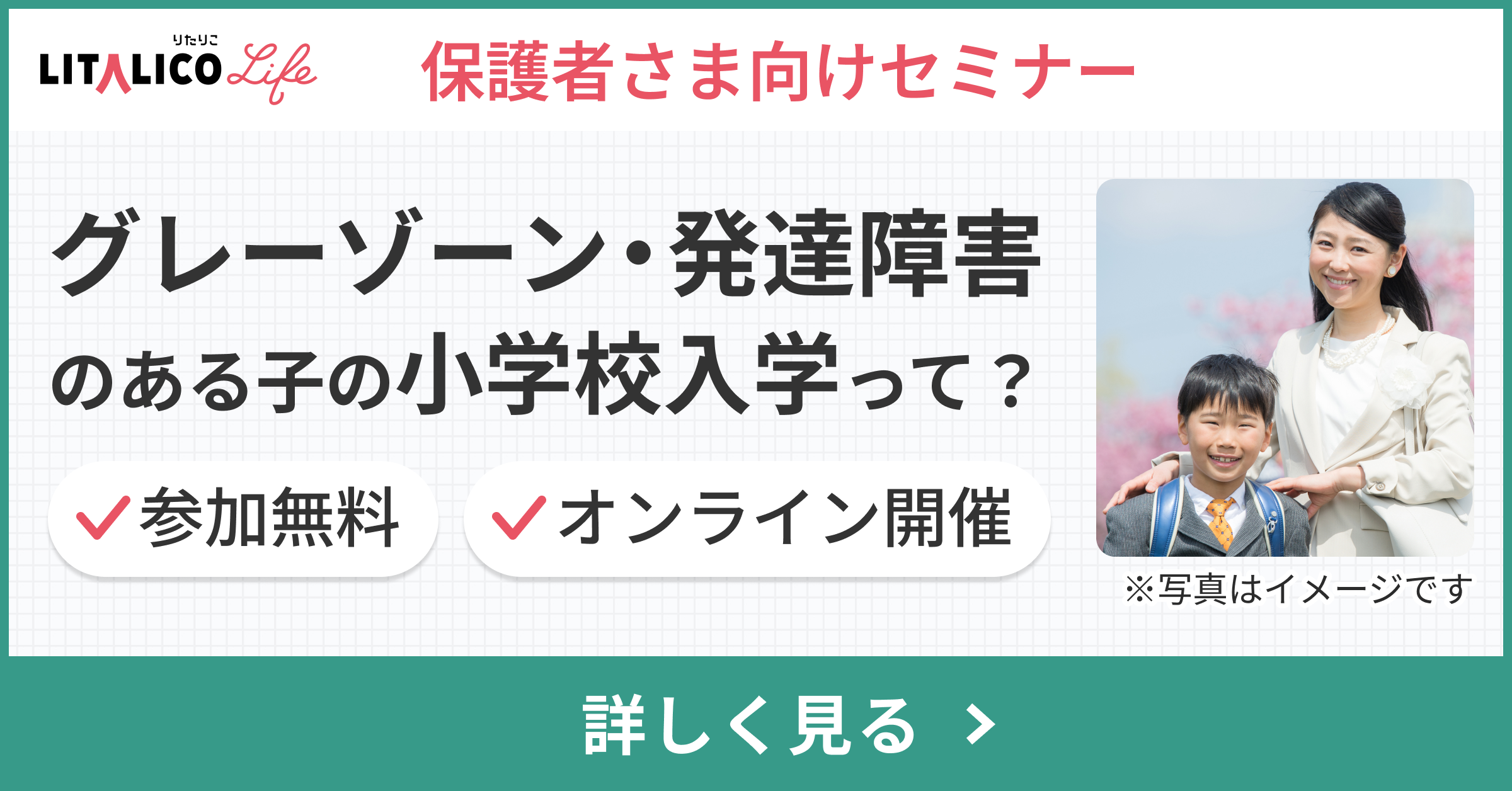
-
 1
1
- 2















