まとめ
ここまで太郎が放デイに通い続けている理由は、やはりデイサービスの先生たちとの信頼関係にあると思います。先生たちは自分を受け入れてくれる安心できる人たちであり、放デイという場所もまた居心地がいいものとなっているようです。
高校に進学後も、今と変わることなく、週に4日~5日通う予定です。家族のようなつながりができているため、私も頼りにしている場所になっています。あと3年間、きっとあっという間ですが大切に通所をしていきたいと思います。太郎自身は、あと3年という期間をどう思っているのか……気になるところです。
執筆/まゆん
高校に進学後も、今と変わることなく、週に4日~5日通う予定です。家族のようなつながりができているため、私も頼りにしている場所になっています。あと3年間、きっとあっという間ですが大切に通所をしていきたいと思います。太郎自身は、あと3年という期間をどう思っているのか……気になるところです。
執筆/まゆん
(監修:新美先生より)
放課後等デイサービスの利用について聞かせていただきありがとうございます。
放課後等デイサービスの利用年齢は制度上は原則6才~18歳となっています。事業所によってまちまちではありますが、ほかに高校生の姿があまり見えなくても、継続利用は受け入れているという事業所は多いので希望があれば聞いてみるとよいかもしれません。
慣れた人間関係があり、信頼できる職員のいる放デイに、思春期以降も通いたいとご本人が思えている場合、小学生の時はただ楽しく遊ぶだけだったのが、ちょっとした日常のことや進路のことなどを話したり相談したりといったことがしやすい場になるかもしれません。家庭でも学校でもない第三の居場所(サードプレイス)として、ホッと一息できる場所はかけがえのないものです。多くの場合は中学、高校と年長するにつれて、放デイはもういいよと言われることが多いかもしれませんが、お子さんご本人が行きたいと思える場に放課後等デイサービスがなっているのだとしたら、よい関係が築けていてラッキーといえるかもしれません。
放課後等デイサービスの利用について聞かせていただきありがとうございます。
放課後等デイサービスの利用年齢は制度上は原則6才~18歳となっています。事業所によってまちまちではありますが、ほかに高校生の姿があまり見えなくても、継続利用は受け入れているという事業所は多いので希望があれば聞いてみるとよいかもしれません。
慣れた人間関係があり、信頼できる職員のいる放デイに、思春期以降も通いたいとご本人が思えている場合、小学生の時はただ楽しく遊ぶだけだったのが、ちょっとした日常のことや進路のことなどを話したり相談したりといったことがしやすい場になるかもしれません。家庭でも学校でもない第三の居場所(サードプレイス)として、ホッと一息できる場所はかけがえのないものです。多くの場合は中学、高校と年長するにつれて、放デイはもういいよと言われることが多いかもしれませんが、お子さんご本人が行きたいと思える場に放課後等デイサービスがなっているのだとしたら、よい関係が築けていてラッキーといえるかもしれません。

放課後等デイサービス(放デイ)とは?利用方法、費用など【専門家監修】
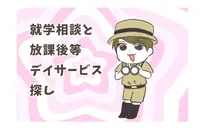
年長から始めた放デイ探し。理想と現実で悩み…見学して実感した「譲れない条件」
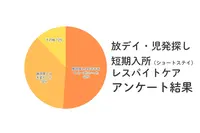
放デイ・児発の探し方とショートステイのリアル!読者アンケート結果や体験談まとめ

学童?放デイ?自閉症グレー息子の「放課後の居場所」探し。支援センターで知った事実に衝撃…

自閉症長男と発達グレー次男の「放デイ」活用術。通う日数も目的も違うのは理由があって
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
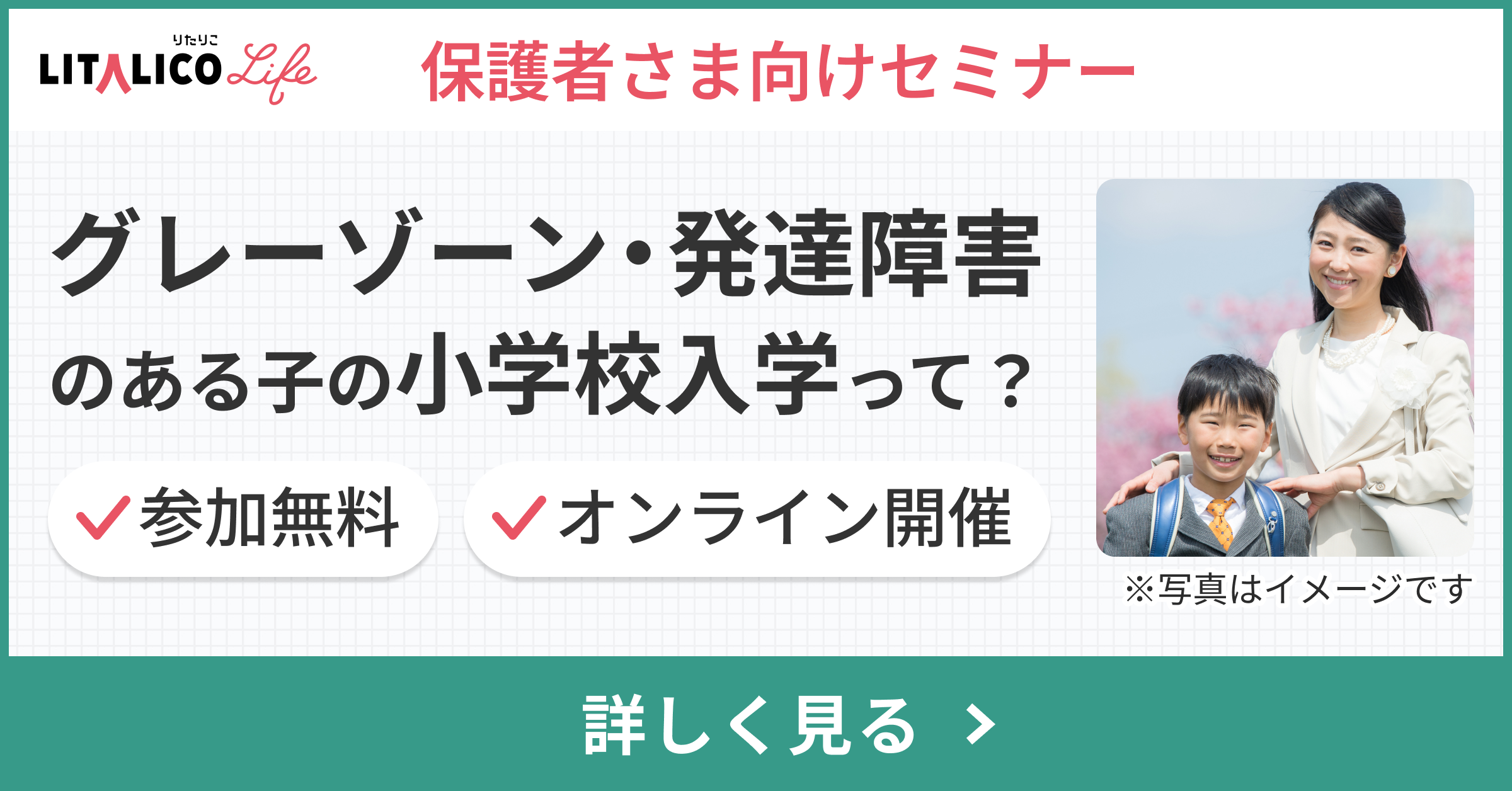
-
 1
1
- 2















