【中学生編】中学生になっても学校の課題提出を忘れがち。内申点は大丈夫なの!?
中学2年生になったコウくん。その特性から学校の課題提出を忘れがちな日々を送っていました。高校進学のために内申点を上げたければ提出物は避けて通れず、さとこさんも頭を悩ませていました。個人面談でも「課題の提出状況に波がある」と先生から指摘され……。『必ずやらなきゃいけないことは具体的な対策を』と親子で考えたアイデアは思春期のお子さんへの対応の参考になりそうです。

提出物が出せない中2ADHD息子、内申点が上がらず高校受験はどうなる!?編み出した工夫とは
このコラムを振り返って
(執筆者:丸山さとこさんより)
提出物に関しては中学を卒業するまでずっと悩まされ、内申点でも苦労しました。とはいえ、今から振り返れば「少しずつ提出できる量は増えていったんだよな~」とも思います。
3年生の2学期で再び忘れ物が増えてきたときも先生方が協力的でいてくださったのは、3年生の1学期までコウなりに頑張ってきたことが伝わっていたのかもしれません(先生方が凄く根気強く、寛容で熱心だっただけの可能性も高いです!)。
提出物に関しては中学を卒業するまでずっと悩まされ、内申点でも苦労しました。とはいえ、今から振り返れば「少しずつ提出できる量は増えていったんだよな~」とも思います。
3年生の2学期で再び忘れ物が増えてきたときも先生方が協力的でいてくださったのは、3年生の1学期までコウなりに頑張ってきたことが伝わっていたのかもしれません(先生方が凄く根気強く、寛容で熱心だっただけの可能性も高いです!)。
丸山さとこさんにとって発達ナビとは?
発達ナビ10周年、おめでとうございます!息子のコウが保育園児から高校生へと成長していったこの10年の間に、障害がある子どもとその保護者を取り巻く環境が少しずつ変わってきたのを感じています。コラムを書かせていただく中で、改めて調べて「今はそうなんだ⁉」と思うこともしばしばです。
息子のコウ自身の変化に加えて彼の周りの状況もどんどん変わっていく中で、新しい情報や体験談が得られる発達ナビは私にとってありがたい場所です。これからも長く、交流や情報発信の場として在り続けることを願っています。発達ナビ様の益々のご発展をお祈り申し上げます!
息子のコウ自身の変化に加えて彼の周りの状況もどんどん変わっていく中で、新しい情報や体験談が得られる発達ナビは私にとってありがたい場所です。これからも長く、交流や情報発信の場として在り続けることを願っています。発達ナビ様の益々のご発展をお祈り申し上げます!
その他、丸山さとこさんのコラムはこちらから

わが子も春から高校生!新年度のさまざまな壁、発達障害親子が工夫と配慮で乗り越えた小中9年間

ADHD息子、高校受験まで半年。「薬を増やしたい」と相談されて…【思春期の服薬・医師からのコメントも】

発達障害息子、小学校入学で途切れた支援。放課後等デイサービスに通えないまま中学生になって…

癇癪もちなのは母!?発達障害息子にイライラ爆発!叱るのは子どものため?それとも自分のため?【臨床心理士と考える】
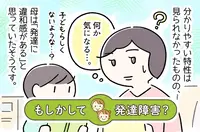
発達障害によくある行動はなかったけれど。 昭和の時代に、わが子の発達障害に気づいた母に理由を聞いてみたら
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如・多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。
ADHD(注意欠如多動症)
注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如・多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。
ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。
発達支援施設を探してみませんか?
お近くの施設を発達ナビで探すことができます
新年度・進級/進学に向けて、
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています
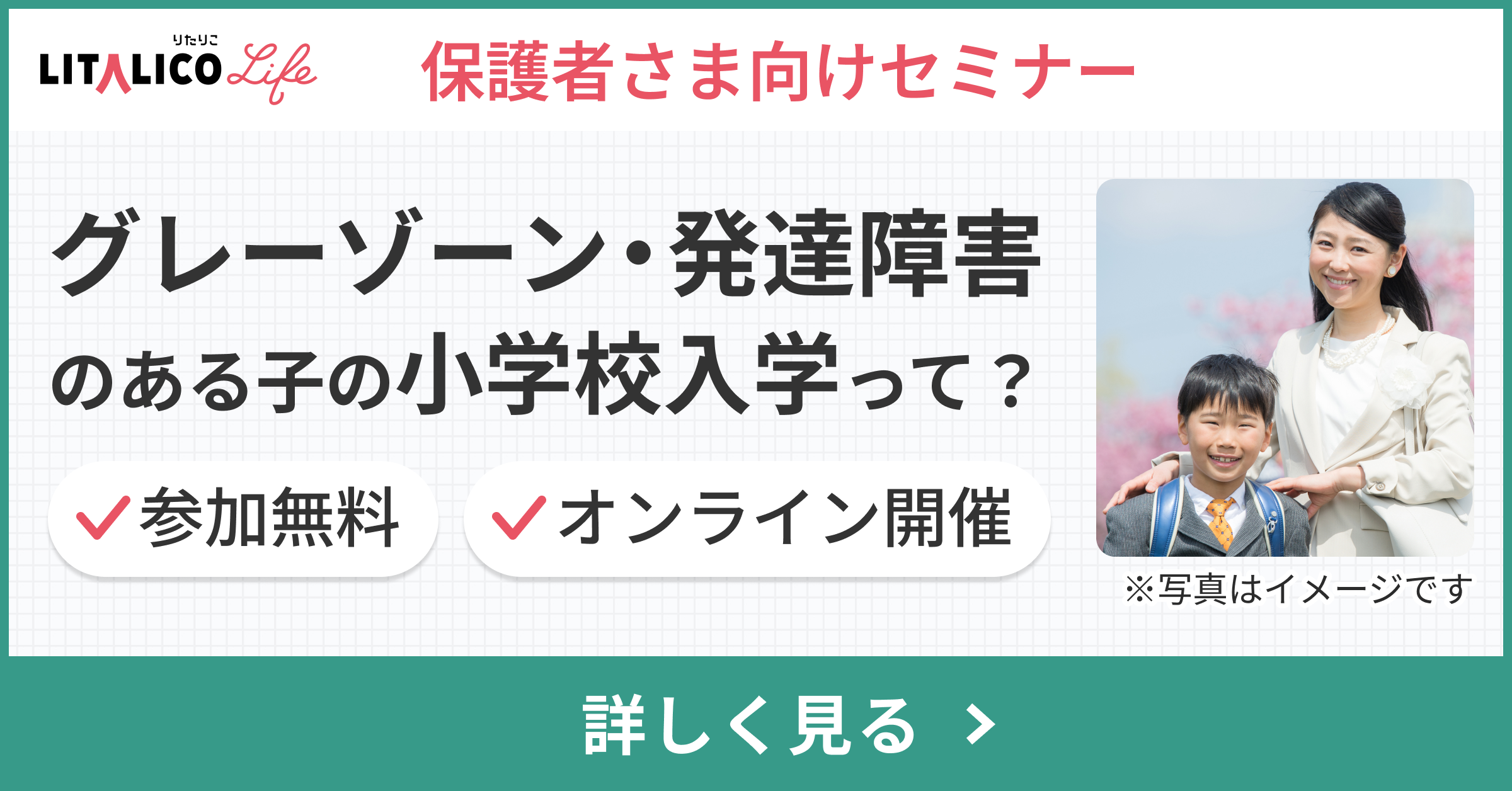
-
 1
1
- 2














